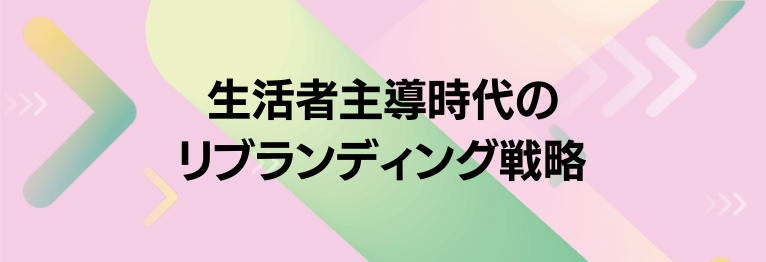
生活者主導時代の「リブランディング」戦略
ブランドの認知度は、重要な資源である一方で、固定化した「ブランドイメージ」が進化するブランド・事業の足かせになりかねないというリスクもあります。こうした課題を解決するため、プロダクトやコーポレートのリブランディングの戦略や、各種コミュニケーション活動が展開されています。本特集では、ブランディング、リブランディングにおいて特に「消費者の側にある固定化したイメージ(≒パーセプション)」を刷新するため、コミュニケーション上、どのような工夫をしたのか?ブランディングに成功している企業の取り組み事例から考察します。
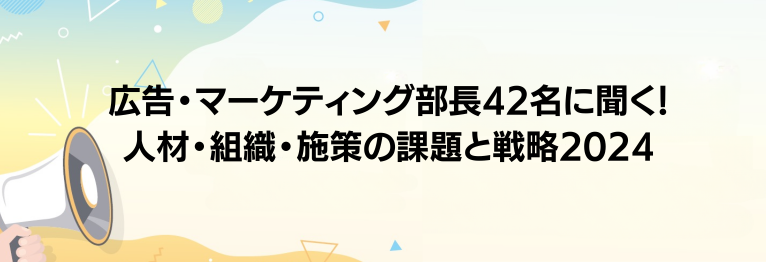
広告・マーケティング部長42名に聞く!人材・組織・施策の課題と戦略2024
メディア環境、市場環境が変化を遂げる中、生活者とブランドの接点をつくり、さらにその関係性を深めていくマーケティングやコミュニケーションにかかわる仕事の難易度はますます高まるばかりです。こうした環境においても、常に存在感を発揮する企業・ブランドのマーケティング戦略をリードしている広告・マーケティング部門の責任者の皆さまに現状の課題や、その課題を解決するための構想を聞きます。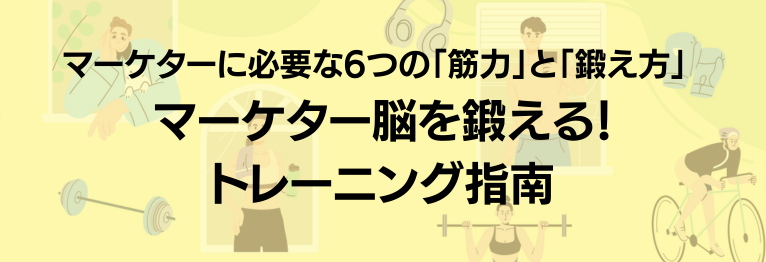
マーケター脳を鍛える!トレーニング指南
情報感度に観察眼、発想力にロジカルな思考力...。マーケターとして第一線で活躍をし続けるためには、日々鍛え続けなければならない、「マーケターの筋力」が求められるのではないでしょうか。日々の仕事、プライベートでの実践の積み重ねのなかに、マーケターにとって必要な「筋トレ」の実践論があるのでは?マーケターにとって必要な「筋力」別に、第一線で活躍するマーケターの方に、その「鍛え方」を伺います。
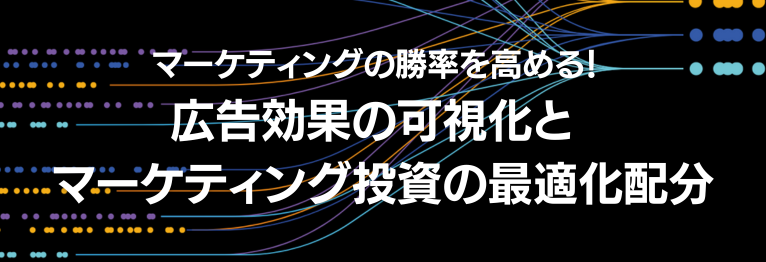
広告効果の可視化とマーケティング投資の最適化配分
勘と経験のマーケティングからデータドリブンのマーケティングへ。これまで長らく効果がわからないと言われていた広告やマーケティング投資の効果を予測する取り組みを行い、データドリブンなマーケティングへと進化を遂げる企業が出てきています。今回の特集では、データ利活用のポイントから最先端のAI技術まで、新たな取り組みにチャレンジをする企業の方々への取材を通じて、マーケティングの効果を最大化する取り組みの方向性を探っていきます。
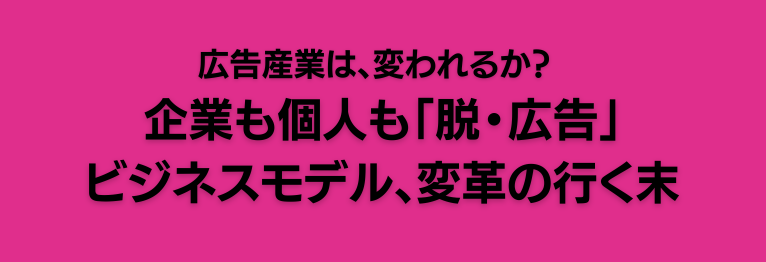
企業も個人も「脱・広告」ビジネスモデル、変革の行く末
おかげさまで月刊『宣伝会議』は、本号を持ちまして創刊70周年を迎えます。弊誌は「広告業界誌」ではなく、広告主も広告業も双方が対象となる、広告・マーケティングの「専門誌」であるという矜持を持って、70年にわたり月刊誌の刊行を継続してきました。広告・マーケティングにかかわる多種多様な事例も手法もすぐに入手が可能な現在のメディア環境のなかで、『宣伝会議』が広告界の皆様に対して、提供できる価値は、何なのか。70年の節目を前に編集部一同、考えを巡らせました。すぐに答えを出せる問いではないですが、専門誌である月刊『宣伝会議』としては、マーケティングやコミュニケーション産業、クリエイティブ産業に携わる方々にとって、社会における仕事の存在意義を再確認していただける存在であり続けたいと考えています。そんな想いを込めて、企画したのが今回の特集です。広告産業が今、どのようにトランスフォーメーションしようとしているのか。特集をお読みいただくと、その変革の行く末が見えてくると思いますし、見た目のあり様が変わっても、変わることのない、この産業の社会における存在意義も導き出していただけるのではないかと思います。
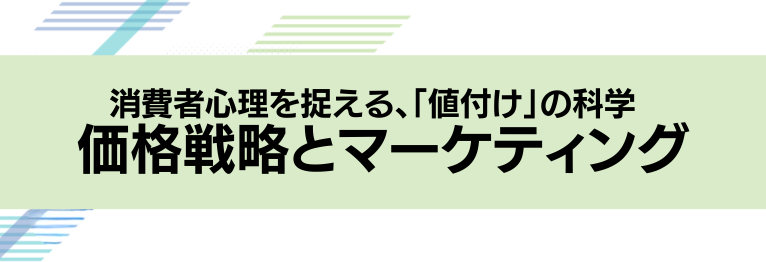
消費者心理を捉える、「値付け」の科学 価格戦略とマーケティング
原材料価格の高騰を企業努力で吸収しえなくなった2023年、日用品の値上げが相次ぎ、消費者の節約意識がさらに高まったと言われています。これまで、安さを維持することが正義のように捉えられvることもあり、値上げに踏み切れない企業が多かったなかで、大きな変化と言えそうです。値上げラッシュの2023年を通じて、企業が改めてマーケティング戦略におけるプライシング戦略の重要性を理解することになったのではないでしょうか。今回は、ヒット商品や店舗などの事例も交えながら、現代消費者に支持される「値ごろ感」を明らかにするとともに、戦略的なプライシング戦略のあり方を考えます。
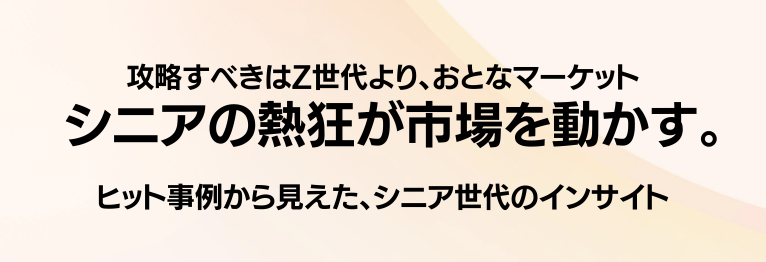
シニアの熱狂が市場を動かす。
100兆円を超える規模とも言われる国内のシニアマーケット。もはや3人にひとりが高齢者の今の環境では、あえて「シニア向け」と銘打たなくとも、多種多様な企業の商品の主要な対象顧客にシニア世代が含まれています。日本国内でビジネスをしていくうえでは、「シニア世代」のインサイトを捉えることは、もはや必須といえるのではないでしょうか。しかし、世代論が通用しなくなってきたと言われる今、「シニア世代の特性」をわかりやすく提示するのは難しいのも事実です。一方で加齢に伴う、身体の変化などもあり、シニア世代だからこその行動や意識の特性は現在も存在します。そんな難しいシニアマーケットにおいて、実際に成功している企業・商品の事例からポイントを読み解いていきます。
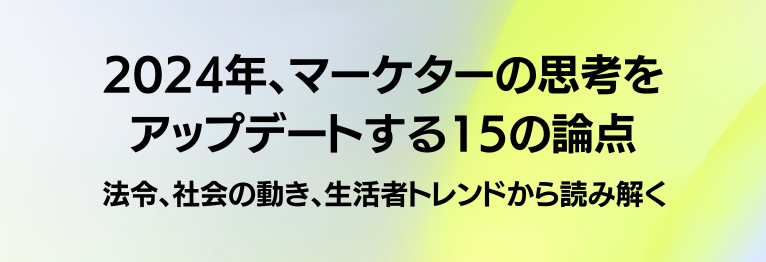
2024年、マーケターの思考をアップデートする15の論点
法令、社会の動向、そして生活者のトレンドが再定義される中、マーケティングの世界も着実に変化を遂げています。社会環境の変化の中で、広告やマーケティングの世界ではおなじみの手法やメディアにはどのような変化が起こるのか。本特集では、コミュニケーション産業の中で、2024年に予想される変化に焦点を当てます。マーケティングテクノロジーからデータプライバシー、生成AI、さらには地方創生とクリエイティブまで、実務家が押さえておくべきアップデートポイントを一挙に紹介します。
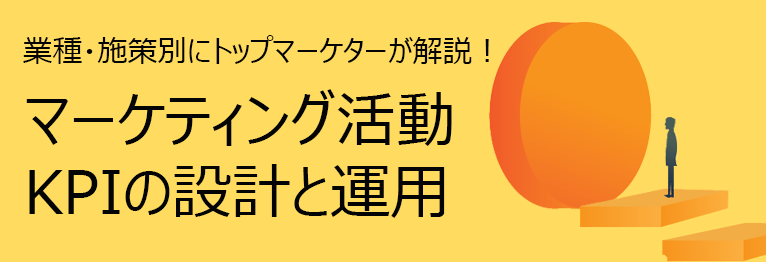
マーケティング活動 KPIの設計と運用
マーケティング活動の成功に際しては複数の要因が絡んでくるため、当然ながら結果はコントロールしづらいものです。しかし、消費者との接点や施策の運用においてデジタル化が進むなか、データを基にしたKPI設計を行い、日々の活動の指針とする流れは一般的になっています。マーケターはいかにKPIと向き合い、事業の成果につなげていけばよいのか。主な業種・商材・マーケティング目標・シーン別に、「マーケティング活動におけるKPI設計」の基本を、各カテゴリーを代表するトップマーケターの皆さんに解説いただきます。
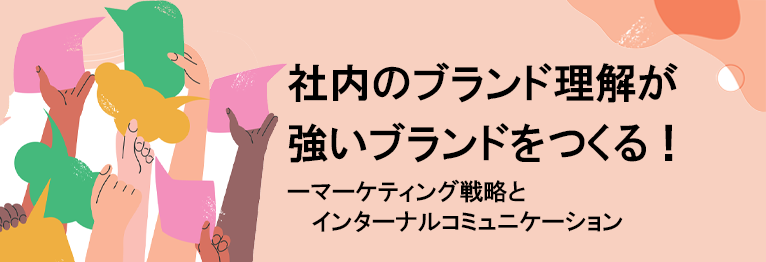
社内のブランド理解が強いブランドをつくる!
小売りや飲食など、お客さまと従業員の直接的な接点のある業態では、接客の質が、サービス体験品質の差として、顧客に選ばれる競争優位性のひとつの要素になってきました。しかしメーカーを含めて、顧客接点のデジタルシフトと、それに伴うダイレクトに顧客とつながる関係性の構築が進むにつれ、サービス業態以外でも、従業員がお客さまに接する姿勢や態度が、ブランド価値を左右する重要な要素になりつつあります。顧客と接する可能性のあるすべての従業員が、パーパスのような企業が目指す方向性を理解し、なおかつ顧客第一の思考をもって接することができるならば、魅力的な体験づくりにつながり、マーケティング戦略を成功に導くことになります。つまりは従業員を対象としたインターナルコミュニケーションが、マーケティング活動にも大きな影響を与えていると言えるのではないでしょうか。マーケティングに生かす、インターナルコミュニケーションの方向性とは?またマーケティング部門がはたして、そこまで全社に対して働きかけることができるのか?など。マ
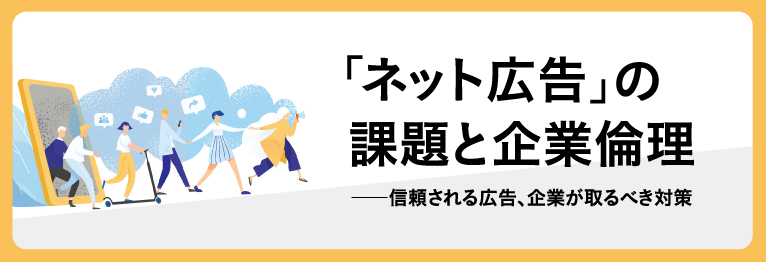
「ネット広告」の課題と企業倫理
国内では昨年「デジタル広告品質認証機構(JICDAQ)」が活動を開始し、ネット広告の取引の透明性担保に向けた取り組みが進んでいます。一方で、その先にあるネット広告とエンドユーザーとの接点においては、まだまだ問題のある行為も散見されます。悪質な行為を行うのは、ほんの一部の事業者であっても、そうした事業者の広告活動によって、ネット広告さらには広告自体にネガティブなイメージを持たれてしまっては、すべてのアドバタイザーが不利益を被ることになりかねません。業界をあげて取り組まなければならないネット広告の体験品質の問題とは何か。また現在の環境のなかで、広告主が対処しうるリスク対策にはどのようなものがあるのか。国内外の最前線の取り組みをもとにレポートします。

SNS時代 新しい「ブランド」のつくられ方
スマートフォンやSNSが浸透し、人々の情報接触行動、企業・ブランドとの出合い方や購入の仕方も変化をしています。情報収集・購買行動が変化をしているとするならば、その先にあるブランド構築のプロセスにも変化はあるのでしょうか。本特集では、最近ヒットし、市場から支持を得た商品・サービスの事例の分析を通じて、今日的な「ブランド構築」のプロセスを考えていきます。

生成AIと広告・マーケティング
これまでもマーケティングの世界では「AIブーム」とも言える現象がありましたし、実務の現場での活用は進んできました。しかしChatGPTの公開をきっかけに現在、起きている現象は、これまでの延長線上では予測できないような新しい可能性を拓こうとしています。マーケティングの仕事に携わる人たちの業務の効率化が実現するのはもちろん、メディアの在り方や、企業と生活者の接点のつくりかたをも変えるようなインパクトが予測されます。大手広告会社が打ち出す活用方針や指針、実際に企業のコミュニケーション活動における活用事例など、想定されるリスクを回避しながら、より有効な活用法を模索する最前線の取り組みをレポートします。

注目51社の今期の戦略がわかる!広告・マーケティング部長アンケート
メディア環境、市場環境が急速な変化を遂げるなかで、生活者とブランドとの接点をつくり、さらにその関係性を深めていくマーケティングやコミュニケーションの施策の難易度はますます高まっています。こうした環境下で、企業の最前線で生活者の気持ちと相対する広告・マーケティング部門のトップの皆さんは、どのような戦略を描いているのでしょうか。変化した生活者意識の本質を見抜き、期待を超える価値創出のために取り組むべきこととは。日本を代表する大手企業51社でマーケティング活動をリードするトップランナーの皆さんの回答から、これからのマーケティングの在り方を考察加えて、最先端の企業マーケティング組織に迫ります。
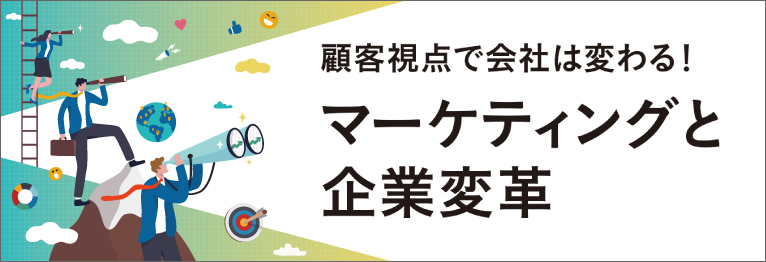
マーケティングと企業変革
マーケティングは顧客をつくり、市場を創造する役割を期待されてきました。しかし、既存事業の延長線上に企業の成長を描きづらくなっている昨今、マーケティングの市場創造機能が時に企業自体のビジネスモデル変革に寄与するケースも増えてきているようです。社会が変化し、様々な業界でビジネスモデルの変革期にある今、マーケター、そしてマーケティングという機能は企業の持続的な成長にどのように貢献できるのでしょうか。最前線で取り組む方たちへのインタビューを中心に実感値と今後の構想についてレポートします。
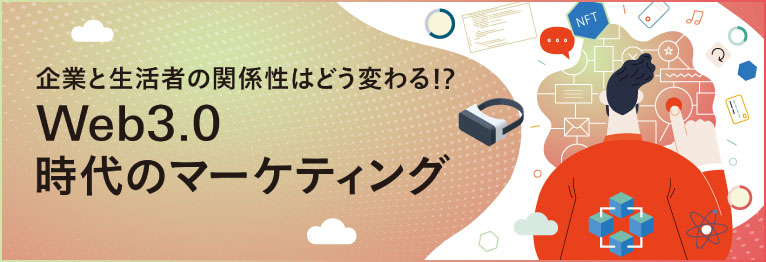
Web3.0時代のマーケティング
国内で「Web3.0」という言葉が聞かれるようになって久しいですが、Web1.0から2.0。さらに3.0へと進化を遂げていく背後には、どのようなテクノロジーの登場、そしてその進化を加速させた生活者の価値観があったのでしょうか。人々の価値観や行動が変化する際、当然ながら企業と生活者の関係性も変わっていきます。特集ではWeb3.0時代のマーケティングをテーマに、生活者が期待するこれからの企業との関係性、さらにブロックチェーンやNFT、メタバースといったテクノロジーを企業がどうマーケティングに活用していけるのか、事例を踏まえて紹介していきます。