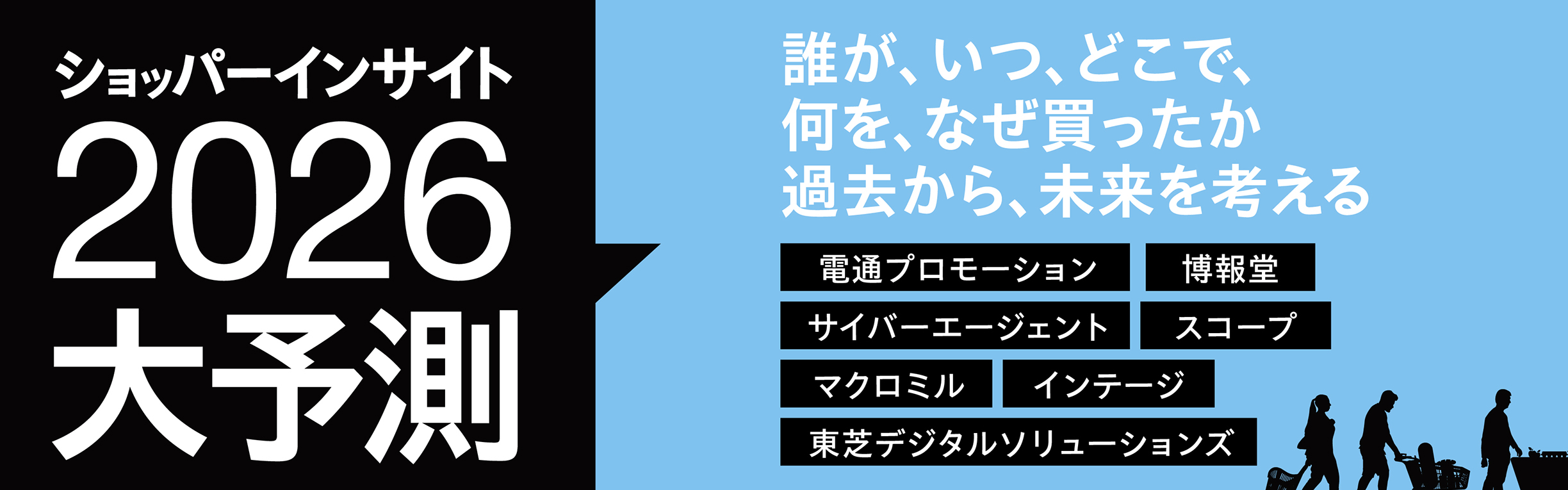
ショッパーインサイト大予測 2026
購買の場におけるデジタル化が加速し、データとして蓄積できるようになったことにより、「誰が、いつ、どこで、何を、なぜ買ったのか」を具体的な時間軸で振り返ることが可能になりつつあります。アプリやEC、リテールメディアなどのデジタル接点を通じて、これまでは見えなかった購買の周りで起きている行動が可視化され、買われるまでのプロセスの実態を捉えられるようになってきたためです。 とはいえ、すべてがわかるようになったわけではありません。データはあくまで行動の結果であり、ショッパーの気持ちそのものを完全に捉えるものではないからです。カテゴリーや業態によって、見える範囲に差があることも事実でしょう。 それでも、立場や視点の異なる知見を重ねていけば、いくつかの共通点が浮かび上がってくるはずです。導き出された共通点は、ひとつの仮説になり、これまで勘や経験、感覚に頼ってきた売り場づくりや販促施策の判断を確かなものに近づけてくれるのではないでしょうか。 そこで本特集では、広告会社や調査会社に直近1年で見え始めた「買われ方の変化」を聞きました。その変化をもとに、2026年のショッパー(買い物客)のインサイトを予測し、売り場で準備することをまとめています。さらにメーカーの視点からも、変化をどのように捉え、何を見て販促のアプローチを判断しているかを探りました。過去をどう読み解くかが、次の一手を左右する。2026年の買い物客は、売り場でどんな行動をとるのでしょうか。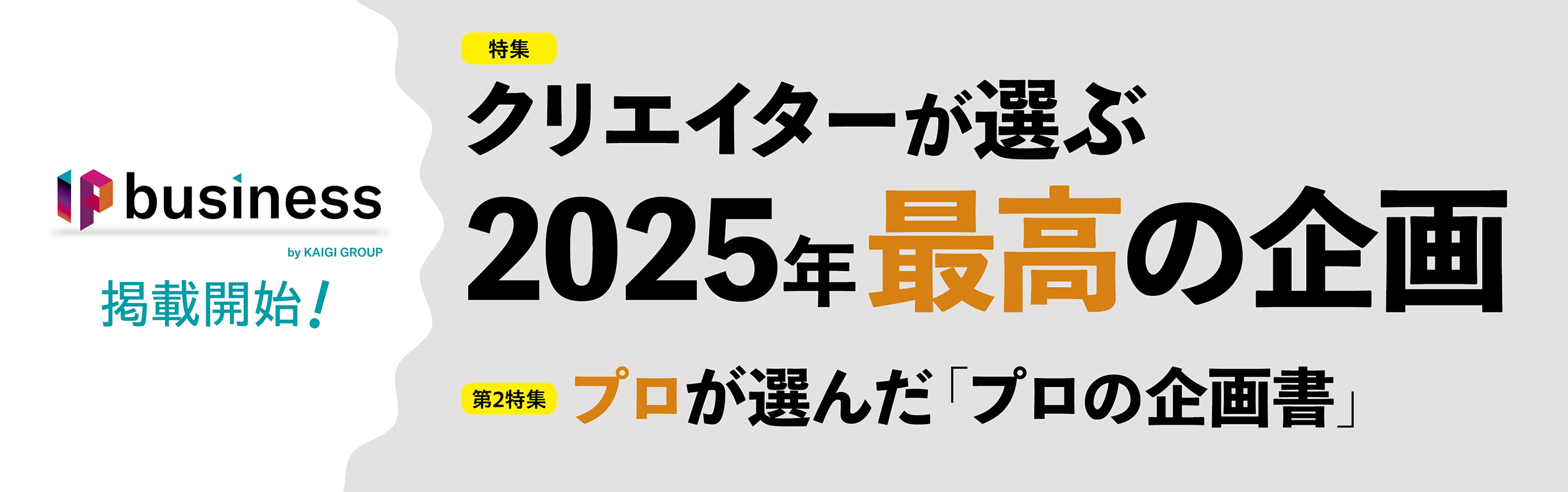
クリエイターが選ぶ2025年 最高の企画
2025年も多くの魅力的なプロモーション施策が生まれました。今回はその中から、“企画のプロ” であるクリエイターが選ぶ「2025年・最高の企画」をお聞きし、1つの特集にまとめました。普段から企画を生業とする方々の視点から見た「上手い」「優れている」企画を明らかにします。また今回は、回答者自身が担当した企画の中で、最も良いと感じた“自画自賛” 企画を聞いているのもポイントです。本特集は新年号。新たな年に移り変わるこのタイミングで、プロが選ぶ、2025年の「最高の企画」を振り返りながら、2026年「話題になる企画」について考えます!
熱狂が生んだEXPO消費 アフター万博
2025年の大阪・関西万博は2900万人以上を動員し、前評判を覆す熱狂のうちに閉幕しました。企業による巧みな店舗や商品の展開、そのプロモーション、そしてユニークなパビリオン体験など、数々の施策は生活者の消費や購買行動をどのように動かしたのでしょうか。大阪・関西万博を起点に、ブランディングと販促の成果を総括し、“万博ロス”と呼ばれる今だからこそ、次なる「売り方」を考えるヒントを探ります。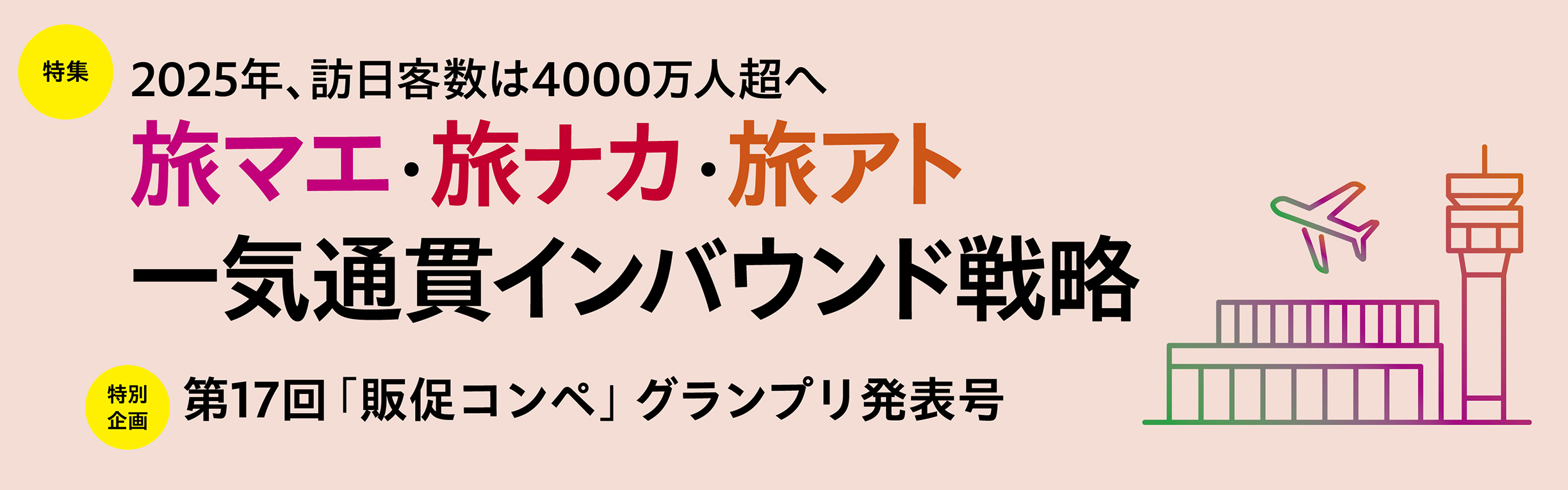
旅マエ・旅ナカ・旅アト一気通貫 インバウンド戦略
インバウンド消費は復調し、訪日客の購買行動は旅行前・旅行中・旅行後の3フェーズでつながっています。そして2025年は、訪日客数が4000万人に達するとの予測も出ており、ますます“巨大マーケット” を攻略する必要性は大きくなっているのではないでしょうか。メーカーや小売、サービス業にとっては、単なる「一度きりの購入」ではなく、来日前からの期待づくり、滞在中の購買・体験設計、帰国後のファン化やリピートに至るまで、一貫した接点づくりが求められるようになりました。本特集では、企業・ブランドがどのように訪日客に向けてブランドを発信し、売上やリピートにつなげればよいのか、旅マエ・旅ナカ・旅アトの各フェーズで成功事例をもとにヒントを探ります。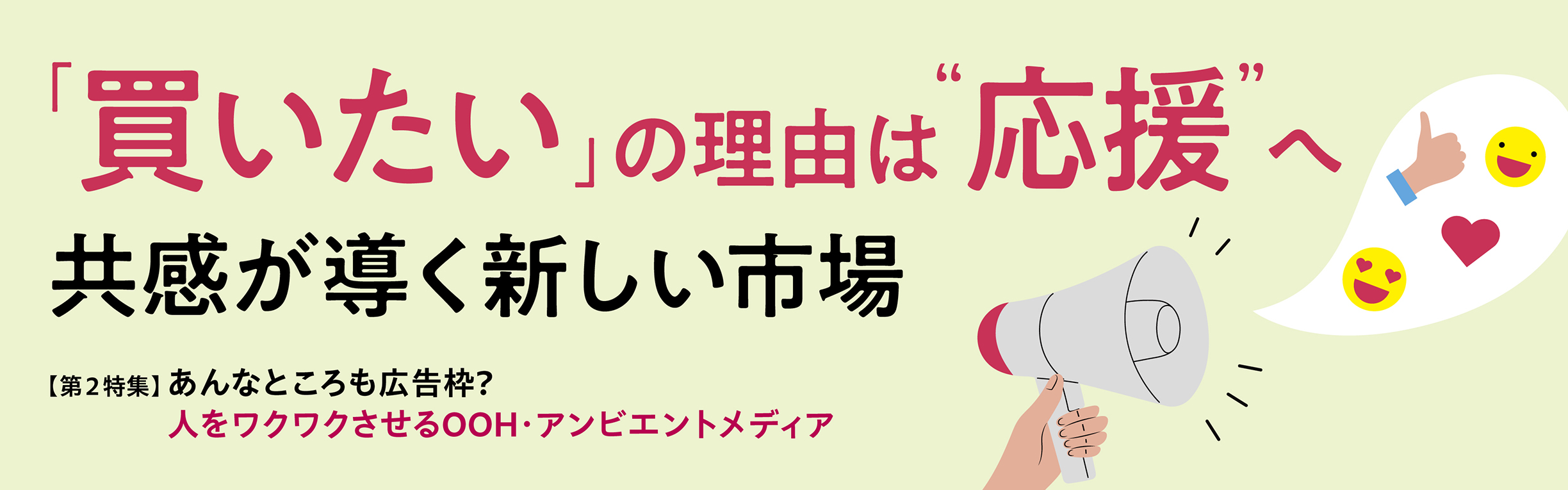
「買いたい」の理由は“応援”へ
「モノ消費」や「コト消費」、そして「イミ消費」の登場に見られるように、消費のあり方は時代とともに多様化し、常にかたちを変えてきました。そんな中で、いま生活者の購買行動を突き動かしているのは、「誰かを応援したい」「共感したから買いたい」といった感情のスイッチです。企業やブランド、地域、クリエイターなどへの“応援消費”が、世代を問わず広がりを見せています。いわゆる“推し活”もそのひとつと言えるでしょう。この新しい消費の原動力となっているのが、共感の熱量です。SNSでの発信、クラウドファンディング、サブスク支援、グッズ購入、リアルイベントへの参加──。その行動の背景には、誰かの“想い”に心を動かされ、自らの意思で選び取る消費の姿があるのではないでしょうか。本特集では、「応援」を軸にした最新の購買行動の潮流をひも解きながら、企業やブランドが生活者の“共感”をいかに設計し、販促・プロモーションへとつなげていくべきかを探ります。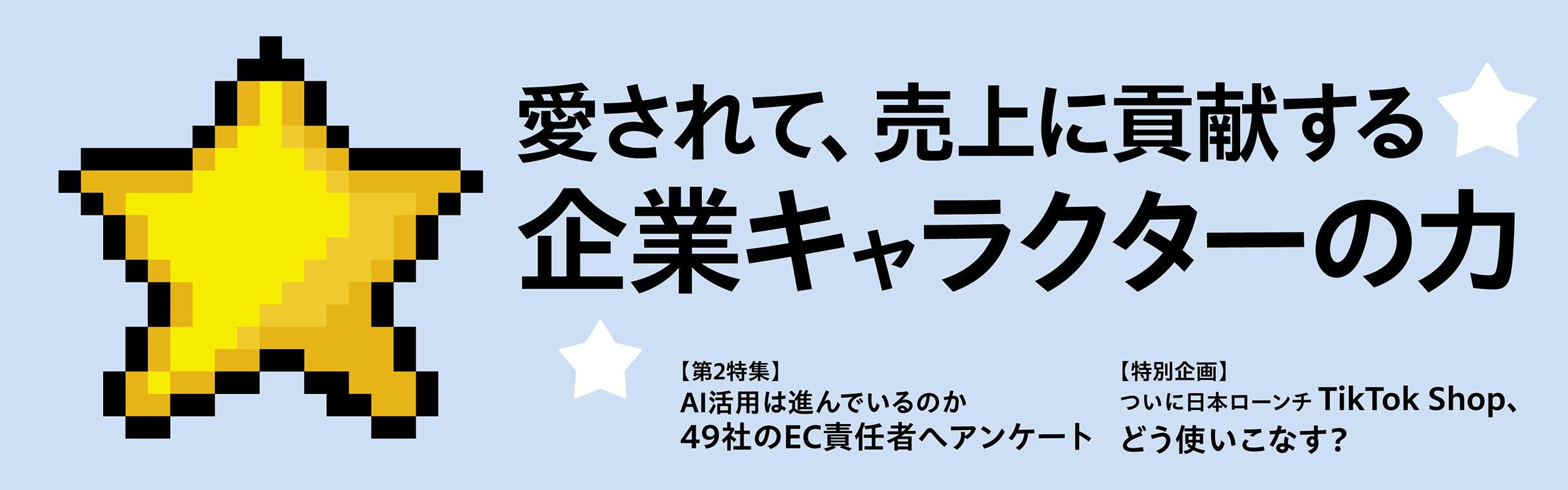
愛されて、売上に貢献する企業キャラクターの力
企業やブランドが育ててきたキャラクターは、単なるブランドの「顔」や象徴を超え、売り場で選ばれる理由となり、ブランドと生活者をつなぐ存在へと進化しています。今回は、そんな企業が保有するキャラクターがどのようにブランド体験や購買行動に影響を与えているのかを掘り下げる特集です。広告塔でも単なるマスコットでもなく、“企業キャラクター”が、企業の中でどのように活用され、どんな価値を生み出しているのか──その力を、いま改めて問い直します。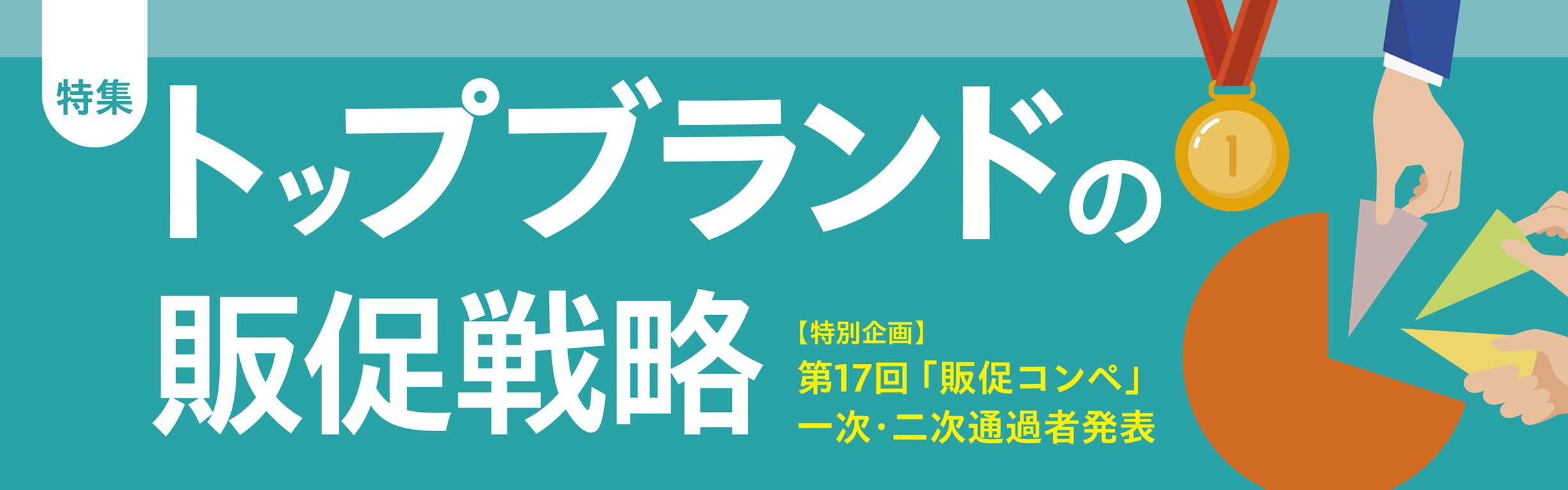
トップブランドの販促戦略
トップシェアや高い売上を維持・拡大しているブランドは、どのようにして“選ばれ続ける存在” になっているのでしょうか。市場に数多くの競合がひしめく中で、確かな成果を出し続けているブランドには、売れるための「再現性ある仕組み」が存在しているはずです。本特集では、各カテゴリーでトップを走るブランドの販促戦略に迫ります。認知の獲得から購買意欲の喚起、リピートやファン化に至るまで──消費者との接点をどのように設計し、どのような仕掛けによって「選ばれ続けているのか」。単発のキャンペーンではなく、継続的な成長を支える設計思想や現場での実行力にも焦点を当てながら、トップブランドの“売り方”を多角的に紹介します。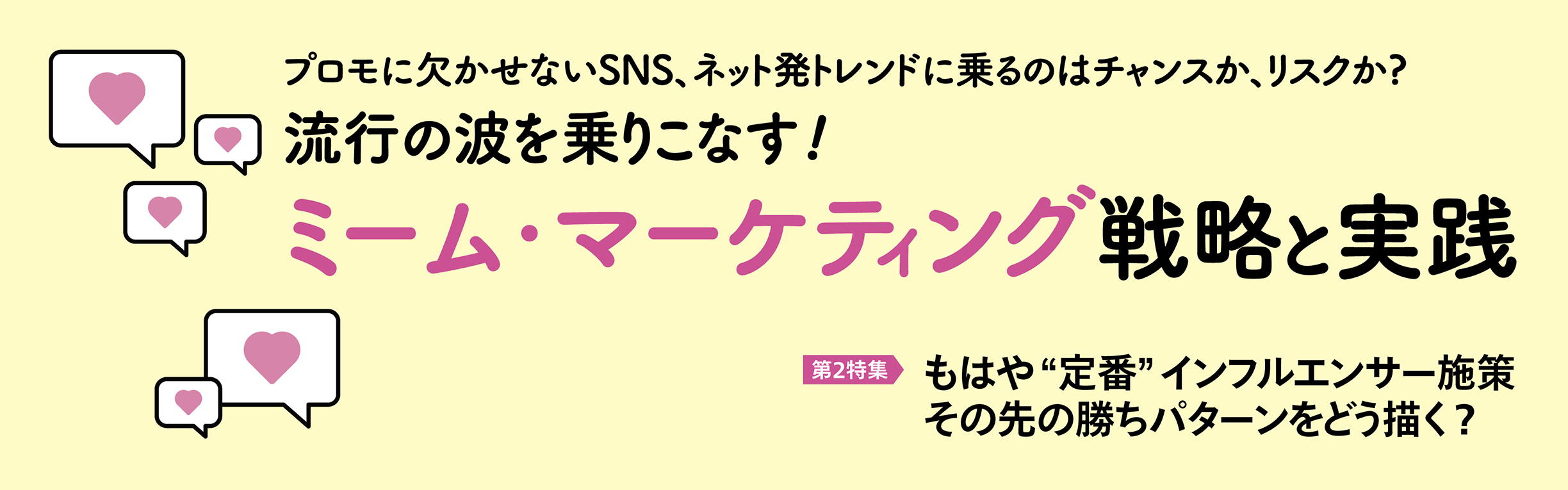
ミーム・マーケティング戦略と実践
SNSを起点とする情報の流れはますます加速し、今日バズったものが明日には忘れ去られる時代に突入しています。生活者の関心は「今」に集中し、ブランドやプロモーションにおいても「トレンドに乗れるかどうか」が話題化の成否を左右するようにもなってきました。本特集では、ネットミームやSNSで生まれるトレンドを瞬時に捉え、巧みにプロモーションへと昇華させて話題を呼ぶ「ミーム・マーケティング」に注目。単なる“ノリ”ではなく、明確な意図を持って仕掛け、成果へとつなげている事例や、その裏側にある体制・判断・設計思想を深堀して紹介します。さらに、共感による拡散のメカニズム、炎上リスクへの備え、そして現場でトレンドと向き合うSNSの“中の人” たちのリアルな声を通じて、ミーム・マーケティングという手法の本質に迫ります。SNSとともに変化する生活者の感情や行動、そのスピードを武器にするのはチャンスか、リスクか─。販促・マーケティング担当者が“今”の空気を企画に取り込むためのヒントを探ります。
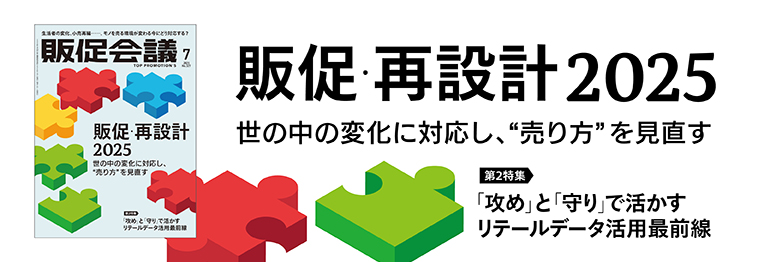
販促・再設計2025
生活者を取り巻く社会の状況に合わせて、消費者の価値観、購買行動も変化しています。かつて定番だった販促の手法や方程式が、今の生活者には届きにくくなり、「売り方の再設計」が求められているといえるのではないでしょうか。さらに近年は、小売業界における統合・再編の動きも加速。店舗の役割や売り場の構造、商談のあり方にも変化が生まれ、これまで通用していた販促提案や設計が、そのままでは機能しづらくなっている現場も少なくないとも聞きます。こうした状況の中では、商品開発や売り場提案の見直しとともに、販促の訴求ポイント、メッセージ設計、媒体の選び方をアップデートする必要があります。従来のテンプレ提案が通用しにくくなり、提案の切り口・成果の捉え方・プロセス設計そのものを見直すことが重要になってきているのです。この特集では、売り方の実務現場に焦点を当て、何を見直し、どう変えればよいのかをひも解きます。生活者の変化や小売の構造変化に向き合い、「販促を再設計」するためのヒントを探ります。
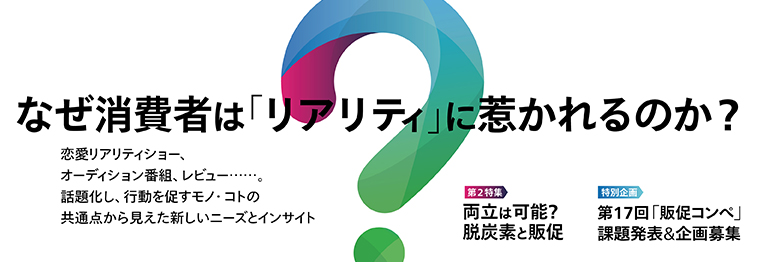
なぜ、消費者は「リアリティ」に惹かれるのか?
昨今、話題になったり、人気が出たり、選ばれやすくなっているモノ・コトの多くには、「リアリティ」という特性が共通しているように感じられます。例えば、オーディション番組、恋愛リアリティショーなど、何かが世に出るまでのプロセスを見せるコンテンツ。また、脱出ゲームをはじめとしたイマーシブイベントのように、消費者が実際にリアルに近い体験を楽しむものもあります。そして、購買・消費という観点で関連性が深いものとしては、「レビュー」や「透明性」といったキーワードも挙げられるのではないでしょうか。ここまで挙げたものはほんの一例にすぎませんが、「リアリティ」が人を惹きつけ、購買・消費を促すひとつのきっかけになっている可能性は大いにあるはずです。今回は、そんな「リアリティ」に惹かれる消費者にフォーカス。なぜ、人はいま「リアリティ」に魅力を感じるのか。それは、商品やサービスを選ぶ際の判断基準になっているのか。有識者への取材をもとに、その背景をひも解いていきます。

プロの企画書 ここでしか読めない「ホンモノ」の資料
世の中に発表されている数々の取り組みの裏には「企画者」が存在しています。そして、その企画者たちが自らのアイデアを誰かに伝える最初の手段として使うのが「企画書」。アイデアから生まれた企画をかたちにし、実行できるか否かの判断材料になる重要な役割を担うのが「企画書」なのです。とはいえ、話題のプロモーション施策も商品やサービスも、それらがどのように生まれ、企画書として落とし込まれたのかは、その施策に携わった人にしかわからないもの。「見てみたいのに見られない」㊙資料です。今回は、そんな㊙資料を公開する特集。話題になったキャンペーンから、新商品開発まで、プロによって制作された企画書を大公開します。ここでしか読めない「ホンモノ」の資料から、アイデアのヒントが得られるかもしれません。
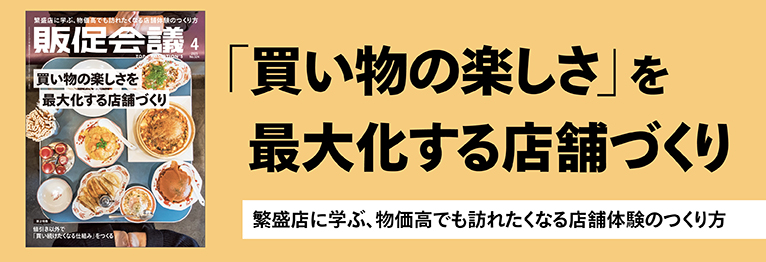
「買い物の楽しさ」を最大化する店舗づくり
最近、街で聞こえてくるのは、「野菜も高い、肉も高い、魚も高い」「あの店のランチも値上げした」といった声の数々。この物価高の中ではやむを得ないと思いながらも、節約志向によって買い物が退屈なものに感じることが増えたのではないでしょうか。しかし、買い物が楽しいと思える瞬間もあるはずです。例えば、趣味にお金をかけるとき、ずっと行きたかった話題のお店に行けたとき、店頭で思いがけない出会いがあったとき、お店の雰囲気や居心地が良さに心が癒されたとき......など、多くの楽しさを感じる場面もあると思います。そして、そんな買い物ができたときには「満足感」や「充足感」も得た体験として記憶に残るはずです。本特集は、この物価高の時代だからこそ考えたい、「買い物の楽しさ」を見つめ直す特集です。楽しさを最大限に引き出すための店舗や体験設計の方法に迫ります。
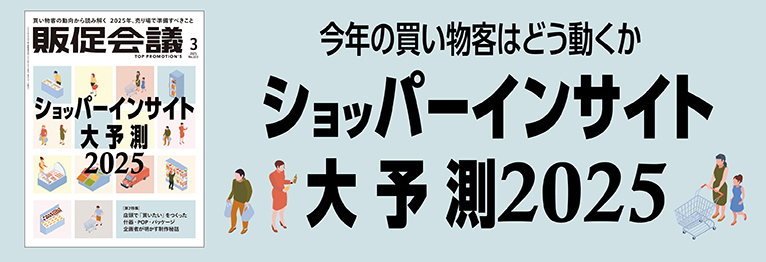
ショッパーインサイト大予測2025
売り場には「買う」をつくり出す要素が散りばめられています。どれだけ事前に広告やプロモーション施策で認知を獲得し、商品への興味・関心を高めていたとしても、いざ売り場を訪れると、価格やPOP、店内放送、気温、社会のトレンドなどの外的な要因によって消費者自身も想定していなかった商品を購入することもあるでしょう。購入の最終的な意思決定の場である「売り場」で、購入の判断を下すショッパーの行動は、謎に包まれているといっても過言ではありません。
とはいえ、ショッパーから「買いたい」という気持ちを引き出し、購入のスイッチを押す工夫は必要。小売・流通、メーカーは、そのためのあらゆる企画を考えているはずです。しかし、その企画はしっかりとショッパーのインサイトを落とし込んだものになっているでしょうか? そもそもショッパーのインサイトを捉えることができているでしょうか?
本特集は、ショッパーの購買行動の裏にあるインサイトを広告会社、調査会社が予測・分析します。2025年のショッパーは、何に心を動かされて購入を決めるのでしょうか。
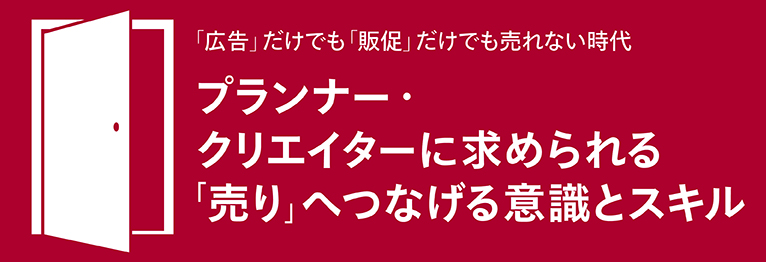
プランナー・クリエイターに求められる「売り」へつなげる意識とスキル
「認知だけでは売れない」と言われる時代。モノにあふれ、生活者との接点やメディアも多様化していくに伴って「知ってもらう」ことがストレートに売れることにはつながりづらくなりました。そこで再注目されているのが「アクティベーション」という概念です。「認知」獲得のその先、ミッドファネルの態度変容、さらにロウワーファネルのコンバージョンまで、消費者の行動を具体的に喚起するプランニングが求められるようになっています。これに伴い、「認知」獲得に主眼を置いていた広告クリエイター、PRプランナーの仕事や役割も変化しつつあるのではないでしょうか。
一方で、「販促」施策だけでも売れにくくなっているのも事実です。プランナーには、ブランドコミュニケーションで培ったブランドイメージや世界観をしっかりと売り場やキャンペーンにも落とし込み、両者に齟齬がないように一貫した統合プランニングが求められています。
ともすれば、「広告」と「販促」の垣根が曖昧になっていると言われるのも、どちらか片方だけではモノが売れなくなっているからだと考えられないでしょうか。本特集では、認知獲得に長けてきた広告会社、PR会社、クリエイティブエージェンシーと、販促やアクティベーションを得意とする企画制作会社に取材。今だからこそプランナー、クリエイターに求められる「売り」への意識とスキルについての意見を聞きました。
イマーシブ・プロモーション ─没入感をつくる体験設計─
昨今、体験を伴うコンテンツにおいて「没入」という言葉が用いられることが増え、1つのトレンドと化しています。そのトレンドはエンターテインメント施設だけではなく、店舗やポップアップストア、イベントといった「空間」を活用するプロモーショナルな施策にも及ぶようになりました。なぜ今、企業は「没入」をキーワードにするのでしょうか。また、これまでの体験とは何が、どう違うのでしょうか。今回の特集では「没入」の観点から、これからのポップアップストアやイベントにおける成功の鍵をひも解きます。
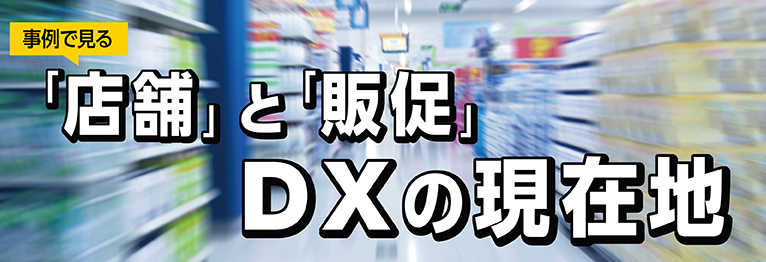
事例で見る「店舗」と「販促」DXの現在地
日々デジタル化が進行する現代。店頭へのサイネージ設置や、チラシやクーポンの電子化は当たり前に。また、アプリやID-POSの登場により、一人ひとりの顧客情報と購買データを紐づけ、効率的な販促にも繋げられるようになりました。さらに、それらのデータを活用することで、施策の効果も可視化できるようになり、買い物体験の質の向上にも貢献できるようになっています。また、人手不足によって業務効率化が求められる今、店舗DXやデジタル販促はこれまで以上に加速している状況です。
本特集では、店舗における販促のDXがどれだけ進んでいるのか、最先端の事例をもとに潮流をつかみます。さらに、これらの事例が「店舗・販促の新常識」として企業に採用されていくのかどうか、実務現場からの意見を聞きました。