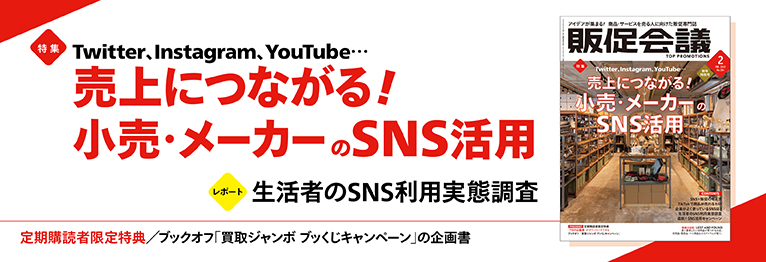
売上につながる!小売・メーカーのSNS活用
コロナ禍前からも消費者と直接つながるツールとしてSNSが活用されてきましたが、店頭など直接の接点を失った後、より強化をする企業が増えています。しかし、ただ活用を始めれば売上に貢献するわけではありません。各SNSごとの特徴をおさえたうえで、自社の商品・サービスにとってどのような目的で活用すべきかを考えていく必要があります。本号では、販売に寄与するSNS活用に焦点を当てて、小売・メーカーにおける最新のSNS活用を取材していきます。
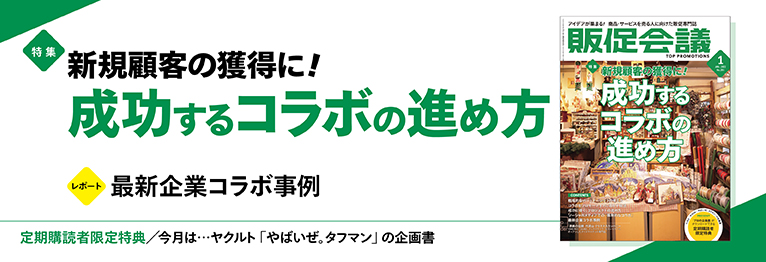
新規顧客の獲得に! 成功するコラボの進め方
自社だけでは届かない層へのリーチを生み出すなどの成果を見込める「コラボレーション」。事業、商品、プロモーションと、様々なレイヤーにおいて企業、コンテンツとのコラボが行われています。ですが、社内の部署間でも大変な進行が、社外ではより大変に。そこで今号では、コラボのきっかけづくりから調整、発売、プロモーションまでを含めた、成功させるコラボの進め方を特集していきます。
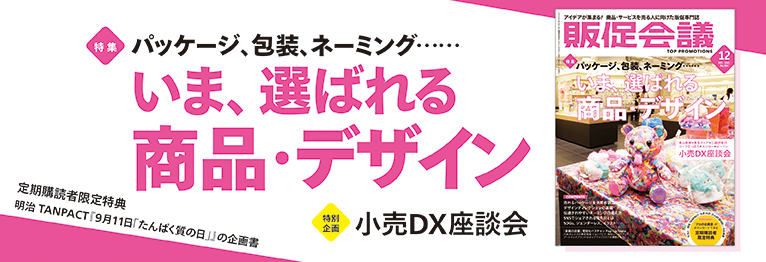
いま、選ばれる商品・デザイン
商品・サービスの満足度をあげることは大前提ですが、体験してもらう前に購入を検討してもらう必要があります。そのためには、商材をパッケージングしている「見た目」が重要になります。見て判断された後に、調べて、購入し、商品を使用します。中身はもちろん見た目にも気を使うことで、その商品の真価が発揮されます。現在はSDGsの観点により、パッケージレス、ジェンダーレスも重視されています。さらに、小売店頭、自社店舗、ECなど、商品の置かれる場所によって見た目の考え方も異なります。いま捉えておくべき、売れる「見た目」になるためのパッケージ、ネーミングなどの考え方について取材していきます。
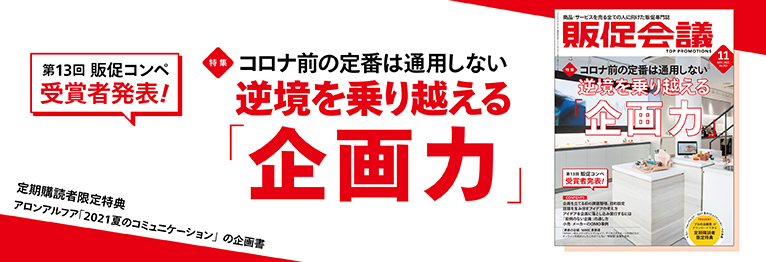
逆境を乗り越える 「企画力」
コロナ禍により様々な問題が企業に生まれています。しかしそれは市場の問題であったり、組織全体の問題であったりと、どうしようもない問題も多いです。そういった逆境のときこそ、多くの問題を乗り越えて売上を向上させる、アイデアのある企画が有効に働きます。ただ従来通りにプロモーションをしてむざむざ失敗するのではなく、新しい企画を行うことが活路を開くのです。ですが、消費者の心を捉えて行動を起こさせる企画を生み出し、実行するための方法を、多くの人は知りません。そこで今回は、人を動かし、売上を上げる企画を生み出すプロセスに焦点を当てた特集を行います。
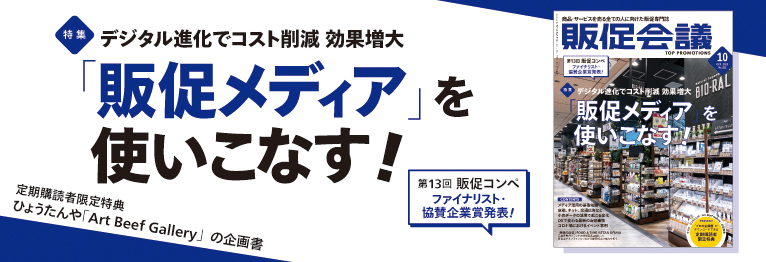
「販促メディア」を使いこなす!
コロナ禍により販促活動におけるメディアの役割・効果が変わってきています。巣ごもり、移動の減少といった人の行動や、生活者の心理・メディア接触の態度などが変化しているためです。また、最新技術によってメディア自体にも新しい潮流が生まれています。人を動かし販売につなげる販促メディアにはどのような変化が起こっているのでしょうか。販促活動に活用できるメディアに焦点を当てて、使い方について見直していきます。

人が動く「瞬間」の設計
このコロナ禍の中、「買う」という行為には意味が求められるようになりました。消費者の財布の紐は固くなり、何かにお金を支払うことに対して合理的な理由が求められるようになってきているのです。そういった状況下に役立つ考え方として、商品・サービスを大きく変えずに買う動機をつくり出す「インセンティブ」施策に焦点を当てます。買って体験してもらえれば満足してもらえるが、買ってもらうまでのハードルが高い商品・サービスにおすすめです。ポイント、クーポン、おまけなど、ただ値引きをするだけにならない、リピートまでつなげる人が動く瞬間の設計方法についてまとめていきます。
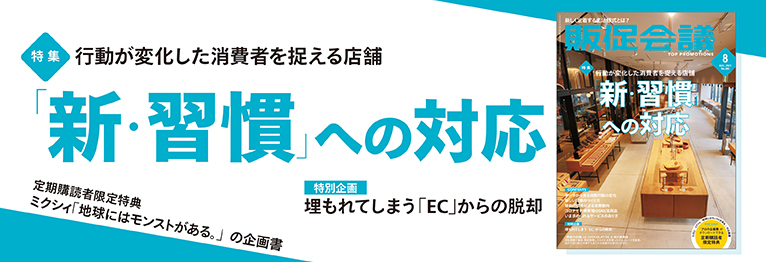
「新・習慣」への対応
人はいますぐ必要でなくても商品を買います。それらの多くは、店舗に寄ることで発生していた偶発的な消費です。しかし、コロナ禍によって生活習慣が変化したことで、今まで惰性で行っていたような「人と会う」「移動する」といったシーンでの消費が消えています。新生活に沿った形での新しい習慣が生まれている今、従来の生活者に合わせていた企業は、その変化に対応した販促を行っていく必要があります。そこで本特集では、新習慣に合わせた体験、商品、サービス、キャンペーンなど、店舗運営の方法について取り上げていきます。
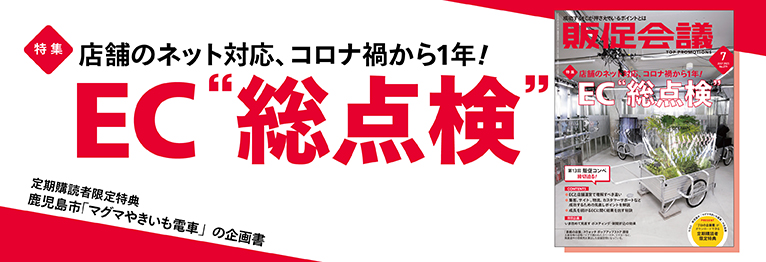
EC『総点検』
昨年4月、1度目の緊急事態宣言で休業せざるを得ない状況の中、実店舗の売上を補完すべく、多くの企業・店舗がECを始めました。しかし、必ずしも準備万端でスタートがきれたわけではなく、約1年が経って思ったほどの成果を出せずに悩んでいる事業者も多いのではないでしょうか。従来の店舗ノウハウの発想のままでいくとうまくいきません。人通りがあり自然流入が見込められていた店舗と異なり、ECは人を呼び込む集客から、リピートしてもらうまでを設計しなおさないといけません。今回の特集では、突貫で始めたECについて、売上を拡大するために必要な「見直すべきポイント」をおさらいします。
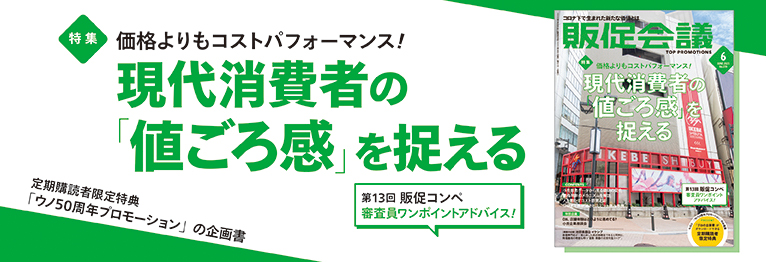
現代消費者の「値ごろ感」を捉える
リモートワークや緊急事態宣言など、コロナ下では日々消費者の行動、心理に変化が起こっています。そのような中で販売促進を行うには、消費者が何に価値を感じてお金をかけているのかを知っておくべきです。消費の動向から、価格判断の軸、ヒットしている商品などを取り上げ、「値ごろ」「パフォーマンスが高い」と感じてもらうことに役立つ情報について取り上げていきます。
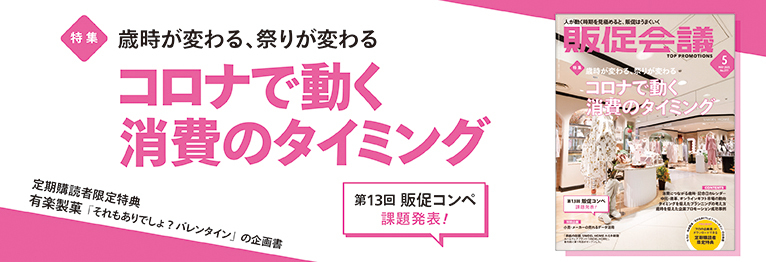
コロナで動く 消費のタイミング
年度替わりに正月、クリスマスなどの古くからあるイベント。さらには海外由来の新たな歳時や企業が制定した記念日・イベントなど、日本には多種多様な時期があります。人が行動する、そしてモノを買うきっかけとなる「歳時・記念日」。歳時はすでに世の中に存在するものなので、うまく使えば効率的に販促活動が実施できます。しかし、コロナ禍によって今までとは異なる歳時のあり方も生まれています。タイミングをうまく活用するための考え方、事例を紹介していきます。
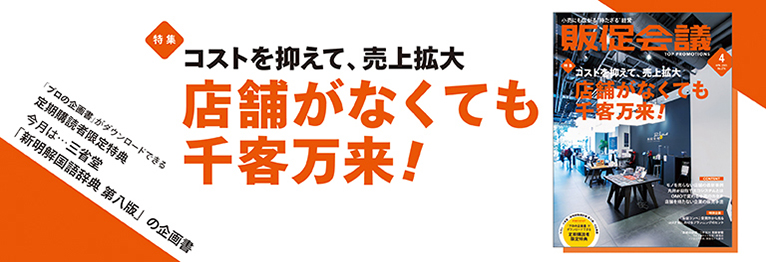
コストを抑えて、売上拡大 店舗がなくても千客万来!
従来の小売企業は、売上を拡大するために店舗の拡大を行ってきた。しかし、大量消費の減退やコロナ禍によるオンラインシフト、ECの普及などにより、店舗を持つ意味が変わってきている。本特集では、リアル店舗の価値の再定義から、店舗を必要としない新しい販売方法までを考えていく。
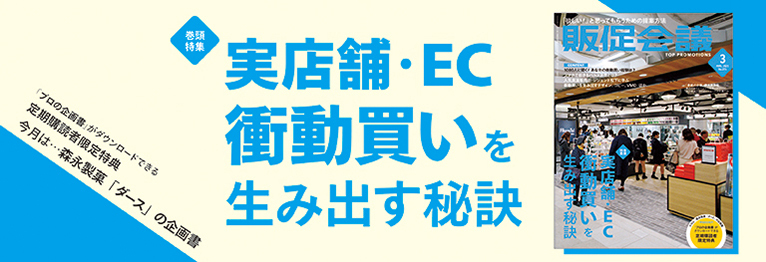
実店舗・EC 衝動買いを生み出す秘訣
コロナ禍による来店頻度・滞在時間の減少や、ECへのシフト、SNSでの事前の情報探索などによって、計画したものしか購入しない「目的買い」の傾向がさらに強まっていると考えられる。店頭での出会いにて促進がされていた「衝動買い」といった購買を、どのように喚起していけばよいのか。店舗、ECなどで新たな需要を生み出すヒントを探っていく。
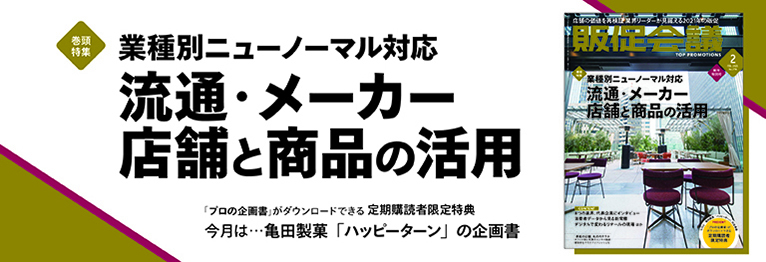
流通・メーカー 店舗と商品の活用
2020年は新型コロナウイルスにより消費者の行動が大きく変化。それに対応するために、各業界の販売方法、販売促進も変化しました。デジタルに対応した新商品の販売、既存商品の新しい使われ方の提案などが挙げられます。今号は各業界におけるニューノーマルから、リテール領域のデジタル化、コロナ禍前と比較した消費者調査データなどを取り上げ、2021年のヒントになる情報を提示していきます。
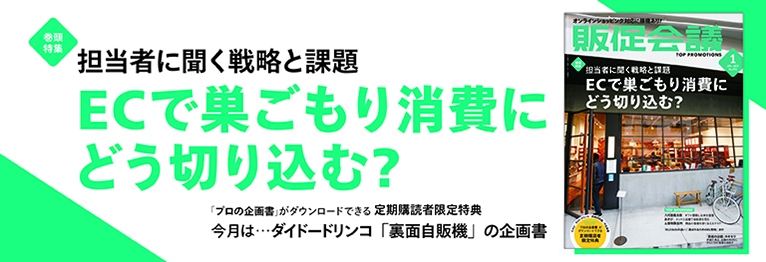
ECで巣ごもり消費にどう切り込む?
コロナ禍で加速した消費者のオンラインシフトにより、ECでの支出が増加しました。そのため、今まで店舗でしか販売をしてこなかった企業も多く参入をしている状況です。しかし、ただECサイトを立ち上げただけで売上が上がるものではありません。そこで本号では、ECを実施している企業へのアンケート、取材を踏まえて、ECでどうやって商品・サービスを販売していけばいいのか、今後の方向性について探っていきます。
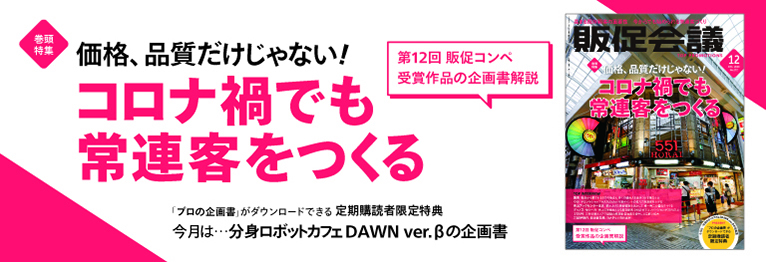
コロナ禍でも常連客をつくる
新型コロナウイルスの影響で店舗への集客が難しくなる中、既存顧客(中でも常連客)の存在は大きくなっています。本特集では、長年愛されているブランドや巧みな手法で常連客を生み出している企業の事例をもとに、今からでも始められる常連客づくりの方法を考えます。
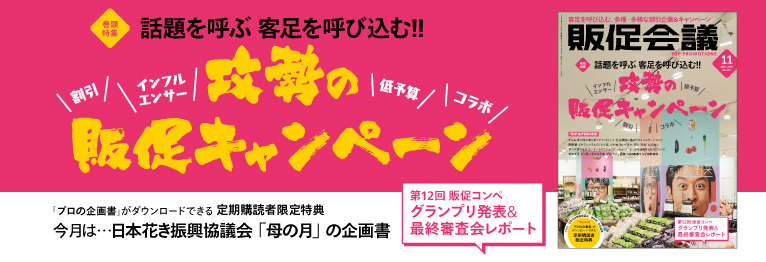
攻勢の販促キャンペーン
新型コロナウイルスの影響で消費者の節約志向が高まる中、割引販売を始めとしたキャンペーンを行う企業が増えています。本特集では、広告クリエイターへのインタビューや企業の最新事例から、「いま本当に効果を発揮するキャンペーンとはなにか」を探ります。