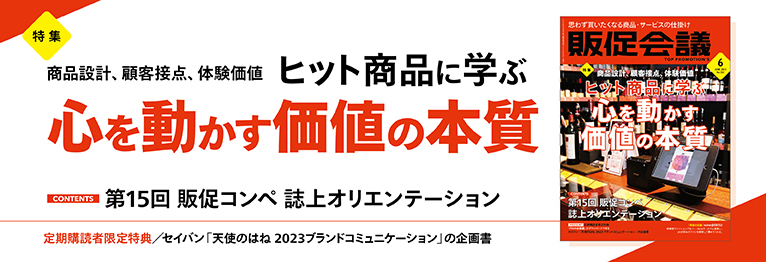
ヒット商品に学ぶ 心を動かす価値の本質
機能性はもちろん価格以上のお値打ち感、「コスパ」への対応が求められる小売の現場。しかし、機能性はコモディティ化し、激しい価格競争が繰り広げられる中で、改めて見つめ直すべきは「消費者は『何に』対して対価を支払うのか?」という、求める価値の明確化にある。ヒットした商品を分析し、現代消費者が機能・価格だけではなく、「お金を払いたくなるもの」の正体を解析する。
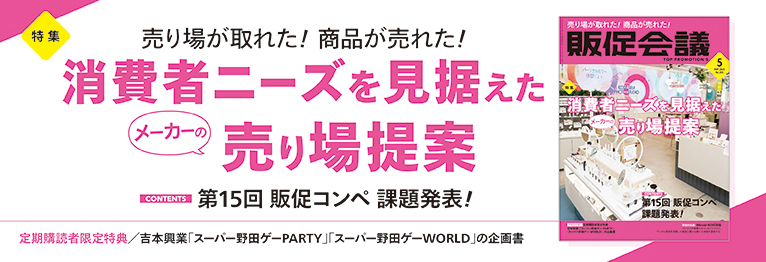
消費者ニーズを見据えたメーカーの売り場提案
コロナ禍により消費者のデジタルシフトが進む中でも、今なお店頭は最大の行動が起きる場だ。商品の買い求めやすさが売上に直結することを考えると、いかに売り場に置いてもらうか、手に取ってもらうかが重要となる。しかし、消費者の多様化により、メーカーは商品数を増やし、流通でもPB商品により力を入れるなど、売り場を確保することは以前よりも難しくなっている。一方、そうした状況下でも、新しく売り場の確保に成功し、配荷を増やしている商品も存在している。今回は、流通営業で成功した事例やプロモーションをヒットさせた商品の裏側を特集する。
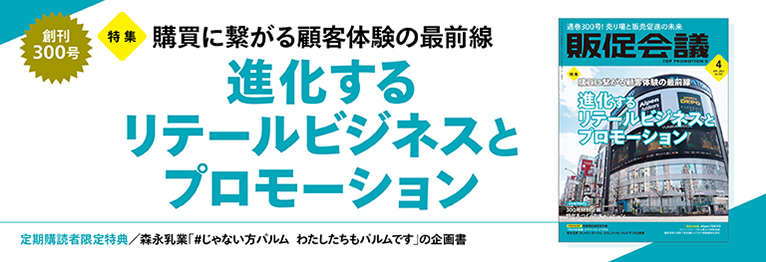
進化するリテールビジネスとプロモーション
この数年で消費者を取り巻く環境は大きく様変わりした。行動や消費が変わり、それに伴ってリテールビジネスのあり方が変わった。改めて顧客との接点や繋がりの重要性を認識する企業も増えたのではないだろうか。本特集では、10年間の消費動向データを紐解き、世界のリテールビジネスの最前線、テクノロジーによるプロモーションの進化を紹介する。
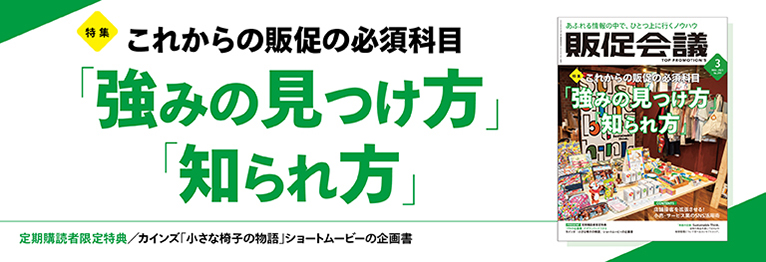
「強みの見つけ方」「知られ方」
インターネットの浸透により、商圏に縛られず自社の商品・サービスの顧客を広げることが可能になった。一方、商圏の縛りがなくなったがゆえに、商品・サービスの対象顧客の設定戦略は、より重要になりつつある。仮説設定がないままには、どんなメディアを使って、どのようなコミュニケーションをすればよいのか判断できず、買ってもらう以前の、「知ってもらう」ための戦略も立てられない。「SNSでバズって...」「口コミで話題になって...」の幻想に囚われず、知られて買われるための適切な第一歩を踏み出すアイデアを紹介する。
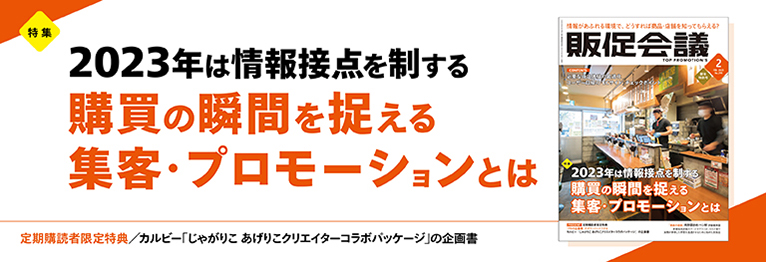
購買の瞬間を捉える 集客・プロモーションとは
かつては消費者がモノを買う意思決定は、店舗や棚の前で商品を選ぶ購入時の体験によるものが重要とされていた。今や、第0の瞬間(Zero Moment of Truth:ZMOT)と呼ばれる、インターネット上での情報接点で購買を決めるなど、商品価値を判断する瞬間は時代とともに考え方が変化してきた。生活者が浴びる情報の量・密度・質が増加する中、企業は自分たちの商品・サービスがどの接点に、どのような強みと弱点があるかを把握することが重要となる。本特集では、購買行動の起点となる「瞬間」に着目し、これからの販促プロモーションについて深掘りしていく。
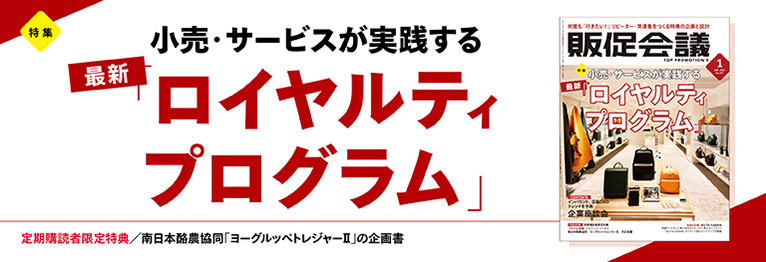
小売・サービスが実践する「ロイヤルティプログラム」
市場の成熟、価値観の多様化やメディア・チャネルの増加、サードパーティークッキーの規制。これらの変化により、新規顧客の獲得がますます難しくなり、獲得コストも上昇している。このような状況を受け、いかにリピート客を増やすか。さらには、企業はアンバサダーともなりうる真のロイヤルカスタマーをいかに増やせるかが求められている。では、金銭的なメリットだけでなく、ファンが能動的にプログラムに参加し、信頼や愛着を高めるために、企業はどのような行動を取るべきか。本特集では識者や企業への取材を通し、ロイヤルティプログラムの現状と事例を紹介する。
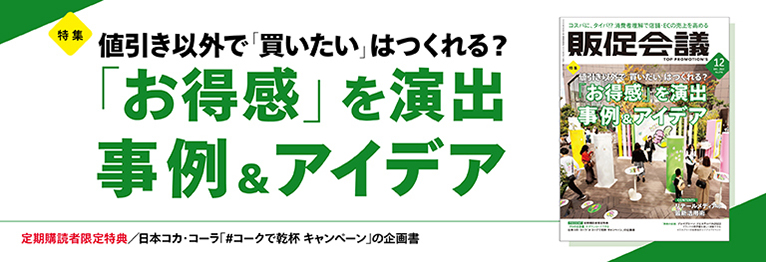
「お得感」を演出 事例&アイデア
まもなく始まる年末商戦。財布の紐が緩みがちな時期に向けて、各社のセールスプロモーションが本格化するが、現在の経済環境を考えれば、「値下げ」という手段だけに頼れない状況もある。それでは、「値下げ」以外に消費者に「お得」と思ってもらえる提案はありうるのか。お得とは、顧客がコストパフォーマンスが高いと感じてもらえている状態にあるということ。では、「値下げ」をしなくてもパフォーマンスが高いと感じてもらえる提案にはどのようなものがあるのだろうか。人の行動を喚起する、小売りの最前線のアイデアを、事例を中心に紹介する。

認知から購買まで いま、販促に活用すべきInstagram
企業の販促施策において、SNS上で購買活動につなげるための施策を展開する企業が増加。企業公式アカウントの情報をきっかけに商品・サービスを購入した経験のある消費者の割合も増えている。中でもInstagramはECをもっている企業では、ショップ機能の活用が進み、ECのない企業もキャンペーンを通じたサンプリングやUGC生成を目的としたギフティングなど販促やプロモーションにまで活用の幅が広がっている。本特集では、Instagramを通じてどのように売上や来店につなげられるのか、成功事例や有識者解説とともに紹介する。
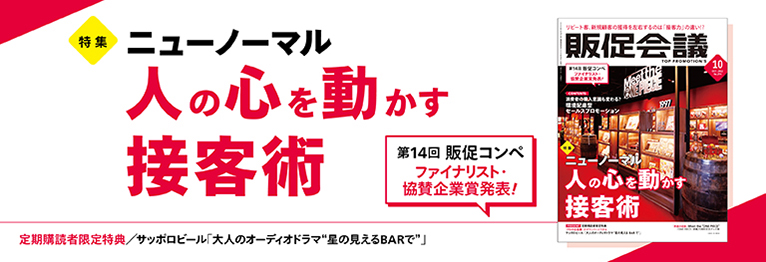
ニューノーマル 人の心を動かす接客術
オンラインでのコミュニケーションが勢いを増す昨今だが、重要視されているのはきめ細かな接客だ。小売店においては、接客が差別化の難しい「モノ」に付加価値を提供する重要な要素となる。また、サービス業では接客の質がすなわちサービスの質に直結する。そのため、小売・サービス業における接客は重要な競争軸となっている。そこでしか体験できないサービスは、強い求心力となり、接客も立派なプロモーションとなる。「接客力」は売り上げを高めるためには不可欠であり、顧客対応はリピート客や新規顧客の獲得を左右する。では、そうした豊かなサービスのために、リアル&デジタルにおける接客は、どのような取り組みが進んでいるのだろうか。本特集では、リアルとデジタルそれぞれにおける新しい接客のあり方について紹介する。
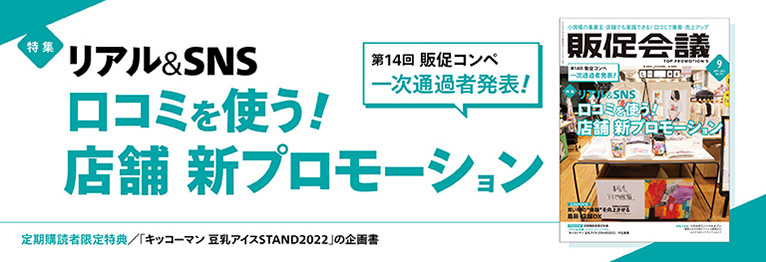
口コミを使う! 店舗 新プロモーション
消費者の購買意思決定において、第三者の発信が与える影響はますます高まっている。特に、景況が芳しくない市場環境の時ほど、消費者の「失敗したくない心理」が高まり、慎重に口コミ・レビューを精査してから買い物をする人たちも増加傾向にある。一方、昨今の口コミをめぐる状況では、良い商品づくりに注力し、サービスレベルを高める努力などの正攻法以外の戦略や技術を学ぶことも重要ではないだろうか。小規模の事業主・店舗でも口コミを味方にするために、日々のビジネスの中で実践できることを事例をもとに紹介する。
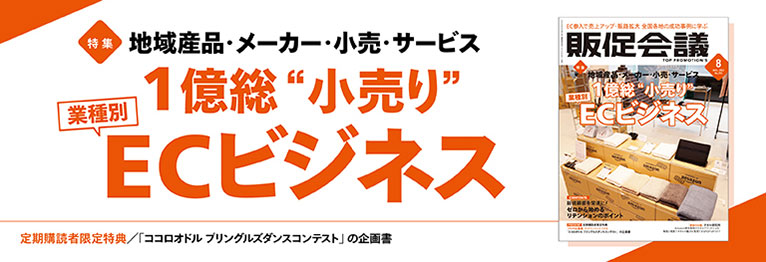
1億総『小売り』ECビジネス
日本においても100年以上の歴史を持つ通信販売。この通販にECという販売チャネルが広がり、また各種ECプラットフォームが増加したことで、より多くの事業者が参入しやすい環境が整った。特にコロナ禍では、これまで店舗外での販売に挑戦していなかった飲食、サービス、小売など、様々な業種による新規参入も相次いだ。一方で、ECを難しく考えたり、思うように売上や集客につながらない「EC初心者」の声も多く聞かれる。本特集では、全国各地のあらゆる業種別の事例や識者たちの見解を元に、「初めてのEC事業」を成功に導くヒントを紹介する。
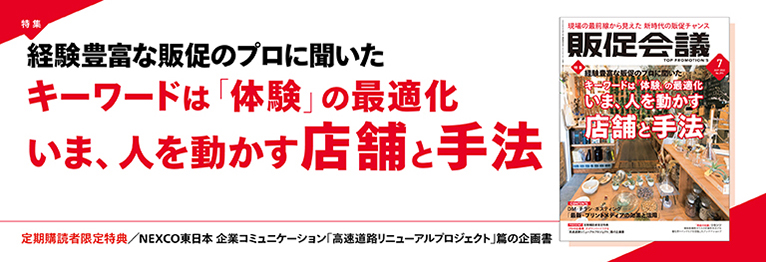
キーワードは「体験」の最適化 いま、人を動かす店舗と手法
コロナ禍以降、消費者接点の多くが店頭からデジタル環境へシフトし、販促を取り巻く環境も目まぐるしく変化している。一方で画面上では得られないリアルな体験への反応の高まりも見られ、消費者がモノを「買う」という意思決定は、機能的価値から情緒的価値による判断へと変化している。こうした中、オンライン・オフライン問わず販促に求められるのは「生活者の心を動かす体験を提供する」ことにあるのではないか。これから先の戦略を描くにはどうしたらよいか。本特集では販促の最前線を支えるプロたちに販促の潮流とトレンドについて聞き、いま、人を動かす店舗と手法を探っていく。
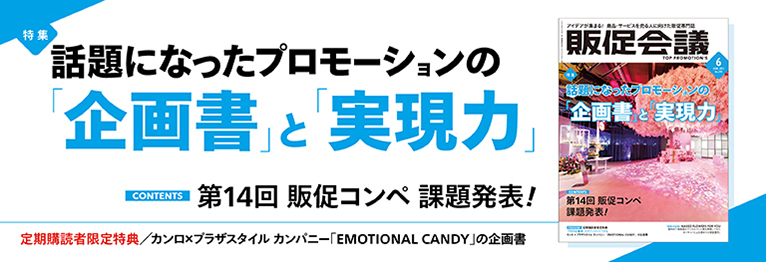
話題になったプロモーションの「企画書」と「実現力」
話題となったプロモーションも、もともとは形のないアイデアから始まっています。斬新なアイデアが求められることが多い中、そうしたアイデアの企画から実現までの道のりは容易ではありません。アイデアを形にするために重要となるのが「企画書」であり、社内外のステークホルダーを巻き込こみ、調整し、実現させる「実現力」です。本特集では企画、実行にフォーカスをあてながら成功までの舞台裏に迫ります。
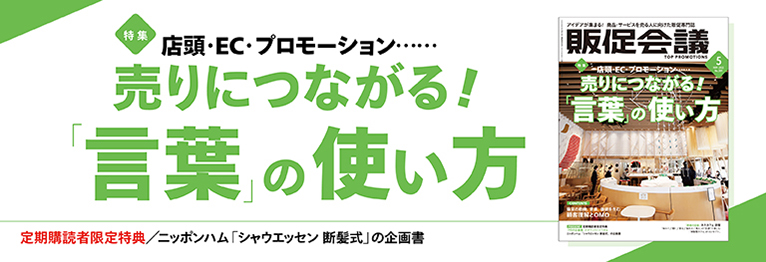
売りにつながる!「言葉」の使い方
コロナ禍により、販売チャネルもコミュニケーションチャネルも大きく変化しています。販売促進においても従来の店頭やチラシ、DMでのコミュニケーションに加えLP、バナー広告、メルマガなど担当領域が広がっているのではないでしょうか。そうした中、どの領域においても人の行動を喚起するための「言葉」の重要性が高まっています。本特集では販促現場に必要とされている「言葉」について買い場・ツール別に紹介します。
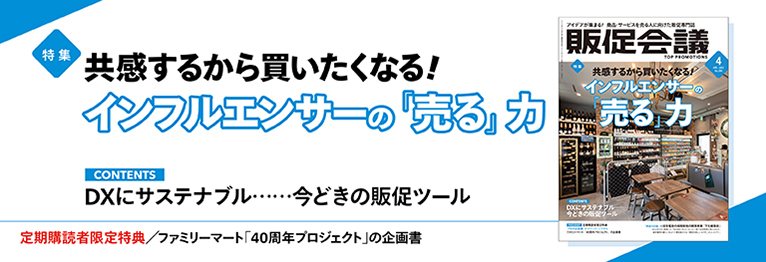
インフルエンサーの「売る」力
あらゆる商材においてSNSが生活者の購買行動に大きな影響を与える中、ますます注目を集める「インフルエンサー」を起用した販売促進。YouTubeやInstagram、TikTokといったSNSで強い影響力を持つインフルエンサーは、なぜ支持をされるのか?フォロワーたちの買うきめ手とは何か?そしてその影響力を販促に活かすポイントとは。プラットフォーム別のプロモーション手段や、消費者の共感した瞬間の「欲しい」を逃さない方法を紹介する。
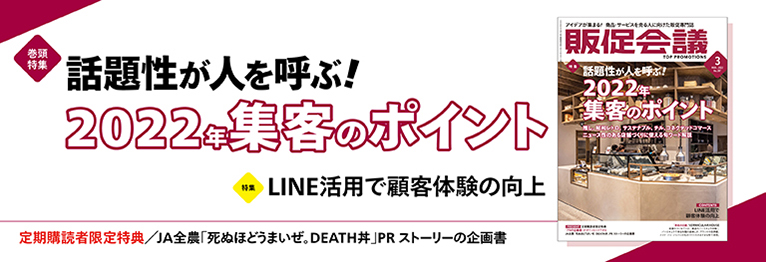
旬を演出する8つの注目ワード
店舗はモノを売るだけでなく、消費者にメッセージを届ける「メディア」としての役割も担っています。店舗を「メディア」として捉えたとき、常に「旬」なニュースが発信されている演出を施すことで、店舗イメージの鮮度を保ち、「いま行きたい」という消費者の動機をつくります。では、店舗のニュース性を高めるような「旬ワード」にはどのようなものがあるのでしょうか?販促企画・施策に生かせる8つの旬ワードを解説していきます。