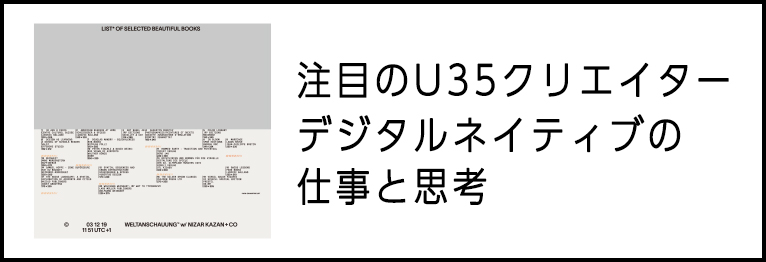
注目のU35クリエイター デジタルネイティブの仕事と思考
東京五輪が開催され、新しい年代が始まる2020年。あらゆるシーンで新しいクリエイティブの力が求められる年になりそうです。そんな年の初めとなる今号、ブレーンでは4年ぶりとなる「U35 クリエイター」を特集します。35歳以下のクリエイターによるプロジェクトチームを中心に、そのクリエイティブ観、働き方に対する考え、どこを目指しているのかなどを取材しました。その他、54名のクリエイターたちにもアンケート形式で回答をいただきました。
クライアントの皆さんはもちろんのこと、一緒に働くクリエイターの皆さん、そしてデジタルネイティブとは普段あまり接点のない皆さんにも、ぜひご覧いただき、新しい世代との出会いのきっかけとして、ご活用いただきたいと思います。
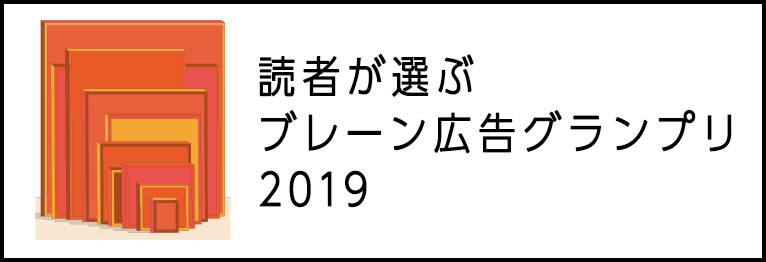
読者が選ぶ広告グランプリ2019
令和という新しい時代を迎えた2019年、あなたにとって「ベスト広告」は何でしたか?ブレーン編集部では、今年も「読者が選ぶ広告グランプリ」アンケートを実施しました。学生、クリエイターの皆さん、さらには広告主の皆さんまで、さまざまな立場の方が選んだ「ベスト広告」を集計。その中から2019年のベスト5を選び、ここで発表します。今年も編集部のトーク形式で、読者の皆さんから寄せられたコメントと共に2019年の広告、そしてトレンドを振り返っていきたいと思います。広告を取り巻く環境がどんどん変化し、さらに進化する中で、2019年のさまざまな出来事を見つめ直し、来たる2020年を迎えるための準備として、この特集を活用いただければと思います。
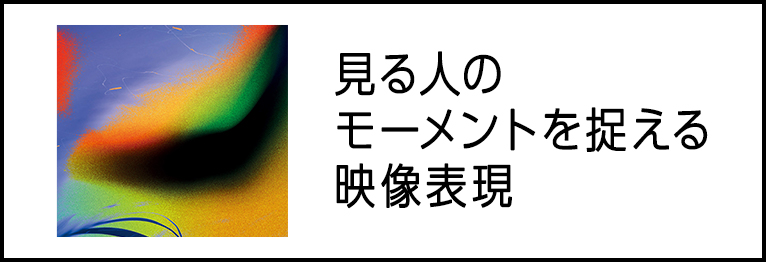
見る人のモーメントを捉える映像表現
この1年くらいの間に、駅や電車、施設内にはサイネージが急増、家のテレビやスマートフォン以外でも映像を目にすることが当たり前になってきました。それに伴い、最近ではテレビCM、バンパー動画、SNS用の動画というように、映像をメディアやデバイスに合わせて新たに制作したり、編集することも増えていると聞きます。さらにはバンパー広告を専門とする会社が誕生し、スタートアップ向けのテレビCM出稿サービスが生まれたり、ビデオグラファーという新しい肩書を持つ人たちも登場。まさにいま、広告の映像を取り巻く環境や制作の体制が大きく変わりつつあります。そこで今号では、CMや動画に関連する新しい動きを捉えると同時に、映像において新たなる試みに挑んだクリエイティブを紹介します。CMにとどまらず、多様な動画の活用に向かう現在、そしてこれからの映像表現を考える上で何が求められるているのかを考えていきたいと思います。
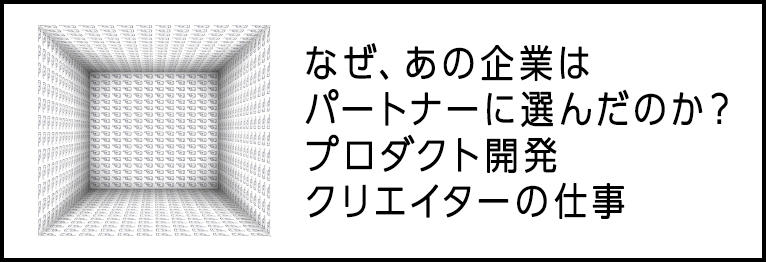
プロダクト開発 クリエイターの仕事
新しい商品の開発は、企業やお店にとって常に大きな課題です。特に現在のように新しい商品が次々と生まれる中で、消費者の印象に残る商品、さらには購入してきちんと使ってもらえる商品を生み出すのは至難の業。技術やデザインの新規性、ユーザビリティはもちろんのこと、最近ではリサイクルやエコも視野に入れて考えていく必要があります。こうした現状の中、本特集では新しい視点で開発されたプロダクトやサービスに着目。企業とクリエイターがパートナーになり、二人三脚で開発した商品だけではなく、クリエイターの提案によって生まれたプロトタイプがどのように活用され始めているのか。その2軸で、開発までのプロセスとクリエイティブを紐解きます。
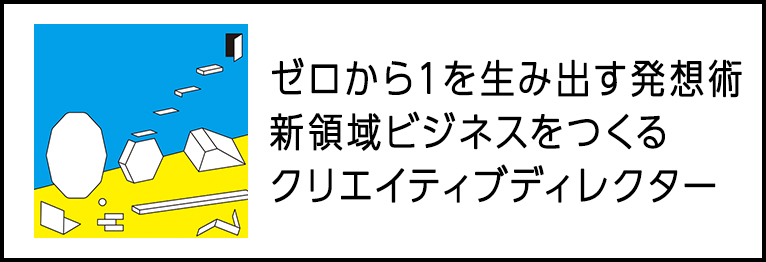
新領域ビジネスをつくるクリエイティブディレクター
従来は「広告およびコミュニケーションのクリエイティブ全体を統括し、実現する人」として位置づけられてきたクリエイティブディレクター。近年はコミュニケーション領域の広がりと共に、その活動領域や手がけるクリエイティブの範疇が変わってきています。新規事業や商品の開発はもちろん、経営、インナー活性化、人事や総務にまつわることなど、これまで企業や社会の表には見えなかった部分で、いまクリエイティビティが必要とされています。今号には、こうした領域を切り拓いている8組のクリエイティブディレクターが登場。いまの時代に求められる「クリエイティブディレクション」とは、どういうものであるのか。その定義を聞きました。
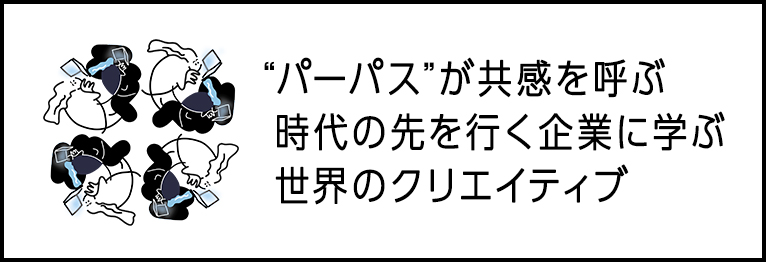
時代の先を行く企業に学ぶ 世界のクリエイティブ
世界最大級の広告祭であるカンヌライオンズは、2018年に会期や部門などを大きく刷新。今年も新たに2部門が設けられるなど、広告界の動きに合わせて変化し続けている。エントリーされる作品は、いずれも大きな成果をあげたブランドキャンペーンや最先端の手法で制作されたクリエイティブなど。そこには、新たな切り口やアイデアを見ることができる。近年は社会課題が大きなトレンドになっているが、いまも変わらずカンヌライオンズは、広告界にとっての新しいケーススタディが溢れる場であることは間違いない。
その現場に行かずとも、受賞およびエントリー作品や審査員が何を語ったかを知ることは、これからの広告を考える上での大きなヒントになるはずだ。本特集では今年のカンヌライオンズの受賞作品を振り返るともに、参加者や審査員による作品・セミナーの分析と解説を紹介する。
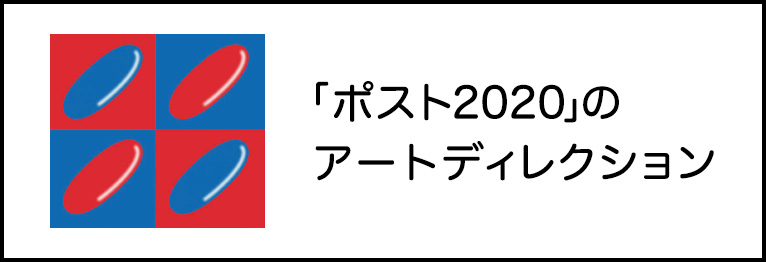
「ポスト2020」のアートディレクション
2000年代前半、広告界では佐藤可士和さんを筆頭にアートディレクターの仕事が広く世の中から注目されるようになりました。新聞広告やポスターを作ることのみならず、OOHでのダイナミックな展開やグッズ・商品開発、さらにはブランドや企業のCIなどまでを手がけ、アートディレクションの可能性とアートディレクターの関わる領域が大きく広がっていきました。
さて、そこから20年近くを経た現在、広告のメディアは大きく変わっています。ポスターからサイネージへ、そしてWeb、さらにはスマートフォンで見るSNSでの広告や動画、プロダクトなど、アートディレクションの表現領域がさらなる広がりを見せています。向き合わなくてはいけない領域やメディアが増える中で、今アートディレクターたちはどんな考えで、自身のアートディレクションを確立しようとしているのか。本特集では、30~40代のアートディレクター9人に、今、そしてこれからの「アートディレクション」について聞きました。
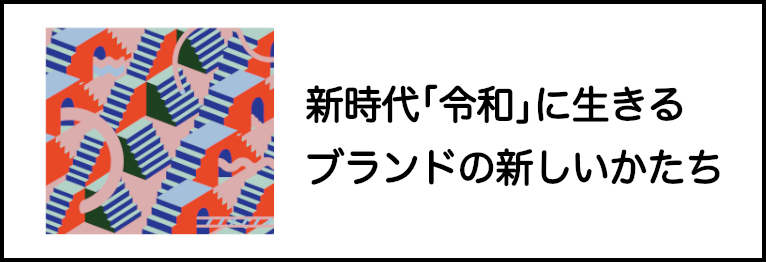
新時代「令和」に生きる ブランドの新しいかたち
時代や社会の流れの中で、企業やブランドがそのあり方を問われている昨今。さまざまな背景や事情からリブランディングし、新たなかたちでスタートを切る企業やブランドが出てきている。これまで培ってきたものを生かして新たなかたちを築き上げるブランドがある一方で、これまで培ってきたものを潔く捨てて、ゼロに近い状態から立ち上げているブランドもある。一つとして同じやり方ではできないのが、リブランディングだ。
本特集では、さまざまな背景から、リブランディグに取り組んだ6つの事例を紹介。それぞれの考え方とクリエイティブの進め方を見ていきたい。
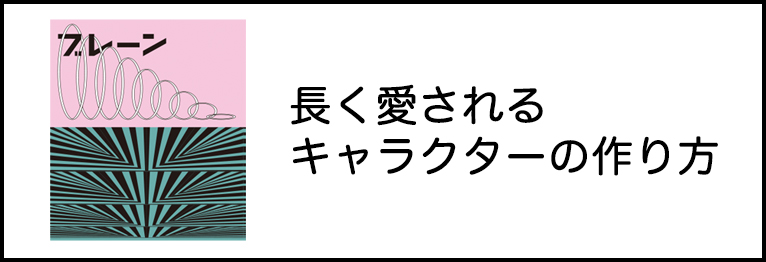
長く愛されるキャラクターの作り方
かつて企業にとってキャラクターは、主にパッケージや販促プロモーションにおいて活用され、それらは「動かず」「話さず」アイキャッチとして大きな役割を果たしていました。近年は企業のSNSの活用と共に、キャラクターは従来の役割を超えて企業のメッセンジャーとなり、企業と生活者をつなぐ存在としても大きくなってきています。企業を取り巻く環境やメディアが変わる中で、広告などのコミュニケーションにおいて、今キャラクターはどのような役割を果たしているのでしょうか。
今号では、人気キャラクターたちがどのようなプロセスで生まれ、なぜ長きにわたり愛されているのかを探ると同時に、従来のキャラクターとは異なる活用方法や展開、そしてデジタルの進化と共に生まれた新たなキャラクターまでを取材。見た目も人格も運用方法も多様なキャラクターたちの生みの親に話を聞きました。
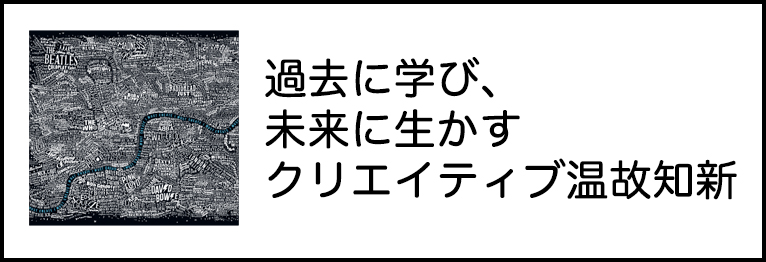
過去に学び、未来に生かす クリエイティブ温故知新
「ブレーン」では昨年、700号を迎えたことを機に、現在のクリエイティブに通じる礎となった日本の広告(CMとグラフィック)を、第一線で活躍するクリエイターの皆さんと振り返る機会を設けました。今のようなデジタルの技術もSNSもない時代に、多くの人々の心を捉え、また動かしてきた広告。そこにはどのようなアイデアとメッセージがあったのか。これらの広告を改めてきちんと見ること。そして、その本質を学ぶこと。それはメディアや手法が多様になった現在であっても、これからのクリエイティブを考える上での多くのヒントになるのではないかと私たちは考えました。本特集では、6組のクリエイターたちがそれぞれの視点で時代を代表するクリエイティブ、自身が影響を受けたクリエイティブをその時代背景と共に紹介します。
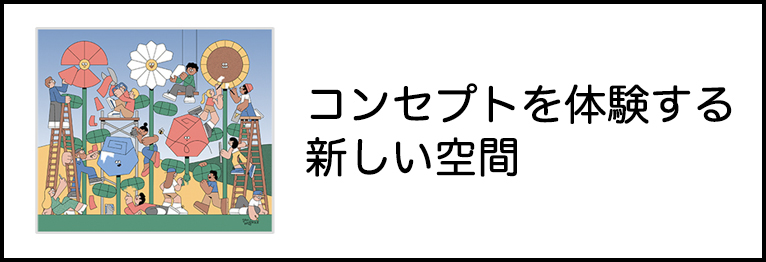
コンセプトを体験する新しい空間
デジタル上に大量の情報が流通し、捉えきれなくなっている今だからこそ、リアルな場での体験が重要性を高めている。そうしたオフラインのコミュニケーションにおいて、企業やブランドはどのように発信したいメッセージをコンセプトにまとめ、提供したい体験を空間に落とし込んでいるのか。本特集では、従来の店舗や施設での体験を刷新する新業態から、新しい切り口でスポーツの魅力が体験できるイベントまで、具体的な事例を通じていま求められる空間を紐解いていく。
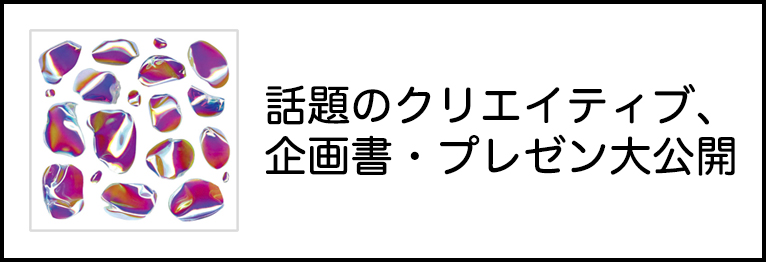
話題のクリエイティブ、企画書・プレゼン大公開
あらゆる仕事において求められる、企画書やプレゼンテーション。広告業界でも、そのスキルの重要性は言わずもがなです。その正攻法を知ろうにも、他の人がどのように考え、作っているのか、なかなか知る機会はありません。そこで今月のブレーンでは、第一線で活躍する広告クリエイターの企画書・プレゼン術を大公開。グラフィックからムービー、イベント、デジタルプロモーションと話題になったクリエイティブが実現されるまでのプロセスを紹介します。
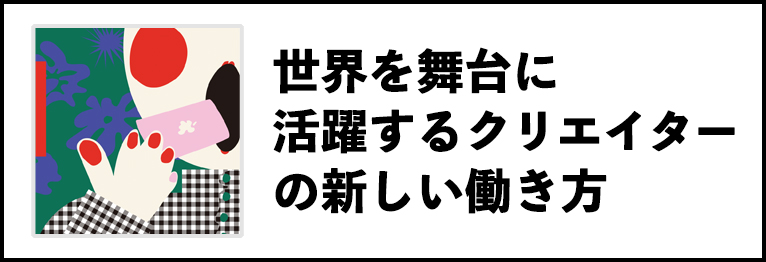
世界を舞台に活躍するクリエイターの新しい働き方
ビジネスにおいても、コミュニケーションにおいても、日本と世界の境界線はなくなりつつある。クリエイティブの仕事にあっても、日本と世界を自由に行き来しながら仕事をすることや、日本にいながら世界のさまざまなクライアントと仕事をする働き方は、もう遠い未来の話ではなくなっている。日本の中だけに閉じこもらず、世界のクライアントと積極的に仕事をしたいと思った時、そこには一体どんな選択肢やスタイルがあるのか。本特集では、先んじてこうした新しい働き方を考え、実践しているクリエイターたちに取材。さまざまな「海外の仕事」のあり方を紹介していく。
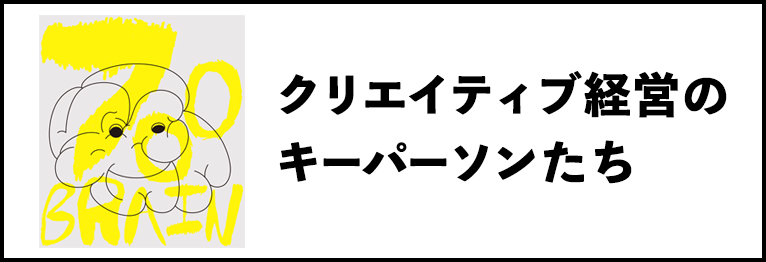
クリエイティブ経営のキーパーソンたち
「デザイン経営」という言葉に象徴されるように、企業にとってクリエイティブの重要性がかつてないほど高まっている。世の中を見渡しても、いま注目され、成功している企業は、商品開発、コミュニケーション、新規事業、あるいはユニークな社内制度まで、全方位的にクリエイティビティを発揮し、新しいチャレンジを重ねている。こうした企業の中には、必ず自らアイデアを考え、常識や前例にとらわれない判断をし、時には外部パートナーの力をうまく借りながら実現していくキーパーソンがいる。
この特集では、アイデアとクリエイティブの力を信じて事業に生かす、各社のキーパーソンを訪ねた。インタビューの最後に皆さんからいただいた「クリエイターに期待する提案」にも、ぜひご注目ください。
広告を超えて広がる言葉の現在形
企業コミュニケーションの中で「言葉の力」が求められる場面が広がっている。例えば、企業スローガンや事業コンセプト開発、スタートアップのミッション開発など、組織やチームメンバーの意識を統一し指針となるような“インナー”向けの言葉。一方で、メディアで引用され、SNSで拡散する、世の中で話題化させる際の“見出し”となる言葉もまた求められている。それに伴い、コピーライターの活躍する場面は広がり、同時に求められるスキルも変化しているようだ。本特集では、現在の企業コミュニケーションの中で求められる新しい言葉のあり方とそのクリエイティブを取材。広告と言葉の最前線に迫る。
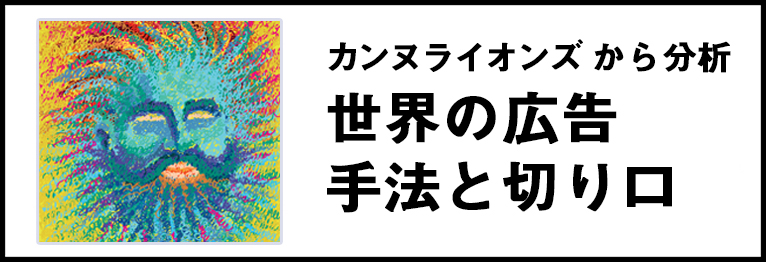
カンヌライオンズから分析 世界の広告 手法と切り口
世界最大級の広告賞であるカンヌライオンズでは、毎年、最先端の手法を使った広告や、社会課題に取り組むための新たな切り口、大きな成果を上げたコミュニケーションなどが表彰され、最新のケーススタディとして共有される。セミナーではマーケティングの潮流や広告の課題が語られ、世界の広告界が向かう方向性を大局的に把握する機会となる。日本では「世界と日本では環境が違う」と考える人も少なくないが、カンヌが事例や企画の宝庫であることは間違いない。今年の特集では、カンヌへの参加経験が豊富なクリエイターの協力を得て、受賞作を手法・切り口別に分析。仕事に生かすためのポイントを話してもらった。