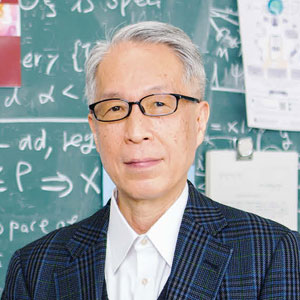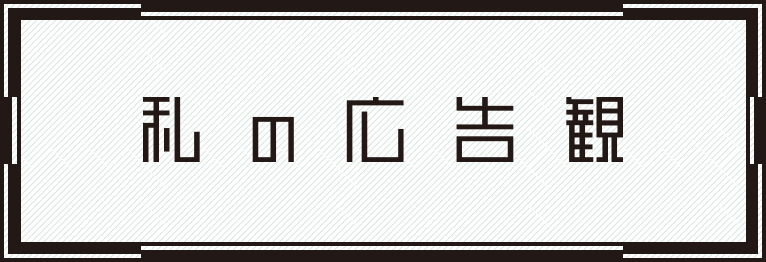「量子ウォーク」研究の世界的第一人者として知られ、この春から横浜国立大学名誉教授となった今野紀雄氏。「数学の魅力を広めたい」という強い思いから無意識に実践していたという同氏の“セルフマーケティング”とはどのようなものなのか、話を聞いた。
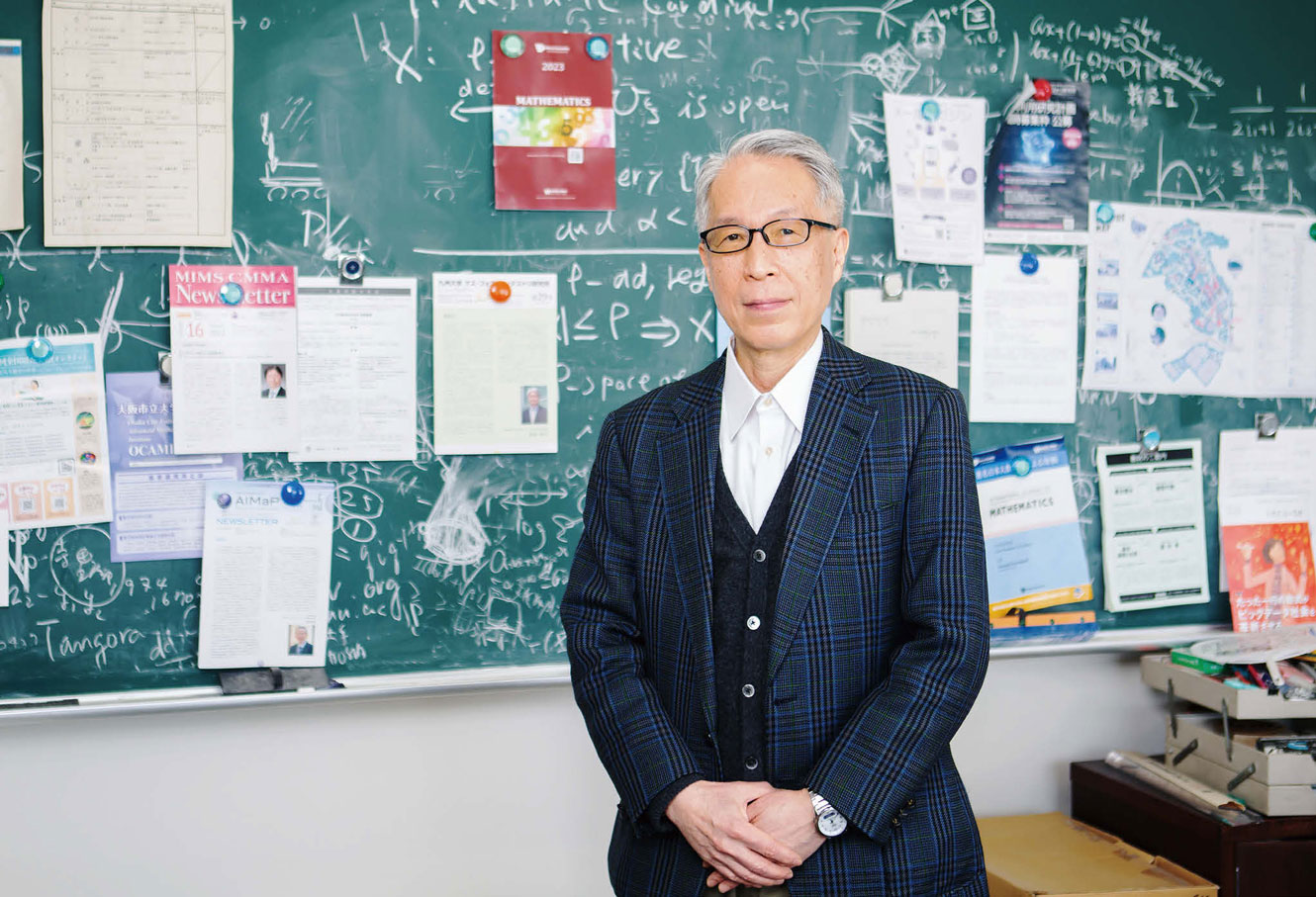
今野紀雄(こんの・のりお)さん
東京大学理学部数学科卒業、東京工業大学大学院理工学研究科博士課程単位取得後退学。博士(理学)。2005年より横浜国立大学大学院工学研究院教授。現在は同大学名誉教授、立命館大学客員教授。研究テーマは、量子ウォーク、無限粒子系、複雑ネットワーク。2018年日本数学会解析学賞受賞。著書に『量子ウォーク』(森北出版)、『無限粒子系の科学』(講談社)、『量子ウォークからゼータ対応へ』(日本評論社)、『図解雑学 確率モデル』(ナツメ社)、『マンガでわかる統計入門』(SBクリエイティブ)など多数。
既存のテーマの組み合わせが新たな研究領域の発見に
数学者で横浜国立大学名誉教授の今野紀雄氏。主な研究テーマに「量子ウォーク」「無限粒子系」「複雑ネットワーク」などがあり、2002年からは「量子ウォーク」の研究に特に力を注いできた。
2008年に「量子ウォーク」の領域における日本で最初の専門書を出版。以降これまでに同領域では8冊もの書籍が出版されており、それらはいずれも今野氏自身と今野氏の元で学んだ学生による著書だ。日本における「量子ウォーク」の第一人者として、教鞭を取りながら、学生と共に研究に勤しんできた。
確率的に不規則・無作為(ランダム)に点が移動する「ランダムウォーク」という現象があり、この「ランダムウォーク」の量子版モデルが「量子ウォーク」とされている。
今野氏が「量子ウォーク(※当時は“量子ランダムウォーク”と言われることも多かった)」に着目したきっかけは、新たな研究テーマを探していた2002年に、試しに「量子」と「ランダムウォーク」という2分野のキーワードを並べてインターネットで検索したところ、数本の量子情報系の論文が出てきたことだった。数学的にはまだ掘り下げきれていない領域であり、今後様々な分野を横断的に関連付ける研究テーマに発展していくであろうと可能性を感じたことから、このテーマを研究することに決めたという。
日頃から視野を広く保ち、専門領域以外のことにも興味を持ってアンテナを張ることを心がけているという今野氏は、「量子ウォーク」の研究のきっかけを振り返り、「結びつける」という発想がブレイクスルーのきっかけとなると話す。
「特許の分野でよく消しゴムと一体型になった鉛筆のエピソードが例えとして挙がるかと思います。鉛筆と消しゴムという、もともと存在していたバラバラのものをひとつに結びつける発想により、ヒットしました。私の『量子ウォーク』の発見も“結びつける”ことで自分の中でブレイクスルーが生まれた。新しいものをいきなりゼロから生み出すのは至難の業です。既存のものを組み合わせるところから始めたとしても、十分に新しい発見はある。アイデアとはそういうものだと思います」。
さらに学術的な研究領域では、発見したものに対してスピード感を持って研究し、いち早く公表して専有...