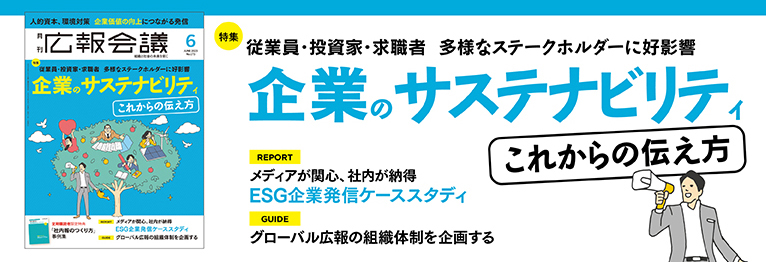
企業のサステナビリティ
企業が持続成長に向け、経済活動と環境・社会課題の解決を両立する。その実現にあたっては、組織の内外に向け、正しく情報を伝えていくことが問われます。社内への方針浸透から、成果・課題についての積極的な発信、外部環境の把握など、いま広報部門に期待されている役割や、取り組み事例をレポートします。
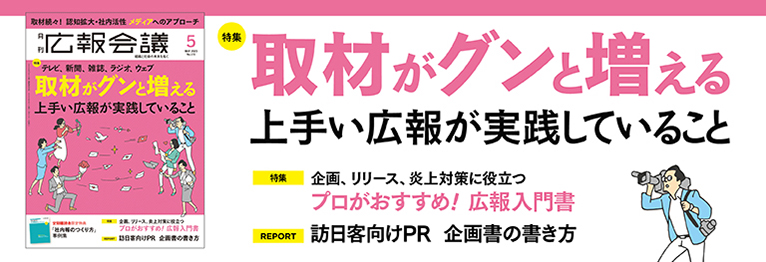
取材がグンと増える上手い広報が実践していること
広報担当者の主要業務であるメディアリレーション。取材が続々と集まると、認知が拡大するだけでなく、社内の活性化にもつながります。継続的にメディアへ出演をしている企業や自治体は、どのような広報活動を実践しているのでしょうか?メディアが関心を持つきっかけは様々。どういったアプローチが取材に結びついたのか、レポートしました。
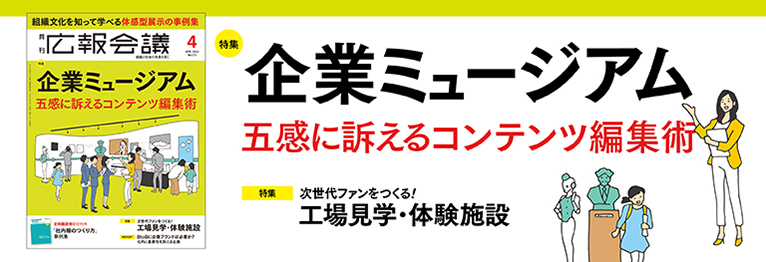
企業ミュージアム 五感に訴えるコンテンツ編集術
「企業ミュージアム」を訪れると、企業が伝えたいメッセージを表現した五感に訴えるコンテンツをたくさん目にすることができます。広報活動において欠かせない企業コンテンツの編集術を学ぶにはぴったりの場所。昨今は、従業員のエンゲージメントを高める空間としても注目されています。
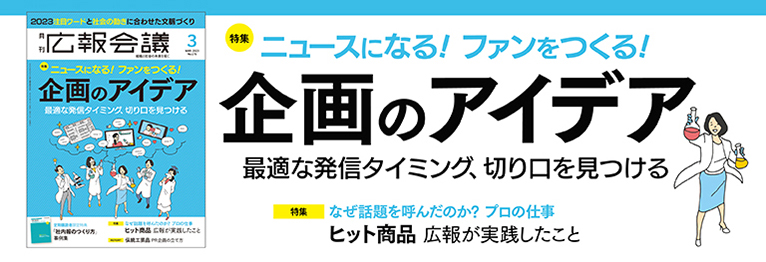
企画のアイデア
「他部門からの依頼を受けて発信する、受託仕事になってしまっている」。そんな悩みが多いのが、商品・サービスに関する広報活動です。しかし、メディアや世間の関心が高まりそうなテーマや最適なタイミングなどを事前に洗い出しておけば、より戦略的な広報が可能になります。本特集では、今注目しておきたいキーワードや出来事、生活者の心理の変化などをレポート。広報の切り口を見つけるヒントをお届けします。
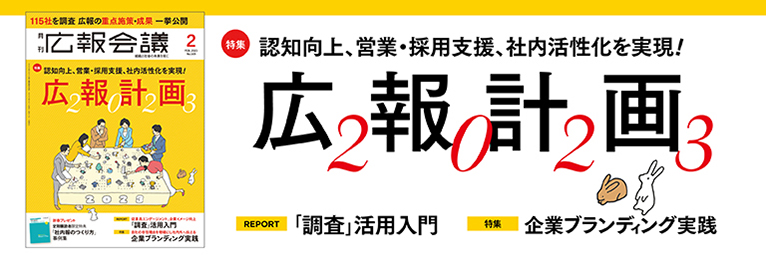
広報計画2023
年初に広報計画を立てることで、企業ブランド向上や営業・採用支援、社内活性化など、社会や経営へのインパクトにつながる活動が実践しやすくなります。重点施策を決めるにあたっては、自社の経営方針を理解するだけでなく、他社が取り組んでいる広報活動についても知り、視野を広げておきたいところです。そこで本特集では、広報部門の担当者に広報の方針や体制づくり、課題、成果などを調査しました。広報計画を立てる上でのヒントにしてください。
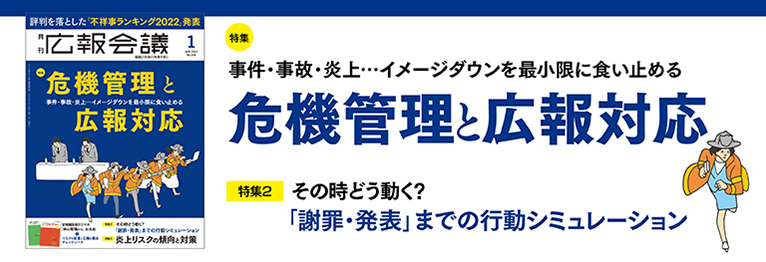
危機管理と広報対応
企業イメージ低下に直結する不祥事。それはどんな組織でも起こり得るものです。しかし、その後の命運を分かつのは、発覚後の対応といっても過言ではありません。イメージ悪化を食い止めるか、それともイメージの失墜を招いてしまうのか。本特集では、事例を紐解きながら、危機管理広報について考えます。
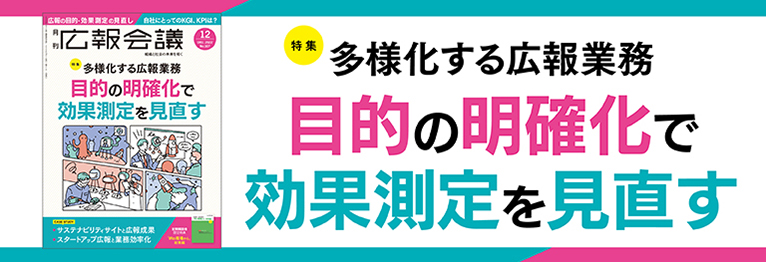
目的の明確化で効果測定を見直す
「広報活動の成果」を問われた時、簡単に計測できるデータだけを収集していないでしょうか。成果を出すための近道は、自社における広報の目的を明らかにし、そのために何をすべきかを起点に目標を設定すること。そして現在地を把握しながら行動を最適化することにありそうです。今や広報の業務は、メディアリレーションにとどまらず、オウンドメディアを通じたESG情報の発信や、ウィズコロナで一体感を高める社内コミュニケーションなど、多様化、複雑化しています。自社に必要な施策を選び取り、実行、改善していくために、広報の目的や効果検証する際の指標について考えていきます。

BtoB広報の実践
企業が提供する価値や目指す方向性を、社内外のステークホルダーに対して広く正しく伝え、支持を得ていく。こうした広報活動が、BtoB事業をメインとする企業においても重要になっています。その背景には、サステナビリティへの意識の高まりがあり、企業の信頼度を高めるコミュニケーションが欠かせなくなっています。しかし、複雑で専門性の高い事業を扱う企業にとって、その情報発信は容易なことではありません。どのような切り口や手法が考えられるのでしょうか。広報事例を紹介するほか、広報担当者の疑問に専門家がアドバイスします。
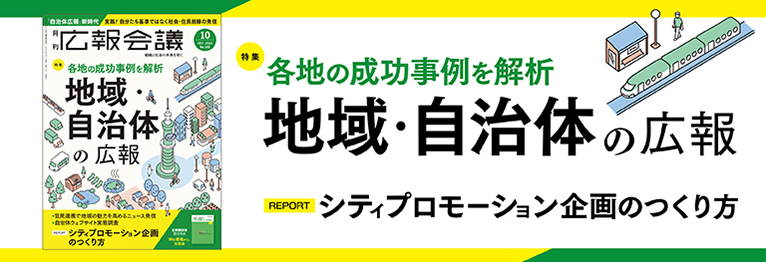
地域・自治体の広報
地域の活性化や対外的なイメージアップを狙った広報活動において、どのような話題づくりや仕掛けを行っていけばいいのでしょうか。メディアがポジティブに取り上げている地域の取り組みを紐解いていくと、地域にある資源、そして世の中の潮流や関心をしっかりと把握し、訴求したい内容を可視化していることが分かります。また、活動を一部に閉じず、関係機関の協力をあおぎ、民間企業や住民からの支援が得られるようなコミュニケーションが行われています。本特集では、各地の事例を分析していきます。

消費者主導で広がる!SNSの広報戦略
SNSユーザーによる投稿は、企業や商品の評判に影響を及ぼします。ポジティブな投稿が生まれ、拡がり、マスメディアで取り上げられるとさらに話題化していきます。また、SNSユーザーの声から事業アイデアが生まれることもあります。こうした良い流れを生み出すためには、どのようなコミュニケーションを設計していけばいいのでしょうか。今のSNS環境や消費者の心理をふまえたうえで、SNSの活用の仕方を考えていきます。
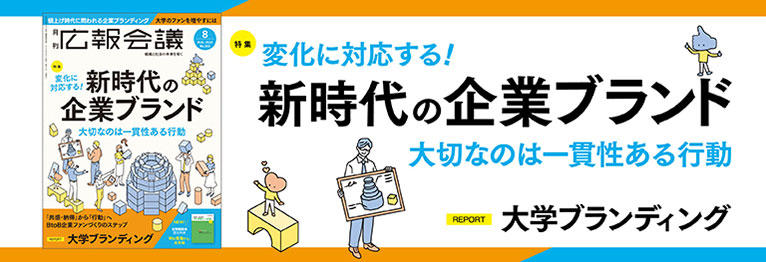
変化に対応する!新時代の企業ブランド
コロナ禍に加え、物価高による影響も出ている昨今。環境変化に伴い事業やサービス内容の変更・改善も行われています。そうした変化の中で、スーテークホルダーからの信頼を維持するには、組織の言行一致が重要になります。事業やサービスの背景にある、企業の存在意義を様々な接点で発信できているでしょうか。企業が目指す姿を社内で日常的に意識しながら行動できているでしょうか。企業ブランドを育てていくには、企業の実態や、どのようなイメージを持たれているか客観的に把握し、社内外のコミュニケーションを円滑にする、広報の役割が欠かせません。
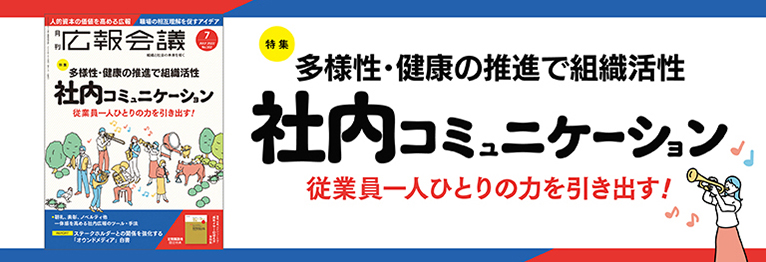
多様性・健康の推進で組織活性 社内コミュニケーション
働く一人ひとりが仕事に誇りを持ち、自発的に動き、力を最大限に発揮する。組織の中で刺激し合い、価値を生み出し、生産性を高めていく。そうした良い循環を生み出すために、広報担当者は重要な役割を担います。組織全体を見渡し、会社の方針・ビジョンが正しい文脈で伝わっているか。社内にいる多様な人材が対話し、相互理解を促す機会が設けられているか。心身ともに健康でいられる企業文化を醸成、発信できているか。そうした視点で社内コミュニケーションを再点検します。
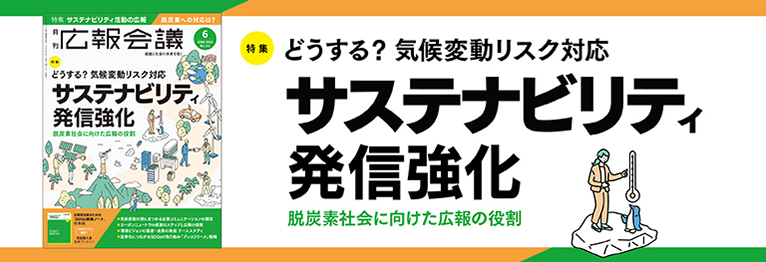
サステナビリティ発信強化
気候変動リスクへの対応については、投資家や取引先をはじめとした要請を受け、また市場の競争優位性を保つためにも、積極的な発信が迫られていますが、まだ着手できていないという企業もあるでしょう。一方で国連のIPCCは「このままでは世界の平均気温の上昇を1.5度以内に抑えられない」と発表。「早急な対応」を呼びかけています。環境課題に対し、企業広報はどのように向き合っていけばいいのでしょうか。持続可能な社会に向け、これまで培ってきたコミュニケーションの知見をどのように活かすことができるでしょうか。
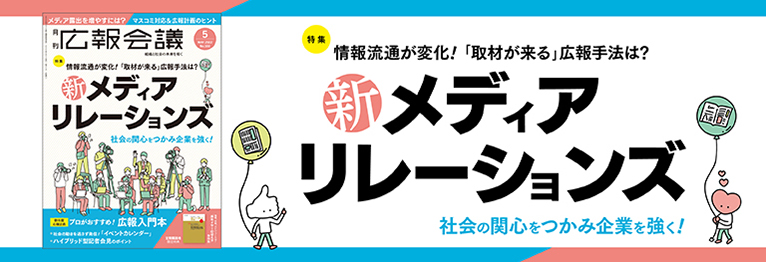
新・メディアリレーションズ
コロナ禍でリアルな接点が減り、従来どおりのメディアとの関係構築が難しくなった、という声が聞かれます。SNSやオンラインセミナーを介して記者とコミュニケーションをとったり、オウンドメディアを有効活用しながらメディア戦略を考えたりする動きも出てきています。特集1では、そうしたメディアリレーションズの変化に加え、新しく広報関連の仕事に就いた方が押さえておきたいメディア対応の心得についてお届けします。続く特集2では、継続して取材が来ている企業のケーススタディ、特集3ではコロナ禍に対応した記者発表会についてレポートします。
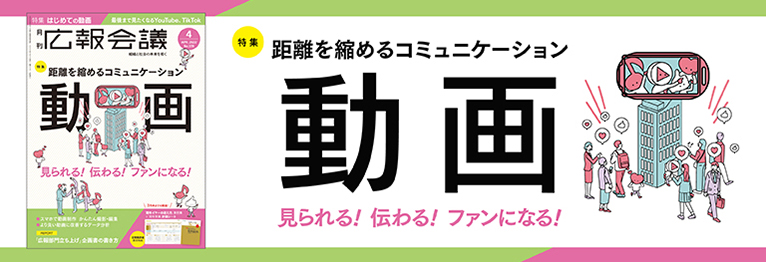
距離を縮めるコミュニケーション動画
ユーザーとの距離感をぐっと縮めることができる、エモーショナルな「動画コンテンツ」。コロナ禍でコミュニケーションが分断されがちな今、注目が高まっています。本特集では、広報・コミュニケーションで動画を活用するメリットはどこにあるのか、動画を公式アカウントから投稿する際の注意点は何か、スマホで動画を撮影・編集する際のノウハウなど、これから動画制作を強化していきたい方に向けたヒントをお届けします。
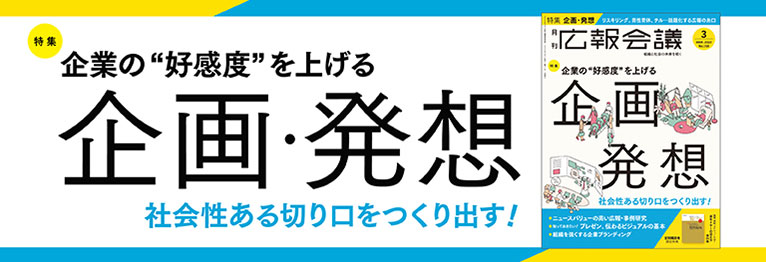
企業の「好感度」を上げる 企画・発想
経済や社会が大きく変わったコロナ禍の暮らしで、人々は自分にとって真に価値のあるものを見極めようとしています。そんな中で広報活動を継続していくにあたって、企業が社会に存在する理由や、社会課題に対してどのような姿勢をもっているのかについて、しっかりと発信していくことが求められます。ニュースバリューがあり、共感される、広報切り口を見つけるためのヒントをお届けします。