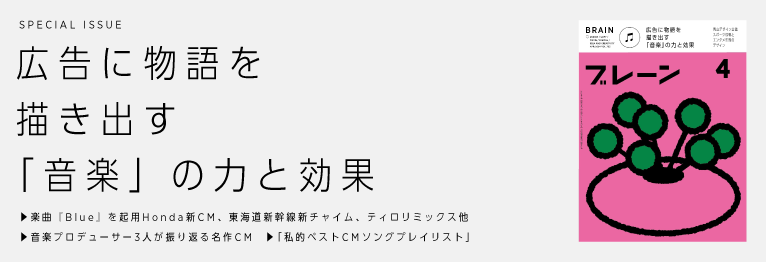
広告に物語を描き出す「音楽」の力と効果
近年、音楽やアーティストのパワーを味方につけた広告展開がより一層増えています。テレビCMにおける楽曲タイアップなどは以前から存在していたものの、Webコンテンツなども含めて有名無名を問わず一歩踏み込んだブランドと音楽の融合が進んでいます。そんなこだわりを持つ企業・ブランドは広告における音楽表現をどのように位置付け、クリエイターとアーティストたちは形にしてきたのか。さらに今回は、名作CM楽曲の数々を各自の視点で振り返りプレイリストとしてセレクト。広告のつくり手だけでなく映像監督、音楽プロデューサー、作曲家など、あらゆる立場から「音楽」の力と効果を検証していきます。
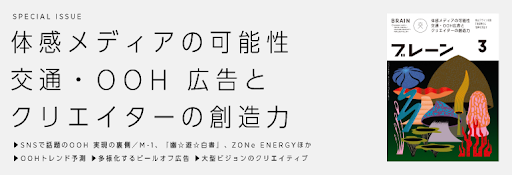
体感メディアの可能性 交通・OOH広告とクリエイターの創造力
「日本の広告費」においても堅調に推移し、今後の成長が期待される屋外広告・交通広告。特に近年は大型サイネージや3D広告など国内でインパクト型の表現が拡張し、体感メディアとしての可能性が広がっています。同時に「SNS上で一瞬で伝わる」といった話題性の獲得に繋がる企画も次々と登場し、クリエイターにとっては「まだ誰も見たことがない」アイデアや提案力が試される場ともいえるでしょう。今回は2023年に実際に掲出された「一体どうやって実現したの?」と気になる広告の数々などを中心に、制作のプロセスに迫ります。
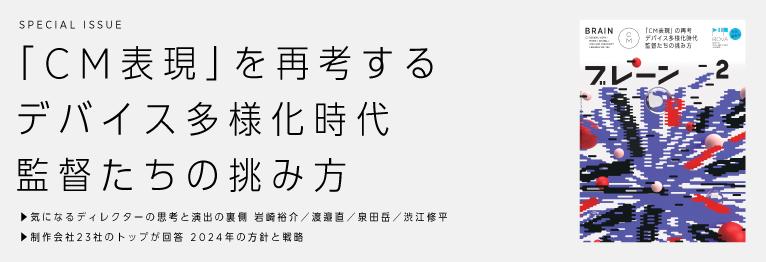
「CM表現」を再考するデバイス多様化時代 監督たちの挑み方
2024年を迎える今、CM制作のクラフト部分を担う映像監督たちはどんなことを考えているのか――。タイムパフォーマンスを重視する視聴者たち、映像フォーマットの多様化、オンライン動画が担うべき役割の目まぐるしい変化、広告か否かの境界線の曖昧さなど、数々の課題を抱える中で、変わってきたこと・変わらないこととは。また、クリエイティブ制作においてどんな役割を担っていくことでよりよい社会をつくることに繋がるのか。話題のCMの演出を手がけている気鋭の監督の声のほか、主要制作会社のトップ・責任者による2024年の戦略と方針もあわせてお届けします。
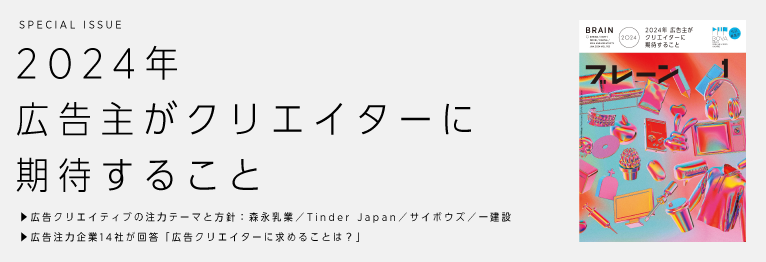
2024年広告主がクリエイターに期待すること
いつもクリエイティブ面で活気のある広告主は、広告会社やクリエイターたちにどんなオリエンテーションを実施しているのか。2023年、広告活動を新たに始めた、または例年以上に注力をした企業・ブランドはクリエイティブに対してどんなこだわりを持っているのか――。今回は企業の広告宣伝関連の責任者、ブランド・事業責任者らにインタビュー。率直に「今、クリエイターに期待すること」をテーマに話をうかがいました。手段や表現、接点が多様化する中、またこの1年で従来の業界慣習なども変わりつつある今、どのようなアイデア、企画実行力が求められているのでしょうか。間もなく2024年を迎えるにあたり、考えていきます。
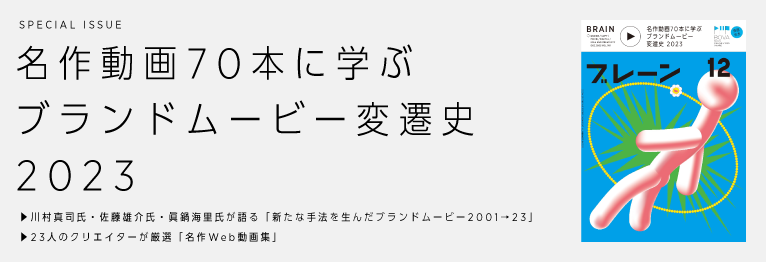
名作動画70本に学ぶブランドムービー変遷史2023
ブランデッド・エンターテインメントから、ショート動画、縦型動画まで。枠や尺にとらわれない、自由度の高い企業・ブランドによるWeb動画のフォーマットや表現は年々進化を遂げています。今回の特集では、2000年代以降に登場した国内外の"名作"と呼ばれるブランドムービーの数々をクリエイターが解説。新たな手法を開拓した映画のような動画はもちろん、あえて"つくり込まない"テイストの映像まで多数登場します。表現が多様になる一方、常に原点にあるのは「企業・ブランドの課題解決につながるか」。ブレーン発のオンライン動画コンテスト「BOVA」も11年目を迎え作品募集が始まる中、ブランドムービーの役割について改めて考えていきます。

地球環境と向き合うサステナブルなデザインの理想形
2015年に国連でSDGsが採択され、持続可能な開発のための17の国際目標が定められ8年が経過しました。目標達成のターゲットとなる2030年まで折り返し地点を過ぎたところですが、この間、世界的なESG投資の広がり、脱炭素社会への移行、カーボンオフセットの実現など、サステナビリティ経営の流れが一気に加速しています。その結果、地球環境の問題に関わる企業のブランドコミュニケーションにもサステナビリティの視点が求められるように。今やクリエイターにとっても、サステナブルなデザインの提案は特別なことではなく、スタンダードなものとなりつつある今。その理想のあり方、またクリエイターが果たすべき役割について考えていきます。
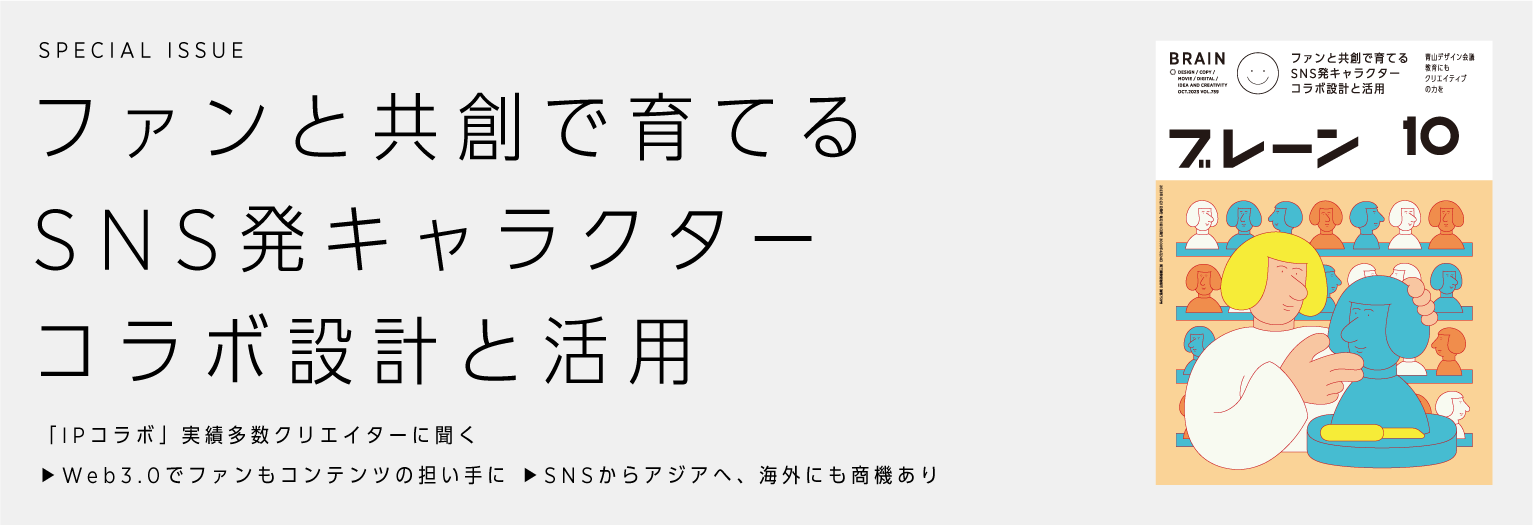
ファンと共創で育てるSNS発キャラクターコラボ設計と活用
あらゆるブランドでキャラクターを活用したプロモーションの手段が広がっています。特に近年、人気を集めているのはSNS発のキャラクターと組んだ、ファンを巻き込み共創していくような企画。CGやAIなど技術の普及によって、既存のIP(Intellectual Property/知的財産)以外のプレーヤーの参入、あるいはオリジナルのキャラクター開発も広がっている今。企業やブランドの課題解決にこれらを用いるケースも増える中、効果的なIPとのコラボレーションの設計と活用の方法などを考えていきます。
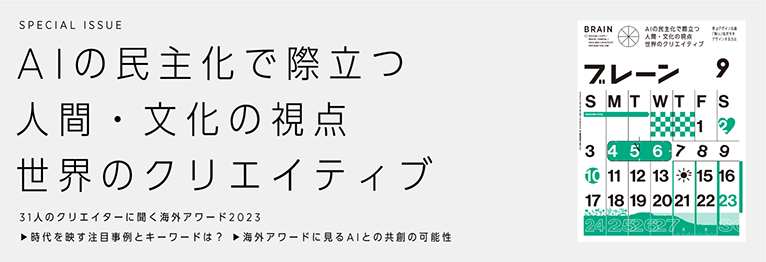
AIの民主化で際立つ人間・文化の視点 世界のクリエイティブ
生成AIの活用シーンの広がり、それに伴うクリエイターの役割の変化などが日々議論されています。テクノロジーとクリエイティビティの関係も変わりつつあり、大きな転換点を迎えつつあるともいえます。そのような状況下で、世界のクリエイティブの流れはどこに向かっているのでしょうか。AIの民主化が進み、人間性(Humanity)や文化の視点が問われるようになってきた今。先ごろ結果が発表されたカンヌライオンズ、The One Show、D&AD、Clio Awardsなどグローバルの各種広告関連アワードの審査結果や入賞事例、現地に足を運び世界の潮流を捉えてきたクリエイターたちの声を交え、考えていきます。
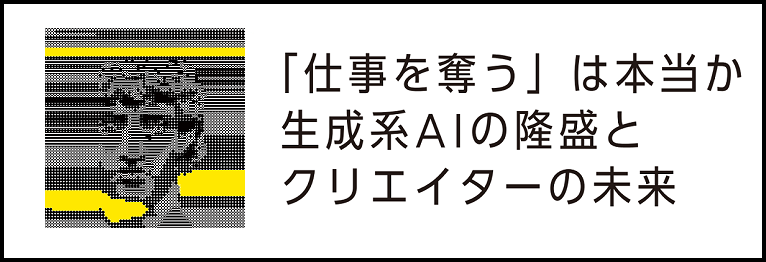
「仕事を奪う」は本当か 生成AIの隆盛とクリエイターの未来
ChatGPTや画像生成などジェネレーティブAIがグローバルで席巻し、クリエイティブに限らずあらゆるビジネスシーンで導入が進んでいる現在。一方で法的・倫理的な側面から問題点が浮上し、規制に動く国や地域もありますが、活用やルールの制定においては議論が続きそうです。その中で生じているのが「AIがクリエイターの仕事を奪うのでは」といった論点。広告コミュニケーションの企画制作においてポジティブに活用される可能性もあれば、既存のクリエイティブ従事者にとっては脅威となるのでは――そのような流れに対し、制作の現場で今起きていること、また問題が生じていることとは。既に先行してトライアルを重ねているプロジェクト事例も交え、未来のAIとクリエイターの関係を考えていきます。
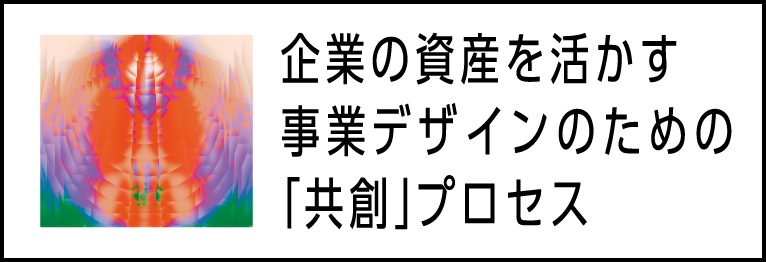
企業の資産を活かす 事業デザインのための「共創」プロセス
企業や団体が新たに取り組む事業やプロジェクトにクリエイターが参画する際、一体どのような役割が求められているのか。一方的な提案ではなく、事業主とクリエイターが良きパートナーとして傾聴と対話を重ね「共創」を進めていくスタイルが広がっている今。2025年開催の大阪・関西万博でも、デザイン視点で「共創」に取り組み、未来社会の在り方を探る動きが見られるなど、注目度が高まっています。また、AIなどテクノロジーを用いた共創の手段も広がってきました。今回は実際にローンチされた事業やプロジェクトの実例について、提案書類や実現に向けてのプロセスがわかる資料を紐解きながら、これらのポイントを探っていきます。

SNSに最適化するクリエイティブ攻略
縦型動画、ユーザー参加型コンテンツなど、あらゆるプロモーションでSNSの特性に合わせたクリエイティブが標準搭載されるようになった今。各社が一斉にマス広告と共存する表現はもちろん、SNSにおける独自の表現も取り組むようになり、埋もれないようなアイデアが求められています。特に従来のメディア環境にとらわれない若い世代に向けては、共感度が高く多様性ある表現を求めて、試行錯誤する状況も。そのゴールも「話題になる・バズる」「エンゲージメントを高める」などさまざまです。これら『SNS特化型クリエイティブ』について、クライアントごとの最適解の見つけ方を考えます。
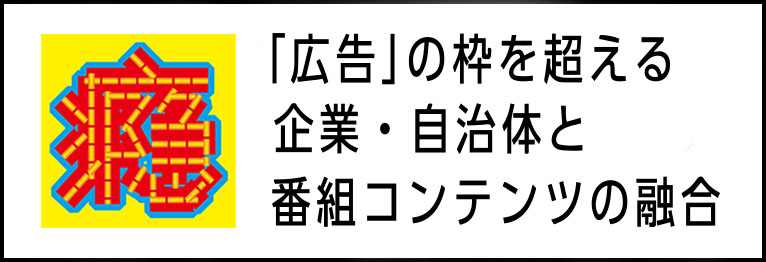
「広告」の枠を超える企業・自治体と番組コンテンツの融合
メディア環境やコミュニケーション手段の変化とともに、テレビ・ラジオ・音楽などのコンテンツとブランドの融合の在り方が変化しています。さかのぼればタイアップ、プロダクトプレイスメント、コラボレーションなど多様な形態でその在り方を模索してきた歴史がありますが、デジタルの普及とともに「ブランデッドコンテンツ」が広がってきたのはこの20年ほどの話。さらにメディアビジネスが変容し、世の中に流通するコンテンツ自体があふれ返っている今、「ブランドが広告を超えて、完全なるコンテンツになる」状態は可能なのでしょうか。その境界線を超えようと試行錯誤する、クリエイターの取り組みに迫ります。
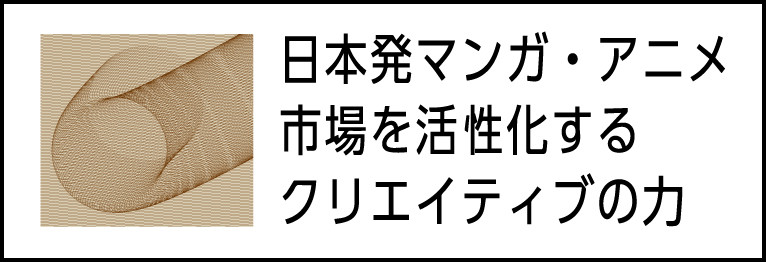
日本発マンガ・アニメ市場を活性化させるクリエイティブの力
2021年、世界における日本のアニメ市場は2兆7422億円と過去最高に達しました(日本動画協会調べ)。出版業界でも電子を含むコミック市場は、紙のマンガのみだった90年代半ばを上回り過去最高となる6759億円と賑わいを見せています(出版科学研究所調べ)。主要駅のOOHを見ても、マンガ・アニメ、あるいはアイドル・音楽といったエンターテインメントに紐づく広告で埋め尽くされている現状も。広告市場においてこれらコンテンツ関連の出稿が増えるとともに、その作品の魅力を引き出す表現や、話題化のためのSNS活用などのアイデアが求められる状況となっています。今回は近年の成功例などとともに、強いコンテンツそのものの勢いをさらに加速させる表現を探っていきます。
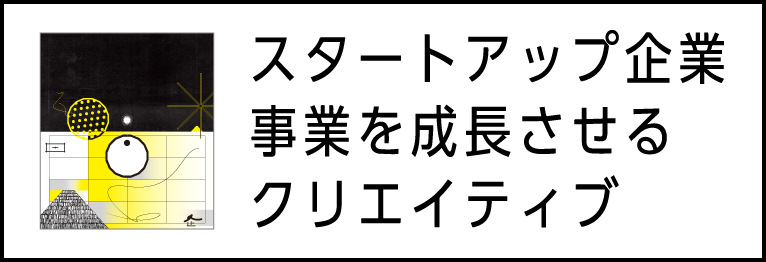
スタートアップ企業 事業を成長させるクリエイティブ
この10年でオンラインゲームや業務改革ツールやDX関連など、BtoBやBtoC問わず、スタートアップ企業による広告出稿が増加しています。広告のクリエイターたちも、投資対効果を求められることが多いこれらの表現に関わるケースが増えてきました。ナショナルクライアントのブランド広告などとは異なるのは、企業・サービスともに全く広く知られていない状況から、一気に認知を獲得しなければならないこと。さらにはコンバージョンや営業アシストなどに繋がる表現を、どう磨き上げていくかが問われること。「売り」を押し出す広告があふれることへの是非も問われる中、最前線にいるクリエイターたちはどのように表現を生み出しているのでしょうか。企業のトップやインハウスクリエイターの声も交えつつ、考えていきます。
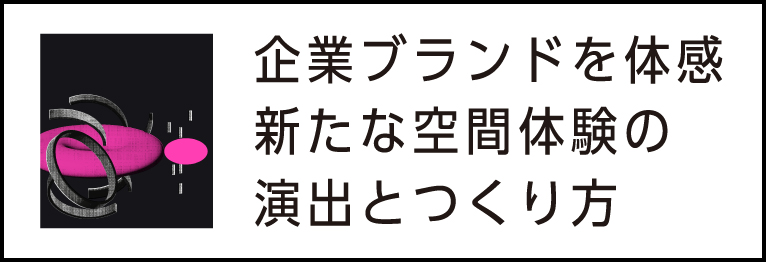
企業ブランドを体感 新たな空間体験の演出とつくり方
コロナ禍を経て、リアルの空間において提供できる体験価値が変わりつつあります。クリエイターとの協働を模索している企業も多く、新たな提案のチャンスも広がっている今。リアルの発信拠点やコンセプトショップ、オフィスなど、企業ブランドを体感できる場づくりの演出・つくり方はどのように変わってきたのでしょうか。オンラインとオフラインのハイブリッドを試行したり、リアルの場に足を運び広く共有したくなる仕掛けを施したりと、各社の実験的な取り組みとともに考えていきます。
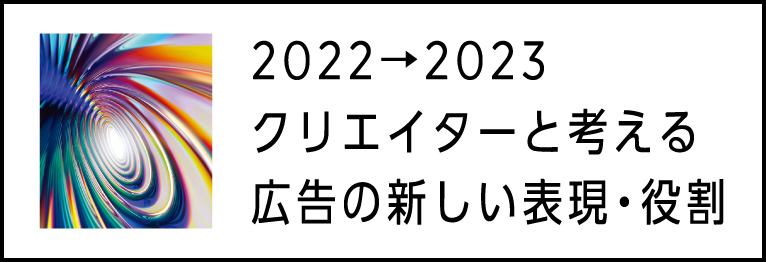
2022→2023 クリエイターと考える 広告の新しい表現・役割
あらゆる要因で社会不安が増大した2022年、円安の加速や物価高など企業や生活者を取り巻く環境も厳しくなりつつあります。その中で近年、勢いを増している社会課題解決に向けた企業メッセージの数々に「広告の役割とは何か?」という声が聞かれることも。「広告に元気がない」などと評されることもあり、世の中をエンパワーメントするという広告の本質に立ち返ろうとする動きも見られます。今、広告制作の担い手たちは2023年に向けてどんなことを考えているのか──この1年で注目を集めた広告の数々とともに、現場のクリエイターたちの声を交えレポートしていきます。