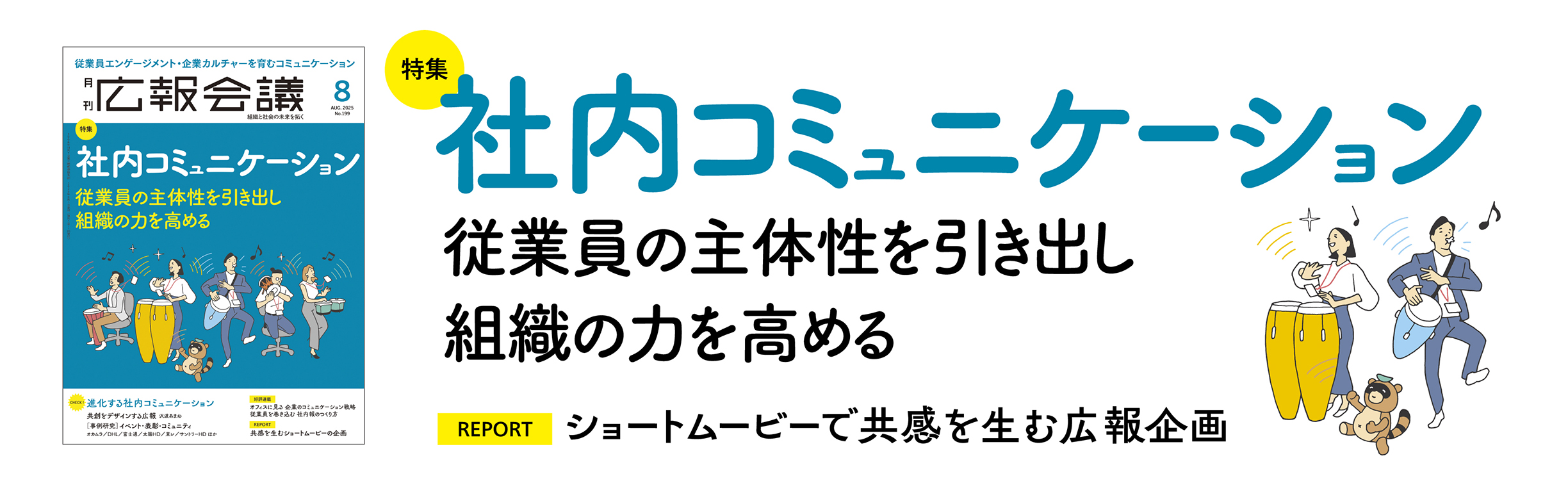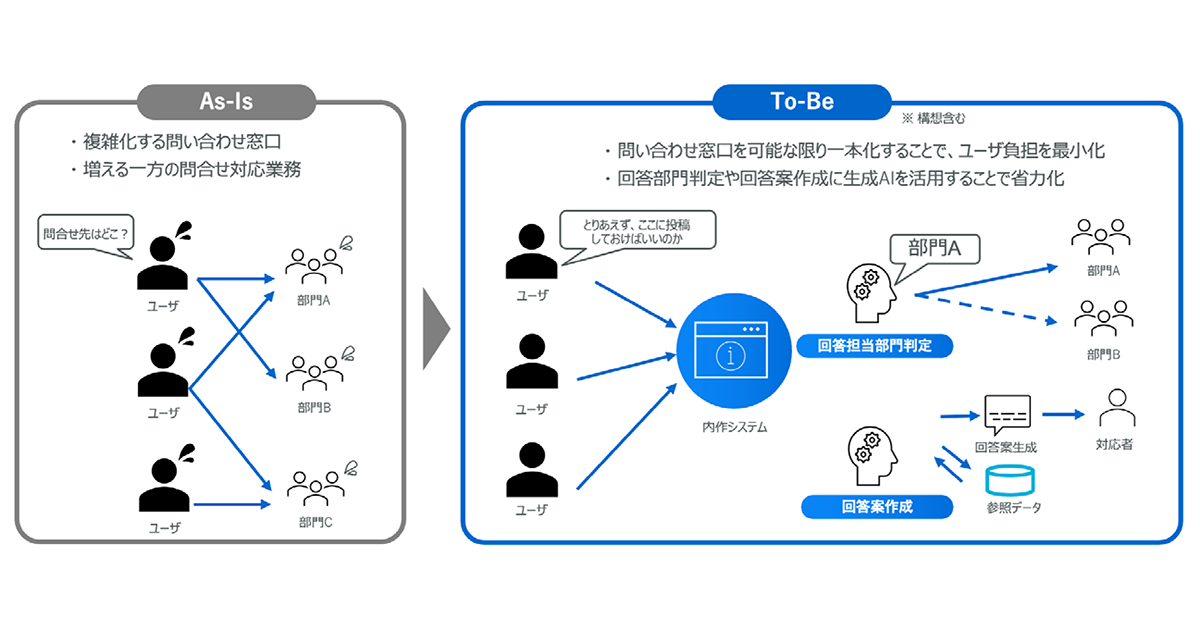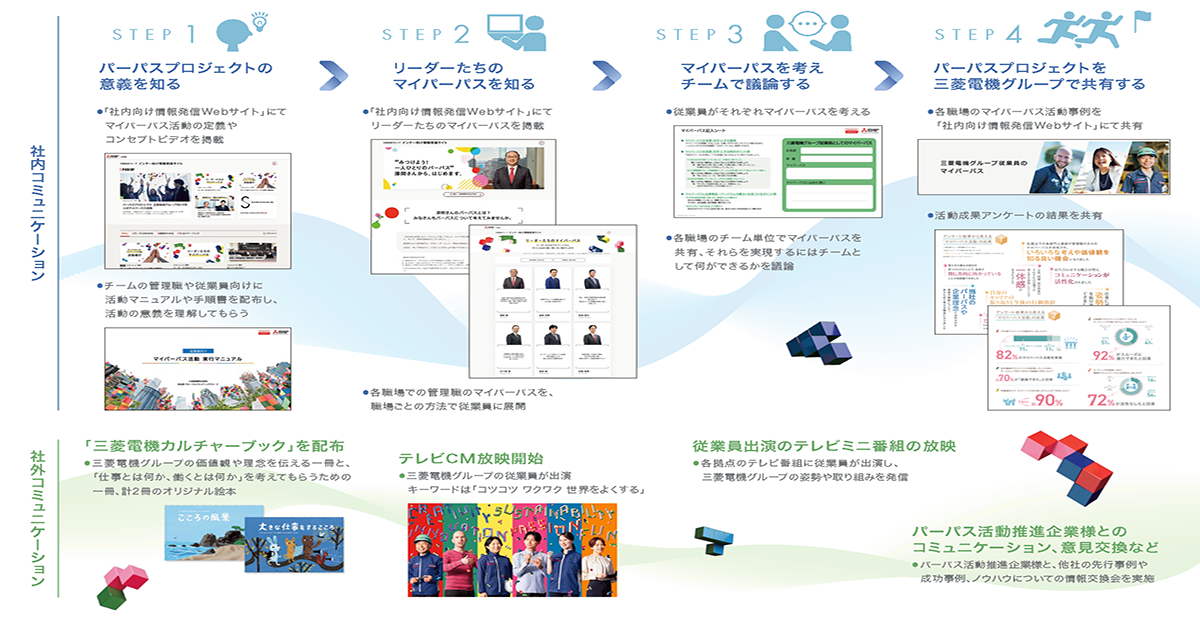チームがうまく機能しない、共通認識が持てない─社内コミュニケーションの悩みは、今や多くの広報担当者にとって共通課題だ。この課題の打開策となりうる「共創」という視点について、多くの企業の組織課題を解決してきた筆者が解説する。
社内コミュニケーションに対する組織の関心が高まっています。2024年11月にアサヒビールとHR総研が実施した調査によると、大企業(従業員1001名以上)の76%、中堅企業(301~1000名)の89%、中小企業(300名以下)の71%が社内コミュニケーションに課題を感じていると回答。
当社あまねキャリアも、社内コミュニケーションに関する相談を企業の人事部門、事業部門の責任者、組織開発担当者などから頻繁に受けています。
なぜいま社内コミュニケーションが重要視されているのか。その背景に4つの多様化があります。
① 人材の多様化
人材の流動化が全国各地で進んできています。転職も復職も当たり前。当社の顧客でも最近になって中途採用を始めた企業や、遠方の他都市に居住する人をフルリモートワークかつ副業で採用し始めた企業、多拠点居住をして東京と地方都市などを行き来しているプロフェッショナル人材に顧問やアドバイザーとして関わってもらう地方都市の企業が見られ始めています。
② 働き方の多様化
働き方の多様化も進んでいます。リモートワークやハイブリッドワーク、副業や兼業を解禁する企業もいまや珍しくありません。時短勤務、週休3日勤務、週3日勤務など週5日×フルタイムでの参画を前提としない働き方を取り入れる企業や個人も増えてきました。働く人のライフステージも多様化しています。育児しながら、介護しながら、兼業しながら、通学しながら、地域の活動をしながらなど「ながら勤務」を許容していかなければ、少子高齢化による労働力不足が深刻さを増す時代において、企業組織運営どころか社会運営そのものが成り立たないでしょう。
「一社専業ではない」「ひとつの勤務先にフルコミットしない」、いわば(個人の)社会への関わり方が多様化していると言ってもよいでしょう。
③ 世代の多様化
職場のジェネレーションギャップも見逃せません。定年の年齢の引き上げなどに伴い、10代・20代の新卒の社員と60歳以上のシニアスタッフでチームを組む景色も当たり前になりました。ベテランを中途採用し、組織の世代構成がガラリと変わるケースもあります。
そうなると世代間のギャップが問題に。ベテランと中堅と若手の間での意見の食い違いや、主導権の奪い合いが起こり、それは特定の世代のエンゲージメント低下をもたら...