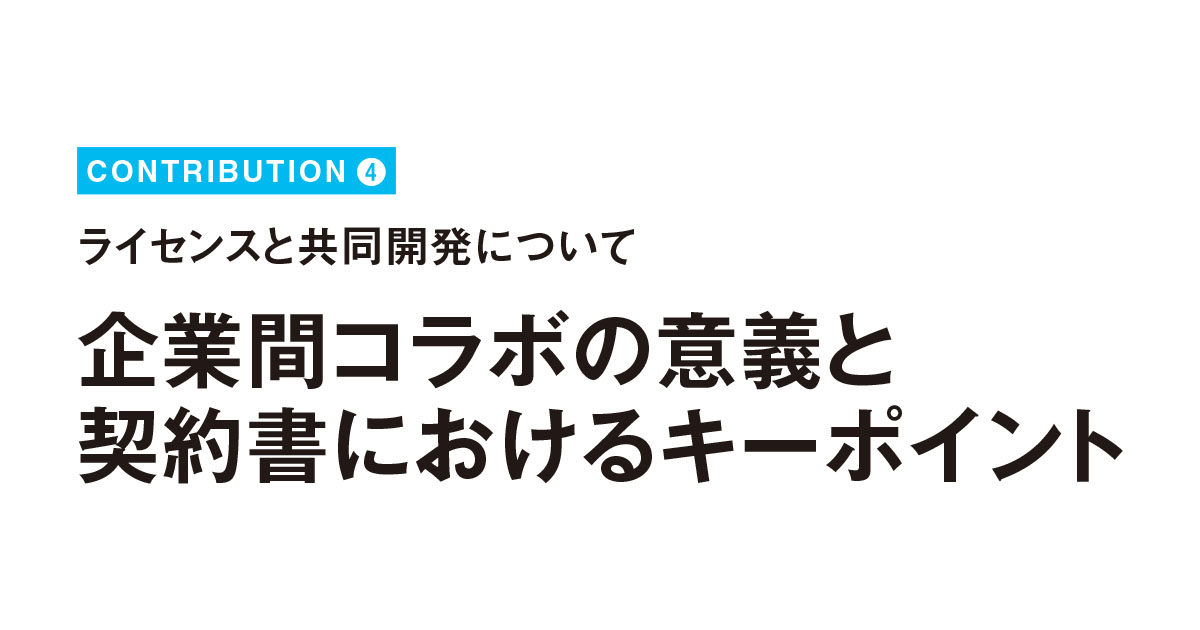コラボレーションとはそもそも何か?まずは位置づけを確かにするところからスタートしよう。「ネスカフェ」で数十件のコラボを手がけてきたネスレ日本 レギュラーソリュブルコーヒービジネス部の島川基部長は「コラボはマーケティングそのもの」と説く。

ネスレ日本は、宅配水大手のアクアクララと協業し、2018年11月1日、ネスレのコーヒーマシンとウォーターサーバーを一体化した機器を利用できるサービスを開始した。一体型マシンは「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」か「ネスカフェ ドルチェ グスト」の2種類ある。容量12リットル(約85杯分)の飲料水ボトルを備え、利用者が水を補充する頻度を減らしたほか、ウォーターサーバーの機能により、冷温どちらの飲み物も楽しめる。また、軟水であることも味わいに寄与している。PR面では、両社の社長が登壇し、サービス開始を発表する共同の記者会見およびメディア向け体験会を開催。また一般家庭に対し、広告以外でリーチすべく、発売開始と同時に家事大手のベアーズと組んだ共働き応援キャンペーンを実施した。体験機会ではサービス発売前、「ネスカフェ アンバサダー」などの既存顧客に簡易試作機を試してもらい、フィードバックを得たほか、調剤薬局など家庭外のタッチポイントで活用してもらい、サービス提供者と利用者が製品にふれるシチュエーションを設けた。
コラボレーションとは問題解決の手段である
今回は「コラボレーション」というお題をいただきましたので、そもそもコラボレーションとは何なのかを考えるところからスタートしたいと思います。
コラボという言葉は、もはや聞き慣れた言葉になっています。そこから連想されるのは、「有名企業やブランド同士の意外な組み合わせやプロモーション」というイメージが一般的かもしれません。
Collaborationという言葉を分解すると、Co(ともに)labor(働き)ate(する)ion(こと)。平たく言えば一緒に働くことです。では働くとは何か?本来は単にからだを動かす、動くという意味でした。そこから、労働の意味が派生し、さらには役に立つ、用をなす、機能するへと広がりました。誰の役に立つのか?お客さまです。
つまり、コラボレーションはお客さまの問題を解決するための手段である、ということです。こう考えれば、本来コラボとは社内外を問わず、お客さまの問題解決に向けた他者との協業を意味することがわかります。つまり、そのブランドの大きさや組み合わせの意外性が主目的となることはありません。この認識を持つことが、コラボを成功させるための最初のステップです。
では、なぜコラボレーションの重要性が昨今、強調されるようになったのでしょうか。この背景にはお客さまのニーズの変化があります。モノや情報が不足していた20世紀は、良い製品や情報を出すことがお客さまの問題解決になりました。
しかしこれだけモノや情報があふれた21世紀においては、モノや情報自体で問題は解決されず、より便利にモノを選択し、使用して、そのベネフィットを得るまでの一連の流れを、一つの「体験」として提供することが求められます。それを自社の限られたリソースのみでは実現できないとすれば、他社との協業が検討の対象となる。これが近年、コラボレーションの必要性が高まってきた理由だと考えられます。
互いのパーパスに共感 共通のビジョンについて合意
私自身この2~3年間で、数十件のコラボレーションを手がけてきました。まさに上述の通り、お客さまの問題解決を果たすために他社と協業する必要性があったからです。
コラボの成功を左右するものは何か?と振り返ってみると、真っ先に挙げられるのは、協業先とのゴールイメージを明確に描くことです。コラボ相手の事業規模が第一に来るわけではありません。
コラボ相手との接点の見つけ方はいろいろありますが、特に顧客の問題や自社の強みと照らし合わせながら、異業種・異業態のニュースに目を向けておくと、視野を広げるのに役立ちます。また、そもそも顧客が抱える課題を解決するためにそのパートナーが必要な理由も明確になります …