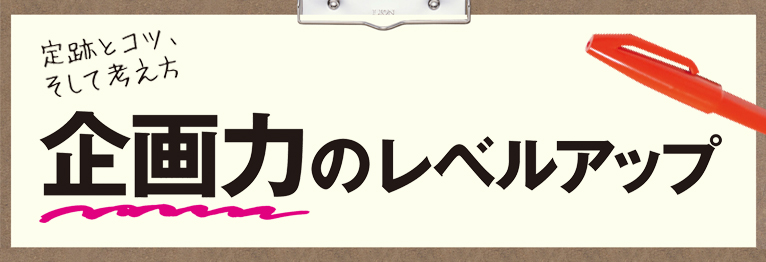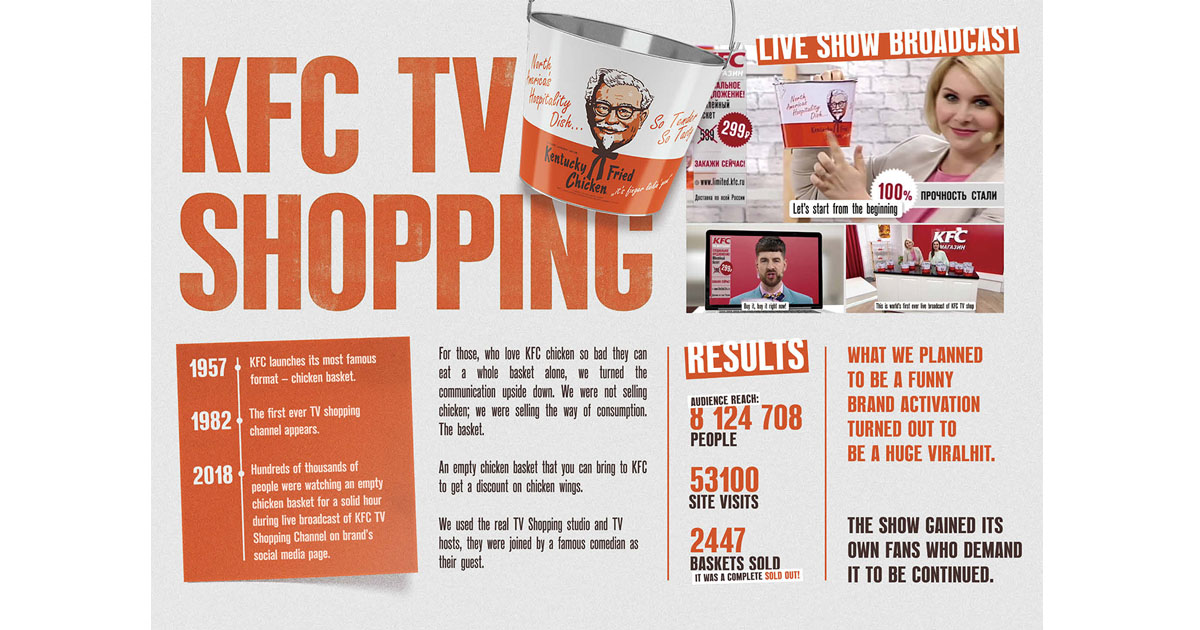ブランドのポテンシャルを開花できるよう、世の中に働きかけられるか。成否は「企画」次第だ。紅茶の新たな魅力を開拓して市場を広げた藤井一成氏が、予測不可能な時代における「企画」について解き明かす。

藤井一成氏(ハッピーアワーズ博報堂代表取締役社長)。ブランドの体験価値を再構築し、事業の可能性を広げる提案を行う。
──企画で最も重要視していることは何ですか?
いろいろありますが、強いて挙げるなら「主観」でしょうか。
──「客観」ではなく?
「主観」です。広告やプロモーションは、ある意味「押し付け」です。そこから目をそらしてはいけません。企画者には、しっかりとした自分の「主観」があるべきです。
プロモーションの企画は、構想から制作、世の中に送り出すまでの間に、さまざまな課題にぶつかることが珍しくありません。一貫性のある「主観」がないと、責任の所在が不明瞭になります。「主観」からの逃避は、企画から実現までの間にいろんなトラブルを起こす原因です。
基本的に忙しくない人はいません。時間あたりの生産性を高めようといった動きもあります。必然的に分業が進み、考える人は考えるだけ、ここは誰、それは誰、と分かれるわけですが、半面、一貫した「主観」がなければ、ディレクションがあいまいになってしまいます。仕上がり自体がまとまらなくなる。
世の中、あらゆることが非連続的に進みます。確実なことは、わたしたちが思っている以上に少ないものです。その中で、確固たる「主観」を持って社会に向き合えるかどうか。
──プロモーションを企画する際に、「主観」以外に指針としていることはありますか。
ブランドのあるべき姿です。
プロモーション領域は基本的に短期的な成果を求められる分野です。だからこそ、そのブランドが、どのように世の中から受け止められるようになればいいのか、という中長期的な視野が欠かせないと思います。
なぜならブランドは未来に続くものと考えるのが前提だからです。
しかし私たちは、このことをつい忘れてしまいがちです。瞬間瞬間の飛距離を求められる中で、ブランドの一貫した人格というものを無視してしまう。あるいはわかっていながらも、瞬間最大風速を高めることを求められる。
距離をつくることが目的化すると、実際上、企画など何でもいいということになります。するとブランド価値を毀損してしまう。
ブランドが将来どういう姿であるべきか。ブランドを永続させようとするのであれば、プロモーション活動ほか、さまざまな施策が、同じ方向を向いている必要があります。消費者にとっては、ブランディング広告だろうとプロモーションだろうと、そのブランドの一側面として接触することになります。一貫性がなければ、ブランド価値は蓄積しません。
売り上げの最大化は当然ですが、それは結果。目的に従って実施したことが正しかったかどうかの指標です。
──ブランドの将来像に着目するようになったのはなぜですか。
世の中に登場するブランドの数は多くなるばかりです。消費者はうつろうもので、新規顧客がつかないブランドも少なくありません。
一方、企業は、効率や利益の追求姿勢を強めています。優良顧客向けのプロモーションは基本的に反応がよく、コスト効率も高い。売り上げも伸びます。1年間の損益計算は、とても良いスコアになります。
しかし成果は出てるんだけども、気がつくと、新規顧客が入ってこなくなっている。消費者はいつかは必ず商品から離れますから、問題が現れるのはずっと先のことですが、気づいてからでは遅い。ロングセラーブランドは特にその傾向が強いのでは。
ブランドを永続させるには、新しい世代を感動させたり、ブランドに愛着を持ってもらったりして、ブランドに新たなお客さんを呼び込んでくることが不可欠なのですが、これこそ、プロモーションが効いてくる分野です。
新しいお客さんが来た結果、これまでのお客さんが離反しても意味がありません。ゆるやかに変化することはあるにせよ、やはり一貫性というのは重要です。そうなると、これまでがどうで、これからどうなっていきたいのか、という点には必然的に目を向けることになってきます。
──プロモーションで新たな顧客を招く上で、重要な点は。
ターゲットの情報行動を理解することが鍵となります。
現代の消費者は、さまざまな情報を吟味したうえで、モノを選んでいます。その中で自社ブランドが勝てる価値をつくらなければなりません。新しい世代がブランドに恋してくれる、新しい回路をつくる必要がある。
何に感動し、共感し、愛着を持つのか。これまでのブランド価値のストックのなかから新しい世代に向けて価値を磨き直すことが第一歩です。
その価値は、企業側とターゲットが共有できることが大事。互いに価値を認め合うには、発信側の「主観」だけでなく、顧客の「主観」をしっかり理解する必要があります。その上で、お互いベネフィットがある状態をつくる。ブランドとファン(顧客)が、双方ベネフィットを享受できる関係にある。そこが到達点。これはステークホルダーに対しても同じだと思います …