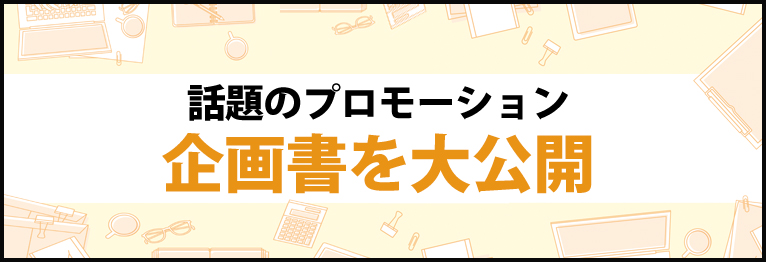昨年夏に実施された養命酒の「夏バテにYomeishuモバイルキャンペーン」は、ユニークなプロモーションでソーシャルメディアを中心に大きな話題を呼び、応募総数は23万通にものぼった。養命酒製造とGMO NIKKOの両社に企画実現までの経緯について聞いた。

(左)養命酒製造
マーケティング部 専門課長 鳥山敦志(とりやま・あつし)氏
(右)GMO NIKKO
取締役 コミュニケーションプランニング本部 本部長 プランナー/コピーライター
神谷みめい(かみや・みめい)氏
「夏バテにYomeishuモバイルキャンペーン」は、特設サイトからプレゼントに応募すると、養命酒の外箱パッケージをイメージしたデザインの「Yomeishuモバイルバッテリー」や養命酒の味わいを再現した「Yomeishuタブレット」が当たるというもの。特設サイトでは、米国大手電子機器メーカーの新製品紹介動画を彷彿とさせるプレゼント景品の紹介動画、そしてそれに広島弁の吹き替えを付けたものが掲載されるなど、ユニークなプロモーションが行われた。
最も大事なのはメッセージが伝わるスピード
──当企画を考案した経緯を教えてください。
神谷みめい:キャンペーンの実施目的は、夏バテや胃腸の疲れに養命酒がいいということをシンプルに伝えるというものでした。夏は人間が夏バテするのと同じように、スマートフォンも気温が高ければバッテリーの減りが早くなる。
また、バカンスに出かけた先でバッテリーがなくなるということもあります。バッテリーのアイデアはすでに養命酒さんから出ていたのですが、それを「あなたの夏バテに薬用養命酒、スマホの夏バテにモバイルバッテリー」としたんです。企画はほかにもいくつか提案しましたが、これが最も鳥山さんにとって響いたということですよね。
鳥山敦志:そうですね(笑)。キャンペーンを実施するときは、メッセージの伝わるスピードがいちばん大事だと思っています。キャンペーンの中にはインセンティブだけがひとり歩きしていたり、タレントやキャラクターとタイアップした際には、プロダクトがただそのタレントやキャラクターと一緒になっているだけというケースが少なくない。
その点でこの企画は、伝えたいメッセージがプロダクトとインセンティブに共通していました。たとえインセンティブがプロダクトを離れてひとり歩きしたとしても、伝えたいメッセージとともに拡散する。そこがすばらしいと思いました。
神谷:キャンペーンの話題はコミュニケーション上のターゲットとは関係なく、パブリシティ文脈に乗って広がった方がいい。いまやスマホはほとんどの人が持っているので、景品をモバイルバッテリーにすることで、本来ターゲットとしている30歳代〜40歳代の男女以外にも広げていければというねらいもありました。
理由づけや説明よりも訴求力を上げることに注力
──企画書にはどのような内容を落とし込んだのでしょうか。
神谷:実はこの企画、企画書は実質2枚なんです。1枚は「あなたの夏バテに薬用養命酒」「スマホの夏バテにモバイルバッテリー」というコアメッセージ。もう1枚は景品のビジュアルイメージです。
基本的には鳥山さんと話す中でアイデアを出し合い、そこから昇華させて企画にしていくため、企画書を細かく作り込む必要がなかったんです。僕の場合、1枚にまとまれば1枚にするケースもありますし、中には5枚になるものもあります。
鳥山:私も最終的にはどのようなアウトプットになるのかというイメージが明確に描ければいいと思っています。社内に向けて説明する際は、私がそこに資料を足せばいいだけですからね。
この企画は、アイデアの段階では単にモバイルバッテリーという景品の案があっただけなんです。初めは、モバイルバッテリーという景品に行き着くために養命酒の紹介を盛り込んだゲームをつくり、それをプレイしてバッテリーを消費したからプレゼントするという流れを考えていました。
しかし「あなたの夏バテに薬用養命酒」「スマホの夏バテにモバイルバッテリー」という強いメッセージを考え出したときに、ゲームは必要ないと感じました。このメッセージ自体が広がっていけば、養命酒は何かをチャージするものであることは伝わる。あとは企画を徹底的におもしろくして、訴求力を上げることに力を注げばいいと感じました。無駄な理由付けや説明に労力を割くことがない、クリエイティブにとって理想的な環境でした。
神谷:企画が通ったあとも、企画をおもしろくするためにいろいろと試行錯誤しましたね ...