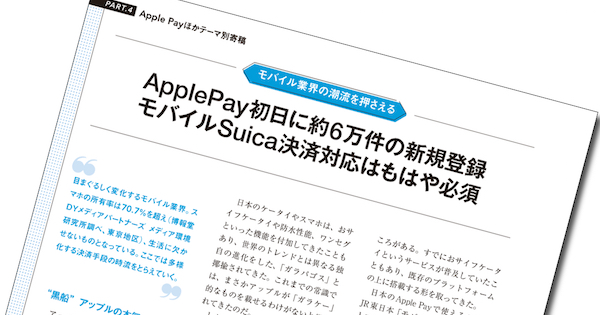検索上位にあるコンテンツは、そっくりそのまま有益なコンテンツか?─中には落とし穴がまぎれているかもしれない。検索エンジン最適化(SEO)サービスを提供し、携わる案件で、日本での全検索の約3.5%を占めるという辻氏に、SEOの視点から、Webメディアへの出稿時に考えたいリスクについて、解説してもらった。

過度にSEO施したサイト 突如として姿を消す場合も
インターネット上には、星の数ほどWebサイトがある。その中には、「粗製乱造」とでも言うべきサイトも含まれる。読みながら疑問符が浮かんだ経験のある人もいるのではないか。
しかし、そうしたサイトを、商品購入ページなどへ集客するために用いる企業は少なくない。名の知れた大手なども散見される。なぜか。
「粗製乱造メディアの特徴のひとつは、広告単価が比較的安価であることが、理由のひとつでしょう」と指摘するのは、検索エンジン最適化(SEO)サービス会社so.la(ソラ)の辻正浩社長だ。
Webメディアでも、広告記事は100万円以上するメディアから、30万円程度で請け負うところまでピンキリ。後者でも、SEO手法を縦横無尽に駆使し、集客力だけを見れば、大手サイトに比肩することもある。そういう意味では、プロモーション効果がないとは言えない。
「ただ、安さ・集客力だけで飛びついてしまうと、落とし穴があるかもしれません」と辻氏は語る。「一つは、信頼性の低い情報を集めている場合があります。そうしたサイトにブランドを露出させることには、レピュテーション(評判)上のリスクがあると思われます」
ネットを利用することはもはや日常生活の一端だ。ネット上で悪評が広まれば、ビジネス上の損失が発生することも考えねばならない。
「もうひとつは、そうしたWebサイトは、突発的にアクセスが制限されることがある、ということです。キャンペーン期間中の目標到達を阻害するおそれがあると言えます
といっても、どうしてそのようなことが起きるのだろうか。辻氏は次のように解説する。
「検索アルゴリズム(結果表示までの情報処理の手順)はどんどん進化しているからです。ここ1年〜2年、特にグーグルの検索エンジンが過渡期に入った印象を持ちます。検索結果の不安定さが目につくこともあります。検索順位が日ごと大きく変わるものですが、検索エンジンからのアクセスが不安定なために悩まれている方もいるのでは」
結果、現在はアクセスを多く集めていても、突然、検索結果に表示されなくなることがあるというのだ。実際、2016年後半でも大手のECサイトや ...