ANA Xは、ANAグループの顧客マーケティング会社。顧客とのデジタル接点と顧客データを基に、パーソナライズされた情報・サービスをタイムリーに提供するマーケティングモデルの確立を目指す。

ANA Xの加藤恭子社長。全日本空輸のマーケティング部門のシステム関連部署に始まり、マーケットコミュニケーション部へ。リクルートライフスタイルとの合弁会社「ANAじゃらんパック」の副社長、社長を歴任し、ことしからANA Xの指揮を取る。
「次回もお願いしたい」コールセンターでの推奨支援
ANA Xは2016年、全日本空輸(ANA)のマーケティング部門の一つだった、「ロイヤリティマーケティング部」を分社化して立ち上がった。同社は「ANAマイレージクラブ」を中心とした顧客関連事業に加え、今春には自社航空券販売機能を備える「ANA SKY WEB」をはじめとしたデジタルオウンドメディアの運営管理もANAから移管。顧客を中心に据えたマーケティング活動の一元化を進めている。
同社が掲げるのは、「顧客を起点としたアプローチ」だ。データ活用の根本にも、この考え方が息づいている。取り扱うデータは、搭乗データはもちろん、「ANAマイレージクラブ」のマイル利用履歴やどこで何を買ったことでマイルが貯まったか、といった積算データ。ほかにも運航データやANAカードの利用状況なども含まれる。
「非常に簡略化した例として、ことし5月、ANAがハワイ路線に大型の航空機A380を就航させた際のマーケティングケースをご紹介します。
このイベントに合わせたプロモーションを企画する際に、搭乗データなどから元々ハワイにはどのような人が旅行しているのか、また、どのような買い物の傾向があるのか、などを調べた結果、沖縄へ旅をした経験のある方が多いことがわかったとします。つまり、沖縄に旅行した経験のある方はハワイ旅行との関連性が高い、という仮説ができます。
そうした方々をメインターゲットに、ハワイ便への新機材就航についてお知らせすれば、施策効果を高めることができます。現在推進しているのは、こうした取り組みです」(ANA Xの加藤恭子社長)
このようなデジタル接点での取り組みに加えて、コールセンター支援にも着手している。すでに顧客情報を保持している顧客から航空券の予約などで連絡があった際、その志向を類推し、ANAカードへの入会を勧められるようにするのが目的だ。
すべての人がカード入会をいま必要としているわけではないし、そもそも自分との関連性の低い提案はあまり心地よいものでもない。しかし、必要としている人に提案しないのは機会損失となる。
また、それとは別に、顧客を考えるオペレーターの心情としては、「忙しいお客さまに対して失礼ではないか」という気持ちが浮かんでも不思議はない。そこで、一定の基準に合致する顧客から入電した場合、オペレーターのパソコン画面上に入会推奨を通知する仕組みを導入した。
「データに基づけば、適切な方にだけお声がけできる確率が高くなります。それを実感してもらうためにも、短期間だけでも試してみませんか、とコールセンター部門と議論を重ね、導入しました。
お客さまと接するスタッフは、自分がお勧めした商品やサービスをお客さまに受け入れてもらえることはうれしいものです。データの力を借りながらその背中を押すのが我々の狙いです。実施してみると、『次回のキャンペーンでもぜひやりたい』という声があがり、手応えを感じています。小さくとも一歩を踏み出せたかと思います」(加藤社長)
この入会推奨判別の仕組みは完全に自動ではなく、一部、手動で選定しているという。今後も改善を重ねる考えだ。同様の取り組みは、航空券を予約したものの購入に至らなかった人に対して選別した再通知を出す、といったことなども行っている …


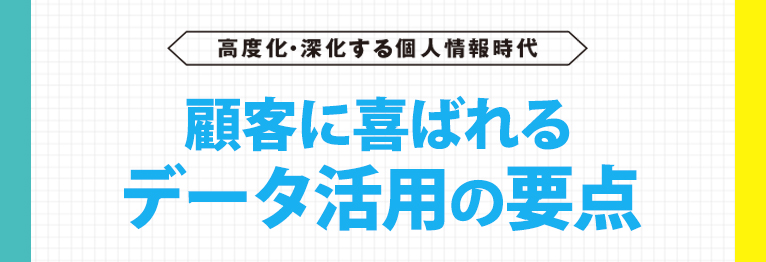

![[PR] 消費者の行動データから潜在顧客を見つけ出す](https://images.microcms-assets.io/assets/9c883224793c4361bfa991c4e6710e04/69a33048b82b4cc9b7d8cf18075a5150/046_ogp.jpg)
