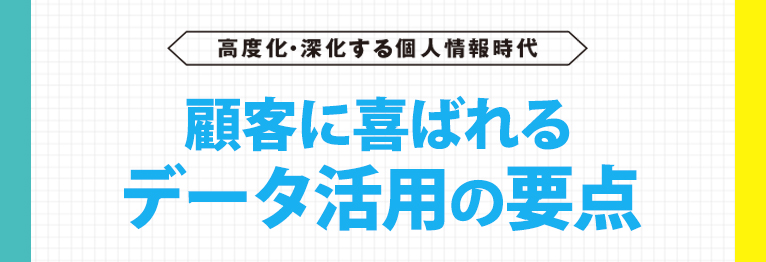実践の場において、顧客データはどのように活用すればよいのか。分析ツール「Target Finder(ターゲット・ファインダー)」を提供している東急エージェンシーに取材した。

消費者が自発的に答えるアンケートなどと異なり、行動傾向には"ウソ"が入りづらい。その行動傾向から潜在顧客を探し出す
(写真=123RF)
既存施策と比べて最大13倍の成果を収める
「Target Finder」は、顧客の購買実態や行動データを基に、潜在顧客を見つけ出し、マーケティング施策の効率を高める、顧客データ分析ツールだ。国立研究開発法人産業技術総合研究所のプログラムをベースに、東急エージェンシーが開発した。
取り扱いのデリケートな個人情報が不要で、分析前に仮説を用意する必要もない点、簡単な操作で見込み客の群を抽出し、広告やダイレクトメールの配信などに使える点が特徴だ。2015年7月に提供を開始、2017年7月にはSaaS版の提供も始めた。
たとえば「Target Finder」では、「ID-POS」のデータを基に、買い物傾向ごとに分類したIDのグループを抽出できる。仮に、自社の食品Aを購入する人は、特定の婦人服や日用雑貨を買う傾向があるとする。ひるがえせば、その服や雑貨を購入する人はほかの人よりも、食品Aを手に取る可能性が見い出せる。
ある化粧品の新規顧客の獲得を目的とした施策では、「Target Finder」で1年分のハウスカードの購買履歴を分析した。顧客IDごとに購買状況を見て、目的とした商品を買う顧客と、似た傾向を持つ未購入者のIDを抽出。そのIDを持つ人にダイレクトメールを発送したところ、それまでに実施した未購入者向け施策と比べ、最大で13倍の購入者が出たという。
購買履歴だけでなく、Webページの閲覧履歴も解析の対象となる。最終的に購入に至る人に特徴的なページの閲覧の流れを割り出すのだ。これは新規獲得もさることながら、Webサイト改善にもつながる。
「Target Finder」にかぎった話ではないが「なぜ、そういった分析になるのか、その結果に賭けることは結局のところ正しいのか」という議論がしばしば生まれる。その際、どこで納得感を得るか。統計学的にその妥当性や信頼性を説明しても、「わけがわからない。結局、大丈夫なの?」となってしまっては元も子もない。手立てが必要だ。
「『Target Finder』の使い方のひとつに、分類後に属性を見てみる、ということがあります」と話すのは、東急エージェンシーの真弓省吾データマネジメント局局長だ。
「行動傾向で分けた各グループには、何歳の、男性か女性か、どんな人が多いのかを見てみると、『なるほど、確かにそうかもしれない』と、ピンと来るケースが少なくない。それが納得の落とし所の一つになると思います」(真弓氏)
デモグラフィック属性が先に立つと、先入観が邪魔してしまうが、まずは属性を無視して行動だけを見る。あとから属性を頼りに、行動を説明できる要素を探す、という順序だ。
加えて、「実証的な姿勢が大切です」と話すのは、同局データアナリティクス部の飯塚久哲部長。
「ディスプレー広告のA/Bテストに近いのですが、効くかどうか試すということ。あるセグメントに、広告なりダイレクトメールなりのアプローチを図り、どれくらい差が出たかを見る。分析→実施→比較のくり返しで、売り上げの伸長を図るのです。そのサイクルを、属人的な視点に依存せずに回す。人間と異なる視点をもたらすことが、データの価値のひとつだと考えています」(飯塚氏)
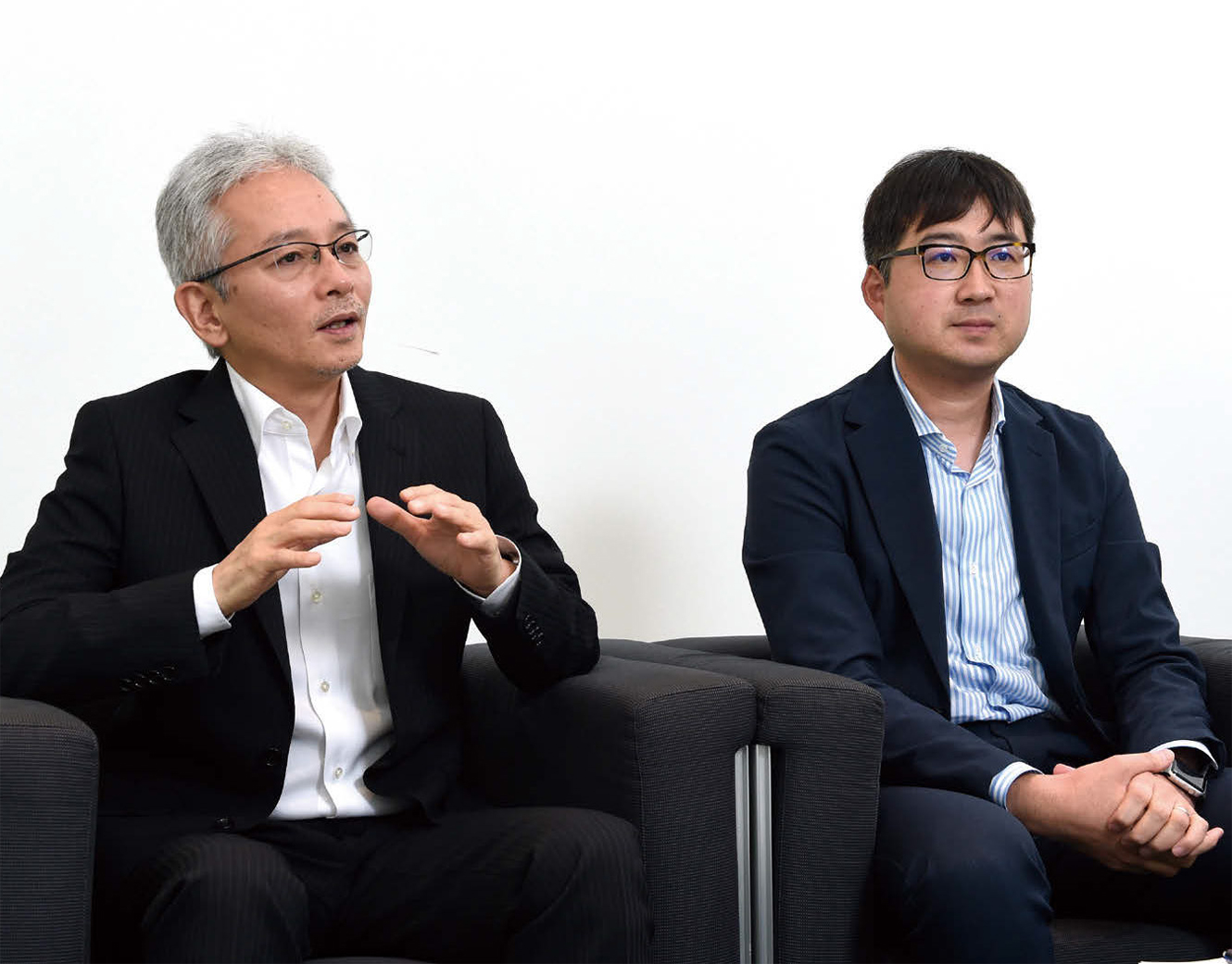
(写真左から)東急エージェンシー マーケティングイノベーションセンター データマネジメント局の真弓省吾局長、同・データアナリティクス部の飯塚久哲部長。両氏は、「広告会社がデータマネジメントに携わる意義は、タイムラグなく実践につなげられる点にある」と話す。
データとの上手な付き合い方
事業評価のサイクルが短くなり、目の前の成果を重視する傾向は高まる一方だ。長期的な視野の重要性は理解しながらも、今月の数字が未達ならその達成に目が向くのは、自然なことではないだろうか。
「短期的な成果と、長期的に成果をあげる仕組みづくり。これらに板挟みになってしまうことは、昨今のデータ活用においても、見過ごせない課題なのではないでしょうか」と、真弓氏は指摘する。
データを活用しながら着実に成果を高める取り組みは、もはや欠かせないものだ。短期的には微々たるものでも、いずれ取り返しのつかないような差がつくことになる。それはわかっていても、やっぱり目の前の数字が……といったところだろうか。
「少しずつ成果を出しながら、顧客のニーズにできるだけ近づいていくには、プロモーションとブランディング双方を備える必要があるのではないかと思います。単にレスポンスを追いかけるだけではなく、有用と思ってもらえるコミュニケーションを重ねていけば、顧客ロイヤルティを高めることにもつながります」(真弓氏)
タイムリーに人の心をつかむようなアイデアは、実に魅力的で、特別なもののように映る。一方、データから顧客を見つけ出し、アプローチを重ね、着実に成果を出していくのもまた、実は非凡なことなのだ。
「データ活用の将来に向けては、顧客理解を深めるために、行動経済学に基づく人間の行動原理を重視し、慶應義塾大学の星野崇宏教授と共同研究を開始しました。加えて、Data Chemistry社の発足に参加し、多様なデータを活用する取り組みをスタートしています」(真弓氏)
お問い合わせ
東急エージェンシー データマネジメント局データアナリティクス部
TEL:03-3475-9486(久保、藤田)