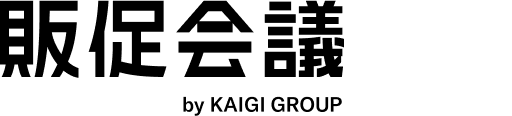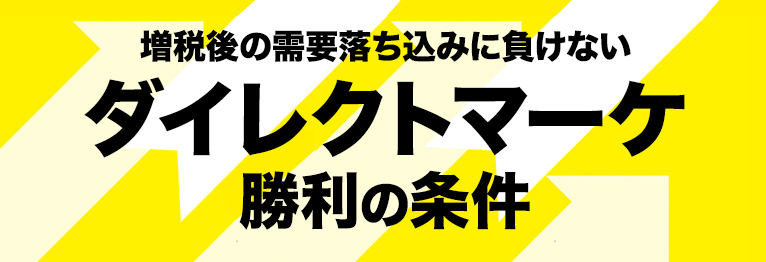ダイレクトマーケティングとデータ分析は切っても切り離せない関係にある。つまり、ダイレクトマーケの成功いかんは、データ分析が力を最大限に発揮するかどうかにかかっている。では、その力を引き出すために、私たちは何を知っていればいいのだろうか。データサイエンスやグループインタビューなどを駆使し、深い顧客理解を支援するデコムの松本健太郎氏が解説する。

(画像=123RF)
「データ分析」の重要さはいまも昔も変わらない
近年、広く世の中で、「データ分析」という語句を目にするようになりました。しかし、言葉だけが一人歩きして、そもそも何に資するものなのか。そこがおざなりになっているようにも思います。
米国ガートナー社のモデル(アナリティクスの4段階)では、データ分析には、何が起こったか(記述的分析)、なぜ起こったか(診断的分析)、次に何が起きるか(予測的分析)、どう対処すべきか(処方的分析)の4段階がある、とされます。
経営もマーケティングも製造も営業も経営企画も含む網羅的な回答としては、データ分析は、「我々は何をしたのか」「我々はどうするべきか」を知るために必要です。「どうするべきか」というのは、利益増大のために、業務効率向上のためにどうするべきか、という意味です。
とは言えこれは、いまに始まったことではありません。これまで人間が、データに頼ることなく「何をする」「こうする」と決められることがあったかと言うと、そんなことはないはずです。
データとは数量ではなく、情報のこと。では、情報とは何か。それは「不確実さを減らすもの」です。
いわゆる"KKD"、勘や経験、度胸も、不確実さに対抗できるものかもしれません。しかし、あまりに属人的すぎて、人材育成や試行錯誤には向きません。
私たちは、組織として継続的に改善をくり返していくために、データ(情報)に向き合ってきたのです。何が起きたかを記述し、その原因を探り、しからば、次はこれこれが起きるはずなので、こう対処する──この一連の流れは、歴史的に大きく変わりません。
それなら、ここまで「データ分析」が注目を集めているのはなぜか。ひとつには、インフラ基盤が安価になり大量のデータを保有できるようになったこと。そして、データサイエンスの手法が民主化され、「R」(統計解析のためのオープンソースソフトウエア)や、「Python」(パイソン、プログラミング言語の一つ)を用いて、簡単に取り組めるようになったこと。これらの環境要因が挙げられると思います。
しかし、やっていることは、昔と何ら変わらないというのが私の意見です。
分析までの準備が重要 目的設定とデータの確認
「手元には膨大なデータがあるが、どうすればよいか」という声を、よく聞きます。しかし、この問いの立て方は、転倒してしまっています。
データサイエンスビジネスのプロセスの前半は、「何がわかればよいのか」という目的を定める→「それを説明するために必要なデータ」の有無を確認する、というふうに始まります。ない場合は計測をするということです。データはあっても正確さに問題があるケースも少なくなく、そのときも計測し直しになります。
データ分析は、分析までの準備が重要です。また、分析後に、ほかに計測すべきデータが見つかったり、目的がそもそもおかしいことがわかったりすることもあります。
「何がわかればよいのか」を見定める上で、そもそも自分たちがどのように業務を進めているのか、つまり業務プロセスを視覚化したほうがよいケースもあります。ただ、その過程で、プロセスの改善を図りたくなっても、それは周囲の反発を招くだけです。あくまで最初は計測するだけ、結果が出たのちに、「このプロセスは適切なのか?」という議論をすべきだと思います。
「データ分析が大事だ、データ分析をせよ」という指示があったとしましょう。おもむろに「データ分析」とWeb検索してみると、「データ分析とは?」「データ分析基礎知識」「データ分析の本質」…などのタイトルが並びます。
「データ分析をしてみよう」→「データ分析とは何かを理解しよう」という思考の流れは落とし穴──と言いますか、無駄です。おいしい料理を食べようとして、プロの料理人に、使っている包丁は何か、それはなぜよく切れるのか、そして、料理の本質とは──を尋ねるようなものです。尋ねてもよいですが、それより、どんなものが食べたいかを伝えるほうが先ではないでしょうか …