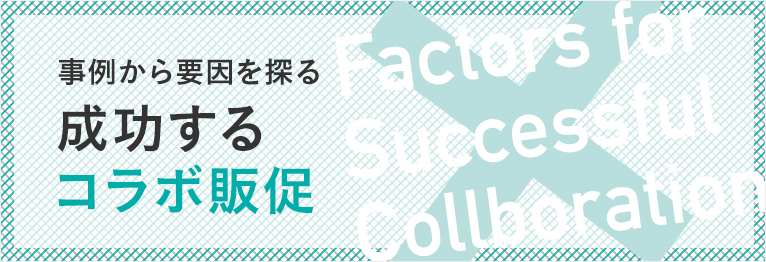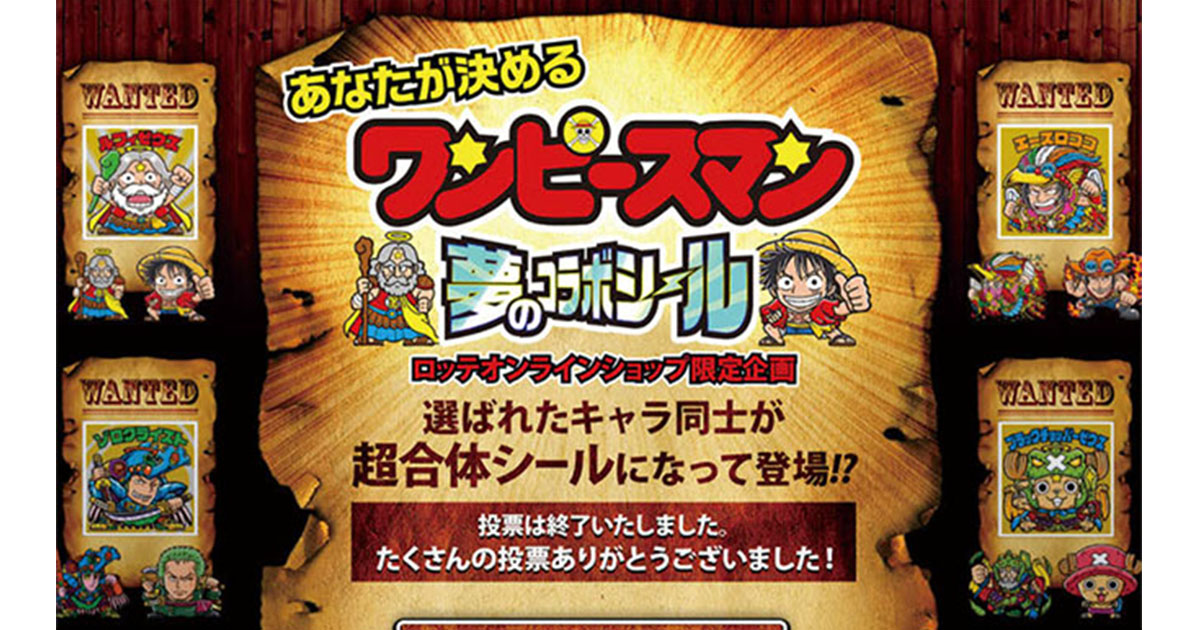ライザップとファミリーマートのコラボレーション商品「ファミマでライザップ」の売上高は、2017年10月時点で、累計40億円達している。おいしく手軽に糖質をコントロールできるフードメニューとして、2016年11月に発売開始後、サラダやカレー、パスタなどさまざまな糖質をコントロールした商品を扱う。商品数は累計50種類を超え、コンビニの健康食品に新風を巻き起こしている。

(左)RIZAP
RIZAPプロダクト事業部 企画開発ユニット 栗田奈央美氏
(右)ファミリーマート
上席執行役員 商品本部長補佐 兼 商品・マーケティング部長 青木 実氏
それぞれが感じるメリットとは?
──まず、どのようなことがきっかけでコラボをすることになったのですか
RIZAP 栗田奈央美:もともとライザップでも、健康を目的とした低糖質商品を手に取りやすい価格で販売し、お客さまに広く健康的な食生活をお届けしたいと考えていたんです。全国に多数展開しているコンビニは一般認知を高めるのにぴったりの場所でした。
ファミリーマート 青木実:お客さまの健康意識が高まる中でファミリーマートでも糖質量に配慮した食品の開発・販売を考えていたので、ライザップとのコラボにつながりました。コラボ商品の標語は「おいしさにコミット」。ファミリーマートの商品開発では、お客さまが「おっ」と思えるようなおいしさと楽しさ、そして驚きの提供を目指しています。そのため単に糖質を抑えるだけではなく何度も食べたくなる「おいしい」商品を生み出して、うれしい驚きを提供しようと考えました。
──コラボのメリットは何でしょうか
青木:ファミリーマート側のメリットは、ライザップの高いブランド力です。新商品は、お客さまに知っていただくまでに時間かかります。しかし、ライザップはお客さまの認知度が高く、そのブランド名やロゴマークから「低糖質」「ダイエット」といったイメージがすぐに頭に浮かぶので、お客さまに瞬間的に「これは糖質量に配慮した商品だ」と認知され、商品を浸透させやすいと考えました。
新商品の最大の課題は認知度向上です。ライザップとのコラボで、最も時間がかかる認知度向上を即座に達成できました。
栗田:ライザップ側のメリットは、全国のファミリーマートの店舗で商品展開できることです。当社は事業の拡大を続けていますが、さらに多くの方々にライザップの魅力を伝えたいと思っています。ライザップの減量期に行っている糖質コントロールと運動をメインにしたダイエットプログラムは知っていても、ライザップが開発した食品のことは知らない方が多いでしょう。そこで、全国のファミリーマートの店舗を利用させていただくことで、ライザップの食品について知られるきっかけになりました。

「おいしさにコミット」という標語のもとに開発されたコラボ商品の数は、累計で50種類を超える(10月時点)。
受け入れられやすい商品から
──コラボにあたって苦労したのはどんなことでしたか
栗田:ひとつは、ターゲットにしているお客さまが異なる点です。ライザップでは健康意識がとても高い方をターゲットにしていますが、ファミリーマートでは一般的なお客さまをターゲットにしています。そのため、ライザップに通うくらい健康意識が高いお客さまだけでなく、より広い客層に向けて商品を提供するファミリーマートで展開する以上、互いの中間点を探って一般的なお客さまにアプローチできる商品になることを目指しました。
青木:健康訴求の商品は伸びしろのあるラインで、ファミリーマート・サークルK・サンクスにいらっしゃるお客さまのうち3割弱のマーケットが将来的に見込めると考えています。ただし現段階ではまだ成長段階であり、その訴求に向けて長期戦でじっくりと取り組む必要があります。そのため初めから極端にストイックさを高めた商品ではなく、これから始める方のきっかけになるような、ライトな商品から開発したいと考えました ...