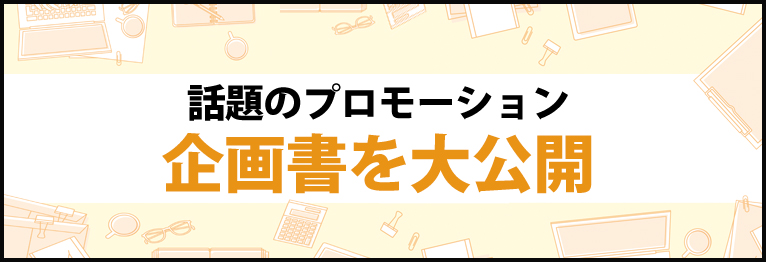電通のクリエーティブ・ディレクター中尾孝年氏と、NECマネジメントパートナー小湊孝志氏が本特集のテーマ「企画書」について対談。中尾氏はアイスの実「江口愛実」キャンペーンなど、東名阪と異なる環境で数々の話題広告・キャンペーンを生み出してきた実績を持ち、一方の小湊氏は25年のグラフィックデザイナー経験を経て、NECの資料制作を手がけるスライド設計のプロだ。企画考案から企画書作成に至るまで、2人のメソッドを聞いた。

(左)電通 クリエイティブディレクター 中尾孝年(なかお・たかとし)氏
(右)NECマネジメントパートナー コンテンツマーケティング部エキスパート 小湊孝志(こみなと・たかし)氏
良い企画であるほど、企画書もわかりやすい
──「良い企画書」というものがあるとすれば、それはどのようなものでしょうか。
中尾孝年:「企画書」とは、その企画を実現させるためのものです。そのため、「企画書の良し悪し」というものがあるとすれば、アイデアを現実のものにできるかどうかが、そのひとつではないでしょうか。「良い企画書」の条件はまた、企画・アイデアのすばらしさをまっすぐ伝えていることです。当然ながら、イマイチなアイデアを良いものに見せかけることではありません。なので「良い企画書」の要素はなによりも、「良い企画」であるということになります。当たり前のようですが。
小湊孝志:では「良い企画」というと何かという話になりますが、それはもちろん、「課題をきちんと解決するもの」ということになります。同じ「解決する」でもコストが低いほうがいい、といった見方も当然あるでしょう。
中尾:そうですね。企画を考えるうえで必要なのは、アイデアの発想力よりも、解決すべき課題をクリアにできることではないかと思います。まさに「良い企画」とは、課題に対して明確な解決策を提示するものであるべきです。
小湊:ただそもそも「いったい何が課題なのかがわからない」というケースもありますよね。
中尾:そうなんです。オリエンテーション(解決すべき課題の前提などを説明する場)で依頼主が提示した課題が、いつも正しいとは限りません。一度立ち止まって熟考し、表面化している問題の根っこには何があるのかを見定めることが重要です。根本的な課題を突き止めてから、その解決策を考える。
課題を正確につかめれば、解決策の精度も増します。解決策が明確な企画はわかりやすく、伝わりやすいので、企画書にまとめやすくなる。反対にイマイチな企画は、解決策がアヤフヤなので企画書にしにくい。解決策がぱっとしないのは課題があいまいだから。もし企画書作りに手間取るようなら、そこに原因があることが考えられますね。
ノートPCを閉じてみよう 「筆圧」に自信の有無が出る
──おふたりは、(課題が見つかった後の)解決策、つまり企画をどのように考えていますか?
小湊:僕はどちらかというと企画を考えるよりも、それをどう見せるかを日々考えていますが、ただ企画を考える時は、とにかく考えて考えて考えて……と、思考量を増やしていきます。そして、たくさん考えた後に一度寝かします。いったん区切ると、企画が頭の中で熟成される。その熟成期間を経て、良い企画が突然ポンと出てくることが多いように思います。延々と考えすぎると思考が迷走してドツボにハマってしまうので注意が必要です。
中尾:僕は紙に書き出しながら企画を考えますね。個人的にはデジタルよりもアナログのほうが一覧性も高く、パッと見ただけで思考の流れを追えるので便利ですね。一度寝かせた後でも、紙を見ればすぐにその時の思考に立ち戻れる。あと、僕は文字の筆圧や大きさに自信の有無が表れるように感じるんですよ。無意識の部分まで見えてくるようです。
小湊:企業では、企画会議を開いて複数人でアイデアを出すことも少なくありませんが、会議室に入ってすぐノートパソコンを開き、みんながパソコンの画面を見ながら企画を練るのは良くないなと感じています。何かアイデアが出るとパソコンで関連資料を調べがちですが、それは過去の情報を掘り起こして並べているだけ。そこから企画として新しい何かを見つけられるわけではないんですよね ...