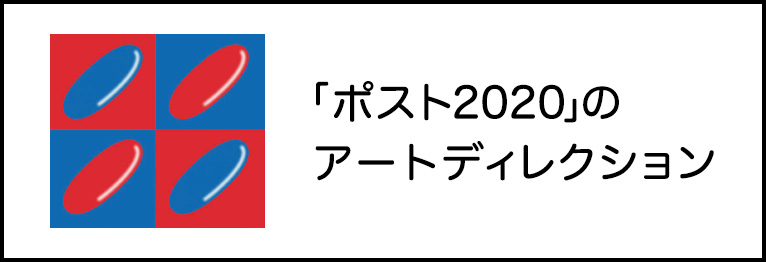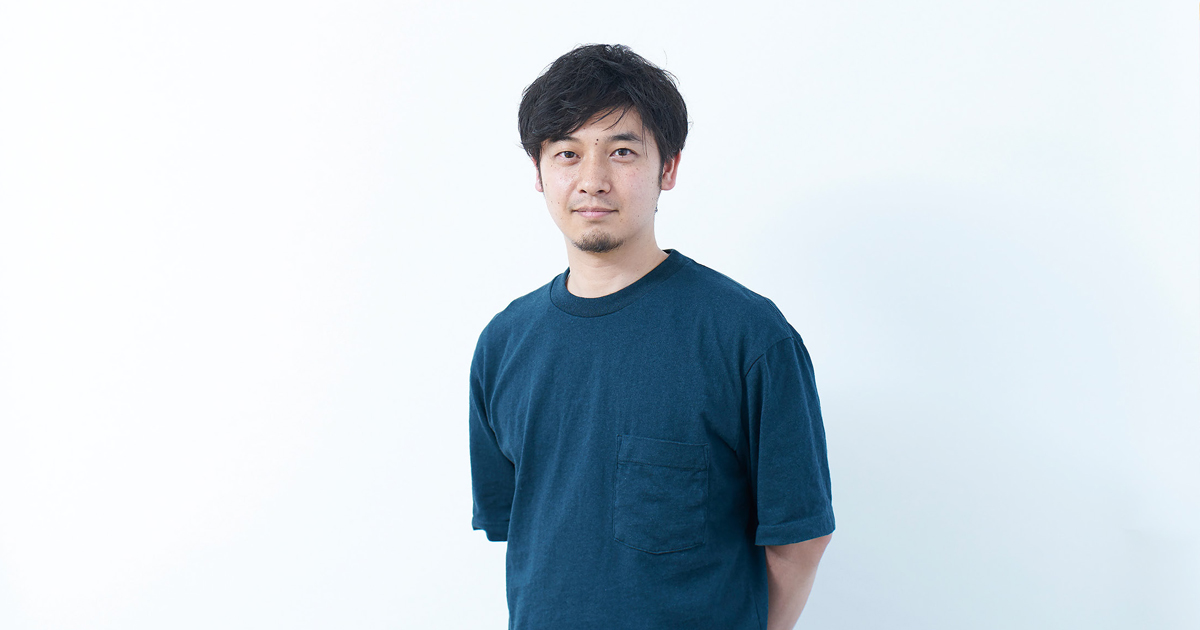「コンピューテーショナルデザイン」を確立し、定着させたい。それを実現すべく、木村浩康さんは日々の仕事の中でさまざまな試みを続けている。

ライゾマティクス アートディレクター/インターフェイス・デザイナー 木村浩康(きむら・ひろやす)
東京造形大学卒業後、Webプロダクションを経てライゾマティクスに入社。文化庁メディア芸術祭最優秀賞など多数受賞。
デジタルデザインからコンピュータの手癖を取り除く
──この10年の間でご自分の仕事を取り巻く環境はどのように変わりましたか。
この10年は僕が所属するライゾマティクス(以下 ライゾマ)という会社が大きく変化を遂げた時期でした。設立当初の仕事はまさにホームページ制作などWeb中心でしたが、社内のR&Dとして制作していたデジタルインスタレーションが店舗などの空間やイベントなどリアルな施策で活用されるようになりました。デジタルインスタレーションは、すでに広告のひとつのジャンルとして確立されていますよね。そのような広告の変化とライゾマティクスという会社の動きが呼応していた10年でした。
最近のライゾマは、"ザ・広告"的なものから、少し離れつつあります。というのは、クライアントと直接向き合って、広告とは違う形で課題解決に取り組むケースが増えているからです。一方で、真鍋大度はELEVENPLAYと一緒に身体性とテクノロジーを融合させる舞台などを作ることにも力を入れています。テクノロジードリブンの仕事がほとんどなので、ジェネレイティブデザインというべきか、コンピュータを使ったデザインを確立させていきたいと思う一方、この2、3年で自分が模索していたのは、コンピュータの手癖をいかに無くしていくかということです。
──そう考えたきっかけはあったのですか。
2016年にギンザ・グラフィック・ギャラリーで「グラフィックデザインの死角」という展覧会を行ったことです。その時にグラフィックデザイナーの方たちと話をする機会を得ました。テクノロジードリブンの会社なので、グラフィック・ギャラリーにできるだけ相応しいものをという狙いで企画を進めたのですが、展示を見た古平正義さんから「なんか、"コンピュータ君"が手癖で作ったみたい」と言われ、それが自分の中で強く響きました。
痛いところを突かれた、というよりも、言われてみれば確かにそうだと思うところもあり、それからコンピュータの手癖について考えるようになったんです。ライゾマにいる以上、テクノロジードリブンでものづくりをすることがほとんど。でも、スクリーンの中に人の血が通うようなものを融合させることができれば、ライゾマ発のアウトプットとして、ひとつステップアップできるのではないかと思いました。

「グラフィックデザインの死角」館内
──具体的にはどんなことを?
例えば、ライゾマが得意とするデータを可視化するデータビジュアライゼーション。データをそのまま使うと機械的になってしまうところに、人の意思を流し込むようなこと、デジタルだけれど、もっと泥臭いことができないかと考えています。それを、うまく言葉にするのが難しいのですが(笑)。
事例でお話しすると、ライフサイエンスと画像解析のスタートアップ「エルピクセル」のサイトは、そういう考えのもとデザインしました。エルピクセルは、ディープラーニングでさまざまな医療画像解析を行う技術を持っているので、そのデータを使って僕らが得意とするデータビジュアライゼーションで表現することは可能でした。でも、ライフサイエンスがテーマの会社なので命を感じさせるものを作りたいと思い、実際に使ったのが脳のMRI画像です …