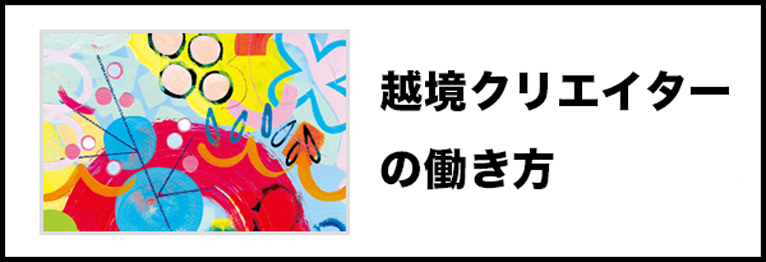建築家、デザイナー、音楽家、エンジニアなど、多様なバックグラウンドを持つ7人のクリエイターで構成される「nor(ノア)」。ここから生み出される作品もその活動スタイルも、いずれもこれまでの既存の定義に当てはまらない。「nor=いずれでもない」という言葉を体現するクリエイティブ集団だ。

norのメンバー。メンバーの1人である中根智史さんが所属するTechShop Tokyoにて。
わからないものへの探究心が7人を結びつけた
会社も職種も異なる7人は、2016年11月、東京で開かれたアートハッカソンイベントで出会った。ハッカソンのテーマは「生命体としてのテクノロジー」。参加の動機はそれぞれだったが、テーマについてディスカッションする機会があり、そこで作ってきた作品やクリエイティブに対する思想を確認し合い、興味関心の領域が近い7人でチームを組み、作品を制作することになった。
ここから生まれたのが第1作の「SHOES OR」で、ハッカソンの最優秀作品賞を受賞した。その副賞としてアーツ千代田3331αの展示スペースの使用権を得たのを機に、活動を始めたのが「nor」である。
「クリエイティブレーベル」という呼び方は、音楽レーベルと近い感覚で使っている。活動のコンセプトやテーマ、目指すものは共にしながらも、参加するメンバーは作品ごとに変わって構わないと考える。外からメンバーが加わってもいい。その枠組みを包括するものとして「レーベル」という言葉を使った。「nor」の「n」は、入れ替え可能な変数も意味する。
メンバーは、普段はクリエイティブエージェンシー、制作会社、UI/UXデザイン会社、ソフトウェア開発会社などに籍を置き、norには全員がパラレルワークとして参加する。これまで3つの作品を作っているが、いずれもICCや六本木アートナイト、Media Ambition Tokyoといった展示する場所のみが用意された状態で始まっている。norでは「何を作るべきかのお題を、全員で探すことから始める」という。
「自分たちでやりたいこと、興味のあることを出し合って議論し、全員が納得して初めて実現のために動き出します。僕らは作る時間よりも、何を作るかについて議論している時間の方が長いんです。自分たちでテーマを設定する作業がnorの活動では重要なので、『こういうものを作ってほしい』という制作の依頼は、norの活動とは相性があまりよくありません。依頼を受けないわけではありませんが、『一緒に作る』メンタルのある人との方が組みやすいんです」と建築家・エクスペリエンスデザイナーの板垣和宏さんは言う。
バックグラウンドの異なるメンバーに共通しているのは「学びに対する探究心」だ。ハードウェアエンジニアの中根智史さんは、「最初のハッカソンのテーマ自体がそうでしたが、答えがわからないものに対する知識を深めていく探究心が強いメンバーが集まっているのだと思います」と話す。議論の時間が長いのは、出自の異なるチームメンバーが議論し異分野が交錯するその時間自体が、学びに満ちているからだ。
作曲家・サウンドプロデューサーの小野寺唯さんは、「専門分野だけの中で仕事をしても従来の枠組みは越境できません。ここではアイデアの初期段階から全員がフラットに参加して同時に考えるので、幅広い視野で総合的に考える学びの場となります。プランナーがアイデアを考えて、プログラマーに発注するような制作プロセスではありません」と言う …