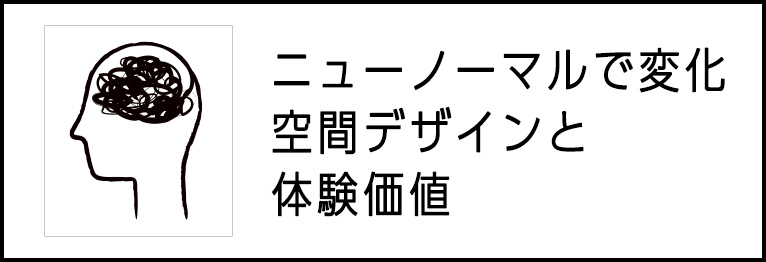群馬県のJR前橋駅から徒歩約15分の場所に2020年12月にオープンした「白井屋ホテル」。車通りの多い国道50号線と、用水路のある昔ながらの「馬場川通り」にはさまれた土地にたたずむ、その建物。前橋市の「まちなか」の活性化がこのホテルから始まろうとしている。


ヘリテージタワー内のオールデイダイニング「the LOUNGE」。植物とアートに囲まれた、心地よい空間。©Katsumasa Tanaka
ホテルづくりから、街づくりへ
白井屋ホテルは、江戸時代から1970年代まで続いた旧宮内庁御用達の「白井屋旅館」、そしてその後2008年まで続いた「(旧)ホテル白井屋」の後身にあたる。(旧)白井屋は、前橋市の中心街の過疎化に伴い、08年に廃業を余儀なくされたのだった。
その後廃虚のような状態であったが、今回、建築家 藤本壮介さんの手により劇的な変化を遂げることとなる。建物は、1970年代に建てられた(旧)白井屋の骨格をそのままに、4階までの大胆な吹き抜けを生み出した「ヘリテージタワー」と、利根川の旧河川の土手をイメージして新たに建てられた「グリーンタワー」の2棟に。ヘリテージタワーの吹き抜け部分には、渡しや階段が縦横無尽に張り巡らされ、その様子に「エッシャーのだまし絵のよう」と、来館者からも声があがる。
このプロジェクトを率いたのが、ジンズホールディングス 代表取締役CEO 田中仁さんだ。プロジェクトの経緯をよく知る前橋まちなかエージェンシー 代表理事 橋本薫さんは、立ち上げ当時のことをこう話す。きっかけは、2013年。
「当時の前橋市は今よりさらにさびれていて。僕はその頃、仲間と共に前橋市の中心市街地“まちなか”を盛り上げる活動をしていました。その中で美術館『アーツ前橋』がオープンすることに。開館の際、僕を含む地元の若者と田中さんに代表される前橋出身の有名人とのトークイベントがあり、それが田中さんとの出会いでした。田中さんと話す中で『どうせなら本気でやろうよ』と声をかけていただいて。本格的に前橋市のための活動に力を注ぐことになりました」(橋本さん)。
そこから白井屋ホテルの再建につながったのが、田中さんがよく口にしていた、こんな言葉だった。「しかし前橋には、いいホテルが無いよね」。時を同じくして、橋本さんはとある噂を耳にする。「閉館後長らくそのままだった白井屋がついに売りに出されるらしい。そこを東京のディベロッパーがマンションにするらしい」。橋本さんは、「それを聞き、つい田中さんに『ホテル、どうでしょう?』と話をしていました。当時僕は白井屋とは全然関係なかったんですけどね(笑)」と振り返る。
「実はその時、他にも数人から声をかけられていて。売却には慎重だったオーナーさんを説得し、購入することになりました」と、田中さん。ただ当時は、「(購入後は)ホテルの専門家に任せよう」と考えていたという。「しかし、ホテルのコンサルタントには『まず無理』だと言われました。当時の前橋市は全国の県庁所在地の中で路線価格最下位の街。言われてなるほどと思ったのは、『ホテルはニーズがあるところに生まれるもの』という言葉です。では前橋の魅力は何か、と考えてみても、答えられない自分がいました」(田中さん)。
群馬県の中核が高崎市と前橋市とで分かれており、新幹線の駅もある高崎市に商業的なものが吸収されつつあったこともその理由だろう、と分析する。
では前橋市が掲げる、市の目指す姿とは、どんなものなのか。答えを探しても、当時の前橋市にはビジョンも存在しない状況だった。それならばと、ドイツのコンサルティング会社 KMS TEAMに、外部の視点から前橋市の分析を依頼。その結果2016年に生まれたのが、ビジョンの原型となった「Where good things grow(良いものが育つまち)」である。さらにそこから、前橋市出身のコピーライター 糸井重里さんの解釈により「めぶく。」という確固たるビジョンが生まれた。
「つまり、街の再建が当初からの目的だったわけではなく、ホテルづくりを起点として、街づくりに広がっていったわけです」と田中さん。街のビジョンづくりとホテルづくりとが...