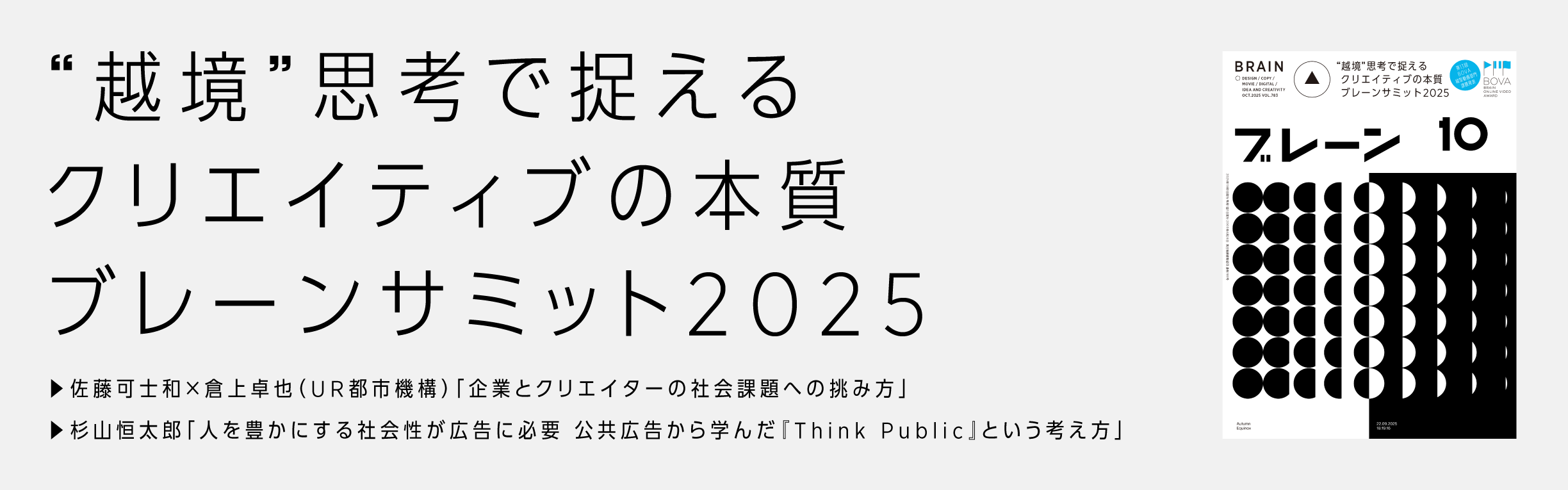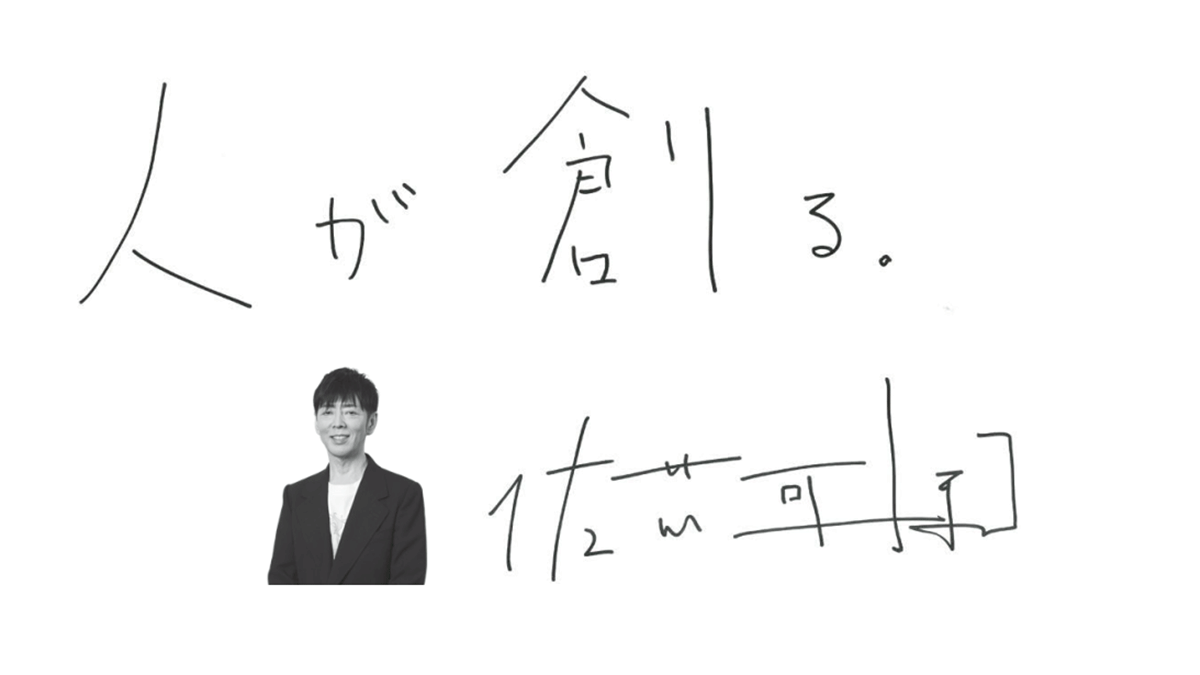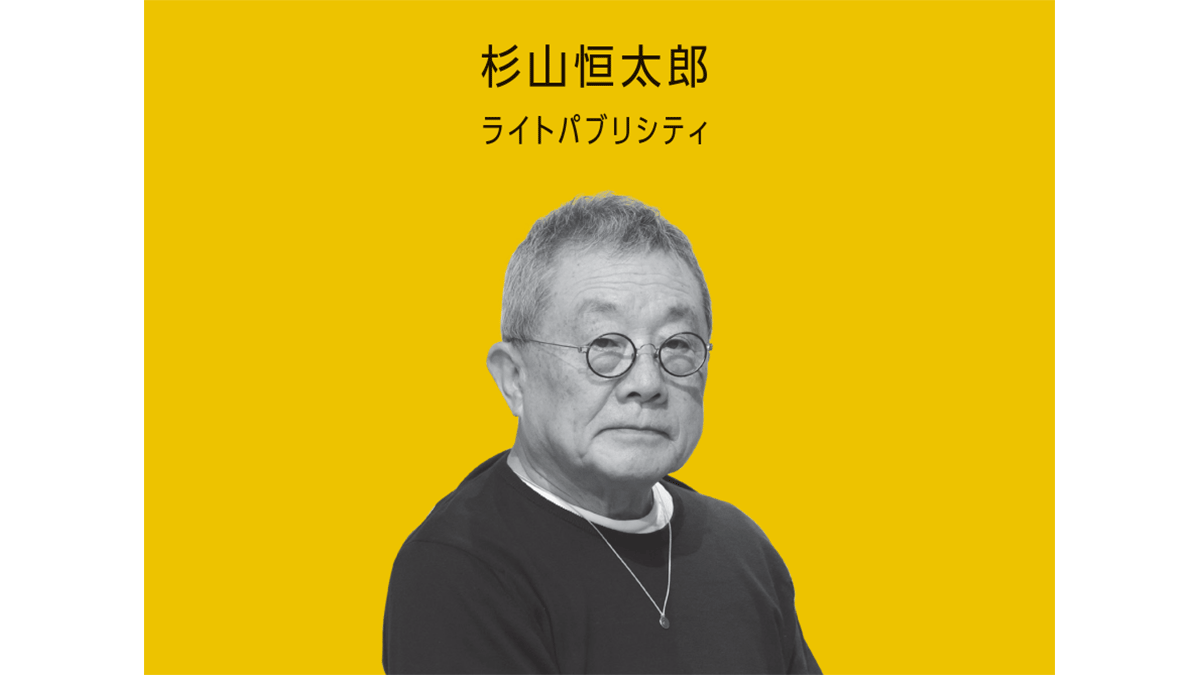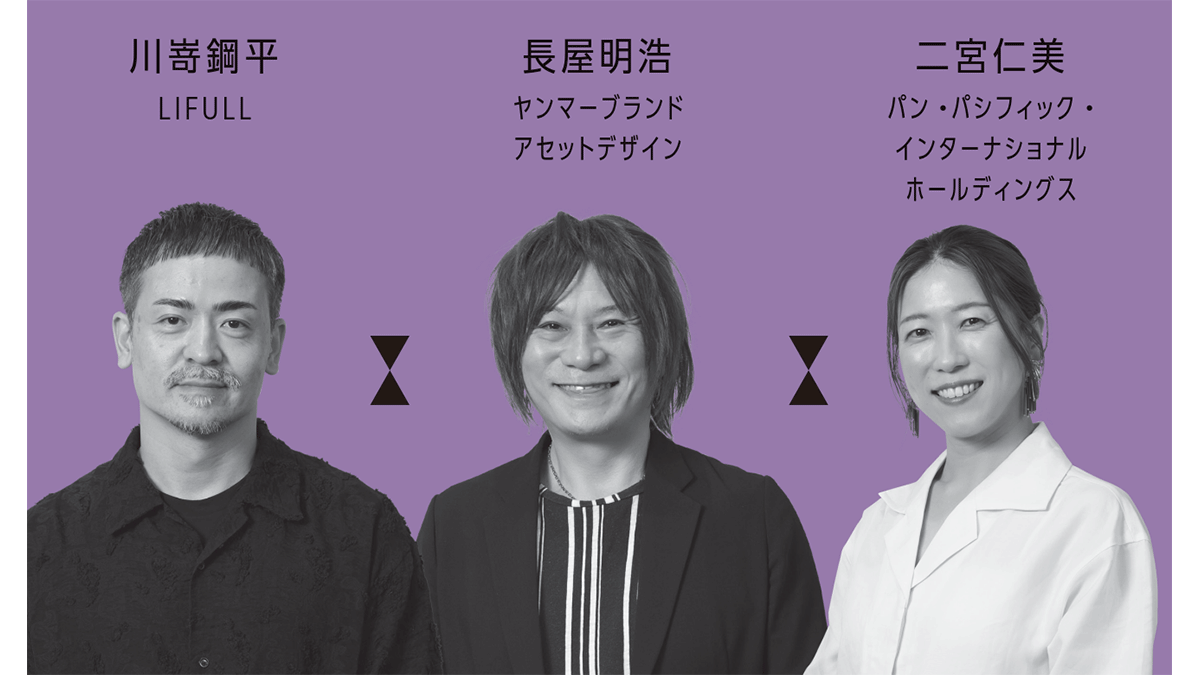社会課題への対応が企業の成長戦略に不可欠となったいま、企業はどのようにアプローチするべきなのでしょうか。「団地」が抱える2つの“老い”という課題に約15年取り組んできたUR都市機構と佐藤可士和さん。両者がたどった軌跡を振り返りながら、これからの社会に求められる企業とクリエイターの共創の在り方を探ります。
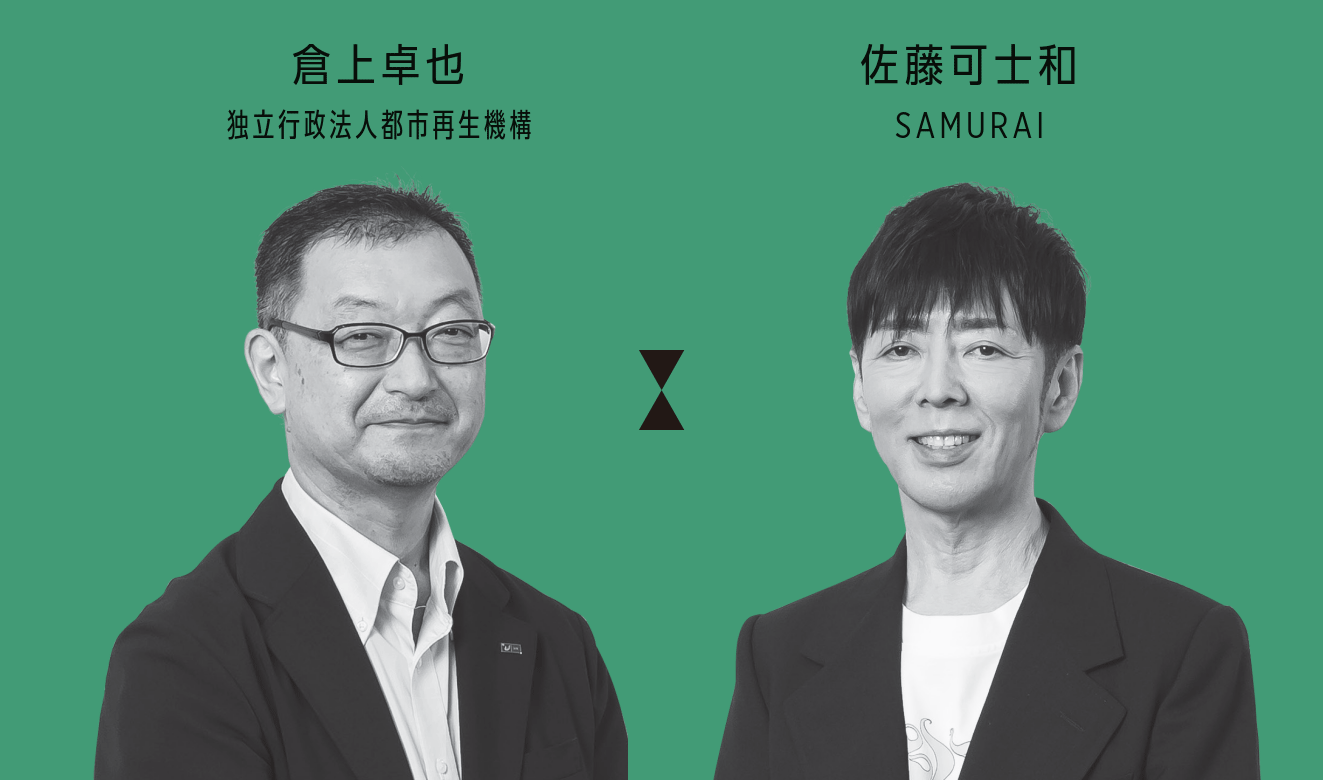
団地が抱える2つの「老い」
倉上:現在、URが管理している賃貸住宅は全国に1408団地、約70万戸あります。そのうち築40年以上経過している団地は全体の6割以上。新築の頃から住み続けている方も多く、居住者の高齢化も進んでいます。団地と居住者という2つの「老い」が、URの大きな課題となっていました。
こうした課題を解決するために、2011年から、佐藤可士和さんや建築家の隈研吾さんを中心とした多様な分野の専門家の方々からアドバイスをいただく「アドバイザー会議」と、居住者や地域の方を含めてエリアマネジメントについて話し合う「エリア会議」と題した2つの会議の場を設け、話し合いを重ねてきました。
佐藤:僕は2011年から携わって、約15年になります。2つの会議をその後「団地の未来プロジェクト」とし、横浜市の洋光台団地をモデルケースとして、新たな団地の在り方を模索してきました。洋光台団地で社会実験を行い、成果のあったことを全国の団地に共有していこうという計画です。
団地のアドバンテージのひとつは、豊かな共用部があることです。広場や小道があり、まるで公園に隣接しているような住環境は珍しいと思います。ただプロジェクト開始当時の洋光台団地は、敷地内の木が育ちすぎてうっそうとしていたり、小道が汚れてしまっていたり、いろいろと手を加える必要がありました。
とはいえ、建物が新しくなったり...