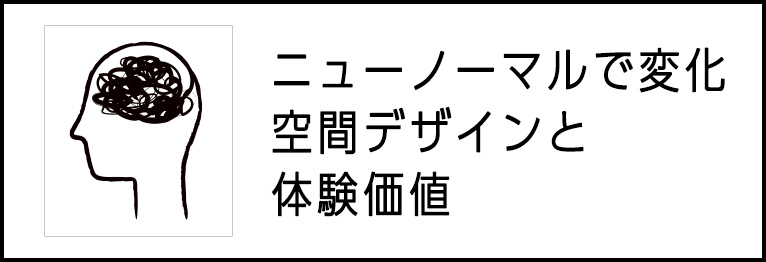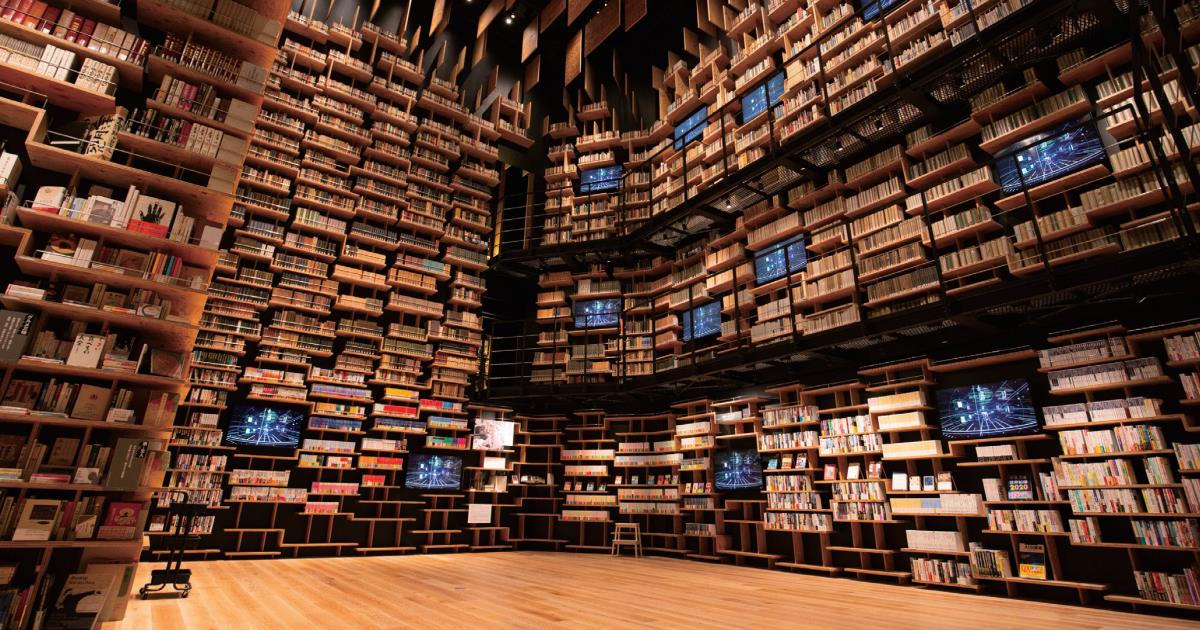京都の中心街、式阿弥町に2019年10月に誕生した「共創自治区SHIKIAMI CONCON(こんこん)」。多種多様な職種の人々がコンテナに入居しそれぞれの活動拠点にしている。「コワーキングスペース」とも少し違う、その在り方について話を聞いた。

「こんこん」の入り口近くに位置するワインスタンド「TAREL」。©Stirling Elmendorf
長屋とコンテナが組み合わさった空間
「こんこん」は油小路通り沿いに位置し、建物は通りから奥へと細長く続く。歩みを進めると、そこには木造長屋3棟と大小のコンテナ19基を組み合わせた異色の空間が広がる。入居しているのは、入り口に位置するワインスタンドや、デザイナー、コピーライター、古着屋店長、不動産仲介業者、福祉施設の運営者、カメラマン、時には研究者チームなどさまざま。それぞれコンテナを月ごとに借り、拠点としている。
この空間を生み出したのは、京都・崇仁新町横丁の空間コンセプトの開発などに携わった経験もある、コンサルティングファーム Nue(ぬえ)代表の松倉早星さん。同社の事務所もこんこんの中にあり、スペースや入居者のコミュニティ運営も松倉さんらが担っている。「こんこんをつくったきっかけは、2017年に長屋3棟と当時駐車場だった土地のオーナーから“この空間で何かできないか”と相談を受けたことでした。初めて土地を見たときから、コンテナを使って空間をつくりたいと思ったんです」と松倉さんは振り返る。
コンテナに興味をもったのは、十数年前に「ミラノサローネ」で、コンテナを使った空間設計を見た記憶からだ。「カラフルなコンテナが自由に組み合わさったさまが印象的でした。実際に大阪港に中古のコンテナを見に行きましたが、外国の港で書かれた記号やサイン、働いている人の手垢が残っていたりして、ビンテージの家具のように絵になるんです。それに世界中を旅してここにたどり着いているのが素敵だなと思って。新品ではなく、中古コンテナを使ってスペースをつくることにしました」。
大阪を拠点にコンテナを活用した物件を多数手がけるmuura 中川泰章さんのコンテナ内の事務所を実際に見に行き、「自分の仕事にフィットする形にカスタマイズしてあり、自分の城のよう」と驚いたことも後押しになったという。
そこで課題になったのが、古くから続く景観の美しさを守るために設けられている京都の景観条例だ。「日本一厳しいと言われているほどで、明るい色のコンテナはNG。すべてモノトーンのコンテナを選び、通りからも見えないようにしています。これまでの空間開発の経験のなかでできなかったことを詰め込みたい一心で、行政との交渉も進めました」。

油小路通り沿いに位置し、建物は奥へと細長く続く。通り沿いからは、コンテナは見えない仕様に。景観条例対策の一環だ。©Stirling Elmendorf

奥に進むにつれ、コンテナが詰まれた全体像が見えてくる。©Stirling Elmendorf
共創しながら自治する「共創自治区」
コンテナを利用することと同時に、松倉さんは初期段階から「共創自治区」というコンセプトも提案している。イメージしたのは、小さな魚が集まって大きな魚を形づくった絵本の『スイミー』のようなあり方だ。「最近は京都にもフリーランスのクリエイターが増えてきましたが、1人で戦うには厳しい状況です。たとえばデザイナーは、本来デザインに時間をかけたいのに、仕事を得るために営業にかける時間も...