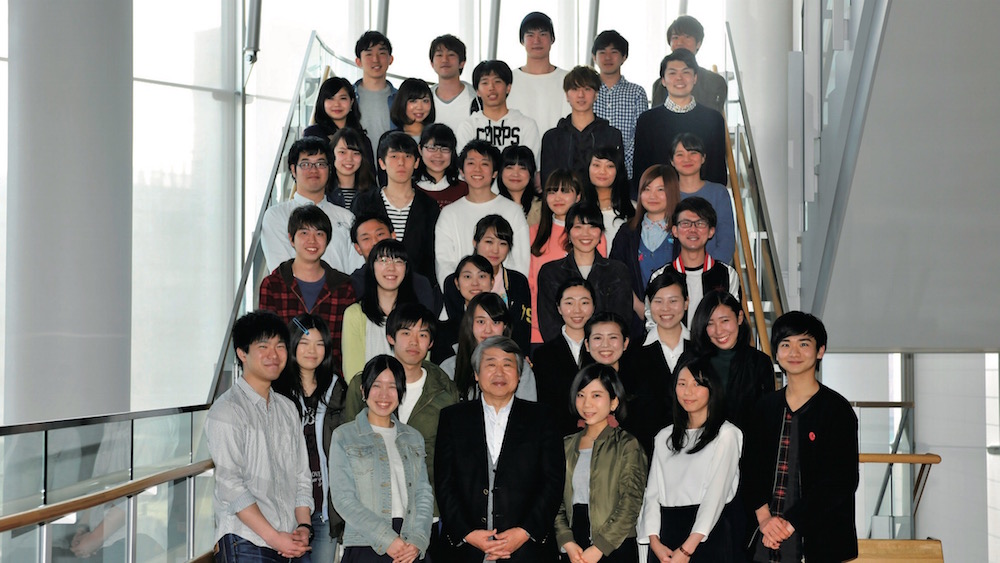「ブランドスイッチ」の理由をアンケート調査でひもとく
専修大学商学部で2013年4月から講師、15年4月からは准教授として教鞭をとる八島明朗准教授。研究のテーマはマーケティングと消費者行動論だ。
消費者はどんなときに、どんな理由で利用しているブランドを変えるのか、また企業が自社のブランドに乗り換えてもらうためには、どれくらいのコストがかかるのか。「ブランドスイッチ(乗り換え)」や「スイッチング(乗り換え)コスト」を明らかにすることが研究の目的だ。主に携帯電話会社を題材に、アンケート調査によるデータ分析を行う。
消費者を囲い込み、ブランドスイッチを防ぐには、満足度を高めることが王道だ。しかし、八島准教授は「ちょっと変化球ですが、消費者はイヤだと感じながらも使い続けることが少なくありません。例えば携帯電話だと、割引があったり、変更の手続きが面倒だったり、という理由で使い続ける人もいます。そうしたネガティブな要因による影響に着目しているところは、私の研究の特徴だと思います」と話す。
研究ではアンケート調査で、一方のグループにインセンティブを与えるサービス、もう一方には手数料を軽減するサービスを評価してもらい、それぞれのプロモーション効果を比較分析する、といったことを行う。
アンケート調査による仮説は、実際の消費者の動きにつながらないのではないかという考え方もあり、八島准教授もその点は認めている。現実に起こったことを調査するのであればビッグデータを用いた方が精度は高まるが、アンケート調査は実際には起こっていない、現実にはない状況も仮説として設定でき、人の評価を検証することが可能だ。八島准教授は、それぞれの特性を理解した上でアンケート調査を選択している。そうして積み重ねた結果から …