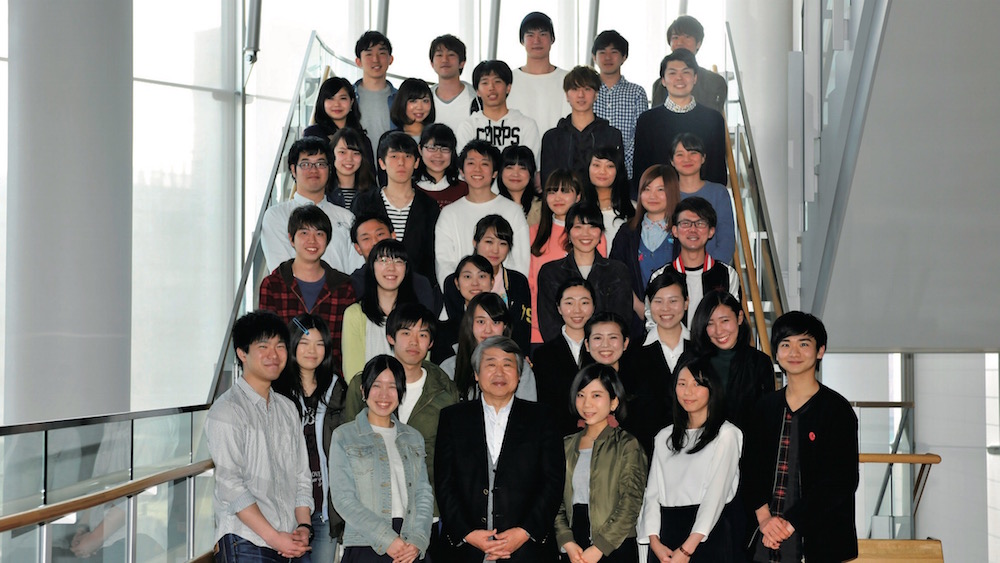価値を生みだす主体は消費者の側にある
東京経済大学経営学部の森岡ゼミナールは2011年5月に開設され、14年4月に2期目の学生が卒業したばかりの新しいゼミだ。
指導する森岡耕作准教授は、消費者行動に注目したマーケティング現象の研究を進めている。ブランド構築を消費者の観点からとらえ、口コミやソーシャルメディアなどによる消費者間のコミュニケーションがブランド形成にどう作用するのか、についても調査している。
ブランドや企業イメージは、発信する企業の側が築いていくものと考えられがちだが、消費者側がどう見て、どう感じるかで決まっていくという側面もある。こうした視点に立つと、消費者は単に商品を購入する側、サービスを受ける側ではなく、自ら何かを生みだす存在であるとも言える。森岡准教授は、「最近は、消費者のような価値受容者が実は、価値を生みだす主体でもあるのではないかという点に興味を持っています」と話す。
消費者間のコミュニケーションにおいてどんな経験価値が、どのようなシーンで生まれているのか。そこから消費者の行動がどう変化していくのか。これらを明らかにするため、段階的に実験とデータの分析を重ねている。価値を創出する過程や、行動への影響が実験を通じて蓄積されつつあり、企業がこうした知見を取り入れることで、イノベーションにつなげられるのではないかと期待する。
社会の動きで注目しているのは、消費者が生みだしたデザインやコンテンツを共有する場が増えていること。YouTubeやニコニコ動画といったものだけではなく、3Dプリンターが一般化することで、立体デザインも共有されていくのではないかと予測する。「原理的には異なるかもしれないですが、3Dプリンターに対するイメージは“どこでもドア”です。ネットワークさえつながっていれば、スキャンしたものをどこでも立体物として出力できるようになっていきます」と森岡准教授。こうしたコンテンツを簡単に共有できる技術によって、現在の流通や販売チャネルをふまえたマーケティングも、広告のあり方も大きく変わるのではないかと見ている。
文系、理系の壁を越えた合同ゼミでイノベーションを学ぶ
ゼミの活動は、関東学生マーケティング大会への参加が中心となっており、学生たちは毎年11月末の最終発表へ向けて研究を進めている。マーケティングの基本的な知識を、ゼミ外の時間に学生自身が選んだ関連書籍を読んで …