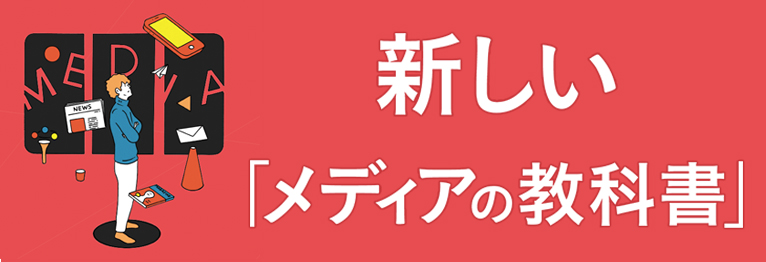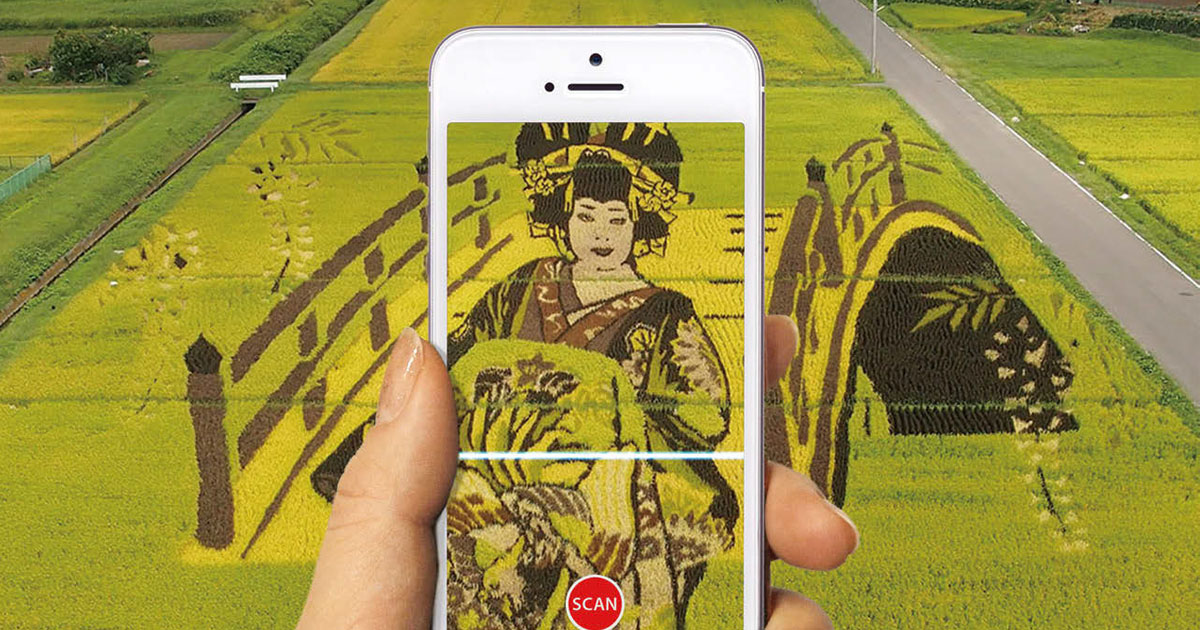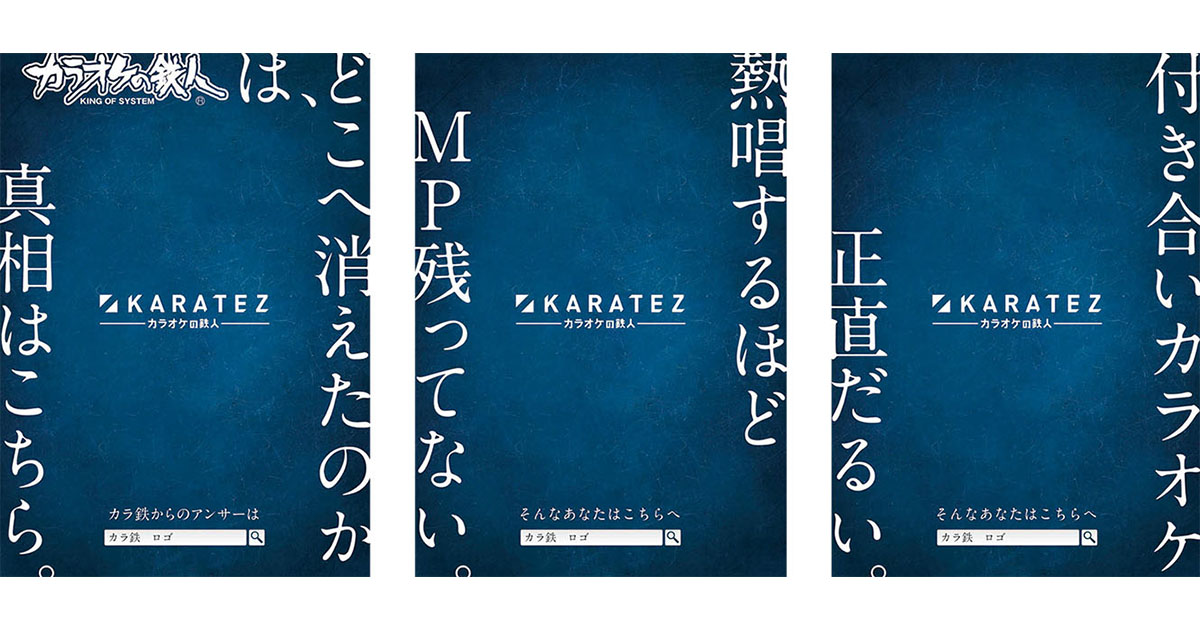ライフカード「カードの切り方が人生だ」、住友生命「1UP(ワンアップ)」、三井住友カード「Thinking Man」など多くのヒットCMを生み出してきた麻生哲朗氏。最前線を走り続ける麻生氏は、デジタル時代におけるテレビの役割をどう捉えるのか。

TUGBOAT CMプランナー 麻生哲朗氏
1996年電通入社。1999年クリエイティブ・エージェンシーTUGBOATを設立。最近の仕事に、住友生命「1UP」、大塚製薬「イオンウォーター」、NTTドコモ「Style’20」、三井住友カード、JRA他。2018年ACC CM FESTIVAL金賞、銅賞他、多数受賞。作詞や脚本など、幅広い分野で活躍。
テレビCMの役割は「一瞬で有名にする」こと
テレビのモバイル化やオンデマンド放送などテレビを視聴するスタイルもますます多様化し、インターネットを介した動画共有サービスでのテレビ番組の視聴など、新しいテレビの見方も広がりつつある。
そんな多メディア環境において、「テレビの役割・強み」とはどこにあるのだろうか。数々のヒットCMを生み出してきたTUGBOATの麻生哲朗氏は、「テレビの本質自体は昔から変わっていない。最も速く有名になれるメディア」と語り、例としてSansanのテレビCMを挙げる。
「SansanはITベンチャーで、会社の名刺を一元管理する全く新しい形のサービスを立ち上げたのですが、テレビという媒体を用いて広告したことで、誰も知らなかった事業がわずか数年で有名になった。Sansanだけでなく新規デジタル事業者の多くが広告においては、テレビに期待しているという実感があります」。
さらに、麻生氏はWebの可能性が語られ始めた時期のCMを例に説明する。ライフカードのテレビCM「カードの切り方が人生だ」(2005~2007年)シリーズである。「続きはWebへ。」のナレーションでWebサイトに誘導し、詳しいサービスや商品については、Webで理解を深めてもらうという戦略だった …