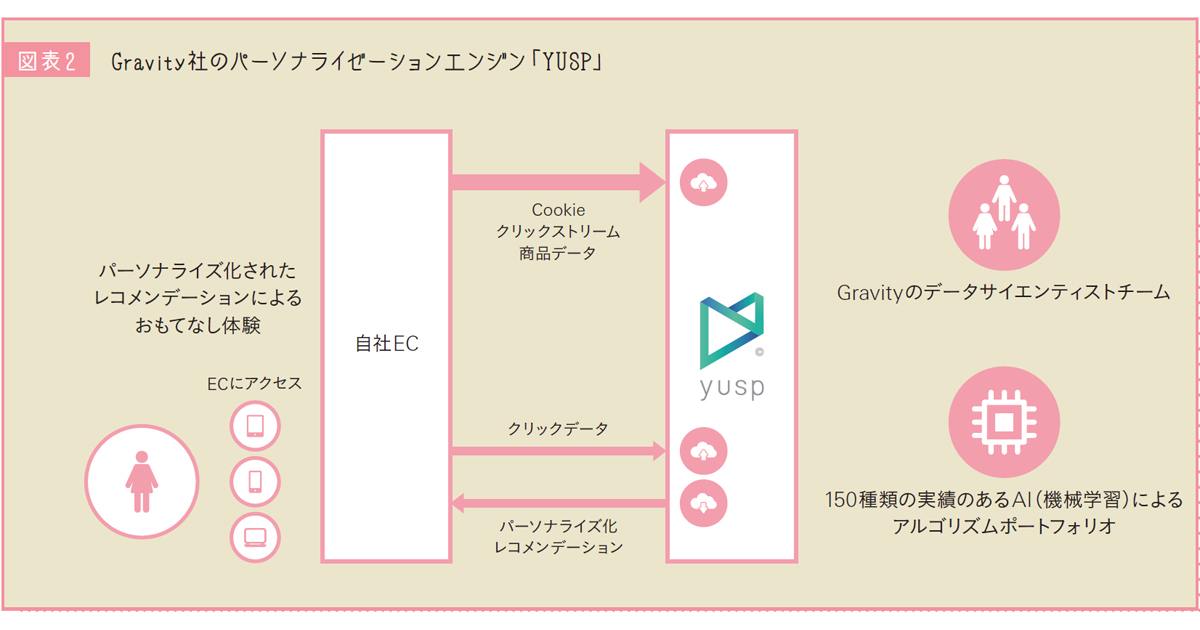直営店を運営する消費財メーカーが増えています。そうした企業にとって、参考になるのがユニクロやZARAなど、アパレル業界におけるSPA(製造小売業)です。店舗の情報をどのように製品づくりや、プロモーションに使っているのでしょうか。そのモデルをファッション業界のコンサルティングを行っている、ディマンドワークスの齊藤孝浩氏に解説してもらいました。
アパレル商品のボトルネックとは何か
アパレルの販売期間は短い。春・夏・秋・冬、1シーズンの販売期間はおおよそ13週間(52週÷4)であり、そのうち店頭で定価販売できるのは約8週間、残りの5週間は値下げ販売されるものだ。各シーズン、販売最盛期に売り逃しをしないだけの在庫を用意しながら、シーズン末までに売り切らなければならないのが宿命だ。アパレルビジネスの利益はいかに値下げを最小限に抑えるか、そしてシーズン末に在庫を残さないかで決まる。
そんなアパレルビジネスのリスクをコントロールするために流通の合理化を図ったのがSPA(アパレル製造小売業)モデルだ。そのタイプは2つに大別できる。小売業が自ら商品企画機能を持ったユニクロやGAP、H&Mのようなタイプと、商品企画機能を持つメーカーが直営店を持ったワールドやポロ・ラルフローレン、ZARAのようなタイプだ。
SPAは流通の「合理化=中抜き」により、消費者と製造現場の距離を縮め、中間マージンを削減し、店頭の需要をいち早く顧客にフィードバックするサプライチェーンを敷いた。SPA化の本質は、合理化によって削減したコストを顧客に適正に還元したところに成功要因がある。それは、サプライサイド都合の商品供給ではなく、消費者が買いたい時期にあわせて(適時)、値ごろな価格で(適価)、必要な在庫量(適量)を店頭に揃えるディマンドサイドに変えたことだ。

(C)123RF
仮説検証(PDCA)のスピードを支える要素
SPAは従来の小売業とメーカー卸業との関係よりも遥かに仮説検証のスピードが速く、たった13週間の季節の中でも需要にあわせて品揃えや在庫状況に修正を加え続ける。それができる理由は、まず直営店があることだ。POSデータを通じて毎日、リアルタイムに販売商品の動向を把握でき、前週の販売動向は毎週月曜日の週次会議で全社に共有される。
この週次の情報共有は、社内の店舗営業部やバイヤーだけでなく、次のシーズンを考えているデザイナーやパタンナーのようなクリエイティブ系スタッフや生産担当者にも行われる。その結果、需要の変化が直ちにサプライチェーンにもフィードバックされることになる。
SPAの店頭情報の活用は、店頭に共存するベーシック商品とトレンドファッションで異なる。まず、ベーシック商品は目的買いをするアイテムであるため、消費者はあの店なら必ずその商品があるはずだと期待して店に向かう ...