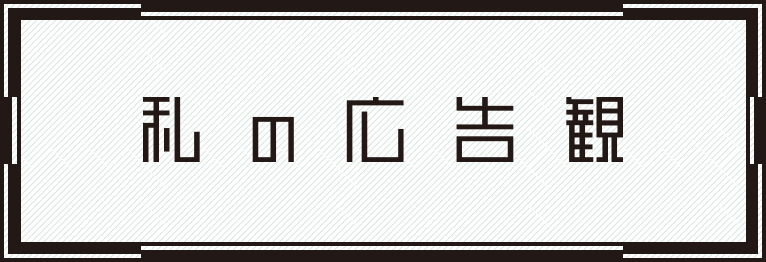人類学者として、人間が他者とともに生きるということを長きにわたり探求している磯野真穂氏。そんな磯野氏が現代の広告コミュニケーションに対して感じていることを聞く。

磯野真穂(いその・まほ)さん
独立人類学者。1999年、早稲田大学人間科学部スポーツ科学科卒。オレゴン州立大学応用人類学修士課程修了後、早稲田大学文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。専門領域は文化人類学、医療人類学。著書に『急に具合が悪くなる(共著・宮野真生子)』(晶文社)、『ダイエット幻想─やせること、愛されること』(筑摩書房)、『なぜふつうに食べられないのか』(春秋社)など。
日常で感じる“違和感”こそ人生をより面白くする鍵
人類に関する総合的な学問である人類学。その範囲は非常に広く、大きく分類すると考古学、自然人類学、言語人類学、文化人類学の4分野にわけられる。磯野真穂氏はその中でも、文化人類学とその下位領域、あるいは第5番目の領域と位置づけられている医療人類学を専門としている人類学者だ。文化人類学と医療人類学は、明確な定義づけはされておらず人によって解釈は異なるが、磯野氏はそれぞれを以下のように解釈しているという。
【文化人類学】人々にとって世界はどのようであるのかを、それぞれの人の視点にできる限り立ちながら観察、聞き取り、資料調査を通じて明らかにしようと試み、その知見から人間とは何かを明らかにしようとする学問。
【医療人類学】人が生まれ、死んでゆく過程において、人々は自ら及び他者の身体をどのように気遣い・考えるのかを、それぞれの人の視点及びその人を取り巻く社会・文化、政治・経済的、歴史状況を鑑みながら、観察、聞き取り資料調査を駆使して明らかにし、その知見から人が身体とともに生き、死んでゆくことの意味を包括的に明らかにしようとする学問。
元々、大学では運動生理学を専攻していた磯野氏だが、人を数字でとらえる自然科学のアプローチに次第に違和感を抱くようになったという。そんな時、留学先のアメリカで出会った文化人類学に感銘を受け、3日後には専攻を変更した。
「留学先から当時のゼミの先生に専攻を変えたいと相談したところ、先生が『僕は自分のゼミが楽しいと思ってもらえるようにやってきた。でも、磯野が楽しいと感じられていないということは、何かが間違っているということ。楽しくないと感じている今の気持ちを大切にした方がいい』と言ってくれました。多くの出会いがある中で、自分が抱いた疑問や迷いに価値があると言ってくれる先生に出会えたことは本当に幸せだと思います」と当時を振り返る。
磯野氏は、文化人類学・医療人類学を通して、大きく2つのことを世の中に発信したいと考えて研究を行っているという。
「ひとつは、医学や生物学、統計学といった自然科学の専門知によって、私たちの生活のすみずみが管理されてしまうことへの抵抗です。自然科学を活用した“正しい”話し方、食事の方法、人との接し方などが話題になることがありますが、それにより私たち一人ひとりの多様な在り方が一色に塗りつぶされてしまうことに違和感を持っています。これは、文化人類学に専攻を変えた時から...