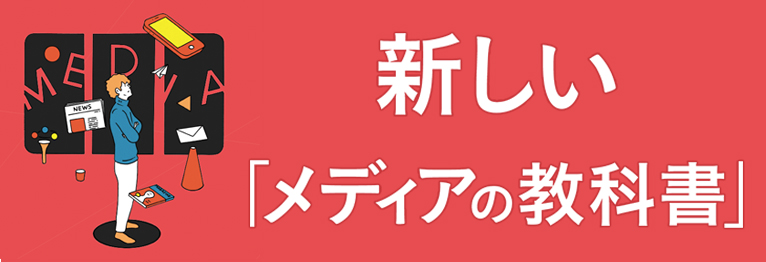メディアの役割は「仲介」言葉の定義から、その本質を捉え直す

コルク 代表取締役会長 佐渡島庸平氏
1979年生まれ。講談社を経て、2012年クリエイターのエージェント会社、コルクを創業。三田紀房、安野モヨコ、小山宙哉ら著名作家陣とエージェント契約を結び、作品編集、著作権管理、ファンコミュニティ形成・運営などを行う。従来の出版流通の形の先にあるインターネット時代のエンタテインメントのモデル構築を目指している。
変化する時代 まずは言葉を捉え直そう
日常の中で何気なく使われている言葉も、時代が変わるのに合わせ「具体」は変化し続けていく。コルク 代表取締役会長の佐渡島庸平氏は、「まずは"言葉"そのものの意味を捉え直すことが重要だ」と説く。
「僕はいろいろなことを考えるときに、まず言葉の意味を捉え直すことで、本質を掴もうとします。その理由として、例えば辞書で『メディア』と引くと、元々の意味のひとつに『仲介』と出てきます。『メディア』という言葉が使われる中で、次第に、具体的なテレビや新聞といった媒体の名称として『メディア』という言葉が使われるようになり、本質的な意味からニュアンスが変わってきてしまうのではないかと思うからです」。
特に「具体」の部分は、時代に合わせて変わっていくもののため、そこだけを見ていると、通用しなくなるとも佐渡島氏は指摘する。
「仮にテレビや雑誌や新聞が『メディア』と称されることが、しっくりこなくなった時に『テレビとは何か』『新聞とは何か』と具体のほうを定義していくのではなく、『メディア』という言葉の意味を捉え直すことが必要です」。
「メディア」の意味のひとつが前述の、「仲介」。インターネットが普及した当時は「直接、人とサービスが繋がることができるようになった今、もはや仲介はいらないのではないか」という議論も起きた …