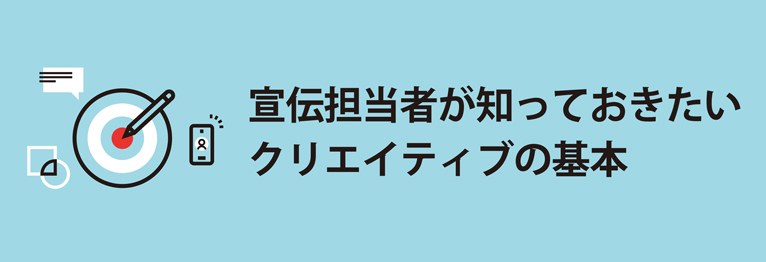- ソーシャルメディア的なスピード感を演出する
- コミュニケーションの素材として『使ってもらえる』コンテンツを意識してみる。
- 「共感の裏返しの反感」をくすぐるコピーは、上手く作用した場合に爆発的な拡散を引き起こす。
ソーシャル時代のコピーライティング、ここがポイント
コピーの新しい評価軸
CMやポスターではワークしたコピーが、Webではそうでもなかった。あるいは、その逆の経験をした方は多いのではないでしょうか。マス広告の世界では、これまでの歴史の積み重ねの中で「コピーの評価軸」がある程度体系化され、感覚的に共有されていると思います。一方Web、特にソーシャルメディアでは、まだまだ誰もが手探り状態です。「ソーシャルメディアにおけるコピーの評価軸」とは、どのようなものなのでしょうか?
事例として注目したいのが「保育園落ちた日本死ね」です。もともとは匿名の個人がブログで発した言葉ですが、あらゆるメディアに拡散されてゆき、最終的に国を動かすことに成功しました。レザルトのすごさも含めて、歴史に残る「名コピー」です。「保育園落ちた日本死ね」の、どのような要素がヒットに結びついたのか?そしてそれらの要素を、どのように広告コピーに応用できるのか?事例の紹介を通して、明らかにしていきたいと思います。
コピーに、「スピード感」を。
かつてのブログ全盛の時代だったら、このタイトルは「保育園に落ちた!日本死ね!」のようになっていたと思います。2chなら「【悲報】保育園落ちたwwwww日本死ねwwwww」のような感じでしょうか。しかしソーシャルメディアは短文の世界です。Twitterは140文字、Vineは6秒。句読点も感嘆符もない「保育園落ちた日本死ね」というコピーは、この脊髄反射的なスピード感をよく表しています。
ブログの本文も「子供を産んで子育てして社会に出て働いて税金納めてやるって言ってるのに日本は何が不満なんだ?」のように、「、」は一切使われていません。実はブログに書かれた原文は「保育園落ちた日本死ね!!!」なのですが、拡散にともなって最後の「!!!」が自然に削除されています。
広告コピーでこのスピード感をよく体現していた事例に、オートウェイの「雪道コワイ」があります。実はCM本篇に表示されるタグラインは「雪道は怖い」なのですが、YouTubeでのタイトルは「雪道コワイ」になっています。みなさんもおそらく「雪道コワイ」と記憶されていたのではないでしょうか。ソーシャル時代を意識した、優れたワーディングです。
コピーに、「タイトル感」を。
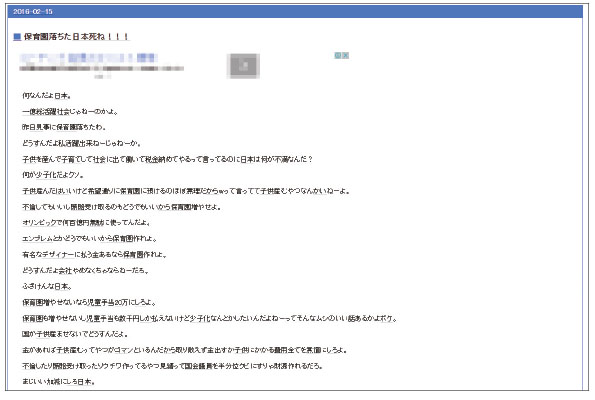
「雪道は怖い」と「雪道コワイ」。ちょっとした違いですが、このコピーがYahoo!トピックスなどに上がったときのことを考えてみてください。クリックしたくなる気持ちは、後者が圧倒的に上だと思います。クリックした先に、「保育園落ちた日本死ね」的な、ソーシャル文脈のコンテンツがあることが分かるようになっているのです。
僕が手かけた事例に、プリッツの「Pしよう。」というコピーがあります。こちらはWeb動画ではなくテレビCMとグラフィックで使用したコピーですが、キャンペーンがはじまると「Pしよう。」というタイトルで広告がまとめられたり、ハッシュタグとして使用されたりするようになりました。
サントリーBOSS「宇宙人ジョーンズ」シリーズや、富士フイルム「フジカラーのお店」シリーズなどのヒットCMを多数生み出しているCMプランナーの福里真一さんも自身が担当したトヨタ自動車「こども店長」シリーズを例にとり、「CMには『こども店長』のような、人に教えやすいタイトルをつける」と言っています。まとめサイトのタイトルになるか?ハッシュタグとして使ってもらえるか?そんな評価軸も持っておくといいと思います。
コピーに、「素材感」を。
話を「保育園落ちた日本死ね」に戻しましょう。このブログは国会で取り上げられただけに留まらず、共感した母親たちが「保育園落ちたの私だ」というプラカードを持って、国会前でデモをするという活動につながりました。現在でもTwitterには「#保育園落ちたの私だ」というハッシュタグでの投稿がたくさん見られます。ブログのタイトルが、プラカードやハッシュタグに発展する。ソーシャル時代を象徴するような現象です。
マスメディアしかなかった頃 ...