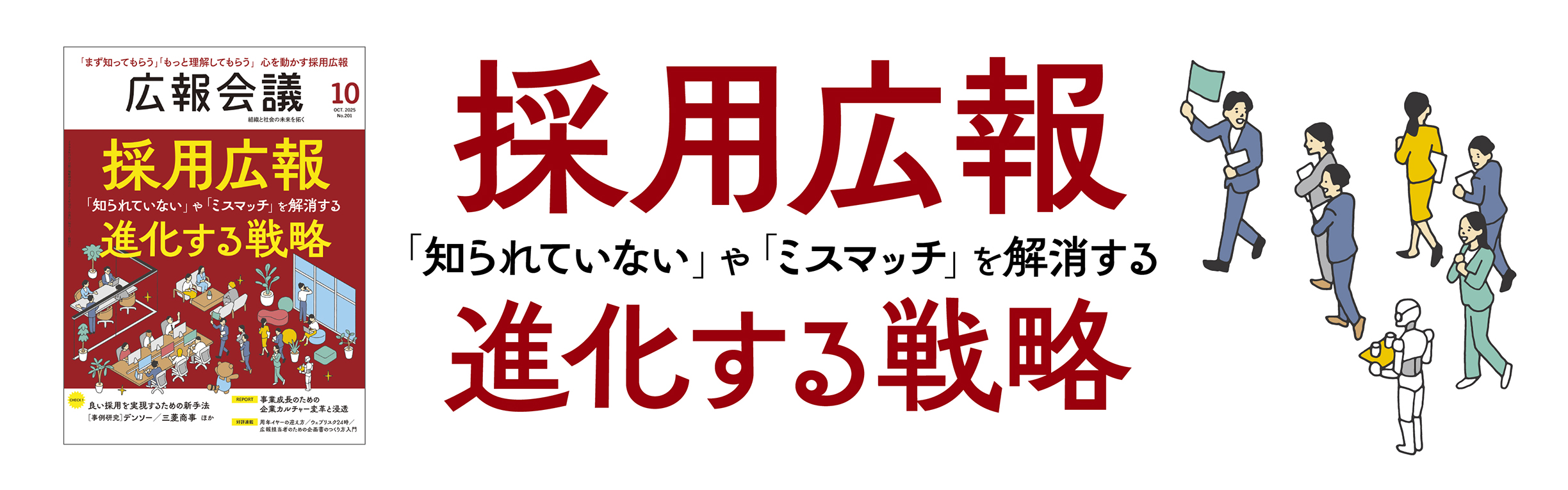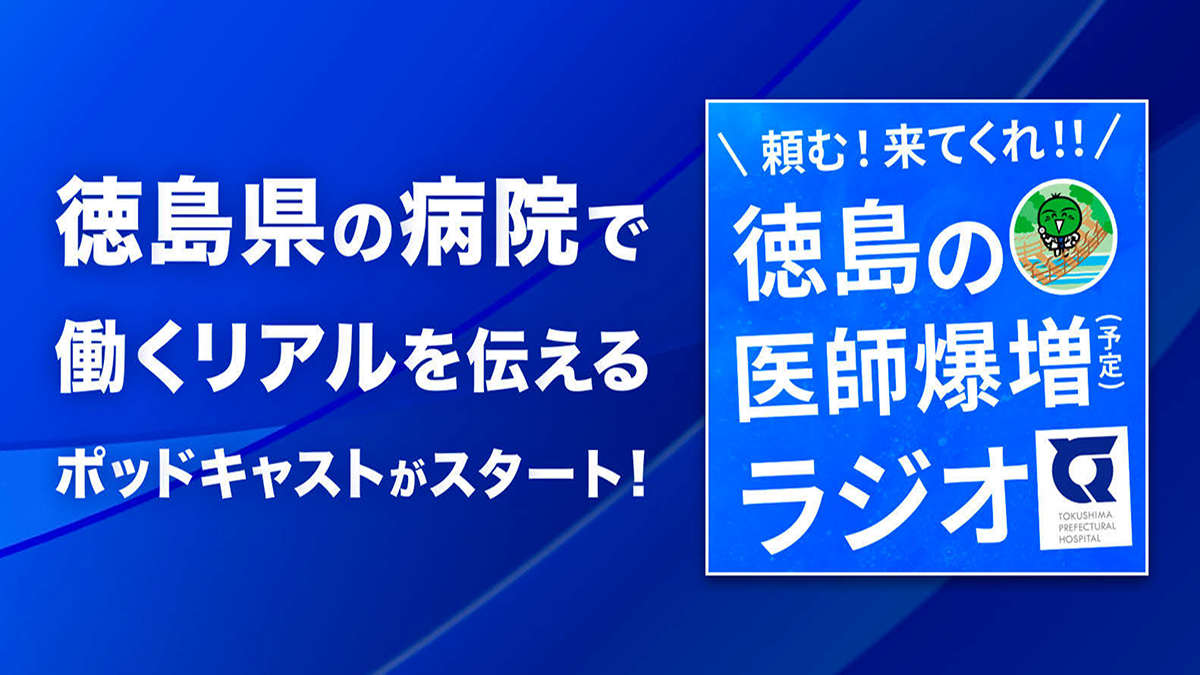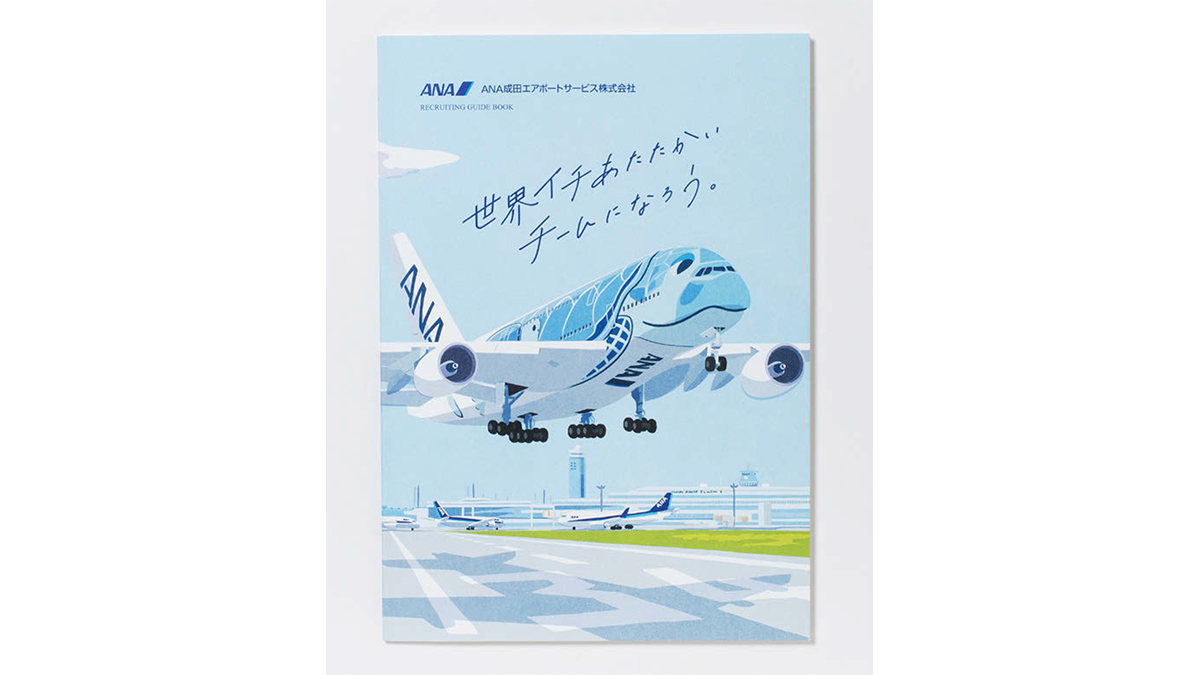「パーパス」や「社会貢献」など、目指す方向を明示する企業は増えた。しかし、求職者が本当に知りたいのは目指す方向性だけではなく、それを達成するための行動が、日常の業務や意思決定にどう現れているかだ。これからの採用広報に必要な視点を解説する。
人材市場は、もはや一時的な売り手市場ではありません。若手や中堅層を中心に、転職やキャリアチェンジが当たり前になりました。就職活動や転職活動は“長期戦・分散戦”の色合いを強めています。ナビサイトや人材紹介だけで母集団形成が完結する時代は終わり、SNSや動画、社員紹介、長期インターン、オンラインイベントなど、接点は年間を通じて多様化し、分散しました。
採用広報が注目される背景
こうしたターゲットの関心の多様化とメディアの分散は、採用広報にも大きな変化を迫っています。候補者の関心を惹きつけ、維持し、最終的に選ばれる存在になるためには、かつてよりも高度なプランニング力やプロデューススキルが必要です。
売り手市場が加速する現在、企業は“選ぶ側”ではなく“選ばれる側”になりました。合わなければすぐに辞められる時代。退職代行やクチコミなど、それを加速する手段も増えています。
だからこそ「何を目指すか(ゴール)」だけでなく「どう目指すか(プロセス)」が問われるようになりました。目標は同じでも、目指し方や進み方が違えば摩擦が生まれます。つまり、「いい企業」と「合う企業」は違うのです。
このような時代、給与や福利厚生といったスペックだけではなく、“スタイル”の発信が重要です。ここで言うスタイルとは、価値観や行動様式のこと。名詞で表現される肩書きや制度だけでなく、動詞で語られる日々の動き方や判断基準こそが、候補者にとっての検討材料になります。
また、従来の「カルチャーマッチ」という概念は、表層的な雰囲気や文化の一致を指すことが多く、実際の行動や意思決定のスタイルまでをカバーできません。これからは、より精緻に“どう働くか”を描く「スタイルマッチ(※No Company独自の思想)」の発想が求められます。
“よくある誤解”とその罠
現代の採用広報にはいくつもの罠や誤解が潜んでいます。ここでは陥りやすい5つのパターンと、その回避のヒントを整理します。
罠①:社員が不在の広報
事業や制度の説明は充実していても、その裏側で働く人の表情や判断の背景が見えなければ、候補者は「自分がこの職場で過ごす日々」を具体的に描けません。特に、スペッ...