著作権を正しく理解する5つのステップ
(1)その情報・素材は「著作物」ですか?
(2)著作権には期間がある
(3)著作権の例外規定─「引用」の注意点
(4)権利者への許可とフリー素材の活用
(5)権利侵害のリスクとメリットを考える
2016年末にキュレーションメディアにおける「パクリ記事」が著作権多数発覚し、目を覆いたくなるほどひどい「コピペ放題社会」が露呈しました。同時に問題になっているのは、逆に過度なまでの「萎縮社会」です。特に違法ではないのに、「炎上が怖いから」と表現が萎縮してしまうケースも目立ちます。2020東京五輪エンブレムの撤回騒動が一つの発端ですが、デザインの現場や広報の現場で恐るべき「萎縮」という形になって暗い影を落としています。
「万人のための法律」へ
この2つの落とし穴の間で、業界内の慣習や勘だけに頼って生きていくのは限界です。これまで著作権というのは、ごく一部のプロフェッショナルだけが知っていればいい「業界のための法律」でした。私は弁護士としてこの分野を専門としていますが、この10年ほどの間に著作権は急速に「万人のための法律」に変わっています。
その背景には、誰でもインターネット上で自由に情報発信できる社会の到来があります。万人が発信者となることが、皆が俳優のように振る舞う「劇場化」という特殊な状況を招き、あらゆるリスクとエネルギーの根源になっているわけです。同時に「炎上社会」が生まれており、特に著作権関連の話題は炎上しやすい。
著作権というのは情報をめぐるルールの話であり、企業の広報にとっても他人事ではありません。メディアに記事として取り上げてもらうだけでなく、日々、オウンドメディアで何を発信していくか。あるいはSNSのアカウントを会社としてどう持ち、どのくらいの頻度で、どの程度の柔軟性で発信していくのか。多くの企業で頭を悩ませていることでしょう。
ここで、一方では …


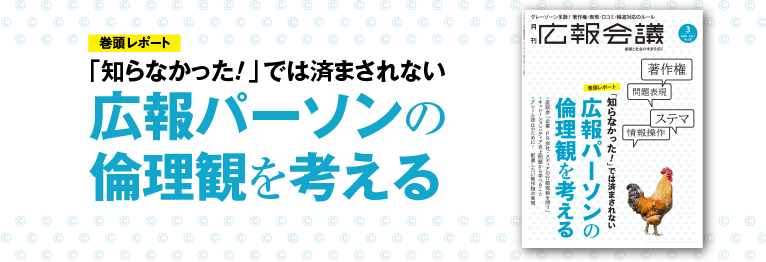
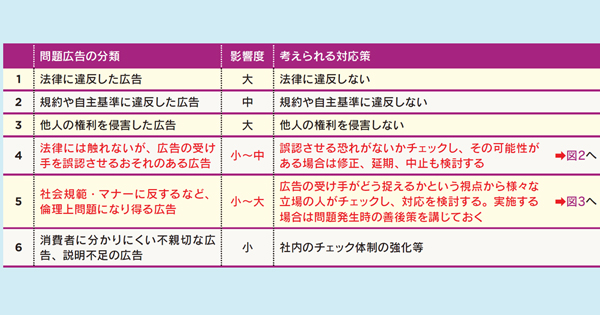
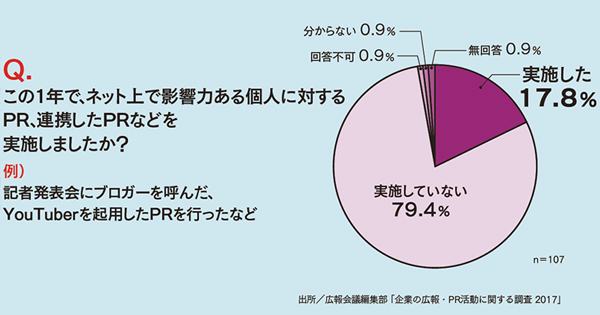
![[PR] 企業の信頼を失墜させる 業界構造から生まれたステマ問題](https://images.microcms-assets.io/assets/9c883224793c4361bfa991c4e6710e04/0a118009a06d4962851ba3a5ad444686/036_ogp.jpg)