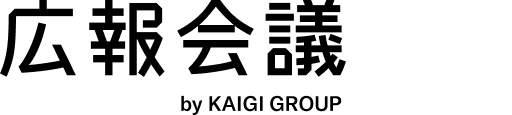「広報関連の新たな企画を実現しようとするも、社内で企画書が通らない……」。そんな悩める人のために、広報の企画を実現するポイントを伝授。筆者の実務経験をもとに、企画書作成に必要な視点を整理していきます。
「届かない相手」の視点で企画を考える
広報企画書の基本構造は「誰に・何を・どう伝えるか」に整理されることが多い。だが、社会課題や生活インフラのようなテーマを扱う場面では、この構造だけでは対応しきれない状況も増えてきた。特に直面しやすいのが、「関心を持たれていない相手」にどう情報を届けるかという課題である。広報活動におけるこうした“偏り”が、実務現場では見過ごされがちだ。「関心がない」のではなく、「自分には関係がない」と感じられていることが、情報が届かない主な原因になっているケースは少なくない。広報実務には「関心ゼロ層」と向き合う局面が随所に存在する。今回は、このような「届かない相手」を前提に企画書を構成するための視点を整理していきたい。
視点1
無関心層は“届かない構造”で捉える
必要なのは語りの巧みさではなく関係設計
「情報をそもそも見ていない人」や「関係ないと感じている人」に、どう接点を設け、どのように意味を見出してもらうかという問いへの鍵となるのが「ナラティブ」である。ここでいうナラティブとは、感動的なストーリーのことではない。「この情報は、自分と関係がある」と相手が感じる構造のことだ。語りの「巧みさ」よりも、関係の設計に着目し、情報が届く状況をつくり上げることが重要になる。ここでは、無関心な相手に向き合う広報企画書の設計を考えたい。
なぜ反応がないのかを、設計の出発点に置く
広報活動において、ペルソナ設定は施策設計の定番とされている。年齢や性別、職業、ライフスタイルなどを基準に「40代男性・管理職」「20代女性・単身・都市部在住」といった理想の顧客像を描き、その人物像に合わせてチャネルやコンテンツを設計していく。
だが近年、「ターゲット設定は正確なのに、まったく反応がない」という企業からの相談が増えている。対象の属性は設計通りで、適切なチャネルも用いている。それにもかかわらず、開封や視聴、参加につながらない。こうした状況では、「誰に届けたか」ではなく、「なぜ届かなかったか」に原因を求めるべきだ。
無関心層に向き合う広報では、「なぜ届かなかったのか」を最初の課題として具体的に捉える必要がある。ターゲットの属性ではなく、「届かない構造」に注目するのだ。その際は、ペルソナの外にある情報遮断の実態を把握することから設計を始めたい。私自身、ペルソナ設計もメディア選定も丁寧に組み立てたものの、いざ実施するとまったく反応がなかった案件がある。理由は単純で、相手がそもそも見ていなかったのだ。こちらの「丁寧な設計」は、最初から相手の視界に入っていなかったのである。
「届かない構造」は4つのタイプに分けられる
情報が届かない理由は状況によって異なるものの、経験上、実務の中では次の4つに整理できる。
図1 情報が「届かない構造」4タイプ
情報疲労型
日常的に多すぎる情報に接しており、通知や広告に強い抵抗感を持っている。企業や行政からの発信に「またか」と反射的に構えてしまう状態。
接点不在型
情報が届くチャネルそのものを持っていない。例えばスマートフォンを使っていない人など。
拒否反応型
過去の経験や印象から、発信元に対して不信感を抱いている。自治体や企業と距離を置きたがる心理が前提にある。
意味不明型
情報に触れてはいるが、専門用語や制度言語が多く、内容が理解できない。前提知識が必要な設計が、無関心を生む原因になる。
こうしたタイプをペルソナ像に上乗せすることで、施策の方向性が根本的に変わる。例えば「子育て中の30代女性」という像に、「Instagramは使っているが、企業や行政の投稿は飛ばして見ている(情報疲労型)」という特性を加えるだけで、広報設計はまったく別のものになる。
属性ではなく「生活の中での接点のなさ」を描く
届かない構造を理解するには、単に “何に関心がないか” ではなく、“なぜ情報が受け入れられないか” を明文化する必要がある。例えば、以下のような形でペルソナと届かない構造を同時に記述したい。
30代・共働き・2児の親。スマートフォン使用率は高いが、子育て情報以外の通知は遮断している。自治体情報に関しては、過去の閲覧経験から「長くて読みにくい」という印象があり、習慣的に避ける傾向がある。
このような設計があれば、「わかりやすい投稿をSNSに上げる」という表層的な施策ではなく、「保育園経由で紙の案内を家族の目に触れるようにする」「地域イベントに参加してもらうきっかけを家族LINEから誘導する」といった設計に変わる。接点のない相手には、生活の中に “意図せず情報に触れる” 場面を先に設計する必要がある。
届かないのは、関心がないからではない。届きようのない構造、いわば “生活動線の断絶” があるのだ。企画書にこの視点を含めることで、広報設計の方向性を根本から見直すことができる。
ここがPoint!①
「届かない理由」から設計を始める
●「届きようがない」構造の把握が第一歩
● ペルソナ設定で満足せず、接点の遮断理由まで書き込む
●「どこで届いていないか」を分類することで、打ち手の精度が向上
● 属性ベースでは設計できない “生活動線の断絶” に着目する
視点2
“触れてしまう”構造を設計する
「届かない」なら、まず「触れる」機会をつくる
「情報をどう届けるか」ではなく「どう触れてもらうか」へと発想を転換したうえで、接点設計の基本的な考え方と原則を整理したい。関心が前提にならない無関心層にとって、「伝え方」よりも「触れてしまう場面」の設計が結果を左右するからである。
「情報が届かない」とは、裏を返せば「そもそも見られていない」「目に入っていない」ということである。そのため、見てもらう前にまず情報に “触れてしまう”状況を設計することが、無関心層を対象とした広報企画の最初の設計論点になる。
広報の一般的な施策設計では、「見せたい情報を、適切なタイミングで、適切な場所に載せる」という組み立てが基本となる。だが、関心を持っていない相手は、その情報が出てくる場所をそもそも見ていない。どれだけ質の高い情報であっても、生活動線の中に存在しなければ、届くはずがない。
そのため、無関心層にアプローチする企画では、「どう伝えるか」よりも「どこで触れるか」を先に設計する必要がある。見られることを前提にせず、「目に入ってしまう」「無意識に視界に入る」「思わず読んでしまう」ような偶発的接触を意図的につくることが...