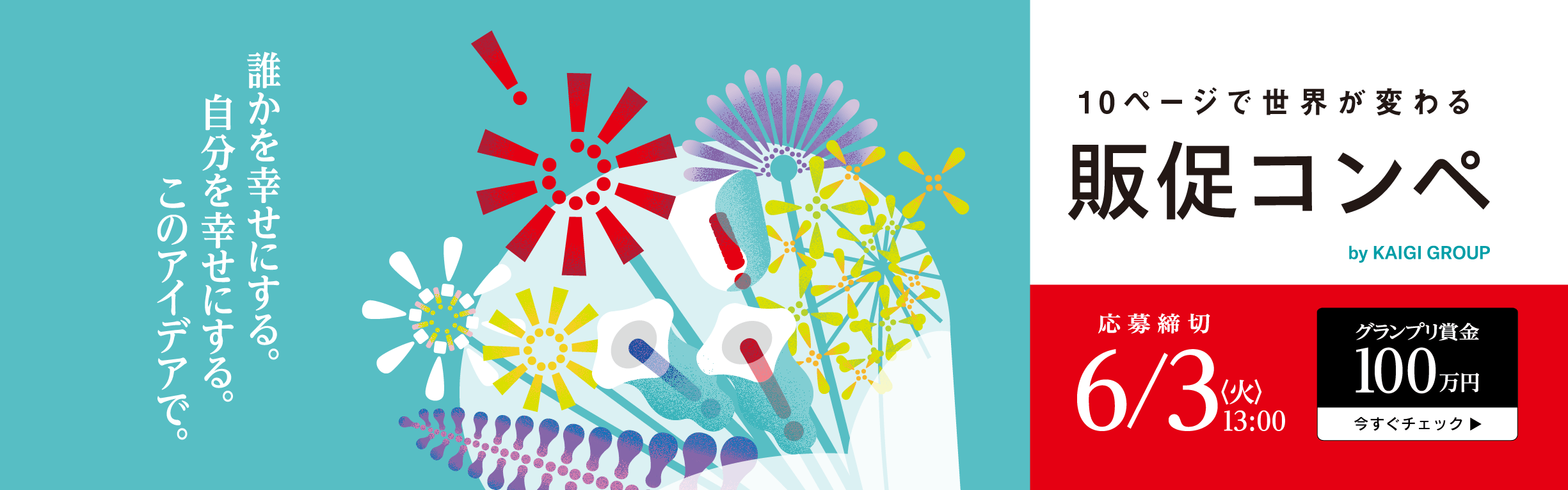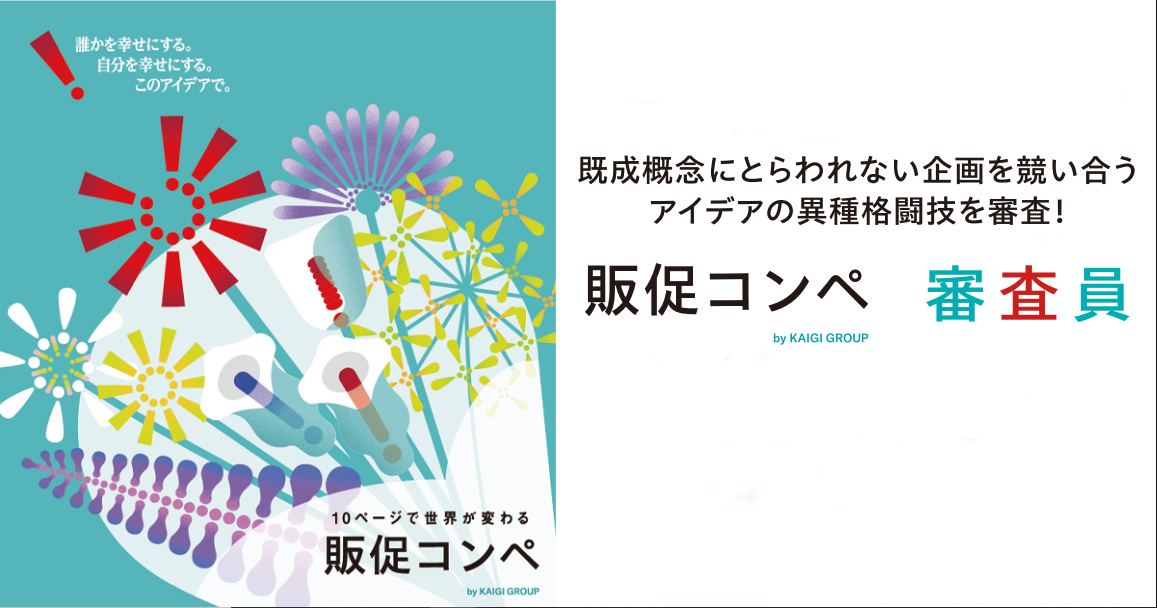第9回販促会議企画コンペティションのグランプリおよび入賞作品を発表する贈賞式が、8月30日に東京国際フォーラム(東京・千代田区)で実施された。
課題数27、応募総数3128本の中からグランプリに輝いたのは、大日本除虫菊の協賛課題に応募した「"えとりかえ"虫コナーズ」。グランプリ受賞者のサーダティ偉伊佐さんは「課題の解決に向けて、とてもシンプルに考えた結果だと思います」とコメントした。
最終審査員長の嶋氏は「シンプルで説明しなくてもわかる企画が多かった。特にグランプリやゴールドに選ばれた作品はそれが強かった。また、これまではスマートフォンなどのデジタルで課題を解決するという企画が多い傾向にあったが、デジタルだけでなくニュートラルにクライアントの課題を解決できる企画が目立っていた」と講評した。

ことし9回目を迎える「販促会議企画コンペティション(販促コンペ)」の最終審査会が、7月末に行われた。最終審査に残った30本の企画書。どのような基準で、何を重視して審査は進められたのか。その模様をレポートする。

審査には発注側の事業会社も参加
優れたプロモーションアイデアを顕彰する「第9回販促会議企画コンペティション」に集まった企画書の総数は3128本に上った。最終審査の対象は、一次審査を通過し、二次審査で審査員が付けた点数の合計得点が高かった上位30本だ。その中から最終的にグランプリ1点、ゴールド2点、シルバー3点を選出するための審査が行われた。
昨年に引き続き、審査員長を博報堂ケトルの嶋浩一郎氏が務め、最終審査員にはアサツー ディ・ケイの石田琢二氏、オイシックスドット大地の奥谷孝司氏、刻キタルの岸勇希氏、プラチナムの吉柳さおり氏、大広の児玉昌彰氏、ハッピーアワーズ博報堂の藤井一成氏らが名を連ねる。さらに今回は、ドミノ・ピザ ジャパンの富永朋信氏、宝島社の桜田圭子氏らも参加した。
審査を始めるにあたり嶋氏は「審査のクライテリアはリアルに人が動くかどうか。コアアイデアがターゲットのインサイトをつかんでいるかが重要です。企画の実現可能性(フィジビリティ)も大事。その視点でのダメ出しもお願いします」と審査方針を述べた。
今回の応募作品の傾向について、藤井氏は「応募数が増加している中で、売り手側だけじゃなくて買い手側の視座で考えている企画もあり、良い傾向」と評価した。一方、児玉氏は「施策案はあるが本当にそれで人が動くのか、と疑問に思う企画が散見されたように思う」と述べ、石田氏も「平均のレベルは落ちていないが、中にはアイデアの核となる部分が定まっていないものも見受けられた」とコメント。
奥谷氏からは「スマートフォンアプリを絡めた企画が多かった印象。アプリは一度作ると運用していかなければいけないため、実施には慎重になる」と、企画の先を見通したアドバイスも出てきた ...