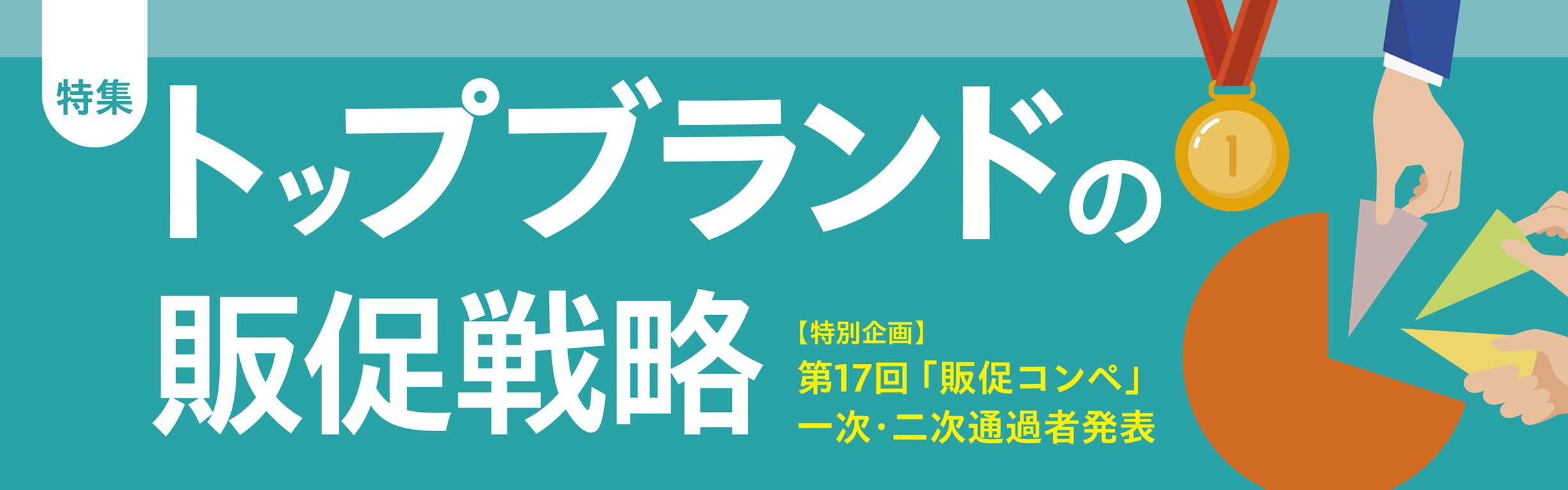2025年9月号の巻頭特集は、「トップブランドの販促戦略」です。ブランドとしての売上を上げるためには、消費者の購買意欲を刺激して商品を購入してもらうことが必要ですが、そもそも商品を手に取ってもらうためには店頭に多くの商品が並んでいることが重要です。そう考えると、店頭でより多くの棚を獲得している、マーケットシェアの高いブランドが優位だということがわかります。
では、市場のシェアを獲得するためにはどうすればよいのでしょうか。市場に数多くの商品・ブランドがある中で、トップに君臨し続け、確かな成果を出し続けているブランドには、売るための仕組みや工夫が存在しているはず。そういった仮説に行きついて生まれたのが今回の特集です。
各カテゴリーでトップシェアを誇るブランド担当者やブランドシェアの専門家に取材し、売れ続けるブランドの裏側に迫りました。
各カテゴリーのトップブランドに聞く自分たちならではの販売戦略
そもそも、どうすればマーケットシェアを知ることができるのでしょうか。日本能率協会総合研究所の情報コンサルタントである德永翔太氏は、その方法について、POSデータだけでなく、Web情報・データベースの有料コンテンツ・生情報の収集が有効だといいます(記事はこちら)。それらの情報を入手した上で適切な市場シェアのKPIを設定し、消費者との接点を多く設けることが市場シェア拡大につながると話していました。
続くトップブランド担当者への取材では、「ビール」「清涼飲料」「チョコレート」「ジャム」「固形石けん」「ティシュー」の6カテゴリーで、それぞれトップとしての地位を確立しているブランドに取材しました。
まず、ビール市場トップシェアの「アサヒスーパードライ」では、消費者との接点の多さを活かし、商品広告でのブランド価値の伝達、量販店での購買のひと押し、飲食店での新たなブランド体験に注力(記事はこちら)。既存のビールラバーはもちろん、ビールを飲んだことがない層やビール離れしそうな人も含めて、新たな接点・飲用機会を増やしていきたいと話していました。
次に取材したのは、7年連続で市場販売数トップを記録する(サントリー食品インターナショナル調べ)清涼飲料ブランド「サントリー天然水」です(記事はこちら)。同社は、トップを走り続けられる要因について「ミネラルウォーター自体のおいしさを活かした炭酸水、有糖炭酸飲料や果汁飲料などのブランド展開・強化」を挙げていました。またブランドコミュニケーションにおいても、水質汚染や気候変動による水不足といった“未来の課題”解決にも注力していることを伝え、消費者が同ブランドを選ぶ理由を設計しているといいます。
1964年に誕生し、チョコレート市場としては後発ブランドだったロッテの「ガーナ」は、「チョコレートの本場スイスを超えるような品質の高さ」と「チョコレート=茶色という従来のイメージを覆す赤いパッケージ」で他ブランドと差別化(記事はこちら)。店頭の売り場づくりにおいても、パッケージの“赤”を活かした「ガーナ」ならではの展開を行いながら、SNSと連動した販促施策を実施していると話していました。
“利用のされ方を見つめなおす”ロングセラーが良く愛される理由
記事はこちらでは、日本初の低糖度ジャムを販売したことで知られるアヲハタに取材。ごろっとした果肉が入った「アヲハタまるごと果実」で、生のフルーツの代わりにちょっとした幸せを届けたいと、パン以外との組み合わせを訴求しています。小売業の人に「アヲハタまるごと果実」を置けば、ほかの商品も売れると感じてもらいたいと話していたのが印象的でした。
そして赤字からのV字回復を果たした「カウブランド赤箱」は、「洗顔としても使えるコスメ軸としての発信」「パッケージデザインや世界観も含めて赤箱ブランドに愛着を持ってもらうためのカルチャー軸での発信」について言及(記事はこちら)。2025年から本格的に始動したLTV向上施策を中心に、この2方向からブランドとしての価値を引き上げていきたいと話していました。
最後のトップブランドは、ティシューカテゴリーのカミ商事「エルモア」(記事はこちら)。消費者との日常的なタッチポイントを自然なかたちで生み出すため、都市部の電車内広告や交通広告を活用しています。同ブランドの「身近で親しみやすい」ブランドイメージとの親和性が高いコミュニケーションを意識することで、日用品を超えた“暮らしのパートナー”を目指すと話していました。
カテゴリーの王者を研究することは自社ブランドの成長にもつながる
またインサイト代表取締役の加藤巧氏は「店頭での可視性を高め、市場に浸透させることこそ、ブランド成長の鍵になると言っても過言ではない」と話します(記事はこちら)。トップブランドがやっていることと、自分たちがしていることの差をまず理解すること。その上で、その差を埋めるための努力をすることが重要だと説明していました。
電通データマーケティング局グロースコンサルティング1部部長の宮前政志氏も、企業が伝えたいことばかりを強調し、ユーザー視点の“共感”や“拡散されやすさ”の設計を怠っていることが、強者に勝てない大きな原因だと指摘しています(記事はこちら)。特にSNS上では、“知られていない”ことを武器に「私だけが見つけた」という新発見を設計すると、一気に話題化することが可能だと話していました。
「トップブランドの販促戦略」と聞くと、この特集は関係ないと考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、まったくそうではなく、どのブランドでも下剋上が可能だと説いているのが加藤氏と宮前氏です。上位ブランドに挑むためには、まずは自社ブランドが所属しているカテゴリーのトップブランドを研究し尽くすこと。そしてトップブランドと自分たちの差を理解し、その差を埋めるためにはどうすればよいのかを考えることであることが、大変有効だといえそうです。