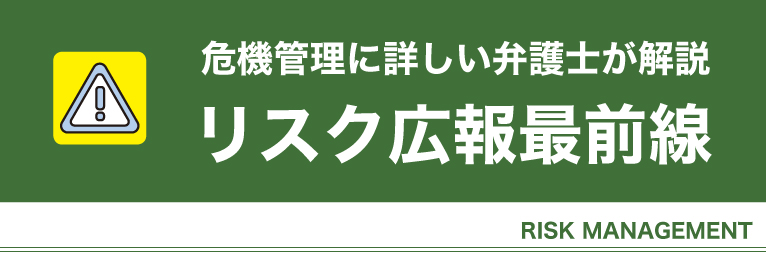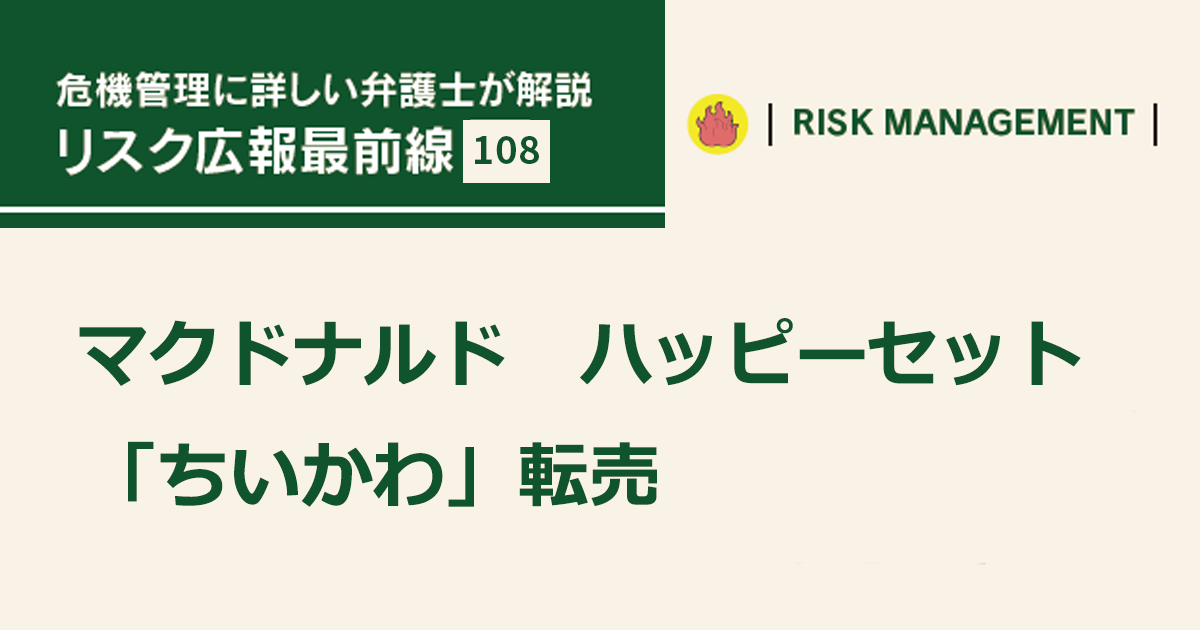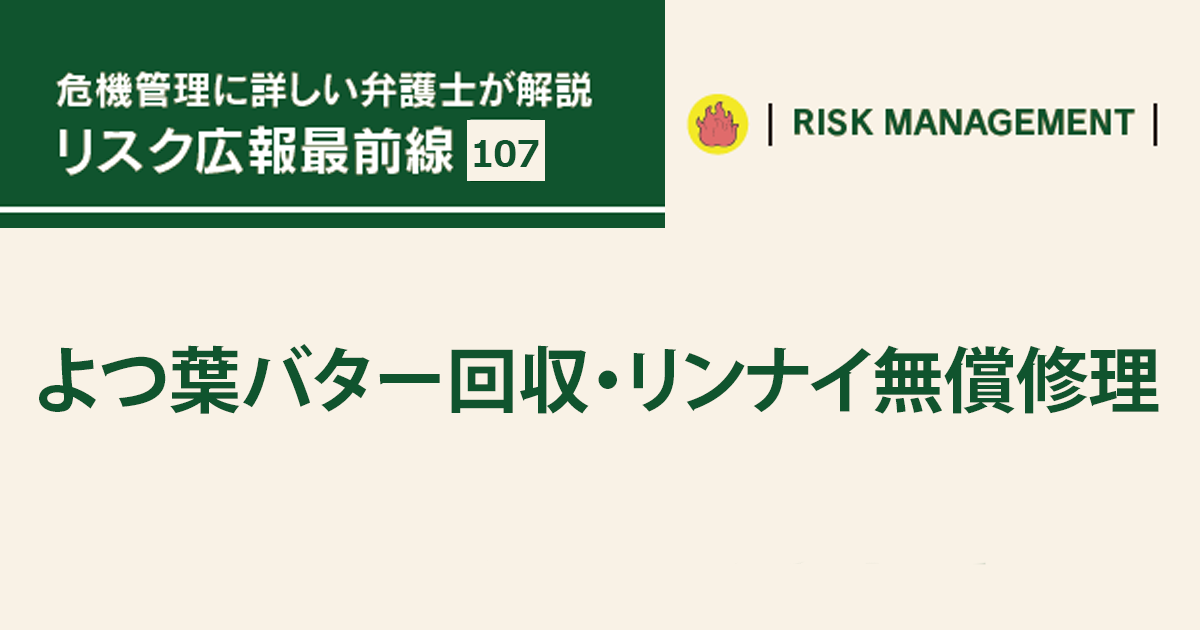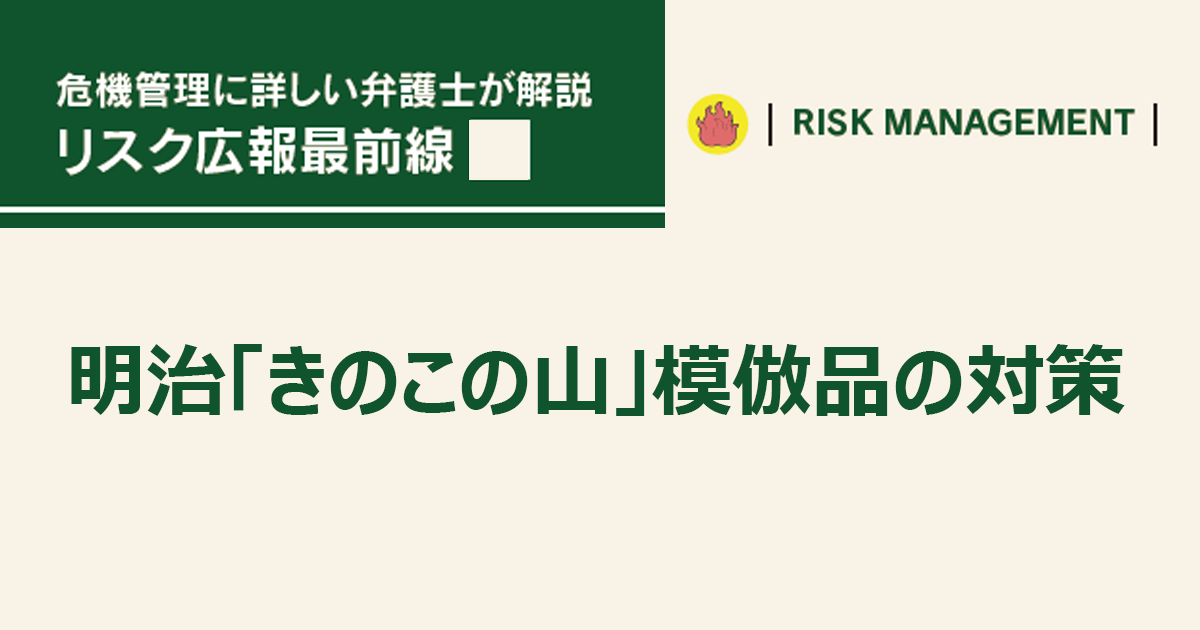複雑化する企業の諸問題に、広報はどう立ち向かうべきか。リスクマネジメントを専門とする弁護士・浅見隆行氏が最新のケーススタディを取り上げて解説する。
問題の経緯
2022年2月11日

三幸製菓佐藤元保・代表取締役CEOは火災発生後、記者からの取材申し込みに対して対応しなかったことから、「取材応じず」などの見出しで記事が出ている(本写真はイメージです)。
©123RF
「雪の宿」などで知られる米菓製造大手「三幸製菓」(新潟県)の荒川工場で2月11日深夜、火災が発生。6人が死亡した。翌12日の昼頃、消防当局による消火活動により鎮火。同社は13日、文書を公表。「(被害者の)ご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族に対し心よりお悔やみ申し上げます。改めて、地域の皆様や、お客様をはじめとする関係者の皆様に、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを心からお詫び申しあげます」と謝罪した。
2月11日深夜、新潟県村上市にある三幸製菓荒川工場で、従業員6人が死亡し、1人が負傷する火災事故が発生しました。事故により死傷者が出るケースは少なくありません。そこで、今回は、こうした事故が発生した後の広報対応を検討します。
過去の出来事が蒸し返される
荒川工場で火災事故が発生したのは、11日23時50分頃。翌12日11時頃には消防による鎮火が確認され、同時に、従業員5人(当時)の死亡が確認されました。
これを受けて、三幸製菓は、13日にコメントを発表(内容は「問題の経緯」参照)。火災事故発生後の初動のコメントとしては、十分な内容だと思います。特に、死傷者が発生した場合には、最優先で、死傷者とその遺族に対してお悔やみと謝罪の言葉を発することは、企業が従業員の生命を大事なものと思っているという姿勢を対外的に表すためにも不可欠です。
しかし、三幸製菓が本当に従業員の生命を大事なものと思っている会社であるかは、広報のテクニックだけで評価されるわけではありません。死傷者が発生するような重大事故が発生したときには、必ずと言っていいほど、過去の事故が蒸し返されます。
実際、12日は、同社新崎工場での火災事故の存在を報道されたのに加えて、荒川工場では1988年から2019年までに計8件の火災が発生していたことが報じられています。13日には、荒川工場の8件中7件は発生原因が共通していたこと、2020年9月には消防本部が立入調査により荒川工場の体制の複数の不備を指摘し、三幸製菓は改修済みと報告していたことなども報じられています。
こうした報道が積み重なると、広報がどれだけお悔やみの言葉を述べようと、三幸製菓が製造過程で火災が発生するかもしれないリスクを軽んじ、十分な予防策を講じていなかったのではないかとの疑いを世の中の人たちに与えてしまいます。
一方、三幸製菓は13、14、16日と連続してリリースをウェブサイトに掲載しました。これらのリリースは、毎度お悔やみと謝罪の言葉を繰り返す他、発表日時を入れて経過報告であることが分かる工夫をし、「事業所外への影響」「原因と対策」...