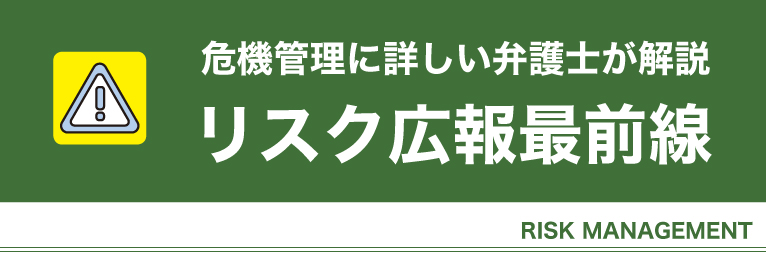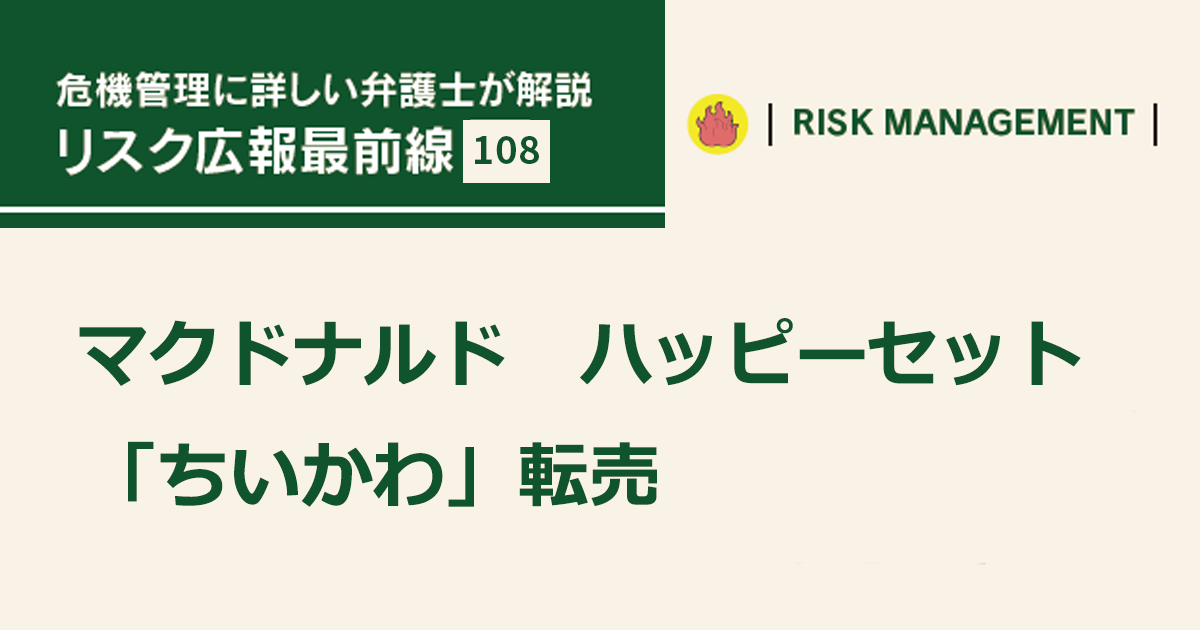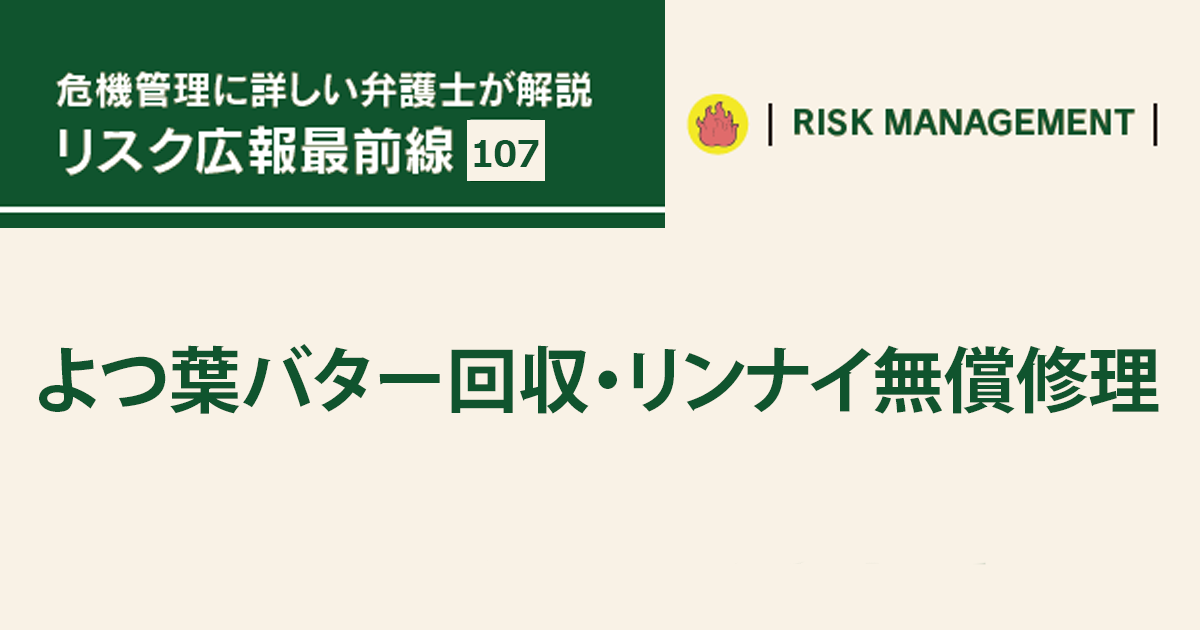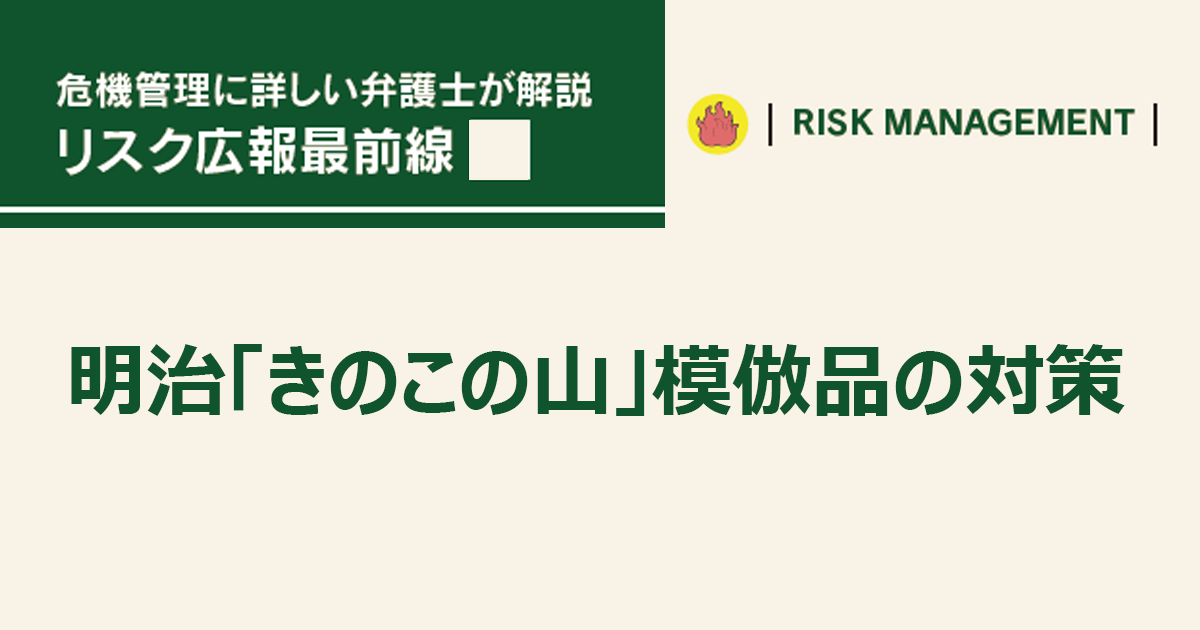複雑化する企業の諸問題に、広報はどう立ち向かうべきか。リスクマネジメントを専門とする弁護士・浅見隆行氏が最新のケーススタディを取り上げて解説する。
問題の経緯
2017年9月13日
埼玉、群馬両県の総菜店「でりしゃす」で購入した総菜を食べた22人が腸管出血性大腸菌O157に感染。9月13日には「でりしゃす六供店」の総菜を食べた女児の死亡が判明した。食中毒を起こした店舗は8月21日から3日間の営業停止処分。その後、9月19日の営業を最後に全17店舗を閉店した。
「あの時ニュースになった企業か」。ある企業の名前を見て、このような連想をしたことはありませんか。メディアによって構築された企業イメージは、良くも悪くも消費者の頭の中に刷り込まれます。特に、重大な事故によって失った信頼を取り戻すのは容易ではありません。
それでは、自社が関係する事故が起き、報道されたものの、自社には責任がないことが判明した場合、どのような広報対応をとるべきでしょうか。「堂々としていればよい」との意見は多いと思います。しかし、信頼回復という点からは、違う答えが導き出されます。
今年8月、全国の飲食店、食品販売店関係者が手に汗を握るような事故が起きました。埼玉、群馬両県で営業していた総菜店「でりしゃす」系列店で購入した総菜を食べた22人が腸管出血性大腸菌O157に感染したのです。
この事故で3歳の女児が死亡、5歳の女児が意識不明の重体となり、運営元のフレッシュコーポレーション社(群馬県太田市)の責任が問われました。同社の広報対応は評価すべき点が多くありましたが、一方で詰めの甘さもありました。今回は、同社の事例から、「信頼回復」に焦点を当てて企業の危機管理広報のあり方について考えていきましょう。
正しいのは「謝罪」か「逆ギレ」か
集団食中毒事故をきっかけに事業の清算に至ったケースとしては、2011年の「焼肉酒家えびす」の事例が記憶に新しいところです。同店が提供したユッケによって計181人が被害に遭い、うち5人が命を落とした悲惨な事故でした。
同店を経営していたフーズ・フォーラスの勘坂康弘社長は、記者会見で事故の責任を加工工場に転嫁したほか「不法なものを提供していたわけではない」と主張しました。この会見は「逆ギレ会見」などと批判され、同社は最終食品を提供した企業としての責任を問われることになりました ...