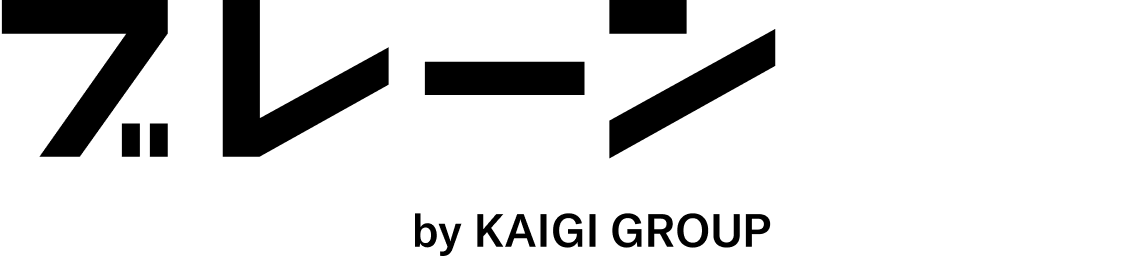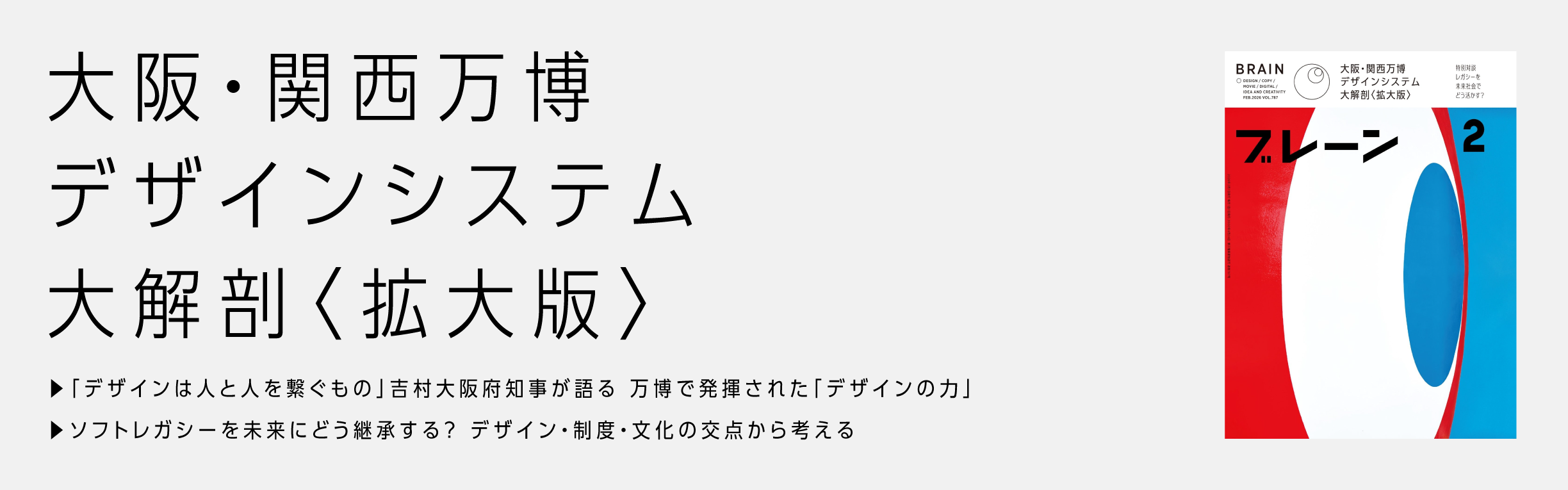「オープンデザイン」の思想を前提とした大阪・関西万博のデザインシステムでは、「こみゃく」を中心とした共創文化が生まれた。閉幕後の今、この一連のデザイン資産をどう使い続け、レガシーとして社会に根付かせていけるのだろうか。建築家の豊田啓介さん(左)、法律家の水野祐さん(右)と共にデザイン・制度・文化の交点から議論する。

東京2020エンブレムの論点
引地:今回お二人にご参加いただいたのは、前回の東京五輪の際のデザインにまつわる議論をベースに、今回の万博におけるデザインシステムのこれからを議論していきたいと考えたためです。実は僕は前回の東京五輪の際にエンブレムのコンセプトムービー制作のプロポーザルに参加したり、組織委員会に一時期出向してブランド開発に携わったこともあり、野老(朝雄)さんがデザインされた東京2020エンブレムの展開を提案したことがありました。その関係もあり、2025年6月に豊田さんに東京大学にお呼びいただいて、野老さんと3人で座談会としてお話ししたことがあったんです。
さらに前の2016年、豊田さんと野老さん、建築家の松川昌平さん、そして水野祐さんによるトークイベント「幾何学は誰のもの?」のレポートを拝見していました。そこでは公共のプロジェクトにおけるデザインの位置付け、それを取り囲む制度について深く議論がされていて、今回のデザインシステムを考案するにあたり、非常に刺激を受けたんです。そうした前回の五輪からの流れもあったので、まずは改めて、当時の議論を振り返れたらと思います。
豊田:そうですね、野老さんがデザインされた東京2020エンブレムは、ごくシンプルな幾何学で構成されています。明らかに個性がありますが、形や線自体はごく一般的なものでしかなく、その調整や組み合わせに野老さんの個性がある。何億通りの幾何学の組み合わせがあるなかで、そのうちの1パターンだけがエンブレムとして突然意味を持ち、それ以外は一部が違った瞬間に法的にエンブレムではなくなる。とはいえ人間は大きなルールを認識しているので、多少パターンが入れ替わっても誰もがこれは東京2020のエンブレムだと認識できます。経済的・法的に定義される価値と、それに対する人間の認識のブレや境界のあいまいさ、そういうことに興味がありました。
同時にあのエンブレムはシステムやルール自体がデザインであり個性であるという革命的に面白い新たなパラダイムを提案していたと思うのですが、その価値に見合った権限や利益還元の仕組みが、野老さんやそれを活かせる人に与えられていなかったと思います。となると、デザイナーやデザインの価値ってどこにあるんだろう?と。デジタルが当たり前になり、ああいったデザインがパラメトリックに生成できる時代に、どこに価値が生まれるのか。そんな話を水野さんに相談していた時期でもありました。パラメトリックデザインやカスタマイズできるコードの価値、そこからの生成物そのものの価値と権利みたいな話もまだあまりされていない時期ではあったので。
水野:私は当時五輪のエンブレム決定の過程に注目が集まる中で、野老さんのロゴが、特にグラフィックデザイン業界からの評価が適切にされていない気がしていました。あの特殊性や展開可能性に対する業界の想像力が追い付いていなかったというか。それを紐解きたいというのもありました。
またあのエンブレムは展開可能性を前提にデザインされていましたが、組織委員会側は商標も含めてロゴとして“固める”方向で進めていました。それは従来の五輪ビジネスの定石としてはある意味当然の方向ではありますが、あのエンブレム・ロゴの可能性を阻害しているのではないかと思われました。固定・静的なエンブレム・ロゴのこれまでの固定観念に対するある種の問題提起として、ああいったトークイベントに結実していったのだと理解しています。
生成的な装置としてのデザインシステム
引地:今回制作した万博のデザインシステムは、見え方は異なりますが、参加...