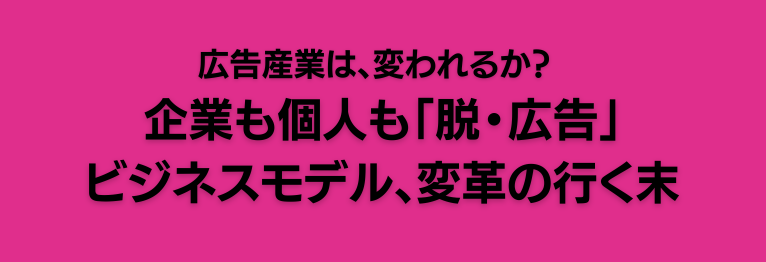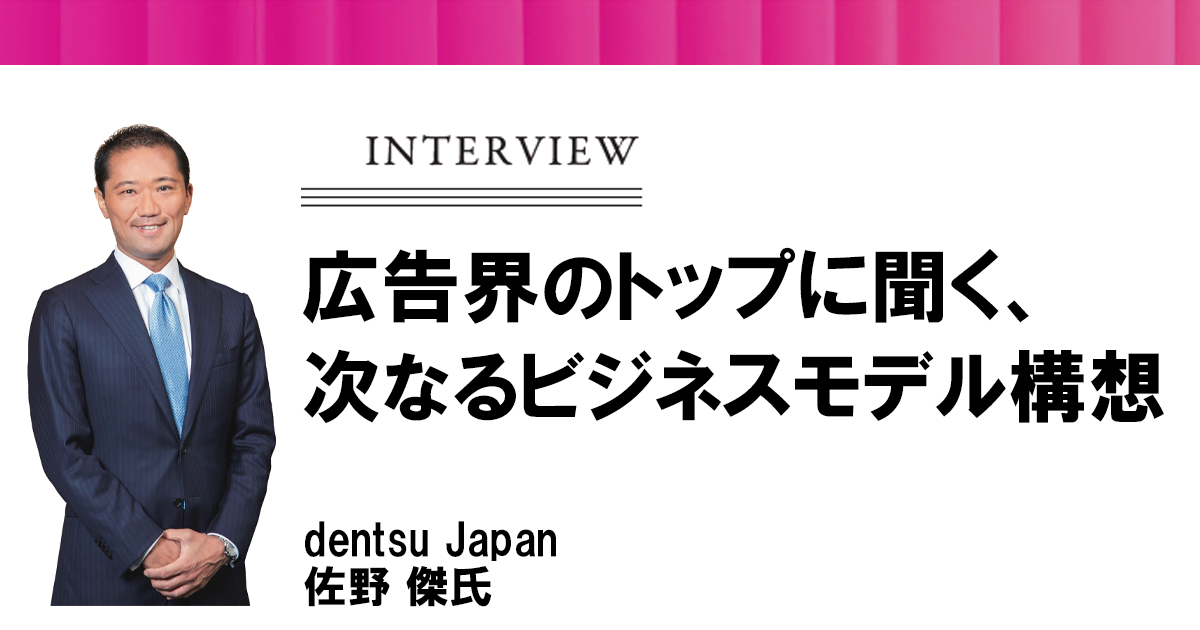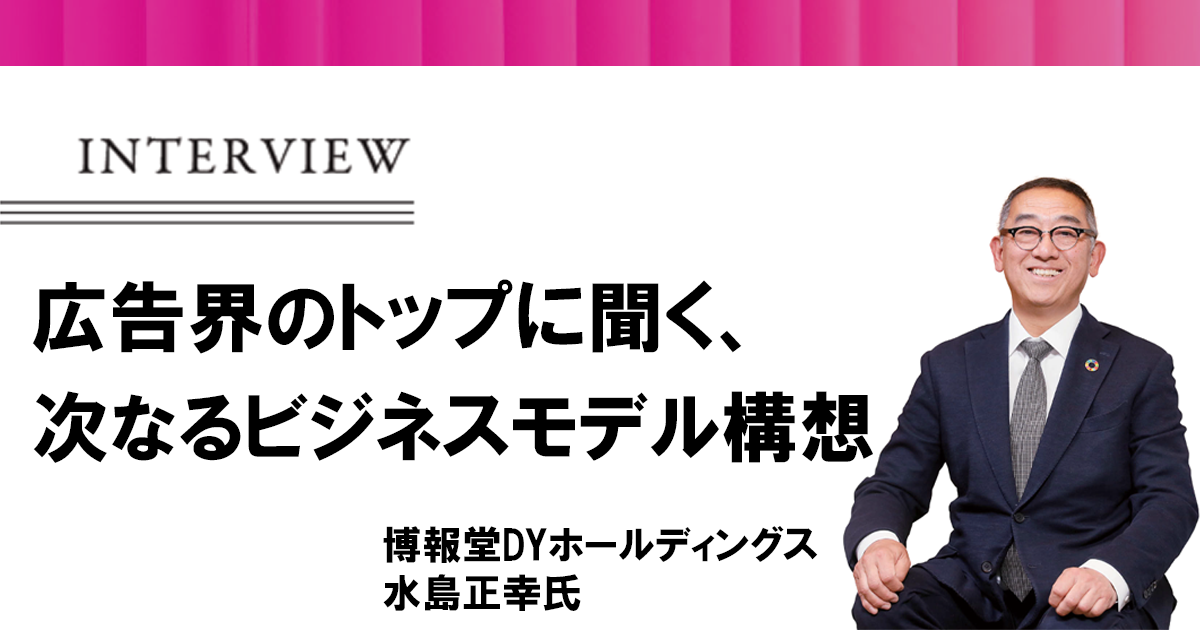年々増加傾向にある、日本のリスキリング市場。一方で、組織的にその育成基盤を整えるためには課題も山積している。あるいはその前段階である学校教育で、できることはあるのだろうか。本稿では、マーケターや経営に携わるキャリアを経て、今「教育」に向き合う3名が議論する。

茨城県立下妻第一高等学校・附属中学校 校長
生井秀一氏
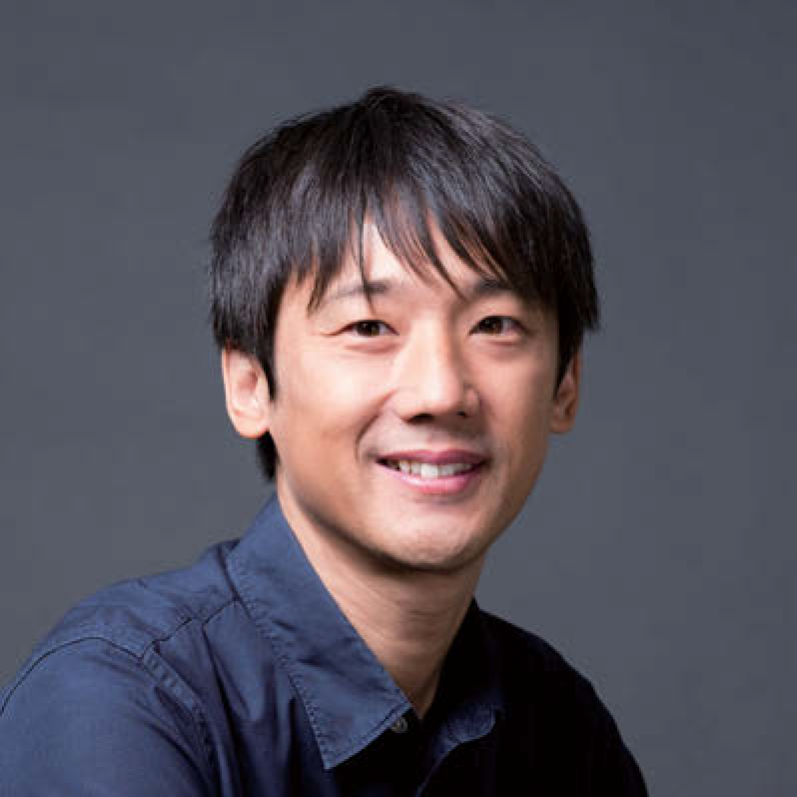
玉井博久氏

Tech0 代表取締役CEO
濱田隼斗氏
「チャレンジをしない」文化は日本人が克服するべき課題だ
─これまでのキャリアと最近の活動を教えてください。
生井:私は花王に24年間勤めた後、2023年4月に茨城県立下妻第一高等学校・附属中学校の副校長、2024年4月に校長に就任しました。移籍のきっかけは、出身地である茨城県であった民間校長の公募です。応募条件は「アントレプレナーシップ精神を育成できるマネジメント経験がある人」。私は、花王ではマーケティング、特にEコマース事業を担当していて、その公募を知ったのはDXの部署を立ち上げたとき。さらに、コロナ禍で世の中が様変わりしたことをきっかけにMBAを取得したり、子育てを通して子どもの教育について考えたりと、教育については課題として感じていたところだったので、運命を感じました。
玉井:私はリクルートやタグボートで広告クリエイティブの仕事をした後、…