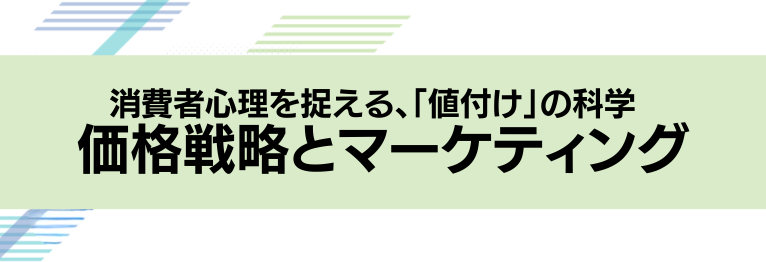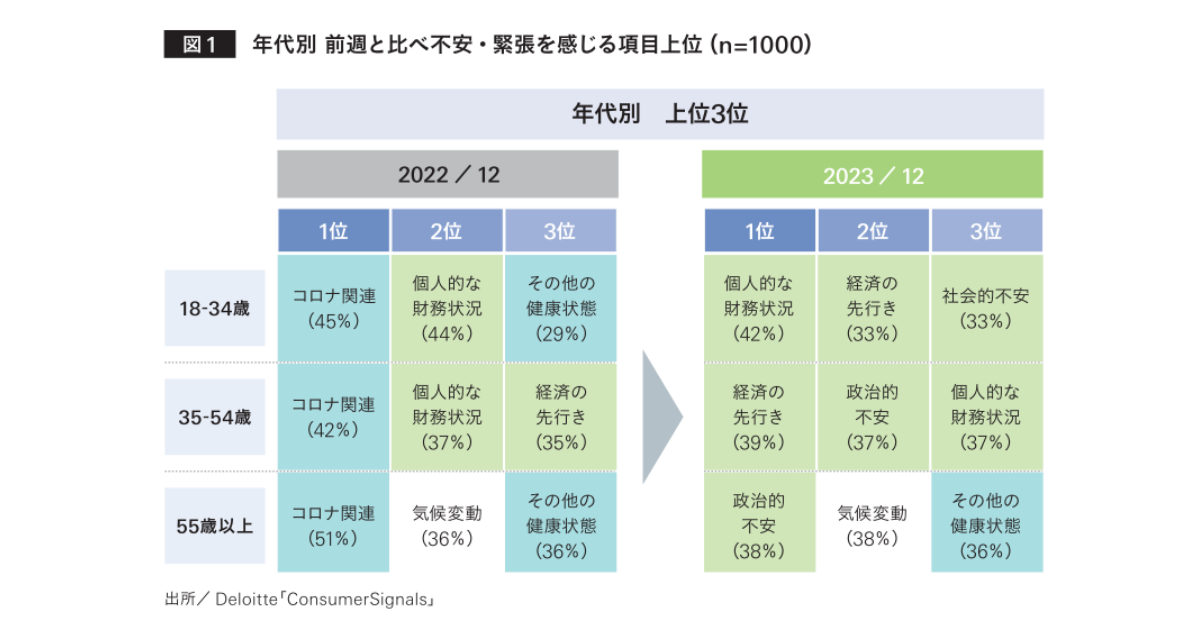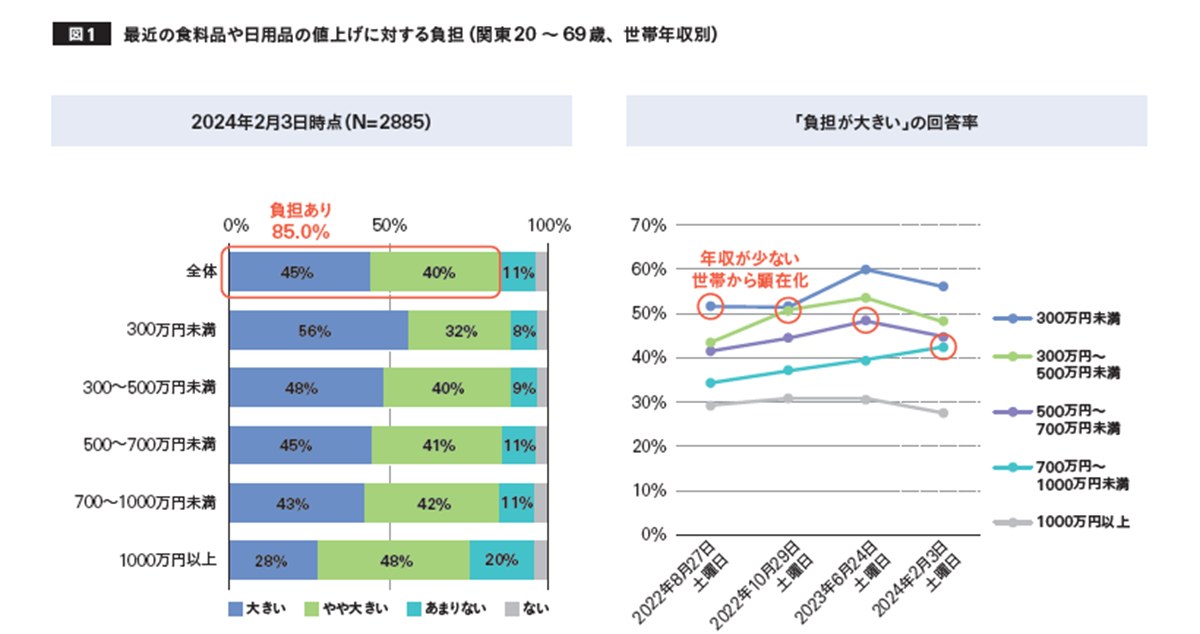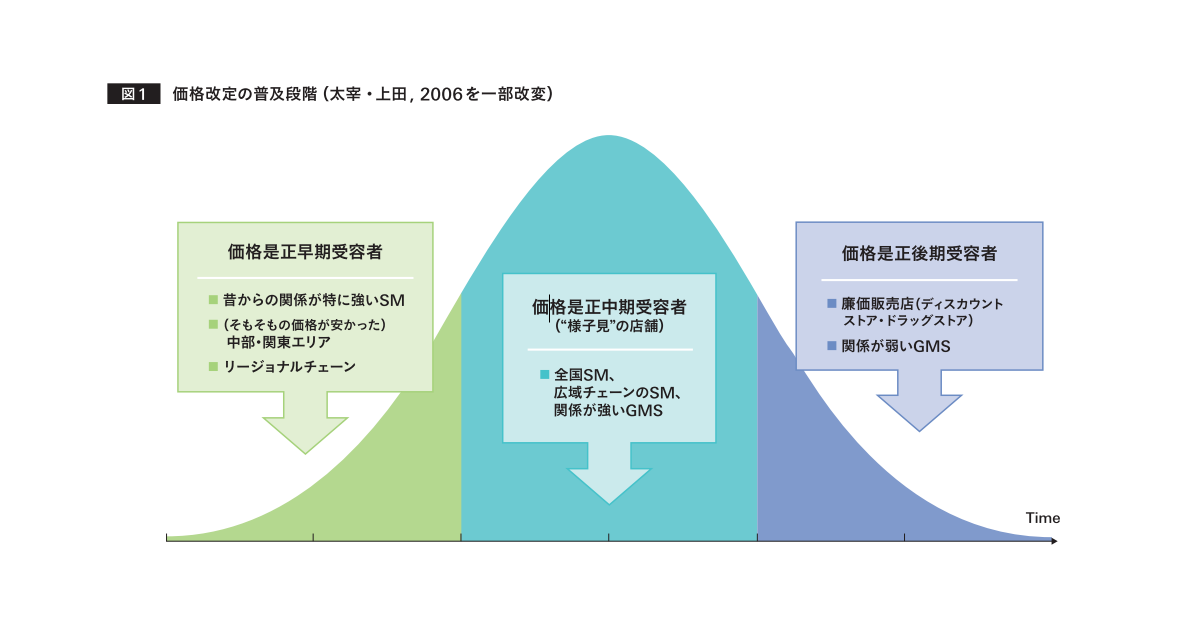2023年から原材料や物流費、人件費などの高騰の影響により、多くの日本企業では商品やサービスの値上げをせざるを得ない状況が続いている。このような状況のなか、企業はどう対応すべきなのか。『価格支配力とマーケティング』の著者のひとりであるボナ・ヴィータ代表取締役の菅野誠二氏が解説する。
価格マネージメントを放棄する 価格無支配力企業にならぬため
日本企業の多くはこれまで海外投資には資源を注ぎながらも、国内の物的・人的投資を控え、固定費の抑制でデフレ価格を成立させてきた。しかし2023年から値上げラッシュが続いているいま、このデフレゲームのルールは変わった。政府からの賃上げ要請に応えられる大企業の従業員はまだしも、企業数では99.7%、従業員ベースでは68.8%に当たる中小企業の従業員がその恩恵を受けられるか否か。ここからが景気回復の正念場だろう。
ここで、「価格支配力」という概念を紹介しよう。価格支配力とは「自社の提供物の販売価格をマネージメントする力」である。「需要を抑制してしまったり、競合他社にシェアを侵食されたりすることなく、利益を維持・拡大するために価格を引き上げる能力」と定義することもできる。私の造語だが、その価格マネージメントを放棄している企業は「価格無支配力 Non-Pricing Power」...