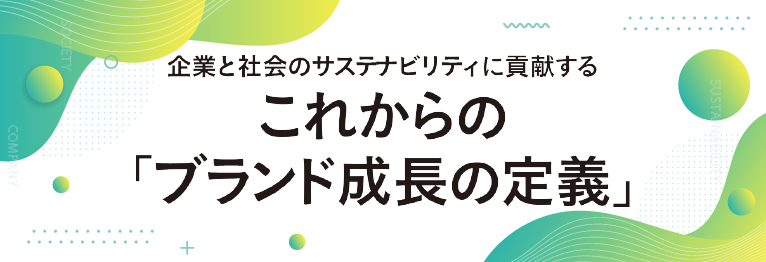人口の減少などに伴い消費市場の縮小が進む現在、「前年以上の売上拡大」以外に、企業の成長を測る評価指標は存在しないのか。世の中に新しい指標・価値観を生み出している2名が、これからの企業の“持続的な成長”のために必要な指標について語り合う。

九州大学 主幹教授/都市研究センター長
馬奈木俊介氏

ファンベースカンパニー 代表取締役社長/CEO
津田匡保氏
「新国富指標」と「ファンベース」いま求められる考え方とは
──活動の領域は異なるお2人ですが、企業活動に新たな価値指標をつくるという取り組みにおいて、共通する点もあるかと思います。
馬奈木:私の2014年以降の注力領域に、「新国富指標」の構築と計測ということがあります。「新国富指標」とは、健康や教育、自然など、これまで数値化できなかった要素を、経済価値に換算する指標であり、社会課題に対する指標とも言えます。
これは、「人がどれだけ健康になった」「環境が改善された」などが、可視化できるということ。この指標を用いて世界各国ごとに計算をしています。地域や国単位で「新国富指標」の向上を目指せば、SDGsで求められる環境・経済・社会の成長が実現できると考えられており、イギリスやパキスタンなど、これを目標として置いている国もあります。
このような国際的な取り組みを行う一方で、国内の企業と共に、「企業の要素技術により行った社会課題の解決が、最終的に企業の利益にもつながる」という観点から、企業による“社会課題解決の価値化・定量化”といった活動も行っています。
企業の方、特に製品開発を行っている方とのかかわりの中で感じたのが、製品を使う人の主観ではなく、例えば「この技術を使えば、汚れを50%除去できる」などから企画をスタートし、その技術を使うことを目標として定め、それを達成するのが開発の目的になっているケースが多いということ。これは、“この商品を使ったら快適だった”“幸せになった”などの、“主観”を評価することができないと思っているために起こることです。
しかし、主観を客観的に評価し、定量化することは可能です。近年ではCX(カスタマー・エクスペリエンス)に注目する企業が増えていますが、それはAIの進化も相まって、主観を評価する重要性に皆が気づき始めたからではないかと考えています。
津田:ファンベースカンパニーは、企業やブランドを支持する“ファン”を大切にし、ファンをベースにして中長期的に事業価値を高めていく「ファンベース」の概念を軸に活動しています。企業やブランドに対するファンの熱量を可視化する「ファン度」という指標や計測サービスも開発し、企業への導入も進んでいます。また、最近ではファンの心理や行動を深く研究する「ファン総合研究所」も社内に設立し、研究開発事業を加速させています。
私がファンベースを重視する考えに至ったのは、前職のネスレ日本での経験にあります。ネスレ日本でマーケティングや新規事業開発に携わる中で、「中長期的に成長を続けていくためには、新規顧客獲得だけに注力していては厳しい」と考えました。
そこで、オフィス向けコーヒー宅配サービス「ネスカフェ アンバサダー」では、新規顧客へのアプローチに加えて、既存のファンとのコミュニケーションにもかなり注力し、顧客のエンゲージメントとLTVを高めていきました。新規と既存のアプローチを両輪で実施していった結果、事業として成功することができたと考えています。既存のお客さまやファンほど大切な人はいませんし、事業の成長には欠かせない存在です。
このような考え方を広め、これからの社会にとって必要なものであると証明していくために、ファンベースカンパニーを経営しています。
ネスレ日本時代の経験でもうひとつ印象的だったのが、顧客と一緒にボランティア活動を行った時のこと。顧客にとっての“おトクさ”や“便利さ”を提供した時よりも、一緒に社会貢献活動をした時の方が、企業と顧客の関係性が強固なものになりました。社会貢献活動などの「体験」は、企業と顧客の間にある壁を壊し、一丸となるためのきっかけにもなるのではないかとの気づきがありましたね。
「企業ビジョンの明確化」が社内・社外に与える影響
馬奈木:今の津田さんのお話は、ネスレ日本という企業が社会課題に対する思いを発信し、そこに顧客が共感した点で、強い関係性が生まれたのではないかと思います。「ネスカフェ アンバサダー」も、津田さんが高校生の時に阪神・淡路大震災で被災され、その時にコーヒーの温かさやおいしさを実感したこともきっかけになって生まれたサービスであると聞きました。
さらには、東日本大震災の時には、コーヒーマシンを持って被災地に行かれたと。このような強い思いを持ってはじめられたサービスであるからこそ、共感が生まれる。企業が思いや考えを明確に発信することの重要性を感じます。