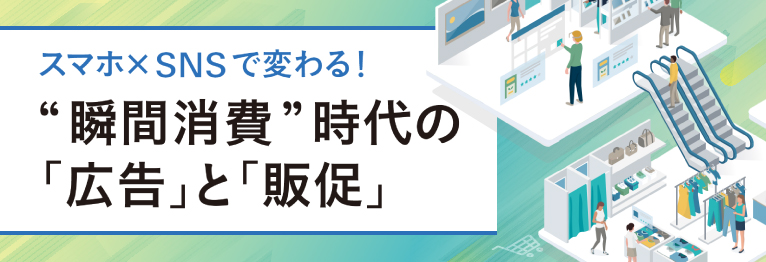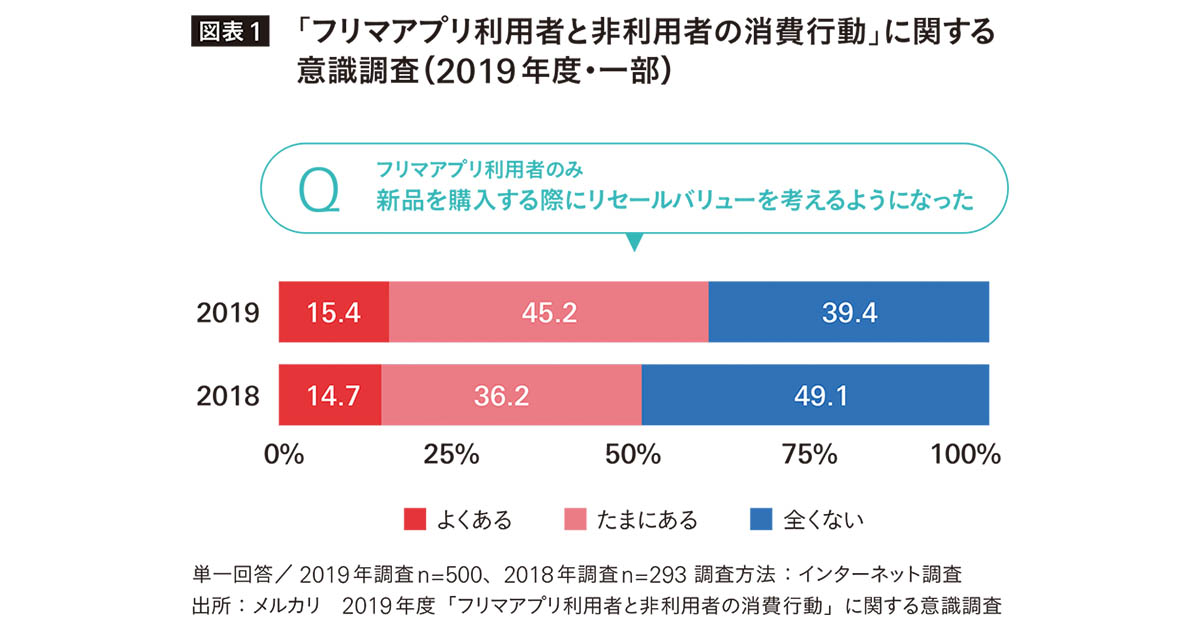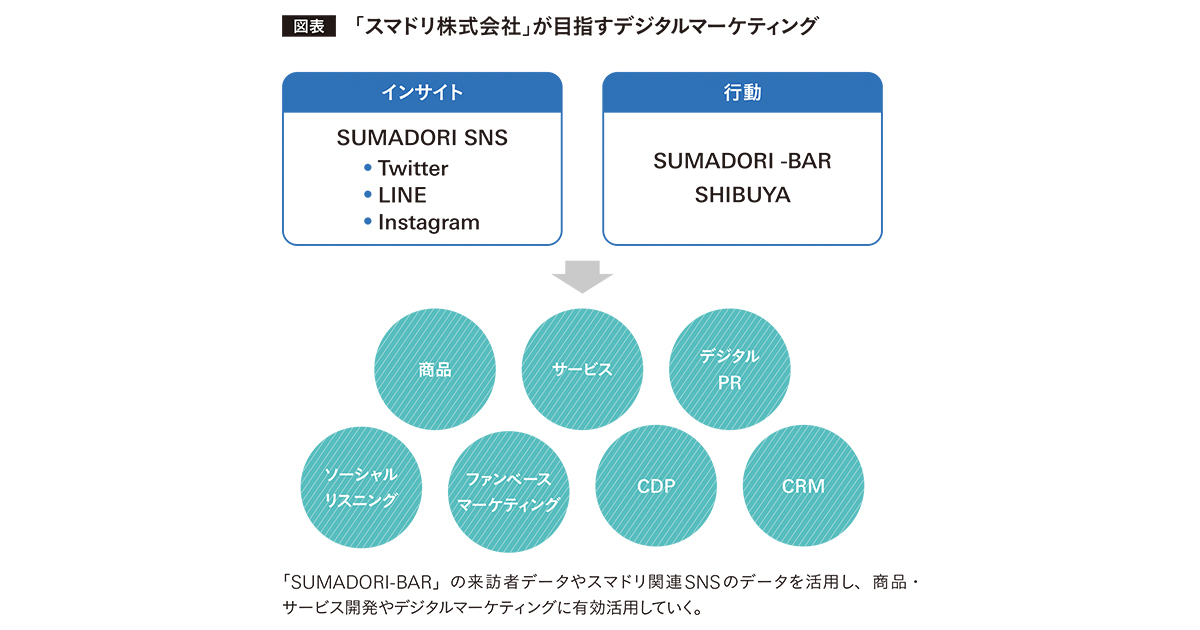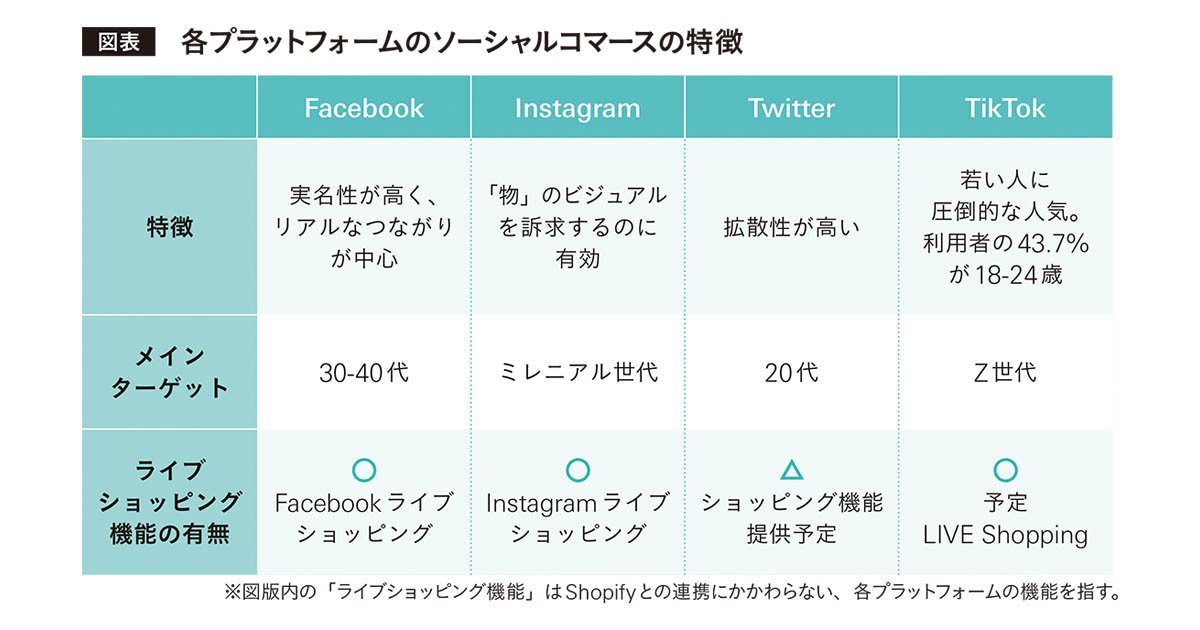リアルの小売り店舗だけではなく、デジタル上にも多くの“売り場”がある時代、メーカーではどのような体制で販売促進を行っているのか。花王のECビジネス推進部で同社のEC領域を管轄する生井秀一氏に、現代のEコマースビジネスを推進する為に効果的な体制や、組織間の意識について聞いた。

化粧品ブランド「est(エスト)」の自社ECサイトでは、オリジナルのショッパーやBOX、メッセージカードを用意しギフト需要に応えている。自社ECではクリスマスなどの催事のタイミングで売上が拡大しているという。
2021年にEC部門を本社に統合 部門間連携で顧客接点を増やす
花王は2021年1月に4つの部署からなるDX戦略推進センターを新たに設立。DX戦略推進センター内の一部署であるECビジネス推進部では、同社のECにかかわる機能を集約し、運営している。
ECビジネス推進部の部長を務める生井秀一氏は、ECビジネス推進部設立の背景について、「もともと花王では、ECに関連する組織が本社と販売会社である花王グループカスタマーマーケティングに散在していました。しかし、これからは『トリプルメディアとショッパーメディア(ECサイト)を融合したコミュニケーション戦略』が必要であり、そのためには、本社の中のひとつの部署に機能が集まっていた方が各事業部門との連携もとりやすく、一貫した戦略も実行しやすいという考えがありました」と話す。
花王がEC市場への進出を本格化させたのは2015年頃。同社が扱うヘアケア用品などの日用品においては、以前は小売りの商品棚を確保することが直接的に売上・シェアに結びつく時代であったが、そこにEC発のブランドが参入。オンライン上での話題も、リアル店舗での棚の維持や拡大につながる時代となった。このような時代においては、“リアル店舗だけ” “ECだけ”ではなく、両者あわせてブランドが拡大するための戦略が必要だという。
「顧客の購買行動を見ても、“普段ECで購入している商品を今日はリアルの店舗で購入する”といった動きがあります。『ECで販売するとリアル店舗での売上が下がるのではないか』という不安もかつてはありましたが、ECで商品を認知し、店舗で購入するという送客も存在します。このような場合、ブランド全体で顧客との接点を多くつくることが重要。リアル店舗もECも、それぞれの役割を認識し、連携することで、シームレスな顧客体験を提供することが...