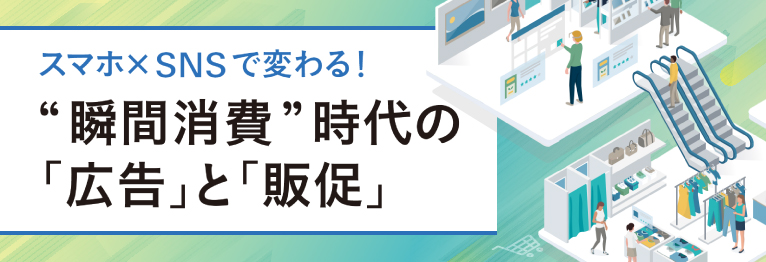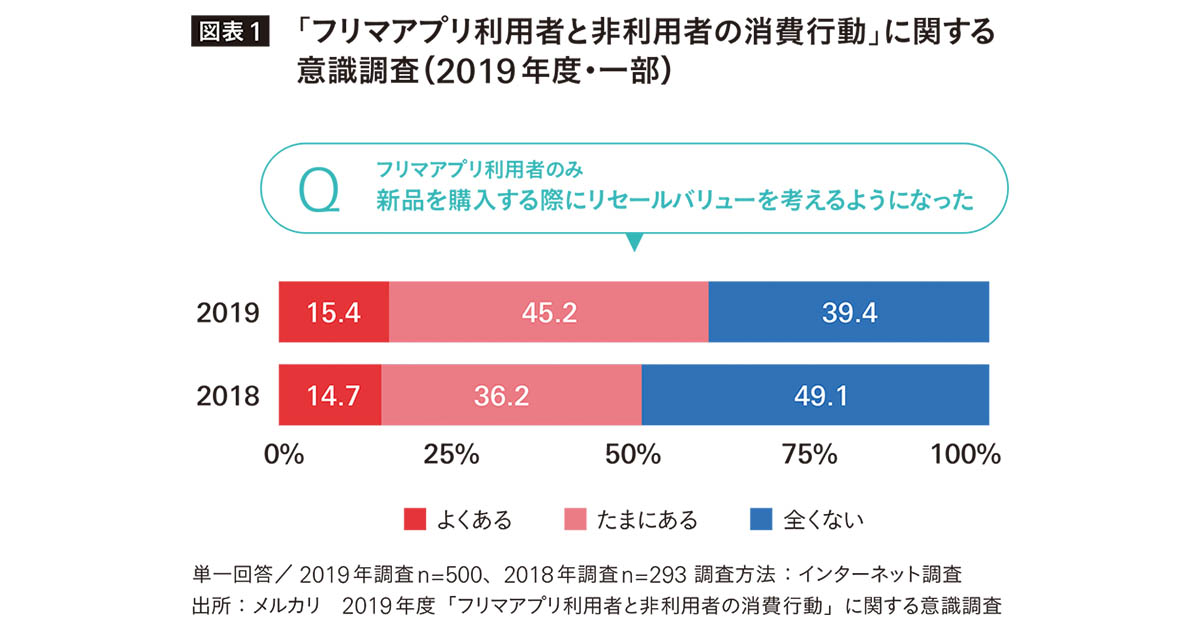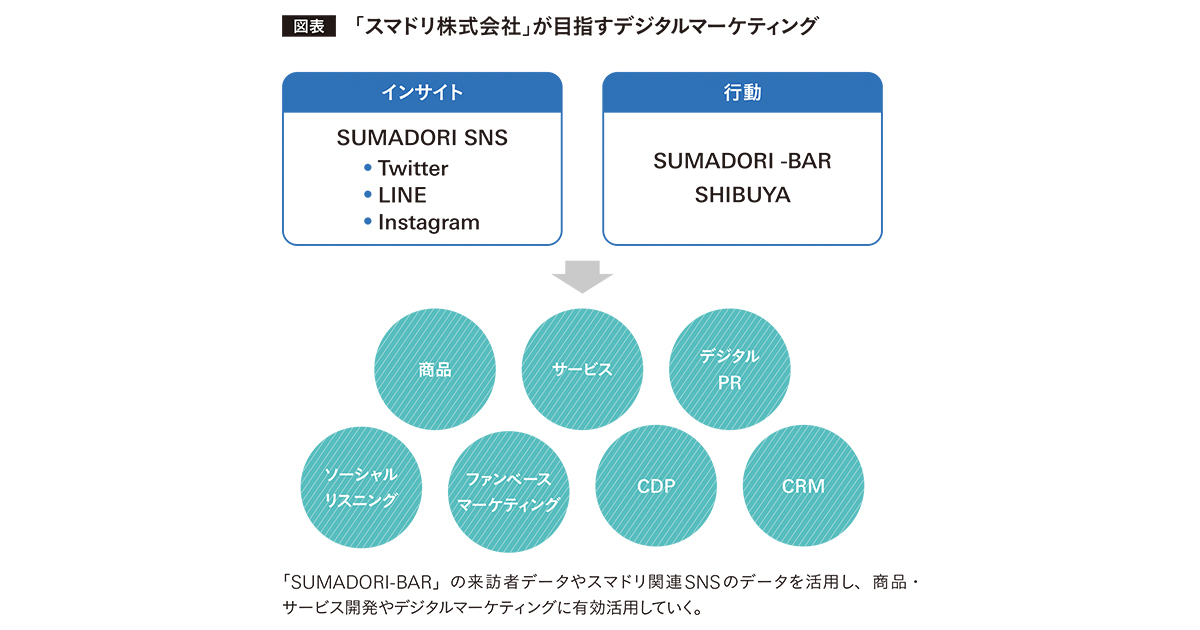広告や販促、PRといった手法を統合したマーケティング・コミュニケーション戦略が必要とされるようになって久しい今、その戦略の企画・実現の最前線にいるプランナー/クリエイターは「セールスプロモーション」という領域をどうとらえているのか。広告会社3社のプランナー/クリエイターが、これからの「セールスプロモーション」の定義について話し合う。

ADKクリエイティブ・ワン
ビジネスデベロップメント本部
デジタルコミュニケーション局
第2コミュニケーション・プランニンググループ
コミュニケーション・ディレクター
田村香穂理氏
2009年ADK入社。プロモーションユニットを経て、2011年よりコミュニケーションプランナー。コアアイデアを起点に、課題解決のための統合コミュニケーション企画と制作を担当。

博報堂プロダクツ
デジタルプロモーション事業本部
アクティベーションプランニング部 チームリーダー
田中直子氏
入社以来、プロモーションプランナーとしてナショナルクライアントの年間コミュニケーション戦略や、体験型施設での生活者ひとり一人に寄り添った体験プランニングを経験。

電通プロモーションプラス
コピーライター/プランナー
久我佳太氏
2008年電通テック(現・電通プロモーションプラス)入社、TCC会員。広告コミュニケーション領域からアクティベーション領域まで。コピーを軸とした領域にとらわれない企画立案と課題解決が主戦場。
改めて「販促」とは何か?デジタル台頭により生まれた変化
──まず、急速に進んできたデジタル化がセールスプロモーション(販売促進)に与えている影響について、感じていることをお聞かせください。
田中:「販売促進」=「買い場での最後の一押し」と考えると、そもそも“買い場”自体がデジタル化により以前と比較して格段に増えていることは、販促に大きな変化を与えていると思います。以前の販促はリアル店舗に買い物に来たタイミングに活動が限定されていましたが、買い場が多様化する中で、“どこで”“どのタイミング”で購入してもらうのかという設計から考えることが、販促には求められるようになったと感じています。
田村:「タッチポイントごとに必要な情報を出し分けていく」という販促の本質的な方法は変わっていないのではないかと思います。ただ、田中さんがおっしゃるようにタッチポイントの種類が格段に増えているので、それぞれの特性に応じた情報設計が必要ですね。
逆に大きく変化したと感じているのが、企業側でコントロールすることが難しい口コミなどの第三者の声が、販売に大きく影響を与えるようになったことです。企業発の情報と第三者発の情報の双方をどのように販促に生かしていくか、という観点も現在の販促には求められていると思います。
久我:今回の座談会に参加するにあたって私自身、日頃「販売促進」と「広告」をあまり区別して仕事をしていないことに気づきました。デジタルの浸透以前は、予算の都合上、あらゆる商品でマス広告を打てるわけではないので、広告を打てない商品のセールスプロモーションでは店頭でのPOPやポスター展開が中心に。おのずと伝えられる情報量にも限りがありました。そのため発信する内容もブランドメッセージなどではなく、その瞬間に商品を手に取ってもらえる“お得”をうたうオファーに限定されがちでした。
しかし、“買い場”も増え、販促領域においてもSNSやWeb動画のような多くの情報を詰めることができる武器を手に入れることになりました。このことが、「販促」と「広告」の境界を薄くした要因なのではないかと思いますね。
──発信の場も手段も増加したことで、販促にかかわる人に求められる役割や能力も拡大したのでしょうか。
田中:そうですね。クライアントに提案できる企画の幅が増えたという実感がありますし、クライアントと話をしていても、広告宣伝と販促の境が緩やかになっていることを感じます。
また、電子マネーやQR決済などの決済手段の変化に、新しい販促アイデアを組み合わせることで、これまでにない体験を...