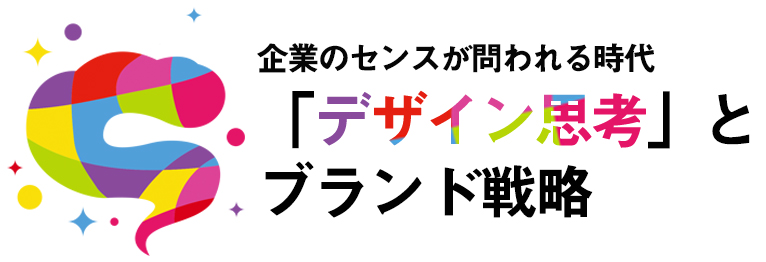自社の課題に合わせ、「デザイン思考」をアレンジして取り入れているという富士フイルム。試行錯誤の末、課題解決から自社の資産を生かしたイノベーションも起こしてきた。Open Innovation Hub館長の小島健嗣氏に、「デザイン思考」の活用に成功した秘訣を振り返ってもらった。

Open Innovation Hubのタッチスペース(写真右)と、色素化学技術による"三色の液体"とアルミ陽極酸化技術による「モルフォ蝶」(写真左)。Open Innovation Hubによってモノや機能価値を介して分かりやすく技術を伝えることができるようになり、それまで関連がなかった企業との間にもコラボレーションが生まれるようになった。
デザイン思考を活用し社内の"共通言語"をつくる
富士フイルムがデザイン思考を取り入れたきっかけは市場の変化だ。写真フィルム市場は、2000年をピークに縮小し、数年後には市場はほぼ壊滅状態になるとの予測があり、実際に富士フイルムでも当時、売上の大きな割合を占めていた写真フィルムの比率が急速に減少していった。
こうした状況を踏まえ、2004年に当時の古森重隆社長(現・代表取締役会長・CEO)は、富士フイルム全体の知恵を融合して新しい価値をつくる「融知・創新」というコンセプトを掲げ、写真フィルムで培った12のコア技術と9つの基盤技術を組み合わせて、新しい成長戦略を構築する方針を表明した。
「ところが、当時は研究室が商品ごとに分かれていて、日常的な部門間の交流はまったくと言って良いほどありませんでした」と、同社 Open Innovation Hub館長の小島健嗣氏は振り返る。小島氏は、研究者同士のコミュニケーションを促進するため融知・創新を進めるプロジェクトチームに参画したが、進めるにあたっては課題もあった。
「そもそも研究者は専門用語で会話するため、同じ理系でも物理の専門家と化学の専門家では話が通じないのです。この問題を解決するには共通言語が必要だと思いました」 …