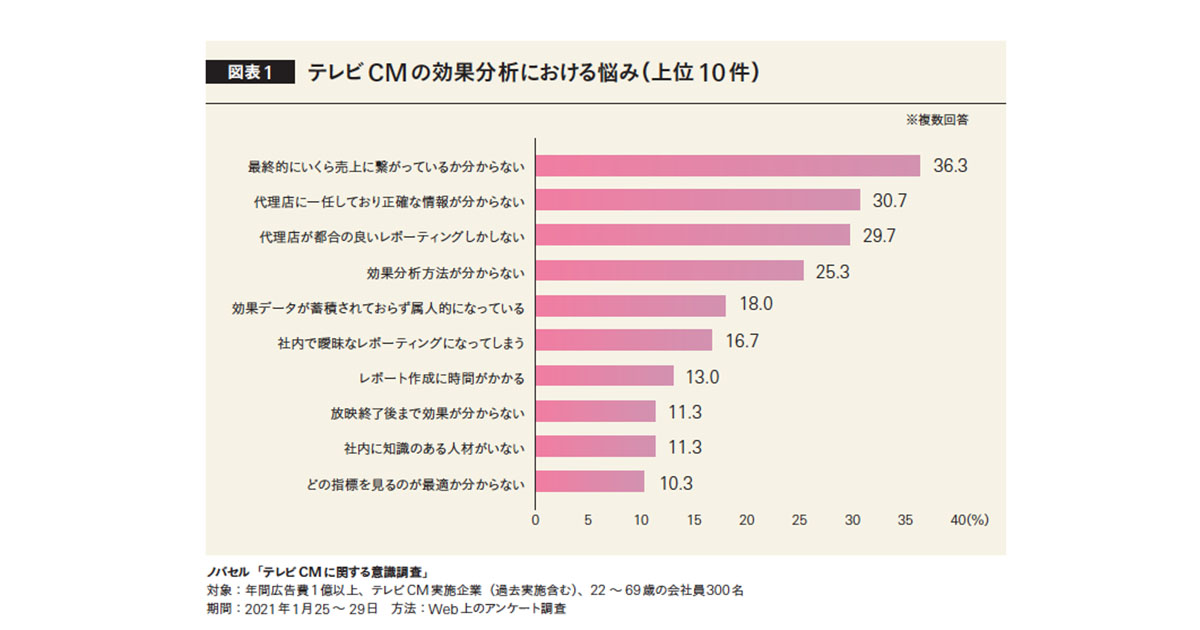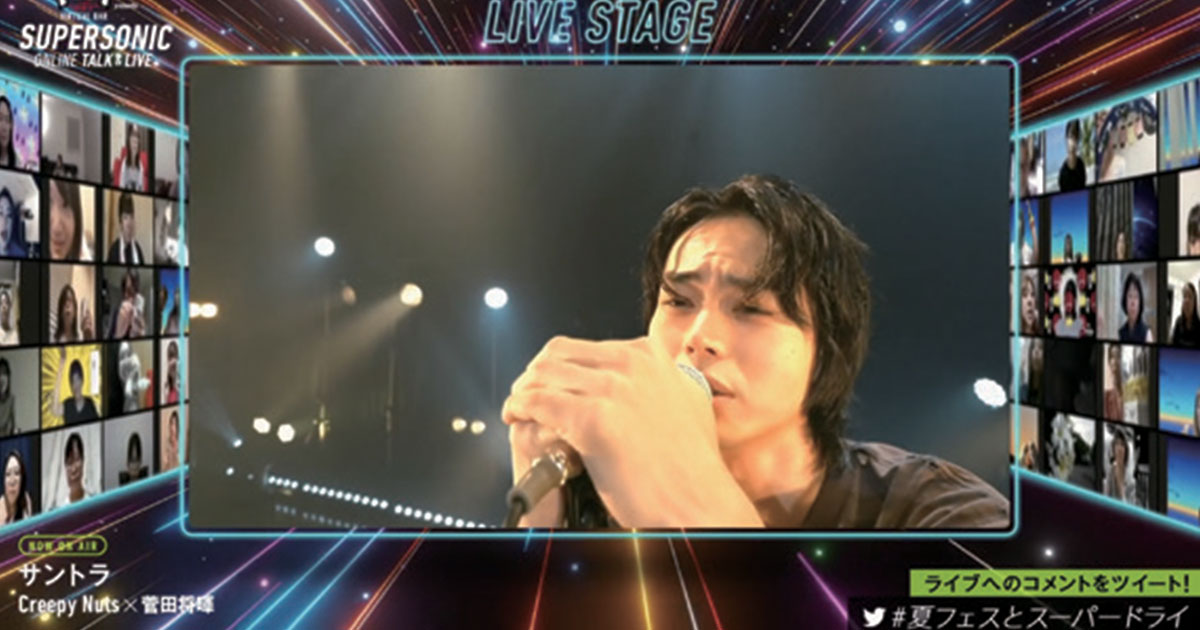日本でもブランド広告主のデジタル活用が進んできたが、マスとデジタルは当然ながら、求められる知識もスキルも異なる。マスを中心としてきた宣伝部でもデジタルが抱える課題を理解していないと、大きなリスクを抱えることになりかねないが、現状はその理解を醸成する組織体制になっていないのではないか。日本アドバタイザーズ協会(JAA)・常務理事の小出誠氏にデジタル広告の諸問題解決における、広告主の組織と人材の問題について話を聞いた。
予算を持つのは約半数!?宣伝部とデジタル広告の関係性
JAAと宣伝会議で2019年に実施した「デジタル広告における意識・実態調査」によれば、「アドベリフィケーションという言葉を知っているか」との問いに対して、調査対象のアドバタイザーの31.5%が「言葉自体を知らない」と回答。
JAAでは今年4月から日本広告業協会、日本インタラクティブ広告協会と共同でデジタル広告の品質を第三者的に認証する組織である「一般社団法人 デジタル広告品質認証機構(JICDAQ)」の事業を開始したが、「業界を挙げた取り組みにしていくためには、アドバタイザーの理解が不可欠。宣伝部にもデジタル広告の諸問題に対する理解が必要」と小出氏は指摘する。
しかし前述の調査でデジタル広告出稿の予算を持っている部門を聞いた質問で、『宣伝部』と回答した人は44.8%。「2年経って変化していると思うが、宣伝部門の約半数がデジタル広告出稿を見ていないという状況だった。自分が管轄していないと意識を持ちづらい面もあるが、そこを解決しないとデジタル広告の品質問題は解決が難しい」と小出氏は語る。
小出氏自身は...