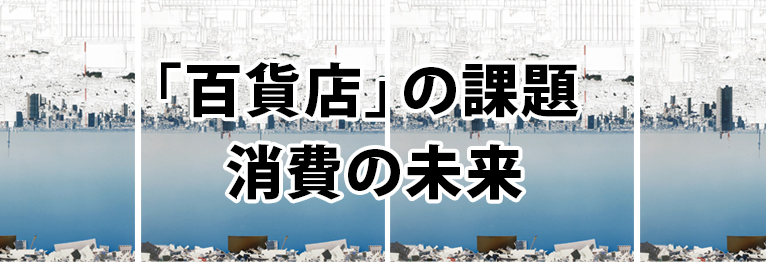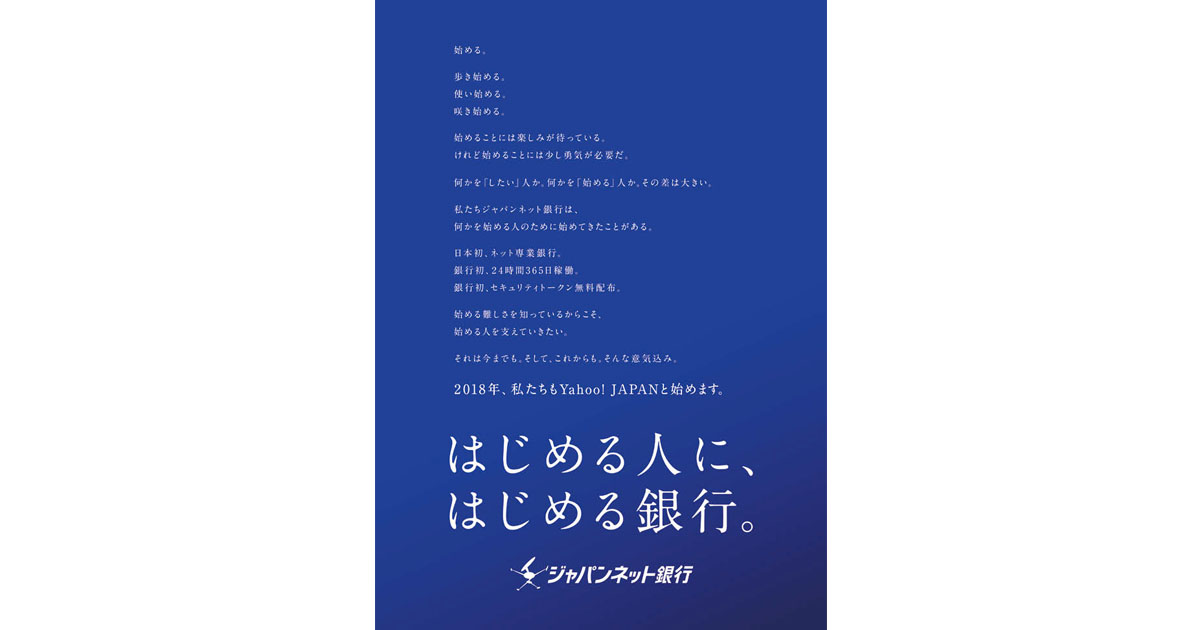百貨店が置かれた状況は、消費者の意識や行動、産業構造の変化など外部環境の構造的変化、百貨店の深い内部課題に起因しています。青山学院大学大学院教授の宮副謙司氏が、成長へ転じる好機か、低迷へ凋落かという歴史的な分水嶺にある現在の百貨店の今後を占います。
消費意識と産業構造の変化に揺れる百貨店
私が注目する重大な変化は、消費者がモノで自己主張し共感を得る「ファッション」の時代は終わり、SNSで自分をブランディングし「いいね」数で満足を得る時代になっているということである。例えば、米国・ポートランドなど先進地域では、すでにICTを活用するデジタルな生活が前提で、デジタルを超えてリアルでの人のつながりやコミュニティを重視する生活への変化が顕在化している。
具体的な購買行動としては、第1に、モノに「こだわる、こだわらない」の2極化が進展している。コモディティなど、こだわらないモノは時間やコストをかけずにネットで購入する。こだわるモノはオーダーや手づくりで自分にとって価値のある物として創造・獲得する動きである。
第2にファッションへの関心は、価格・品質で創りだされたラグジュアリーを頂点とする従来の商品ヒエラルキーでなく、また、発信される流行トレンドでもなく、自らの価値観で選択される。
また、この5年ほどのスマートフォンの急速な普及やICTビジネス活用の進化など「デジタルの大波」が日本に押し寄せ、産業構造にも大きな影響を与えている。例えば、ICTの活用により、消費者の個別オーダーを短期で可能にする製造体制(島精機製作所など)や、縫製メーカー自体が消費者に向けブランド化しネットワーク化してオンラインで消費者から受注する動き(ファクトリエ)など大きな変革が始まっている。
また「アマゾン・エフェクト」と「シェアリング・エコノミー」の2つの変革ショックも大きい。アマゾン・エフェクトは、アマゾンが取扱商品領域を食品(しかも生鮮)やファッションにも拡大し売上を伸ばしていることの影響である。アマゾンは、日本での売上高1兆円を超え第6位(2016年)の小売業になり、さらに2桁成長を続けている。
またシェアリング・エコノミーは、メルカリという代表企業が市場の認知も実際の利用も急速に高まっている。消費者間の流通、新品に限らず自分に価値あるものなら中古でも買うというモノの流通がさらに普及すると、小売業のあり方そのものが問われることになる …