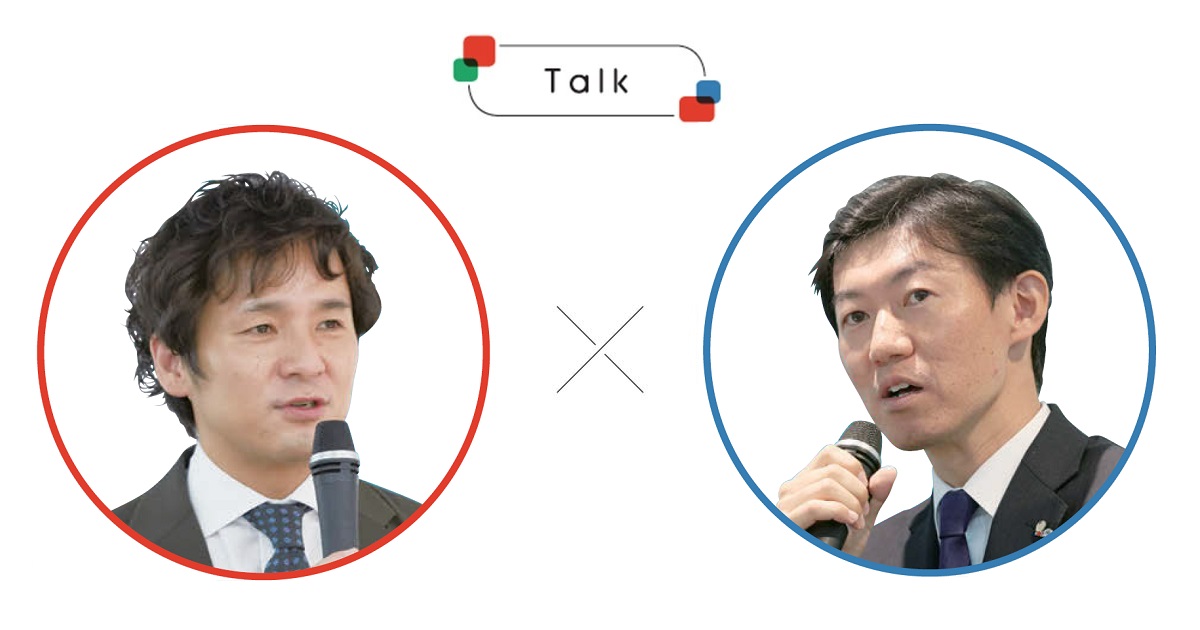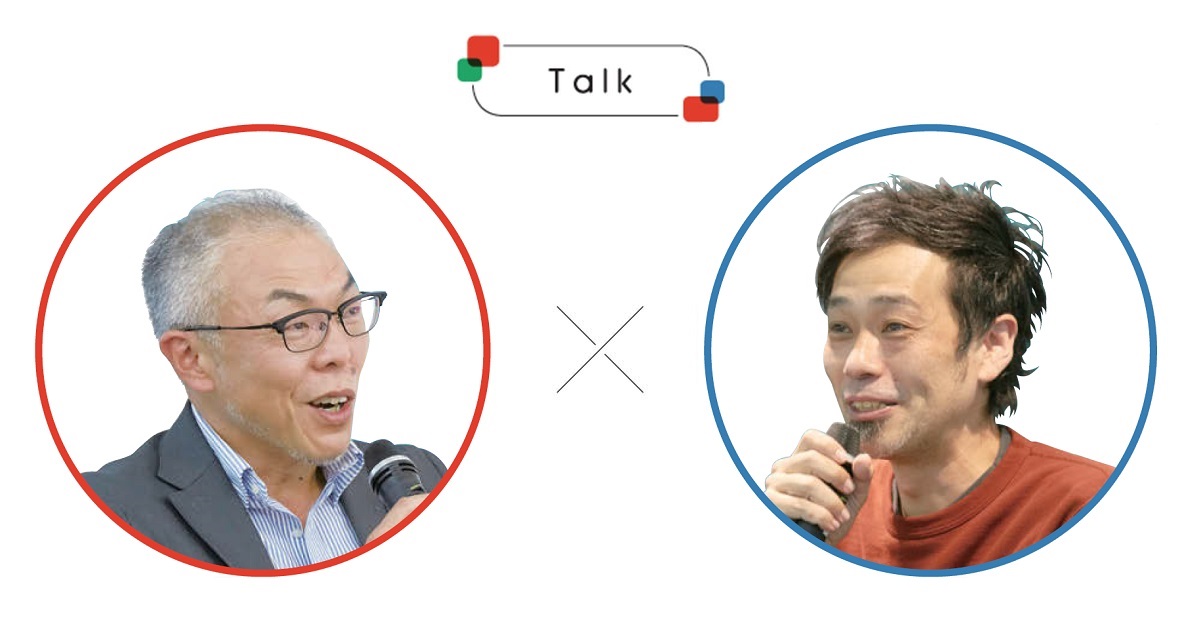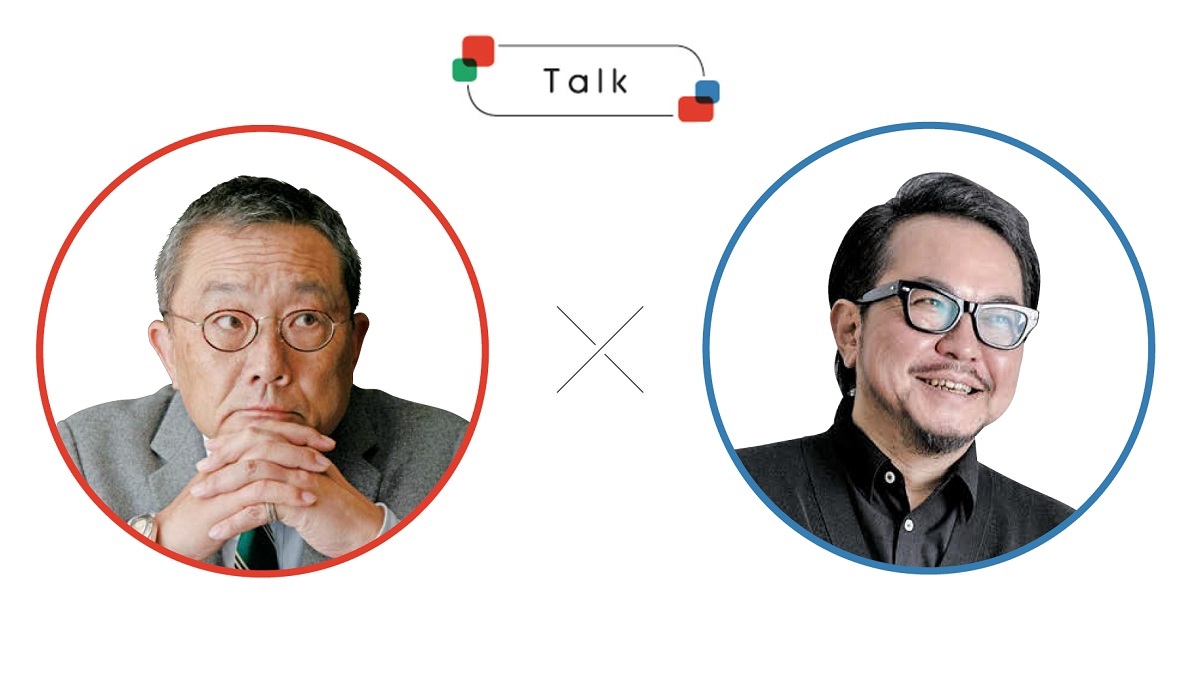「タニタ食堂」をはじめ、広告宣伝以外の手法でも企業名を知らしめ、ブランド力を高めてきたタニタ。企業価値向上にもつながるような、話題をつくる広報活動のポイントについて、同社の広報活動を統括するブランディング推進部 部長の猪野正浩氏に聞いた。

「タニタ食堂」や「タニタカフェ」は、“市場創造型広報”によって生まれたタニタの新たなビジネスだ。
10年以上CMは出稿せずとも広報の力で話題になり続ける
「タニタ食堂」や「タニタカフェ」、企業とのコラボレーション商品、他社商品の監修など、多方面でメディアから取り上げられる機会の多いタニタ。しかし、ここ10年以上、同社ではテレビCMによる広告宣伝を行っておらず、その他のペイドメディアへの出稿も年に数回ほど。SNSなどの自社メディア以外では、ニュースリリースやメディアからの取材依頼を受ける形の記事によってほとんどの発信を行っているという。
それではどのようにしてニュースをつくり出しているのだろうか。
同社ブランディング推進部 部長として広報活動を統括する猪野正浩氏は、タニタに入社した当初、広報部門が間接部門とされており宣伝費用の獲得が困難であったため、フリーパブリシティでの露出をいかに増やすかを検討したと話す。
「まず行ったのは、メディアとのコネクション構築です」と猪野氏。「ある時知り合いから『メディアの数には限りがあるけれど、企業は星の数ほどある』と言われました。星の数ほどある企業の中でタニタという会社を知ってもらわなければならない。まずはそこから取り組むべきだと考え、メディアに対して説明に行ったり、サンプルを持って行き使ってもらったりといった活動を5年ほど行いました」と話す。この時の地道な活動により、メディアの中でのタニタの認知度は向上した。
しかし...