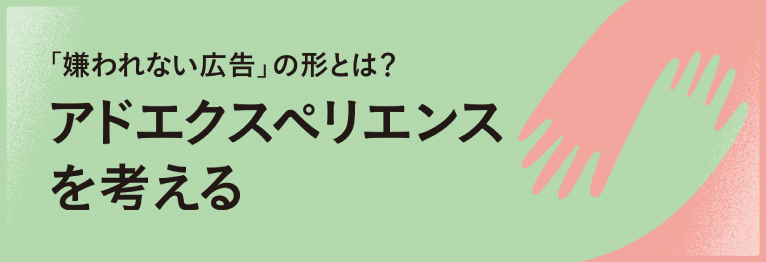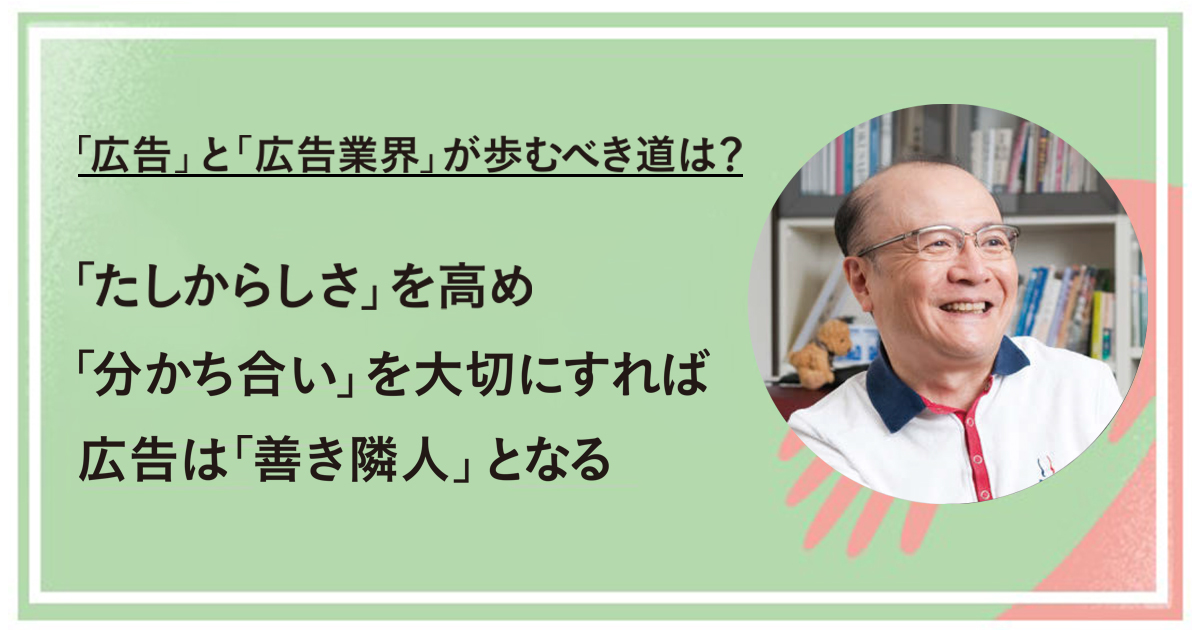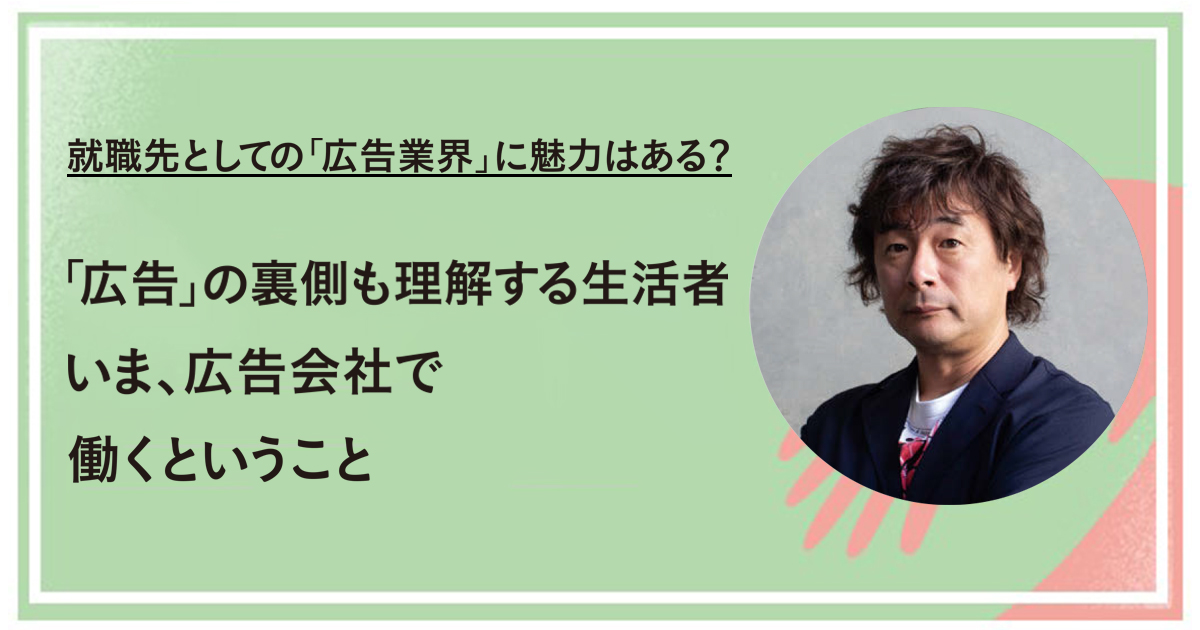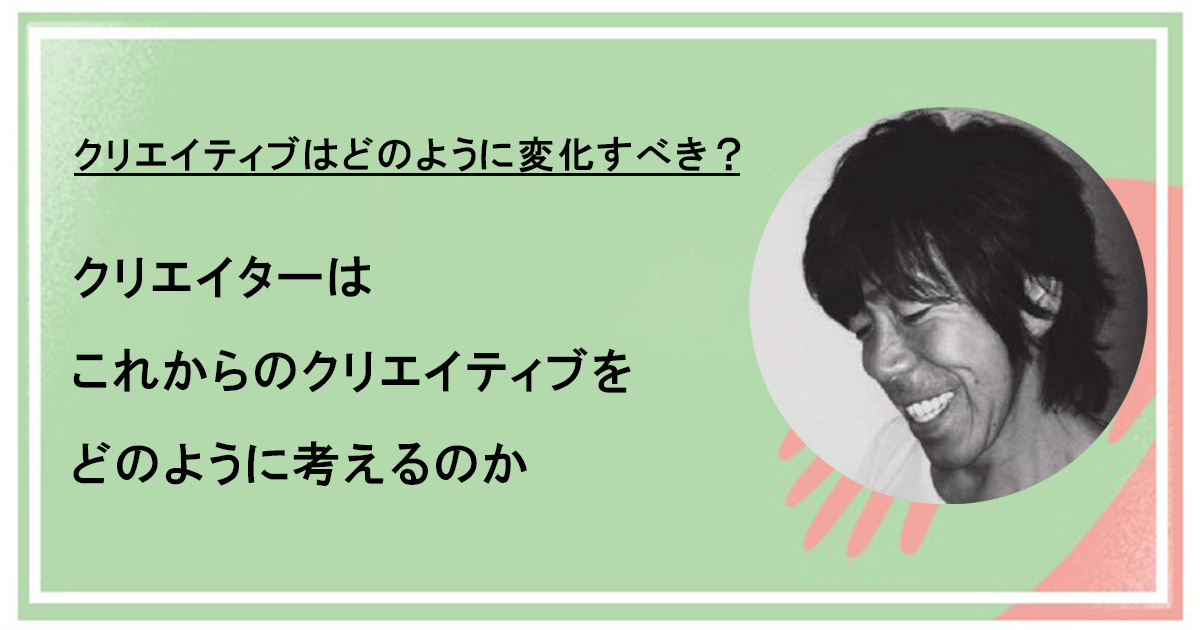生活者の消費行動がWeb主体となり、広告をめぐる環境が激変する中でも、多彩なブランドのラインアップを誇るサントリー食品インターナショナルでは、話題となる広告を数多く生み出し続けてきた。その秘訣は一体どこにあるのか。同社コミュニケーションデザイン部長の木下卓也氏に話を聞いた。
広告を通じた“人格”の形成 製品とともに伝わる工夫
サントリー食品インターナショナルのサントリーコーヒー「BOSS」は今年発売30周年を迎えた。周年に合わせて、おなじみの「地球調査シリーズ」の最新作が放映され、中島みゆきさんが出演。今回も「BOSS」というブランドの人格を感じるクリエイティブでテレビCMも話題になった。
「地球調査シリーズ」の開始は2006年。その間、現在に至るまでメディア環境は激変してきた。生活者との接点が変わる中で、コンテンツとして話題になる広告を生み出し続けるために、同社ではどのような方針を掲げているのだろうか。
同社コミュニケーションデザイン部長の木下卓也氏は、次のように答える。
「クリエイティブについて言えば、やはり、お客さまにずっと愛され続けるブランドコミュニケーションを心がけてきた、という一点に尽きます」と木下氏。
サントリーの使命は「人と自然と響きあう、潤い豊かな生活文化の創造と実現」であり、根底にはサントリーの製品があることで生活者の暮らしがより潤い豊かなものになるようにという思いがある。それは広告にもずっと受け継がれているのだ。
同社では、個別のブランドの「人格化」を意図した発信を心がけるケースも多い。その代表例とも言えるのが前述の「BOSS」シリーズだ。
「我々は、ブランドの“人格”を感じ取ってもらうことで製品自体とお客さまの関係性が深まる、そういうコミュニケーションをとても大切にしています。『BOSS』の場合は、“働く人の相棒”というコンセプトがあり、全ての働く人に寄り添い応援するコミュニケーションを一貫して行っています」と木下氏は説明する。
“人格化”をはじめとしたブランドを「主語」にしたコミュニケーションを大切にしてきた同社だが、その一方で、今の時代はそれだけでは消費者に届かなくなっていることも痛感しているという。
「SNSを見ていると、特に若い世代には、ブランドを主語とした企業が伝えたいことを発信するものはなかなか見てもらえない、という現実があります。それに対応するには、コミュニケーションのパターンを増やしていく必要があります。そのため、実験的なことをやる企画枠を設けることで、毎年新たなチャレンジを行うようにしています」。
近年行われた調査によれば、デジタル広告の存在を鬱陶しいと感じている...