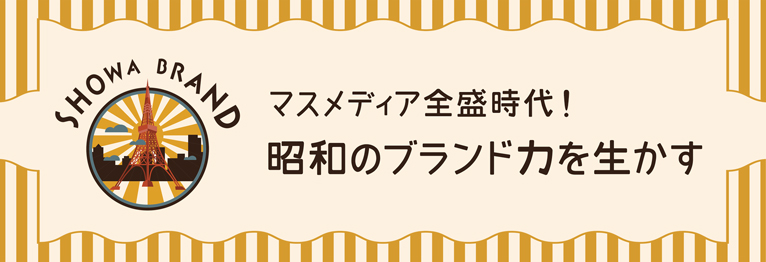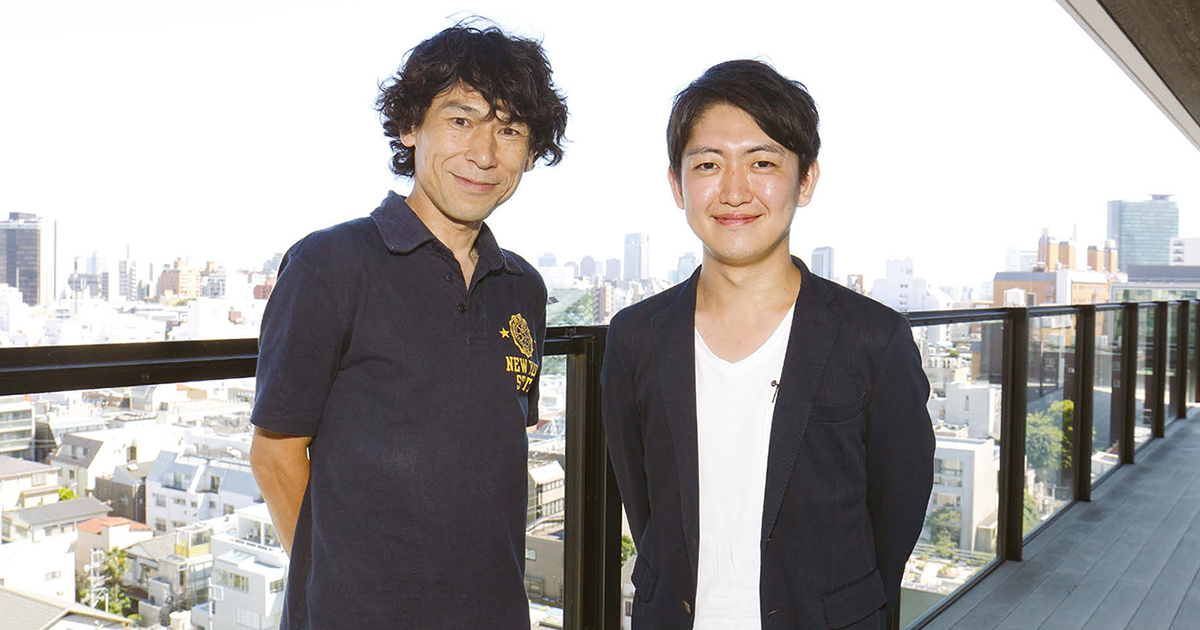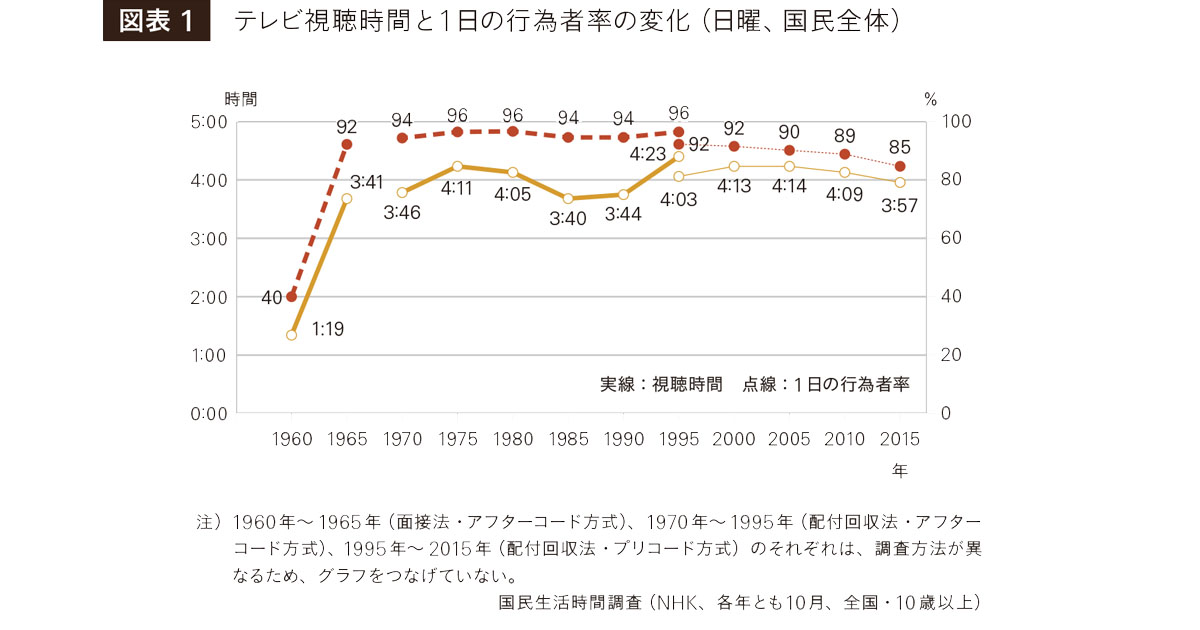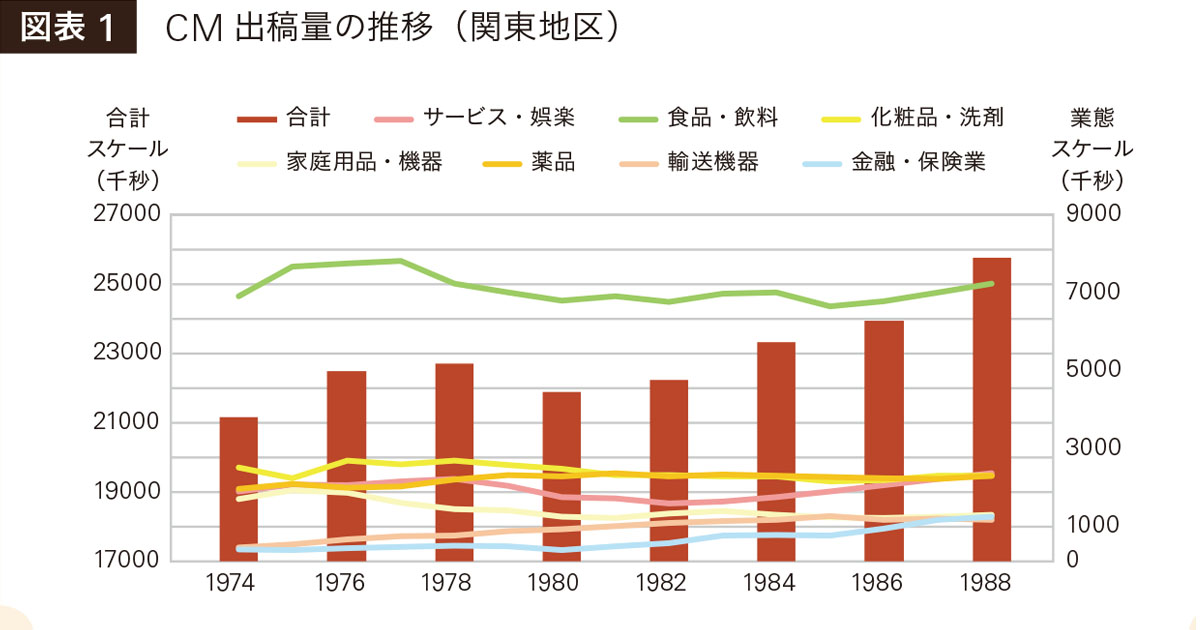5月25日、明治「カール」が東日本での販売を終了するというニュースが日本を駆け回りました。テレビCM「それにつけても、おやつはカール」のフレーズが有名で、スナック菓子を代表するブランドのひとつです。なぜカールは多くの消費者から認知されていたにも関わらず、そのブランド力を生かせず終売してしまったのでしょうか。ブランド戦略に知見を持つアウディジャパン デジタル&CRMマネージャーの井上大輔氏に分析してもらいます。

なぜあのカールが? 東日本「終売」への驚き
明治「カール」の東日本終売はソーシャルメディアで話題になり、マスメディアでもしきりに取り上げられた。これは「カール」というスナック菓子のブランド力が、いまだに衰えていないことの証左だろう。しかも、このニュースは百貨店の凋落のような時代の変化を象徴する出来事としてではなく、単純な驚きとして受け入れられた印象がある。「え、なぜあの『カール』が?」と。
では、なぜ明治「カール」が終売なのか。また、なぜブランド力がある商品が終売の憂き目を見ることになったのか。私はキーワードが3つあると考える。「Eコマースの興隆」「バイヤーの焦り」「交渉力としてのブランド」だ。
ブランドがテーマになると、それをどのように構築するか、というブランディングの議論になることが多いが、今回の論点は「構築されたブランドをどう活用するか」になる。その場合、メーカーはブランドを主に3つの用途に活用できると考える。「1.既存のカテゴリーにおけるビジネスの効率化」「2.他カテゴリーへのビジネス拡大(ブランド拡張)」「3.ライセンシングなどブランド自体のマネタイズ」だ。
日本企業が得意とするのは「1」の領域で、それはさらに「価格プレミアムによる収益性強化」「新ライン追加時の品質保証」「指名買いによる広告宣伝費の削減」などに細分化できるが、今回のケースで重要なのは「(小売や卸の)バイヤーとの交渉力」になる。基本的には、商品にブランド力があれば、メーカーは小売との交渉で優位に立つことができる。それは、伝統的な日本企業にとっては、おそらく最も魅力的な(社内コンセンサスを得やすい)ブランドのメリットだろう。
小売や卸のバイヤーはプロであり、時に消費者とは少し違う視点で買い付けを行う。「スナック」「飲料」「日用品」などカテゴリーごとに売り場の戦略があり、まずはそこを起点に意思決定するのだ。さらに消費トレンドやカテゴリーの先行きなど、消費者自身からは見えていない、俯瞰したデータが手元にある、という違いもある。それゆえ、消費者を代表するバイヤーとて、消費者とまったく同じ視点で買い付けをするとは限らない。
押し寄せるEコマース FMCGも逃れられない
Eコマースの興隆はここであえて論じるまでもない。ただ、日用品や食品といったFMCG(日用消費財)のEコマース化は、流通が他に類を見ないほど発展した日本では他のカテゴリーと比べ遅れており、特にスナック菓子はEコマース化が難しいことが知られている。
中身が壊れやすく、配送に独自のパッケージが必要だが、時計などの高級商材と違い、パッケージにそれほど投資できない ...