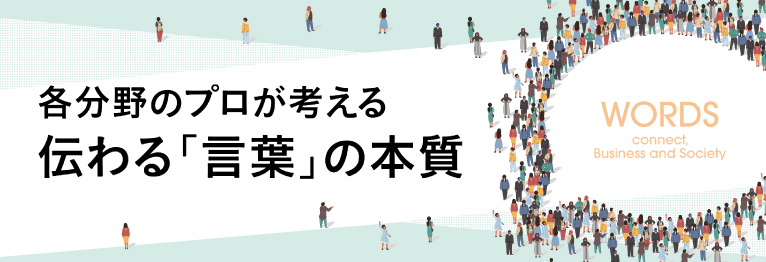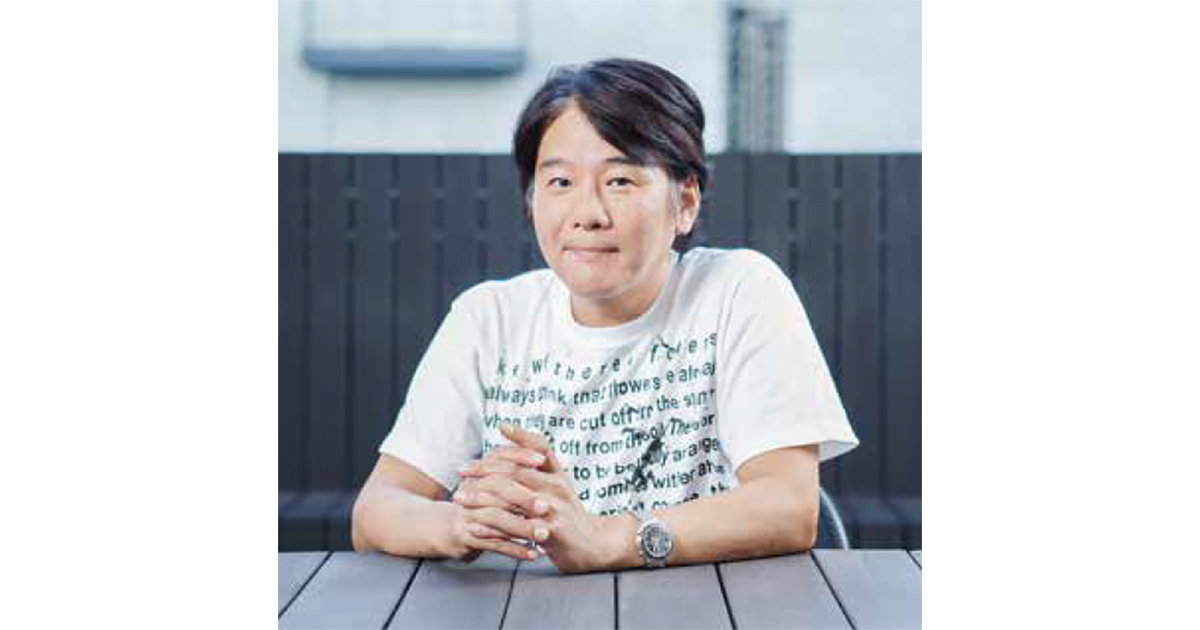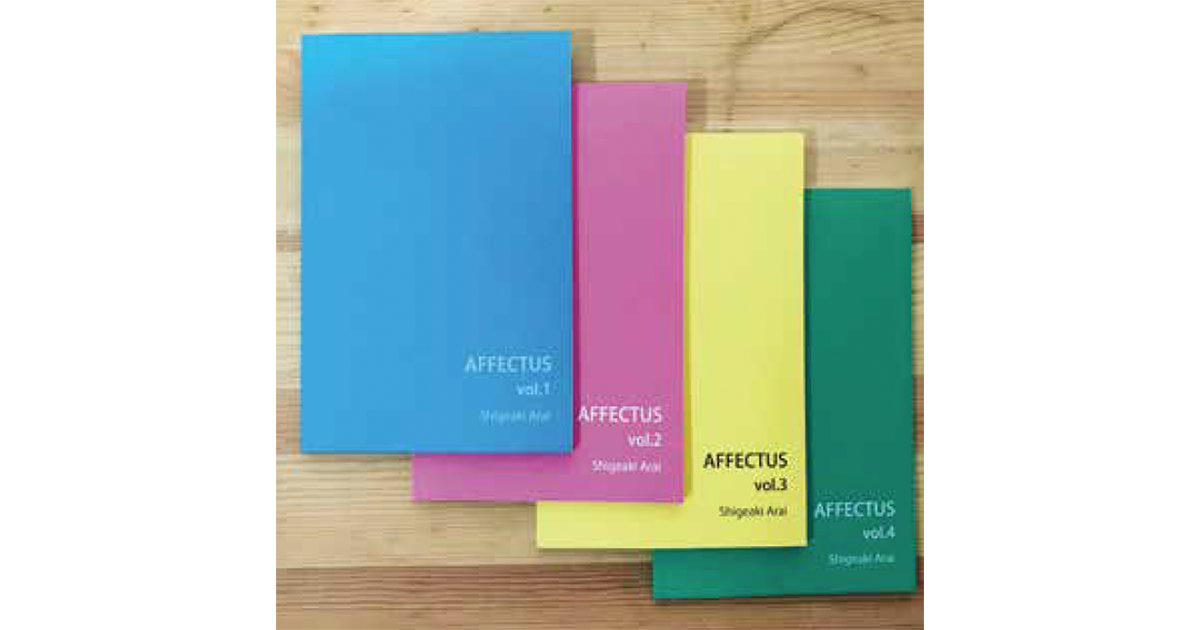あらゆる職業において、「言葉」はもっとも重要なコミュニケーションツール。とりわけ、公務員という職業は、業種・業界、属性の異なる住民たちと毎日「言葉」で会話する必要がある。だからこそ、一発で「伝わる言葉」を話す力が必要だと話す、藤枝市理事の山梨秀樹氏に話を聞いた。

藤枝市理事
藤枝市人財育成センター長
山梨秀樹氏
1983年4月、静岡県庁に入庁。2019年3月に同県を定年退職し、同年4月から藤枝市理事。2020年4月から同市人財育成センター長を兼ね、現在に至る。著書に「伝えたいことが相手に届く!公務員の言葉力」(ぎょうせい)。
役所にコールセンターはない 職員全員に「言葉力」が必要だ
地方自治体の公務員として、「言葉」についての著書を最近刊行したほど、「言葉」のもつ力や、その使い方の工夫について常に考えています。
役所仕事と言葉の力を結びつけて考える人は、まだ少ないかもしれません。しかし、私たちは日々さまざまな人々と言葉でコミュニケーションをとっています。窓口、電話、FAXにメール、FacebookやInstagramなど、コミュニケーションの手段も実に多岐にわたります。
それは民間企業も同じでしょう。しかし、民間大手企業には「コールセンター」や「お客さま窓口」といったものがあり、問い合わせについてはそこで対応しているケースが多いと思います。つまり、お客さまと直接話をする専門部署が存在する。
役所にコールセンターはありません。どこの窓口でも現場でも、職員全員が、常に第一線でお客さまと相対で接しています。私たちの「お客さま」は極めて多様。市民・県民・国民の皆さまであり、年齢、性別、出身地、国籍を問わず、多くの人々と毎日接します。つまり公務員にこそ、あらゆる人々に向けて簡明に伝えられる「言葉力」が必要なのです。
言葉を磨くきっかけは市民からの罵声だった
私が「言葉力」を磨こうと決めたきっかけは、若い頃、市民の方々に向けたある施策の説明会での出来事がきっかけでした。説明の最中、私は1人の市民の方から、「何を言っているのかわからない」と怒鳴られてしまったのです。多くの市民の前で私は頭が真っ白になり、次の瞬間、深々と頭を下げていました。
恥ずかしい思いをした訳ですが、この出来事があってから、「お役所言葉」は通じない、もっと相手の身になって言葉の力を磨かなければダメだと思うようになりました。あの時、私に指摘してくださった方には今でも感謝しています。
公務員の大切な仕事のひとつに、「説明責任」を...